【生誕100周年】小説家・萩原葉子のおすすめ作品

萩原朔太郎の娘として知られ、晩年に至るまで小説・エッセイを精力的に発表し続けた作家・萩原葉子。『蕁麻の家』を始めとする萩原葉子のおすすめ作品を紹介します。
2020年に生誕100周年を迎えた小説家・エッセイストの萩原葉子。詩人・萩原朔太郎の娘としても知られ、デビュー作『父・萩原朔太郎』で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した後も数々の賞に輝くなど、高い評価を得ている作家です。
昨年から今年にかけては前橋文学館で記念展「なぜ踊らないの」が開催され、ふたたび注目を集める契機にもなりました。今回はそんな萩原葉子のおすすめの小説・エッセイをあらすじと共にご紹介します。
『父・萩原朔太郎』
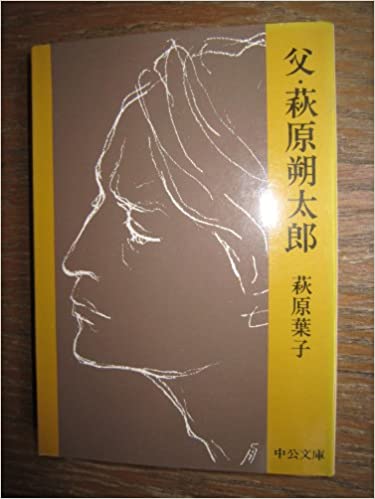
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/412200618X/
『父・萩原朔太郎』は、萩原葉子が1959年に発表したデビュー作のエッセイ集です。萩原は本書で第8回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞し、本格的に作家活動をスタートさせました。
エッセイを書き始めたきっかけは、同人として加わった文芸誌『青い花』のメンバーらに勧められたからだった、と萩原は本書の前書きのなかで語っています。本書のテーマはそのタイトル通り、“日本近代詩の父”とも称された萩原の父、朔太郎を巡る思い出。萩原は、大詩人であった父の人間らしい一面をエッセイのなかで詳細に綴っています。
たとえば、『晩酌』というエッセイでは、父・朔太郎が家で晩酌をするときの姿はまるで子どものようだった、と明かします。
父はお酒を飲むと、まるでたあいない子供になってしまう。そして酔ってくると、しだいにお酒をびしゃびしゃお膳にこぼしはじめ、それにつれてお菜を、膝の上から畳の上いちめんにこぼすのだった。だから父の立ったあとは、まるで赤ん坊が食べ散らかしたようなのであった。祖母はあと始末がやりきれないとおこるが、私は、こうして酔って童心になりきった父の方が、ふだんの父より好きだったし、もうてれくさくもなくなり、ずっとよかった。
また、『手品』というエッセイには、朔太郎が晩年にアマチュアのマジシャン・クラブに入会し、手品を趣味としていたというエピソードが出てきます。朔太郎亡きあとに家族が書斎を整理すると、「手をふれるべからず」と書かれた下から手品のタネ明かしを書いた紙が大量に出てきた──というのです。
父は病気で、死を予感して、こうして用意していたのだと思った。ふだんは、とてもルーズなたちなのに、むしろあきれてしまった。そのほかには、何一つ死ぬ用意などしていなかった。(中略)私は、そこに父の姿を目のあたり見たように思い、もう父はこの世のどこにもいないのだという激しい悲しみが改めて全身を襲ってきて、泣いた。
萩原は本書のなかで、父のことを“うそや、その場の取り繕いということのまったくできないたち”で、“臆病”だったと評しています。馬鹿正直でうそがつけない故に、忙しいときに客が突然訪ねてきて長居をしていくことを朔太郎は異常なほどに怖がったと言います。
気が弱く堂々と振る舞うことはできないけれど、家のなかで自分だけの世界に入ると途端に天真爛漫になる朔太郎。そんな姿がありありと浮かんでくるような名エッセイです。
今になってみると、これを書いていた二年間というものは、私の生涯で最も幸せな月日であったと、しみじみ思う。
と、萩原は本書の執筆時をそう振り返っています。
『天上の花・蕁麻の家』
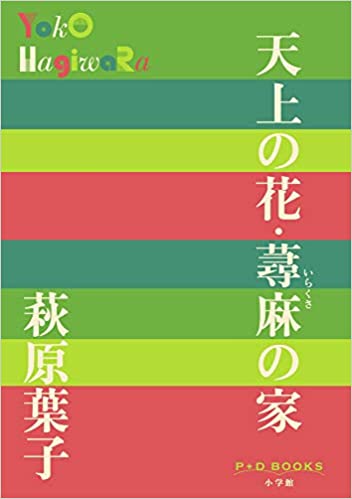
出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352396
本書には、詩人・三好達治についての思い出を綴り第55回芥川賞候補作となった小説『天上の花』と、自らの暗い生い立ちについて語り第15回女流文学賞を受賞した『
『天上の花』には、父・朔太郎に師事し、萩原が幼い頃から家族ぐるみで交流のあった三好達治のエピソードが克明に記されています。幼少時の萩原は非常に無口で人見知りの激しい子どもだったものの、頻繁に家を訪れる三好のことだけは信頼できた──と萩原は語ります。
紺ガスリの和服に袴をつけ、襞はきちんと折り目正しく畳まれ、和服の襟元はきっちりと打ち合わせてあった。
「先生おられますか?」と、とっ拍子もなく高い声で言い、父が二階から降りて来る姿を見ると、はっとしたように姿勢を正して、襟元を掻き合わせるのである。
姿勢良く、がっちりと骨太の体格で、言葉は大阪訛りがあって、何かにつけて“ハイ” “ハイ”と、兵隊のように受け答える人だった。
外見の粗野で固く、オクターブ高い声の調子に似ず、目には何故か泣き顔のような優しさがあって、私はその目を信頼したのかも知れなかった。心もち下がった目尻の上瞼にホクロがあって、そのホクロは子供心に安心感を抱けると思った。
萩原にとっては、歳の離れた優しい兄のような存在であった三好。三好はやがて萩原の叔母である慶子に恋をし、ふたりはそれぞれ一度は別の相手と結婚生活を送るものの、困難を乗り越えた末に再婚します。しかし、派手さや華やかさを好む慶子と無骨な三好の関係はしだいにすれ違い始め、三好は途中から慶子に激しい暴力を振るうようになった──と萩原は綴ります。
三好についての萩原の記述は、父の弟子であり自身の恩人であった人物について書かれたものとは思えないほど、非常に辛辣かつ素直。三好を美化せず、よい面も悪い面も淡々と記した本作は、壮絶でありながらもとても読み応えのある作品となっています。
『蕁麻の家』は、そんな萩原自身の半生を語った自伝的作品。“蕁麻”とは、葉の全体に棘を持ち、触れると激しい痛みを感じる植物です。幼い頃に母が家を出て行ったことをきっかけに、気性の激しい祖母や叔母を始め家族たちから疎まれていた主人公・
『天上の花』と『蕁麻の家』はどちらも非常に痛ましく陰惨な話であるものの、同時に力強くもあり、萩原の生涯を知りたい方にとっては一読の価値のある作品です。
『閉ざされた庭』

出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352424
『閉ざされた庭』は『蕁麻の家』の続編にあたる、1984年に発表された長編小説。父が死去したのちの約10年間のエピソードが綴られています。
物語は、主人公・嫩が父の死後に家を出て、結婚生活をスタートさせるところから始まります。嫩の夫となる人物は、真面目さだけが取り柄の会社の上司・古賀。意地の悪い祖母や叔母たちは、学生時代に知り合った男に騙されて妊娠した経験を持つ嫩のことを長らく“
「こんな汚ない部屋に住まわせるのですか」古賀は繁った樹木の陰の古ぼけた立看板に、「木馬館」と、浮き出ている文字を見て不機嫌に言った。(中略)嫩は、「あ奴を家から出すために結婚させる」と、聞き飽きるほど祖母や叔母たちから言われていたし、暗い思い出のある家には住みたくなかった。狭くてもアパート住まいはむしろ、嬉しかったのだ。
「どうしてふたばさんはこんなところで、我慢するんですか?」と言った。
嫩が返事に詰っていると、
「そんなところ何度拭いたって、同じことさ」と、怒りを極限まで我慢した声で言った。嫩は今更に、古賀が初めて家に来た時のことを思い出した。「ぼくがこんな立派な家に住めるなんて!」と、勝手に思い込んで喜んだあの時の嬉しそうな顔が、いまの苦い顔と重なった。
アパート暮らしの貧しく劣悪な環境への不満は古賀の元来の卑屈さに拍車をかけ、夫婦は愛し合うことなくすれ違っていきます。やがて子どもが生まれるものの、古賀は育児に非協力的で、嫩は古賀の横暴な仕打ちにただ耐え続けるのでした。
本作は萩原が書いた自伝的小説3部作の2作目にあたり、その内容は『蕁麻の家』と同じかそれ以上に壮絶かつ陰惨です。しかし、1997年に発表した3作目の『輪廻の暦』では、嫩がどうにか離婚の道を選びとり、書くという行為のなかにわずかな光を見出していくさまが描かれるのです。3部作をあわせて読むと、萩原がその辛い人生のなかでも執筆をある種のセラピーのように用い、自身の歩みを進めていったことがよくわかります。
おわりに
萩原は夫との離婚後、かつて家族を捨てて家を出た母をなんと自ら引き取り、同居を始めます。ひとりで子どもを育てながら母の世話をし、執筆活動も続けることはとてつもない重労働でしたが、萩原はこの頃に突如フラメンコなどのダンスを習い始め、情熱を注ぐようになったのです。
萩原のひとり息子で映像作家の萩原朔美は、40歳を超えてダンスに熱中し始めた母を当初は疎ましく思っていたものの、ダンスの発表会で若い女性たちに囲まれて浮いている彼女の姿を見たときに、初めて「応援しよう」と心から思った、と語っています(『死んだら何を書いてもいいわ──母・萩原葉子との百八十六日』より)。晩年の萩原はダンスを生きがいとし、80歳を超えてもなお活き活きと踊り続けて生涯を終えたと朔美は言います。
自伝的小説3部作を始めとする萩原の作品の多くは陰りのある重々しいものですが、一方でダンスにまつわる入門書などではエネルギッシュで情熱的な面も見せています。書くことと踊ることを通じて人生をすこしずつ好転させていった萩原。その生涯に、彼女の著作を通してぜひ触れてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/09/28)

