【イベサー、プリ、ヤマンバ…】「ギャル文化」を正しく知るための3冊

「ギャル」という言葉のイメージがひとり歩きしている昨今。今回は、“盛り”や“イベサー”といった「ギャル」と彼女たちを取り囲むカルチャーについて改めて知り、考えるきっかけとなるような3冊の書籍をご紹介します。
「ギャル」という言葉を聞いて皆さんが最初にイメージするものはなんでしょうか。ゼロ年代に流行のピークを極めたヤマンバ・ギャルやギャルサーの女子たちを連想する方もいれば、渋谷の女子高生を連想する方も、派手なメイクをしたモード系の女性を連想する方もいるかもしれません。
そんなさまざまなイメージを抱かせる一方、援助交際や家出、非行などと結びつけられ、漠然とした悪い印象で報道されることも少なくなかった「ギャル」という存在。近頃では「見た目は派手だけれど実はいい子」の代名詞のようにSNS上などで消費されることも増え、そのイメージはカオスなものになりつつあります。
今回は、そんな「ギャル」と彼女たちを取り囲むカルチャーについて改めて知り、考えるきっかけとなるような3冊の書籍をご紹介します。
『「盛り」の誕生 女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識』(久保友香)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4778316630/
本書は、メディア環境学の研究者である久保友香による、“盛り”の歴史を振り返る1冊です。“盛る”とは2002年に自費出版されたイベントのパンフレットの中で初めて使用された言葉で、女子がメイクやプリクラ、アプリなどで顔を加工する行為のことを指します。
著者は90年代の渋谷から始まったプリクラブームを筆頭に、ゼロ年代にガラケーの普及によって巻き起こったブログ・自撮りブーム、2010年代からのインスタグラムや加工アプリのブーム──を時系列に沿って振り返りながら、女子たちが目指す顔がいつどのように、どんな技術の発展とともに変化してきたかを紐解いていきます。
中でも興味深いのが、2012年にプリクラメーカーによって開催された「ヒロインフェイスコンテスト」というミスコンテストについてのエピソードです。このミスコンテストのエントリーには証明写真のようなプロフィール画像は必要なく、プリクラ機で撮影したプロフィール画像で応募することができるという革新的なものでした。
このコンテストの参加者の女性たちの中には、実際に会場に集まってみるとプリクラの画像とは別人のような女の子も少なくありませんでした。しかし、それでも活き活きと歌やダンスを披露する彼女たちに、著者はコンテストのあと「なぜ盛るの?」と問いかけます。
私は思いきって、
「なぜ盛るの?」
と聞いてみた。彼女は答えに詰まってしまった。そこで違う聞き方をしてみた。
「男の人の目を意識して?」
彼女はこう答えた。
「ぜんぜん違うことはないけれど、そうではない」(中略)
そして少し間を置いてから、彼女はこう答えた。
「自分らしくあるため」
自分らしくあるために顔を盛る、という文化と同時に、その行為が“量産型”(=同じような顔・外見)に近づいていってしまう謎についても、著者はプリクラの技術やギャル雑誌の特集といったデータから丁寧に紐解いていきます。
日本のギャル文化とは切っても切り離せない概念である“盛り”を多角的に知ることができる、ユニークな1冊です。
『ギャルとギャル男の文化人類学』(荒井悠介)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4106103346/
『ギャルとギャル男の文化人類学』は、かつて渋谷で有名イベサー(ギャルとギャル男から成るイベントサークル)のトップを務めていた経験を持つ社会学者の荒井悠介による新書です。「イベサー」の成り立ちを歴史的に振り返りつつ、フィールドワークとして数百人のギャル・ギャル男たちへのインタビューを重ねることで、彼らの社会観や未来像を解き明かすことに成功しています。
本書は、著者である荒井自身が2001年、大学1年生のときに有名イベサー「ive.(イヴ)」の一員となって初めて渋谷センター街に足を踏み入れたシーンから始まります。
見ると、センター街のメインストリートとその「枝」にあたる横道の角に、十人ほどのギャルが輪になり、地ベタに座って何やら談笑している。
強めのパーマとエクステンション(つけ毛のこと)を入れたカラフルな髪に、筆者よりもはるかに真っ黒な肌、目と口の周りは化粧で真っ白に縁取られている。まるで野生生物を威嚇するライオンキングのような出で立ちをした、真っ黒なギャルの群れ。ブランドのロゴの入ったバッグ、手や胸元にはジャラジャラとしたアクセサリー、露出度の高いワンピース、どぎついメイク、針のような付けまつ毛。いわゆる典型的な「ヤマンバ・ファッション」に身を包んだ女の子たちだった。
著者はイベサーの先輩に命じられてここで初めてヤマンバ・ファッションのギャルに声をかけますが、その派手なファッションからは想像できなかった「お疲れさまです」という言葉が返ってきて面食らいます。聞けば、彼女たちは「ive.」と同じ系列のイベサーに所属しているギャルたちだと言うのです。
彼女たちからサークル名の入った名刺を社会人のように手渡された著者は、“都会のギャル”たちがテレビや雑誌でたびたび目にしていたイメージとも、著者の地元・立川で水商売をしているギャル系の女子たちとも違うことに大きな衝撃を受けます。やがてイベサー内のトップを経てサークルを卒業した著者は、イベサーに所属するギャル・ギャル男たちの社会観に関心を抱き、研究対象としてフィールドワークをおこなうようになります。
ギャル・ギャル男たちのインタビューを通して本書で紐解かれてゆくのは、彼らに共通する「サークル内での人間関係が将来に活きる」「若いうちにできるだけ遊んで落ち着くべき」という意外なほど保守的な価値観です。著者のあとに「ive.」の代表となった人物は、
「サークル界ってマジでダルイ付き合い多いじゃないですか。楽しんでないわけじゃないんすけど、他サーのイベに行って、ナゴミも行って、上の人との付き合いも多いんですよ。でも、俺はまだ社会人じゃないからわかんないんすけど、そうゆうマメさとか、人付き合いの上手さって、がんばった人は絶対に将来活きてくると思うんですよね」
と語ります。
本書を読むと、ゼロ年代のイベサーに所属していたギャル・ギャル男たちは、所属するコミュニティとファッションが奇抜ではあるもののいわゆる“普通の若者”であったことが見えてきます。イベサー内での立ち居振る舞いや礼儀作法などギャル・ギャル男特有の文化を知るにはもちろん、かつての「ヤマンバ・ギャル」や「ガングロ男」への漠然とした偏見を捨てるためにも必読の1冊です。
『渋谷学』(石井研士)
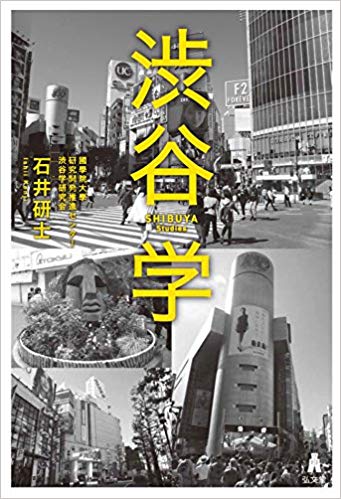
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/433525069X/
『渋谷学』は、渋谷にキャンパスを構える国学院大学で宗教学の研究をおこなう石井研士による、渋谷という独特なカルチャーを持つ街を地域学の観点から分析しようとする1冊です。
本書の中では、今後予定されている再開発によって2027年に渋谷がどのような街に姿を変えているかという予想や、例年大きな注目を集める「渋谷ハロウィン」についての分析に混じって、渋谷109を中心としたギャル文化についての考察が展開されます。
愛称はマルキュー。内部はティーンズファッションの人気テナントがひしめく商業施設である。
東急電鉄グループのひとつ、東急モールズデベロップメント(TMD)が運営しているため、ビルの名称の109に、10(とう)+9(きゅう)の意味が込められている。営業時間も109に合わせて、午前10時から午後9時までとなっている。また109という数には、施設内に109店舗を出店させること、「108の煩悩」を一つ超えた地点から出発することなどの意味も込められている
……といった「109」にまつわる豆知識なども豊富で興味深く、2000年前後に渋谷を闊歩していた「ガングロ」「ヤマンバ」ギャルたちの特徴や流行・衰退についての分析もおこなわれています。
ヤマンバの特徴はおおよそ四点である。第一に髪を白・金・銀・灰色などに染め、メッシュを入れ、故意にバサバサにし、髪が傷みまくった状態である。第二に唇は白い。第三に目元はパンダのようで、ラメ化粧やパールメイクといった明るい配色で、ボリュームのあるつけまつ毛をしている。第四は厚底の靴である。
“ギャルの聖地”であると同時に“渋谷系”カルチャーの生みの親でもあり、さまざまな商業施設や企業が立ち並ぶ街でもある渋谷。唯一無二の街の歴史と文化を多角的に知ることができる本書は、ギャルカルチャーはもちろん、地域学に関心がある読者にもおすすめの1冊です。
おわりに
ご紹介した書籍が“ゼロ年代のギャル”(ギャル男)たちを対象に分析したものが中心であることからもわかるように、2010年代以降の“ギャル”文化を分析・体系化した書籍はまだ数が少ないのが現状です。そしてそれは、“ギャル”が以前にも増して多様化し、“量産型”から離れたカルチャーとして枝を伸ばしつつあることを証明しています。
近年では、インスタグラムの流行によって「NEOギャル」(=2010年代以降の新しいギャル)、「バーチャルギャル」(=非実在のバーチャルなキャラクターによるメディア活動)など、新しい形の“ギャル”が次々と登場しつつあります。これからも進化していくであろう日本のギャル文化から、これからも目が離せません。
初出:P+D MAGAZINE(2019/10/30)

