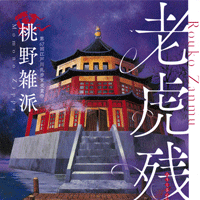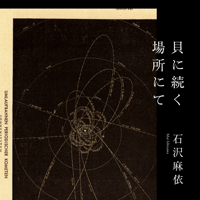今月のイチオシ本【デビュー小説】
『隣人X』
パリュスあや子
『隣人X』は、第14回小説現代長編新人賞の受賞作(鯨井あめ『晴れ、時々くらげを呼ぶ』と同時受賞)。それぞれに悩みを抱えた3人の女性が小説の軸になる。文学部の修士課程修了後、新卒派遣社員として大手企業に勤めはじめた土留紗央。40代にさしかかった今もコンビニと宝くじ売り場のバイトをかけ持ちする就職氷河期世代の柏木良子。居酒屋で働きながら大学進学を目指す19歳のベトナム人留学生グエン・チー・リエン。
「今日的なテーマにまっすぐ挑戦し、辛気臭い話に落とさずにエンターテインメント作品として仕上げ、しかも読者に何かを考えさせるプラットフォームを提供できていることを、高く評価しました」(中島京子)
「……現代の社会が抱える問題と巧くリンクさせ、登場人物の置かれた環境や心情を通じて難民や移住外国人の受け入れ、違法労働について投げかけてくるところに作者の並みならぬ手腕を感じた」(朝井まかて)
……というふうに選評の一部を抜粋すると、アクチュアルなリアリズム小説のようだが、実はその背後に、大きなSF設定がある。内乱が激化した母星を旅立ち、宇宙を漂流していた異星生命体とのコンタクトが成立し、米国政府は、彼ら「惑星生物X」を難民として受け容れると発表したのである。Xには、対象の見た目はもちろん思考や感情まで含めて完璧にコピーする能力がある。日本では、市町村ごとに平均的な20代男女を1名ずつ選んでコピーさせ、一定期間の研修ののち、日本人型の「惑星難民X」として社会に送り出すことが決まる……。
「人間そっくりに擬態する異星生物」や「難民としての異星人」は、SFでおなじみのモチーフだが、本書の特徴は、それをジャンルSF的に扱うのではなく、現代日本の背景と一体化させたこと。人間そっくりの異星人難民と共存する社会を、主人公たちが生きる日常としてごくあたりまえに(いやもちろん、作中でも大きな論争が起きるのだが)描く作風が新鮮。いわゆる風刺SFともまた違う、独特の小説世界をつくりあげている。
(文/大森 望)
〈「STORY BOX」2020年11月号掲載〉