辛辣さが癖になる 『兎』の著者・金井美恵子おすすめ4選
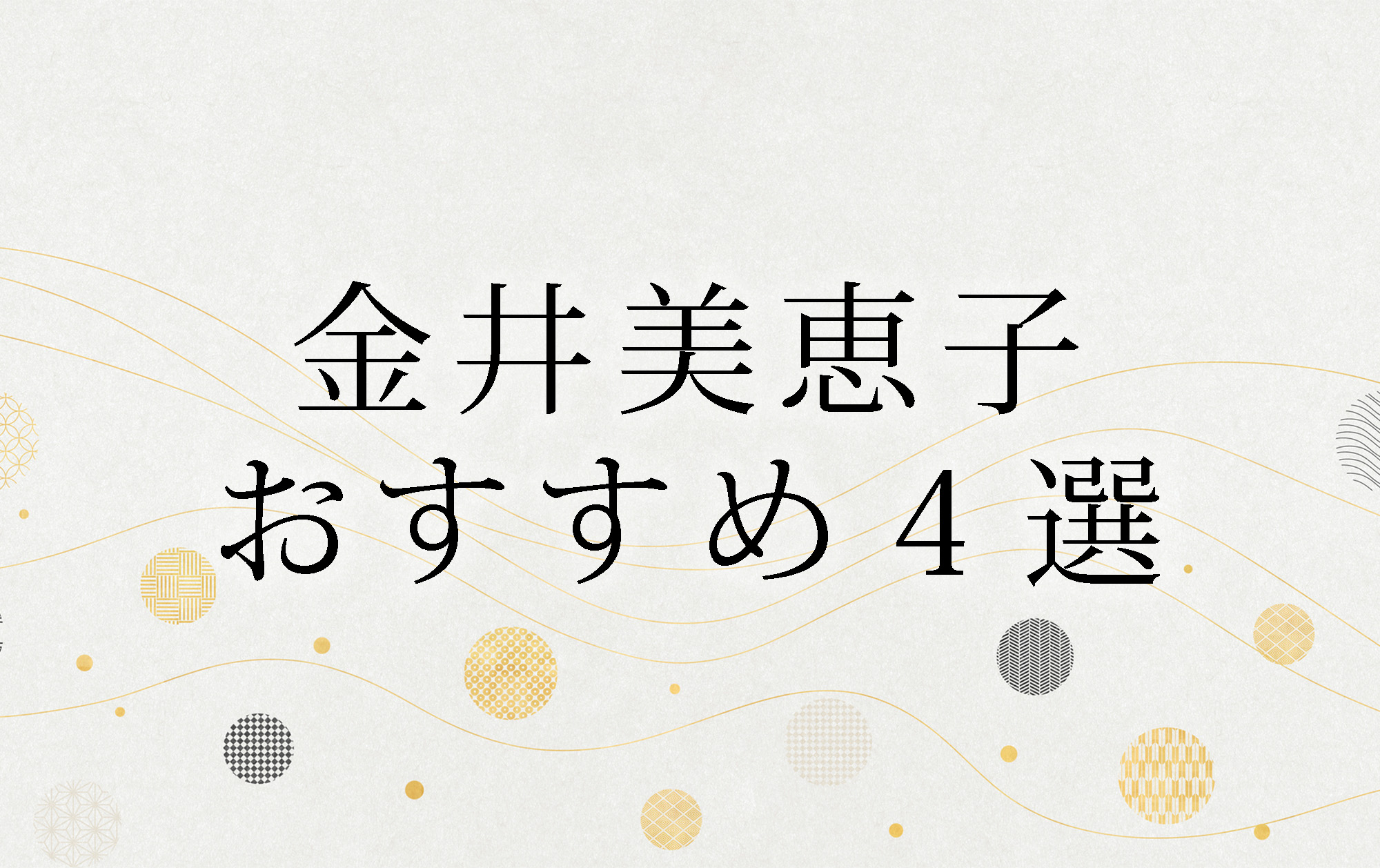
2018年、『カストロの尻』にて第68回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した金井美恵子は、膨大な知性と教養に基づく辛口な文章が魅力の、文学ファンのあいだでは言わずと知れた作家です。そんな著者のおすすめ作品4選を紹介します。
『文章教室』エッセイ講座に通う中年女性。その目的は、自己表現か作家デビューか

https://www.amazon.co.jp/dp/4309405754
絵真は、サラリーマンの夫と一人娘の女子大生を持つ専業主婦。習い事で、現役作家が教える文章講座に通うことに決めます。
講師の作家は、“世の中にはこの程度の文章を書いておけば事が足りるとする人間とこれを恥ずべきこととする人間と、二種類の人間が生息する”うちの、「自分は後者だと思い込んで」いるタイプで、受講生に、「私はなぜ文章を書きたいのか」という課題作文を与え、自分が小説を書く理由としては、「小説を読んだからだ」と答えます。
自分の内面を見つめ直すために文章を書きたいという絵真に対し、周囲は冷笑的です。女友達からは、「きちんと見つめたところで、つまんない平凡なおばさんの姿しか見えてこない」と言われ、娘からも「主婦のマスタベーション」と言われます。
ある日、実家に帰った絵真は、向こう隣りに仕事部屋を借りているらしい講師の作家と偶然鉢合わせます。
自己表現をすることで欲求不満をなだめようとしている図々しい中年女が、訳のわからない自己愛に充ちた「文章」とやらの相談という名目で自分を仕事場まで訪ねてきたのだと思い込み、実に不快な腹立たしい気持ちだった。こういう図々しい女というものは、仕事場にまで押しかけてくるというのに、おれの小説なんか一冊も読んだことがないのに決まっている。
当の講師でさえ、内心では、文章教室に来るのは「更年期の見本」のような女性が多く、その客観性に欠けた自己陶酔気味の作文には辟易しており、作家の妻は、そういう素人の書いたものを読んでいて消耗しないか、と夫に問う始末です。
しかし、周囲の考えに反して、絵真は、自己を見つめる作業、すなわち文章を書くことに熱中します。その背景には、忍ぶ恋があるのですが、恋をしたから文章を書きたくなるのか、文章を書いて物思いに耽っているから恋をしたくなったのかが、判然としないような状態です。そして、娘が婚約者を自宅に連れてくる日の直前に、本当の自分を取り戻したいといった理由で、実家に帰りたいと言い出します。そのときの夫と娘の反応はどのようなものでしょうか。
作中に、“あらゆる小説は、小説の小説、すなわち、メタ・ノヴェルである”という一節がありますが、本作はその筆頭というべき小説です。例えば、「今日この頃です」といった手垢のついた表現を使うことの是非や、小説を批評する際にしばしば用いられる「陳腐な物語」とか、「紋切型」といった言説について、「そもそもこの世に陳腐ではない物語があるのか否か」とか、「紋切型という批評自体が紋切型」等々……。
作品全体が、小説とは何か、文章を書くとはどういうことかを示唆する内容になっています。
『道化師の恋』文学的素養はないのに、まぐれで文学賞をとった男子大学生とその周辺
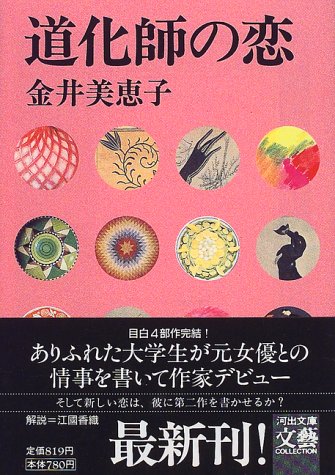
https://www.amazon.co.jp/dp/4309405851/
善彦は、早稲田大学政治経済学部に在学中。実体験をもとに「なんとなく、書けちゃった」小説を、ある文学賞に応募して第2席に入賞します。善彦は誰にも話していなかったため、人づてにその知らせを聞いた母は興奮気味。選考委員の作家の1人が遠戚にあたると知り、「初めに挨拶しておけば受賞できたかもしれなかったのに」と夫に言って、「そんなコネが通じるか」と呆れられたり、ママ友たちから、ご子息が作家になられたのは血筋か教育の賜物か、と訊かれて得意になったり、はたまた、授賞式に着ていく服に口出しするなど、当の本人以上に舞い上がってしまいます。
善彦は、母にせっつかれて、選考委員の作家宅に挨拶に行きます。(ちなみに、この作家は、前述の『文章教室』に出てくる「現役作家」)
(作家は)確かに感性はいいね、感心したよ、などと言い、で、どんな作家のものを読むの? とありきたりの質問をするので、善彦は、小説はあまり読まないんですよね、と答え、作家は、でも、と口ごもり、でも、小説を読まないで小説を書けるかい? と言った。
あくまで偶然入賞したまでだと答える善彦。謙遜や自己
どうしてこの人たちは、映画を見なかったり小説を読まなかったりすることに大騒ぎするんだろう(中略)それ以外に、世の中にはもっといろいろなことがあるのに、もっとずっと重要なことがあるだろうに。
と思ってしまいます。他の文学関係者たちとの温度差を感じつつも、デビューしたからには第2作を書かねばなりません。小説はデビュー作よりもそれ以降書き続けていくことが難しい、ということを、善彦は痛感します。
善彦は、文芸評論家の新妻・桜子(前出の『文章教室』の絵真の娘)と偶然知り合うのですが、彼女は、「全ての小説は書かれてしまったんですものね、現在、引用することによってしか、小説なんか書けるはずないわねえ」と善彦に理解を示し、「才能を持っている人がそれを伸ばさないのは罪悪だ」と励まします。しかし、善彦は冷静に自己分析をしていました。
小説なんて、どうでもいいんだよ、と善彦は(桜子に)言った。ぼくにとって小説がどうでもいい以上に、小説にとってぼくなんか存在しなくても何の関係もないわけだし、なんであなたが、そうぼくが小説を書きつづけるべきだって考えるのかわからない。
もう小説は書かないと言う善彦に対して、選考委員だった作家は説得します。
小説にとって自分は何かってことだけど、(中略)そういう発想はすごく面白い、小説とは何か、という古いけど新しい問いを
顚倒 させたわけだけど、そういう発想が出来るんだもの、余計に書かなきゃいけないよ。
著者は、文庫版のあとがきで、本作は風刺小説だと述べていますが、小説の新人賞の周辺の出来事を痛快に描いた一作です。
『お勝手太平記』江國香織がすすめる“読む麻薬” 初老の女性の手になる意地悪な手紙文

https://www.amazon.co.jp/dp/4163900977/
60代のアキコさんなる人物が、日々のよしなしごとについて、方々の友人へ手紙を書き送る、その書簡を収録した小説です。
私たちの世代の女の人が大好きな、あの、絵手紙なの。あれって、描いてあるのが、スイカだろうとトマトだろうと、(中略)、孫の作ったおにぎりだろうと、あの絵手紙の主題は「見て、見て! あたしが描いたのよ。ど? いい感じでしょ? 絵は下手でも、人生の幸福とか豊かさにあふれててさ」という唯一の単調な主題につきるのです。(中略)ああいうものは、相手を選んで出さなきゃ駄目だわねせっかくの豊かな感性と幸福の力作を鷹揚に理解してくださる方にね。
雑誌の著名文化人のアンケートなんかでね、時々、「私の嫌いな言葉」とかさ「使いたくない言葉」なんての、やるじゃないの。そういう時に、今頃、事新しいかのように「生きざま」なんて答える文化人がいてさ、これって、もう何十年も前から、ある種の著述家たちに毛嫌いされて滅多に眼にすることのなくなった、いわば死語化した言葉だと思うのに、まだ例にあげる人がいる(中略)近頃、よく見聞きするのが、ボランティアが園児相手にやるという絵本の〈読みきかせ〉と〈気づき〉じゃありませんか?
「読み聞かせ」、「気づき」の他にも、「(文章を)綴る」という言葉も自分では使わないというアキコさん。文法がどうのというわけではなく、ただ「やな言葉」だという感覚が理解できる読者は、アキコさんの良き文通相手になれるでしょう。
ところで、前述の「生きざま」という言葉を嫌った著述家に『日本語八つ当たり』というエッセイでも知られる江國滋がいますが、その娘で直木賞作家の江國香織は、本作を「読む麻薬」と評しています(丸善ジュンク堂オンラインコンテンツ 金井美恵子トークイベント「アキコさんは私だ⁉」より)。確かに、アキコさんの言うところの「超オールドミス的皮肉屋ぶり」な文章は、読んでいるとついにんまりしてしまう中毒性があります。例えば、老年男性が、今時100円ショップでいくらでもメモ帖が売っているのに、広告の裏紙でメモ帳を作るのは、エコか暇人か、とか、娘を持つ高齢女性は、娘婿が自分の夫より出世が早いのが自慢の種だとか、正月のおせち料理はちっとも好きではなかったのに、高齢の母に気を遣って用意していたのを、母が認知症になり、こんなもの全然好きじゃなかった、と言い出し、もっと早く言ってほしかった、とか……。
これもアキコさんの言によれば、「こまやかな事を大切にする批評精神にあふれた」1冊です。
『待つこと、忘れること?』食と文学は不可分か。食文化をめぐる、甘辛エッセイ

https://www.amazon.co.jp/dp/4582831176/
この作品は、日々の料理や思い出の味、文学・映画における食のシーンの考察などについてのエッセイを収録しています。
例えば、「トマトの具」という一編。著者は、ある雑誌の、離婚のきっかけという特集で、「味噌汁の実にトマト、生活レベルの差が破局を」という記事を目にします。田舎で育った女性が都会の裕福な男性と結婚し、彼女にとっては夏の定番の味噌汁を作ったところ、夫の同居家族は誰も口をつけなかった、という内容です。
お味噌にトマトはあわない、というのかなあ、成金の馬鹿家族は、と考えているうちに、ひらめいたのが、その頃の夏(今もですけど)、すっかり気に入って何度も作っては食べた冷し汁のことでした。(中略)そこに、サイの目に切ったトマトを加えてみたら、どうだろうか、(中略)と、さっそく試してみたところ、冷し汁にトマトの酸っぱさと甘さがぴったり調和して、それ以来、冷し汁にトマトは絶対、欠かせません。(中略)というわけで、人間は偏見にとらわれてはいけませんね。
ちなみに、冷し汁とは、すり鉢を使って味噌を冷たい出汁でのばして作るもののことで、冷めた味噌汁のことではないとのことですが、食に対する固定観念のなさと、こまやかな愛情が伝わってきます。
他に、「お茶より映画を」という一編。ある地方都市で開かれる国際映画祭で、高校茶道部の女子たちが、外国人に抹茶をふるまったということについて、
(日本の最高学府の頂点校の総長で映画批評家としても著名な)彼は、お茶を差し出すボランティアの女子高校生たちに、あなたたちはお茶なんか出していないで、映画を見に行きなさい、と言ったそうです。(中略)「茶の湯」というのは、その創造者の堺の大商人、千利休を見てもわかるように、充分な、というより充分以上の金力を持ったうえでなければ、ワビとかサビといって教養を床しく見せようにも様にならない、というのが原則です。(中略)ですから、お金持ちの家に生れなかった魅力的な若い娘は、あるいはお金持ちに生れても、古来、外側のモードよりも中味(頭であれ、肉体であれ)を重要視してきたものです。
と指摘しています。
食にまつわる、読む愉悦に浸れるエッセイ集です。
おわりに
作家が憧れる作家。山田詠美は金井美恵子をそう評しています(『吉祥寺ドリーミン』より)。事実、芥川賞選考委員の川上弘美は、若い頃、「本が好きなら金井美恵子は読まなきゃ」と人に勧められて読んだと言い(『文學界』2022年6月号より)、芥川賞作家の朝吹真理子は十代の頃から愛読したと述べています(『早稲田文学2018年春号 特集:金井美恵子なんかこわくない』より)。コアな文学ファンにとっては必読の作家といえるでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2022/06/15)

