【カルト飯からLAのファストフードまで】“ローカルな食”を知ることができるノンフィクション3選

マフィアが宴席で楽しむ豪華な食事や、被差別部落のみで長らく食べられてきた絶品料理。はたまた、LAのローカルなスーパーのサラダ……など、世界には、ある地域やあるコミュニティの中だけでしか食べられていない、知られざる“食”がさまざま存在します。そんな“ローカルフード”に焦点を当てたエッセイを3作品ご紹介します。
ローカルフード、という言葉を聞いて皆さんが最初に抱くのは、どんなイメージでしょうか。それは実家の定番料理や故郷の居酒屋の名物料理、あるいは観光旅行先で食べた屋台の料理といった、思わず舌なめずりをしてしまいそうになる食事かもしれません。
しかし、世界の知られざる地域や普段あまりメディアにスポットが当てられることのない地域には、本当の意味で“ローカル”な食が眠っているのです。今回は、そんなローカルフード、限られた人々だけが食べているものにフォーカスしたノンフィクション本を、3冊ご紹介します。
『LAフード・ダイアリー』
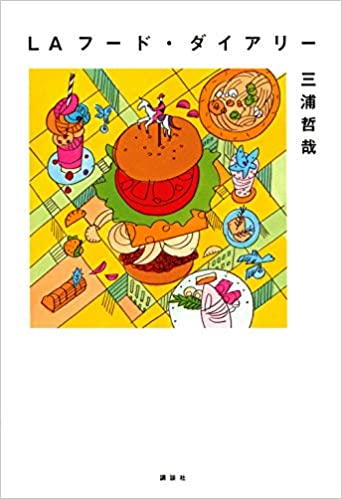
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/406522134X/
『LAフード・ダイアリー』は、映画研究家の三浦哲哉による、1年間のロサンゼルス滞在記です。
三浦は教員として働く日本の大学のサバティカル(研究のための長期休暇制度)を利用し、2019年春から2020年の春にかけて、妻とふたりの幼い子どもたちを連れLAに拠点を移しました。南カリフォルニア大学で映画の研究をする傍ら、三浦はいつの間にか研究と同じくらい、LAの食について知見を深めることにも夢中になったと言います。本書では、三浦がLAで日常的にしていた自炊のメニューやレストランでの食事、ファストフード、知人の家で振る舞われた食事、あるいは料理研究家による本のレビュー──などさまざまな側面から、LAの食が紐解かれていきます。
「スロー対ファスト」とか「オーセンティック対リミックス」というような、私自身これまで少なからず囚われてきた対立構図がある。LAの食には、それを軽々と超える自由闊達な生命力があるようにも思えた。「多様性」とは何か、それをいまどう擁護しうるか。こんにち最も切迫したこの問いに対する貴重なヒントを、私はここでいくつも得ることになる。
と語る通り、LAの食には既存の“アメリカっぽい食”というイメージではくくりきれない自由さや奥深さがあるようです。たとえば、自社開発の製品を中心に近年勢いを増しつつあるというスーパーマーケット、トレイダー・ジョーズのサラダに三浦はまず感激します。
サラダは大きな棚に常時十種類近く置かれている。基本的にどれもハズレがなく、たとえば「サウスウェスト・サラダ」なども印象的なおいしさだった。各種の葉物野菜の上にブラックビーンズの水煮、刻んだトマトとアボカド、カリカリのトルティーヤチップスが載っていて、「タンジー・ランチ・ドレッシング」をかける。tangyは、つんとした、ranchは農場風のという意味で燻製のフレーバーが食欲を掻き立てる。油と酢を乳化させたこのドレッシングが、野菜と豆の瑞々しさを際立たせている。スーパーやコンビニのサラダパックにありがちな異臭のしない、全般に清々しい風味で、爽やかな液体を飲むような心地である。
三浦による鮮やかかつわかりやすい食のレポートは、単なるローカルフード論に留まらず、なぜLAではさまざまなバックグラウンドを持つ多様な食が生まれ、それが独自の形で進化を遂げているのかという文化論や映画論にまで膨らんでいきます。中でも、LA住民から愛されつつ2018年に亡くなったベテランの料理評論家、ジョナサン・ゴールドの料理批評をめぐる論考と食体験は、LAの食事の歴史的背景とともに2020年代のリアルなLAフードを知ることのできる、貴重かつ非常におもしろい記録です。
『ハイパーハードボイルドグルメリポート』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4022516747/
テレビ東京系列で2017年から不定期番組として放送され、いまや大人気コンテンツとなった『ハイパーハードボイルドグルメリポート』。本書は、シリーズ企画、演出、ロケ、撮影、編集までをひとりで担っているディレクター・上出遼平が自ら番組を書籍化した1冊です。
本書の「まえがき」にはこうあります。
「ヤバい世界のヤバい奴らは何食ってんだ?」
番組の掲げる旗印はたった一つ。普通は踏み込めないようなヤバい世界に突っ込んで、そこに生きる人々の飯を撮りに行く。いかにも粗暴、いかにも俗悪。
しかし、実際に見たヤバい奴らの食卓は、ヤバいくらいの美しさに満ちていた。
食卓には、文化、宗教、経済、地理、気候、生い立ち、性格その他人間を取り巻く有象無象が現れる。食は多種多様な「生活」の写し鏡だ。それなのに、食い物を口に放り込んだらそこには万国共通の表情がある。至福。安堵。希望。時に絶望。
“グルメリポート”の名前を冠していますが、本書で仔細に綴られるのは食事にまつわる話だけではなく、情勢の安定しない国々や閉鎖的なコミュニティの中で暮らす人々の生活や人間関係、また、数々の修羅場をくぐり抜けてきた上出による命がけの取材交渉術です。いちテレビ番組からスタートした企画とは信じられないほど濃厚で危険な取材を通じ、内戦が続いたリベリアの旧墓地に住む人々の食事や台湾のマフィアたちの宴会、ロシアのカルト宗教内の食事などが浮かび上がってきます。
中でも壮絶なのが、リベリアの元少年兵たちの食事にスポットを当てた1章目。元少年兵のギャングたちが住むアジトに車を走らせた上出は、レーガンという名のリーダーに出会い、彼らがかつて内戦時に“人食い”をしていたという話の真相を聞き出すためにレストランで食事を奢ります。
「何か食べたいものあります?」と聞くと「キャッサバの葉か…いや、ペッパースープが食いたいな。風邪気味だから。あとは米。米はもう1週間食ってない」と答えた。
アーメッドの案内でペッパースープを出す店に入る。胡椒の効いたスープが出てくるのかと思いきや、供されたのは唐辛子が効いた唐辛子スープだった。確かに汗がたくさん出るから調子の悪い体にはよさそうだ。
内戦の実情についてはさまざまなことを語るものの、“人食い”については言葉数が少なくなるレーガン。カメラ抜きで廃墟に場所を移すとようやく、こんな話を語り始めます。
「前線に出る時、俺たちはいつも呪術師(ドクター)の助言を求めに行った」
レーガンは重い口を開いた。
「彼は俺たちに指示を与える。例えば子どもの眼球を1対持ってこいと。それで俺はバラックの子どもを拐って首をはね、目玉をくり抜いてドクターに渡した。ドクターはふたつの目玉を一旦水に浮かべ、再び持ち上げて俺の目にその雫を垂らした。もう一度、今度は口に垂らされて、俺はその雫を飲み込んだ」
そのときに得た呪術的な力によって自分はいまも生き残っている、と彼は言うのです。上出はこの日の取材を終えた夜、正義というものの正体が心底わからなくなり、眠れなくなったと綴ります。
“グルメリポート”としてはもちろん、それだけではない異国や異文化のリアルを知ることができるノンフィクションとしても、本書は稀有な作品です。
『被差別のグルメ』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B01DK63FBG/
『被差別のグルメ』は、ノンフィクション作家の上原善広による、“被差別部落の食事”に焦点を当てた1冊です。本書の前書きで、「おふくろの味」、「故郷の味」といったポジティブな意味合いで使用されることの多い“ソウルフード”という言葉について、上原はこんな衝撃的な事実を述べます。
一九七〇年代、ある女性が路地から引っ越して、出自を隠して、一般男性と結婚した。彼女は徹底的に路地という出自を隠し、やがて子ももうけた。しかし、彼女は幼い頃から慣れ親しんだ食文化だけは隠しきれなかった。
煮物にアブラカスやホルモンを入れる。
サイボシを買ってきては食卓に出す。
アブラカスは牛の腸を炒り揚げたもので、サイボシは馬肉の燻製のことだ。いずれも路地でしか食べられていない。
そんな、今まで見たこともない食事を出された夫は、やがて彼女の出自を知ることとなり、彼女は夫やその親戚から執拗なイジメに遭い、結局、無理やりに離縁させられたという話だ。
「本物のソウルフード」とは、先に記したように、それを出すだけで“離婚沙汰”になる恐れがあるほど、苛烈なのだ。
慣れ親しんだ食文化が人のバックグラウンドを残酷にも明るみにし、それが原因で再生産される差別がある──。あまりに悲しく切実なことですが、上原はさらに、そのような“多様な食”の存在そのものが、(差別は存在しないと言い張るマジョリティたちによって)隠蔽されることに警鐘を鳴らします。差別をする人々にとっては“今まで見たこともない食事”であっても、被差別者たちにとってそれは実際に“ソウルフード”であり、愛着や懐かしさを覚える味であることは間違いありません。上原は本書を通じ、そのような“日本の正しいソウルフード”を紐解いていこうとします。
路地生活者がしていた上記のような食事のほかにも、アイヌの人々による鹿肉料理や団子、在日韓国人の人々による焼肉料理などにスポットが当てられ、それらの食の歴史的背景や実際の味わいが詳細に描かれます。それらはやがて差別史というマイナスのイメージを超え、限られたコミュニティの中でしか食べることのできない、とっておきの食事のレポートへと変化を遂げていきます。
本書は日本の被差別地域出身の人々の暮らしや境遇のリアルを伝える貴重な1冊であるとともに、丁寧な文化的・歴史的解説を踏まえた上で垂涎もののグルメの数々を読者に教えてくれる、傑作ノンフィクションです。
おわりに
私たちは生きようとする限り、“食べること”から逃れられません。だからこそ“食”はいつでも、それがよい思い出に結びつくものにせよそうでないにせよ、人々の生活と文化、歴史を饒舌に伝えるものです。
今回ご紹介した3冊のノンフィクションはそれぞれLA、危険とされる辺境の地、被差別地域というまったく違った場所とコミュニティに焦点を当てたものでありながら、著者がその地域の人々に丁寧におこなうインタビューや実食レポートからは、食を楽しむことの贅沢さや、馴染み深いものを食べられることの安心感が共通して伝わってきます。文化論としても食エッセイとしてもそれぞれに味わい深い3冊を、ぜひ読み比べてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/06/07)

