【映画化記念】名作SF小説『夏への扉』、原作の3つの魅力

2021年に公開される映画『夏への扉 -キミのいる未来へ-』。本作の原作は、ロバート・A・ハインラインによる名作小説『夏への扉』です。時代を越えて多くの人々に愛され続けている本作の魅力を、詳しいあらすじとともにご紹介します。
ロバート・A・ハインラインによるSF小説『夏への扉』が、三木孝浩監督・山崎賢人主演で『夏への扉 -キミのいる未来へ-』として映画化され、公開前から早くも話題を呼んでいます(※新型コロナウイルスの流行による影響を受け、現在公開延期中)。
原作は、1956年に発表された長編小説。タイムトラベル小説の名作として世界中で支持される本作は、SFファンのみならず、ジュブナイル小説や恋愛小説好きの読み手からも半世紀以上にわたって愛され続けてきました。
今回は、そんな『夏への扉』の原作小説に焦点を当て、作品のあらすじと魅力をたっぷりご紹介します。
『夏への扉』のあらすじ
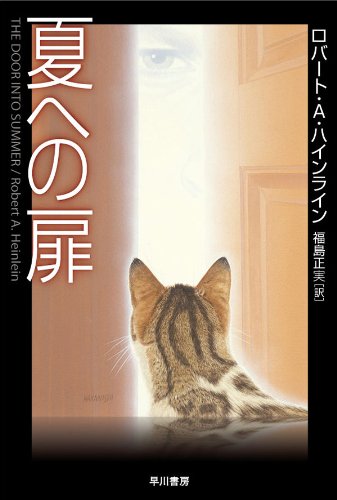
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/415011742X/
本書は、天才発明家であるダニエル(ダン)とその愛猫・護民官ペトロニウス(ピート)を主人公とする物語です。
1970年の冬、ダンは絶望の只中にいました。それまで、家事用ロボット「文化女中器(ハイヤード・ガール)」を始めとする多数のガジェットを発明し、親友であるマイルズとそれらの発明品を売るための会社を興して成功への階段を上りつつあったダンでしたが、ある日、マイルズと新商品の開発・販売にまつわる会社の方針をめぐって対立。その際、会社の秘書でダンの婚約者でもあったベルという女性がマイルズの肩を持ったことをきっかけに、ダンはベルに騙されていたと初めて気づきます。
運悪く、結婚のお祝いと称し、エンゲージリングの代わりに会社の株式の一部をベルに譲渡してしまっていたダン。事業規模の拡大のために財閥の傘下に入るともに、ダンが地道に作ってきた発明品の大量生産を始めるというマイルズの提案は、マイルズとベルふたりの賛成によって決定づけられてしまいました。その決定を到底飲み込むことができなかったダンは、会社を追い出され、仕事と婚約者を同時に失ってしまいます。
意気消沈したダンは、相棒のピートとともに、当時実用化され始めた冷凍睡眠(コールドスリープ)につき、30年後に目覚めることを思いつきます。しかし、冷凍睡眠につく直前、失恋以来毎日欠かすことのできなかったアルコールを抜き、素面になって考え直してみたことで、30年も眠るよりも、いますぐにマイルズとベルに復讐すべきではないか──と考えを改めるのです。
マイルズとベルに面会すると、なんとふたりは結婚したばかりだとダンに言い放ちます。ダンに罵詈雑言を浴びせられ、頭に血が上ったベルは、ダンに麻薬を注射。ダンはそのまま自分の意に反して冷凍睡眠に送られることとなり、ピートは行方不明になってしまいます。
それから30年後の2000年。目を覚ましたダンは、自分が冷凍睡眠に入る前に資産を預けていた保険会社が、倒産してしまっていたことを知ります。無一文になってしまったダンは就職先を探すと同時に、マイルズの義理の娘であり、30年前にも自分を慕ってくれていた心優しい少女・リッキィの行方を追おうとするのです──。
【『夏への扉』の魅力その①】“近未来”の描写の鮮やかさ

アイザック・アシモフ、アーサー・C・クラークと並び、世界SF界のビッグスリーとも呼ばれたアメリカの作家、ロバート・A・ハインライン。彼の手によって本作が書かれたのは、1956年のことです。つまり、ダンにとっての“現在”である1970年も、ダンが冷凍睡眠で送り込まれた2000年も、ハインラインにとっては近未来でした。
1970年のシーンでは、ダンがエンジニアとして開発したさまざまな発明品の詳細が描写されます。たとえば、ダンの代表作でもあるロボット掃除機「文化女中器」は、このように描かれています。
文化女中器は(もちろん、これはのちにぼくが改良を加え完成したセミ・ロボット型でなく、市販第一号時代のである)どんな床でも、二十四時間、人間の手をわずらわせずに掃除する能力を持っていた。そしておよそ世の中には、掃除しなくてよい床など、あるはずがないのだ。
文化女中器は、一種の記憶装置の働きで、時に応じてあるいは掃き、あるいは拭き、あるいは真空掃除器とおなじように塵埃を吸収し、場合によっては磨くこともする。そして、空気銃のB・B弾以上の大きさのものがあれば、これを拾いあげて上部に備えつけた受け皿の中に置き、あとで、彼らよりいくらか頭のよい人間様に、捨ててよいかどうかを判断してもらうこともできるのだ。こうして、文化女中器は一日二十四時間、静かに汚れを求めて歩く。曲がり角であろうとどこだろうと、塵ひとつ見落とさず、すでにきれいになっている床は素通りして、一刻も休まず汚れた床を求めてまわるのだ。
「文化女中器」にまつわる描写は、現代で言うルンバのようなロボット掃除機の特徴とほぼ一致することに驚かされます。また、ダンが冷凍睡眠で送り込まれた2000年のシーンでは、
新聞は、三十年以前とそう変わっていないように見えた。少なくとも体裁は似ていた。この新聞はタブロイド型で、用紙は昔のラフなパルプ用紙ではなく、つや出しのアート紙で、写真は多色刷りか、さもなければ黒白の実体写真になっている。(中略)
しばらくのあいだぼくは第一面しか読めないのかと思っていた。どうやって新聞の裏を返していいものやら見当がつかなかったのだ。どう見ても、新聞はぴたりと書架に張りついて動かないように見えた。
ところが、偶然にぼくの手が新聞の右下の端にふれたとたんに、新聞の表面が、その端を起点にして、いきなりくるくると巻きあがり、次のページを読むのに邪魔にならないように縮んでしまったではないか。ここに触るごとに、ページはいくらでもめくれるのだった。
といった、新聞にまつわるユニークな描写も見られます。ハインラインが想像した2000年には、新聞紙の紙は紙のままでありつつ、Kindleのような読書用のデバイスも彷彿とさせる物体に進化していたようです。
上記のようなガジェットにまつわる描写のひとつひとつにオリジナリティがあり、非常に先見性にも富んでいるのが本書の大きな魅力のひとつ。しかしながら、冷凍睡眠から目覚めたダンが最初に医師に尋ねるのが「先生、映画館のロビーには、まだポップコーン自動販売機が置いてありますか?」というとぼけた質問であることも、ダンという人物のシニカルで人間らしいキャラクターや本書を貫くユーモアをよく表しており、クスッと笑ってしまうポイントです。
【『夏への扉』の魅力その②】ダンの愛猫・ピートの愛らしさ

「猫SF」とも呼ばれることの多い『夏への扉』。ハインラインが“世のすべての猫好きにこの本を捧げる”と序文で記していることからもわかるように、本書の中の猫にまつわる描写は、猫好きであればつい満足して微笑んでしまうものばかりです。
ダンの相棒であるピートは、当然ですが人間語を話しません。しかしダンとピートはお互いのことを誰よりも理解し合っており、
「ウエアーア」
「落ち着くんだ、ピート」
「ナーオウ」
「何をいうか。我慢するんだ。首を引っこめろ、ウェイターが来る」
といったやりとりが、随所で繰り広げられます。作中でダンはピートのことを“我儘無類の猫”と表現しますが、実際には誰よりもピートのことを深く愛しているのは明白なのです。たとえば、実は猫嫌いのベルが、猫好きのふりをしてピートを抱き上げようとするシーン。機嫌を損ねたピートは、ベルの手を引っかいて逃げてしまいます。そんなベルにヨードチンキを塗りながら、ダンは言うのです。
「……しかし、きみのかわいがりかたは、犬のかわいがりかたで、猫のじゃなかったんだよ。猫の場合はたたいたりしちゃ絶対だめだ。なでてやらなきゃいけないんだよ。それに猫の爪の届く範囲で、急激な動作をしてもいけない──つまり、こっちがこれからなにをするかを、猫に理解するチャンスをまず与えてやらなくちゃいけないんだ。しかも、猫がこっちの愛撫を望んでいるかどうかが問題だ。望んでもいない愛撫を与えようとすると、つまりそれは、いささか礼儀にはずれたことになる。猫はとても礼儀を重んずる動物だからね」といってぼくはためらった。「ベル、きみは猫は嫌いなんだろ?」
この言葉に大いに頷く猫の飼い主は、非常に多いのではないでしょうか。
また、ダンは、
なぜそんな面倒な動物をチヤホヤするのだと訊かれたら、ぼくには、なんとも答えようがない。(中略)にもかかわらずぼくは、眠りこんでいる小猫をおこさないために、高価な袖を切り捨てたという昔の中国の官吏の話に、心の底から同感するのである。
ともはっきりと言い切っています。
本書の中で、ピートはダンを救うのに非常に重要な役割を果たします。さらに、ダンに協力し、彼を愛してくれる人たちもまた、猫好きの人間ばかりなのです。猫を毛嫌いし迫害しようとする人間は凋落していき、猫好きはハッピーになれるという、ある種(猫にとっての)勧善懲悪ものである点も、本書のチャーミングなところです。
【『夏への扉』の魅力その③】「SFの鬼」福島正実の名訳
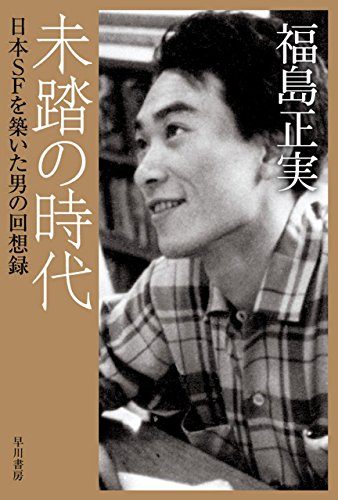
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4152031387/
『夏への扉』を最初に訳し、1957年に日本で紹介したのは、編集者・SF作家の福島正実。福島は初代『S-Fマガジン』編集長としても活躍した人物で、当時はまだ日本で“少年や少女のためのもの”“荒唐無稽な大衆小説”とされることの多かったSFの地位を引き上げた立役者です。
彼は1950年代当時、「SFに手を出すと出版社は潰れる」と周囲から忠告されながらも、SFを日本に定着させるべく奔走しました。福島は、SFが日本で流行しない原因のひとつには粗末な翻訳がある、と自身の回想録の中で述べています。
挫折の原因として見逃せないのは、元々社版のSFの翻訳の、あまりのお粗末さです。じっさい、ある程度以上の評判になり、二十冊も連続刊行された海外小説シリーズで、およそこれほどの誤訳悪訳珍訳ぞろいの欠陥翻訳を並べたものは、他に類をみなかったといっていい。(中略)
SF用語は無造作に一般用語に置き換えられ(たとえばある本ではray-gunがピストルとair carが車と訳されたため「ピストルで足もとをなぎはら」ったり「車が市の上空を旋回」したりすることになった)天文学、物理学、生物学用語には通りいっぺんの訳語があてがわれ、その結果、意味も通りにくい文章ができ上るというていたらくとなった。
──『未踏の時代 日本SFを築いた男の回想録』より
強い口調で粗末な翻訳者を非難する福島。彼は「SFの鬼」と呼ばれるほどにSFに情熱を注ぎ続けた人物で、その科学的知識や海外SF作品への造詣の深さはもちろん、詩情あふれる名訳を生み出せる翻訳者でもありました。
『夏への扉』の冒頭は、ダンの家には11もの扉があり、冬、雪が苦手なピートはダンにその扉をひとつずつ開けてまわるようにせがんだ──というエピソードから始まります。
彼は、その人間用のドアの、少なくともどれかひとつが、夏に通じているという固い信念を持っていたのである。これは、彼がこの欲求を起こすたびに、ぼくが十一ヵ所のドアをひとつずつ彼についてまわって、彼が納得するまでドアをあけておき、さらに次のドアを試みるという巡礼の旅を続けなければならないことを意味する。そしてひとつ失望の重なるごとに、彼はぼくの天気管理の不手際さに咽喉を鳴らすのだった。
この文章を読むだけでも、福島の訳の美しさが伝わるのではないでしょうか。本書が日本で熱狂的に支持され続けている一因には、間違いなく彼の名訳があると言えます。
おわりに
『夏への扉』は、冷凍睡眠を利用したタイムトラベルや、パラドックスを起こさずに過去の自分をいかに救うかといったSF小説の王道とも言うべきテーマを背負いながらも、「ロマンチックな青春小説」「ジュブナイル小説」とも形容されることの多い作品です。中には、本格SFと呼べないという理由で本作を評価しない評論家もいますが、訳者である福島正実は、かつてSFというものについてこのように語ったことがあります。
SFは、本来的に、科学的であるよりも、ロマンチックで、空想的で、思索的であるべきはずなのである。
その意味からいって、SFには、もともと変格も本格もないのである。SFの領域は、幻想文学と哲学とに境を接する、大きな広いスペースにわたっているはずなのだ。
──『未踏の時代 日本SFを築いた男の回想録』より
この福島の定義に則れば、『夏への扉』はまさに“本来的”なSFと言えるのではないでしょうか。ダンやピートといった癖のあるキャラクターや、ご都合主義とも呼べるような幸福感のある展開が肌に合わない方もいるかもしれませんが、冒頭の数ページを読んでぐっときた方は、必ずや本書の虜になるはずです。まだ本書を手にとったことがない方はぜひ、ダン、そしてピートとともに、ロマンチックな時間旅行を楽しんでみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/02/02)

