【芥川賞候補作『母影』ほか】尾崎世界観のおすすめ作品3選

小説『母影』が第164回芥川賞の候補作にも選ばれた、尾崎世界観。ロックバンド・クリープハイプのフロントマンとして活躍する傍ら、小説やエッセイ作品などを精力的に発表し続けています。今回は、そんな尾崎世界観のおすすめの作品とその読みどころをご紹介します。
ロックバンド・クリープハイプのボーカルとして人気を集めるとともに、半自伝的小説『祐介』や数々のエッセイを発表し、書き手としても注目を浴びている尾崎世界観。2020年に発表した短編小説『母影』は、第164回の芥川賞候補作となったことでも話題を呼びました。
言葉遊びや押韻を多用した詩情あふれる表現や、怒りや苦しみ、情けなさといった生々しい心情をさらけ出す作風がその大きな魅力です。今回は、最新作『母影』を中心に、尾崎世界観のおすすめの文章作品を3作品ご紹介します。
芥川賞候補作。母親と娘のいびつな関係を繊細な筆致で描く『母影』
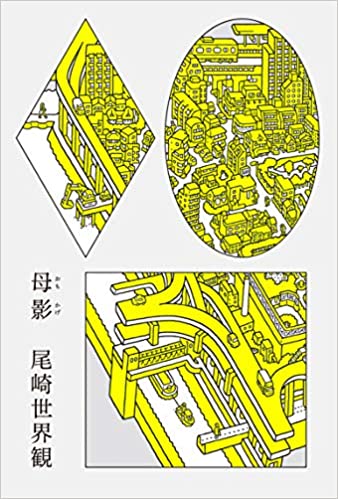
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103521422/
『母影』は、尾崎世界観が2020年に発表した短編小説です。本作は第164回芥川賞の候補作にも選ばれ、話題を呼びました。
本作の主人公は、小学生の「私」。「私」は母親とふたり暮らしをしており、学校が終わると決まって母親が勤務するマッサージ店を訪れます。「私」はそのマッサージ店でいつも、客に施術をしている母親の姿をカーテン越しに見ながら学校の宿題をしていました。しかしあるときから、母親がなにか後ろめたいことをしているのではないか、と「私」は気づき始めます。
私はわかった。二人はカーテンの向こうで恥ずかしいことをしてる。私が今いちばん恥ずかしいのはウンコをすることだけど、きっとそれよりもっと恥ずかしいことだ。でもそれが何かわからないから、耳から無限に恥ずかしいが入ってきた。早くお母さんの恥ずかしいを止めないと、お母さんがお母さんじゃなくなっちゃいそうだ。
「私」はその後ろめたさの正体を掴めないまま、母親が得体の知れないものに変わっていってしまうような恐怖を感じています。「私」は、“これからお母さんをなんてよべばいいんだろう”と葛藤します。
私がまだお母さんをママってよんでたころ、お母さんはただの丸い玉だった。その玉の近くにいるだけでうれしかったし、その玉にさわると安心した。(中略)だけど私が大きくなるのといっしょに、ママの形もだんだん変わってきた。ただの丸じゃなくなったから、もうそれをママってよぶのはおかしいと思った。だから、私がはじめてお母さんをお母さんってよんだとき、お母さんはやっと今のお母さんの形になった。でも、お母さんがカーテンの向こうでお客さんといるとき、お母さんはもうお母さんの形をしてないのかもしれない。もしそうだったら、私はこれからお母さんをなんてよべばいいんだろう。
母親の変化をどのように捉えればいいのかわからなかった「私」は、本作の終盤で、自分と母親をめぐる環境や自分の心境について作文に“書く”ことを決めます。その決断によって、読み書きのうち“読むこと”しか得意ではなかった「私」の世界が広がり、母親と娘のいびつな関係に変化の兆しが訪れるような気配を感じさせて物語は終わります。
カーテン越しの“影”の描写を中心に据えたストーリー構成も巧みですが、本作の最大の魅力は、少女の一人称視点で描かれる詩情豊かな表現の数々です。
きいろい線の先に石だらけの大きな穴ぼこがあって、その中を二本の線が見えなくなるまでのびてる。来るよ。お母さんが見てる遠くの方から、電車の顔がぬっと出てきた。電車はどんどん近づいてきて、キャーッてさけびながらだんだんスピードを落としていった。
擬人化や比喩、押韻を多用した情景描写や台詞のやりとりの端々から、クリープハイプの詞世界を連想する方も多いはず。唯一無二の文体を堪能することのできる1作です。
売れないバンドマンのどうしようもない日々。半自伝的小説『祐介』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163904786/
『祐介』は、尾崎世界観が2016年に発表したデビュー作である半自伝的小説です。タイトルの『祐介』は尾崎世界観の本名であり、本作は、彼がひとりの青年・尾崎祐介からバンドのフロントマン・尾崎世界観になるまでの日々を綴った作品です。
主人公は、スーパーマーケットでアルバイトをしながら、いつか売れてスポットライトを燦々と浴びることを夢見るひとりのバンドマン。理想は大きいものの、実際には彼らのライブには常に数名しか客が来ず、メンバー同士の仲も険悪。主人公は、数少ない女性ファンと投げやりに一夜を共にしたりしては悪態をつくという、どうしようもない日々を送っています。
作中で描かれる主人公の情けなさ、堕落ぶりはあまりにもリアル。ライブハウスのチケット売上ノルマを達成することができず水道が止まったり、切符をなくしたと言い張って電車代をタダにしようとしたり──と、若いバンドマンの鬱屈とした日常が、非常に赤裸々でありながらも、どこかユーモラスに描写されます。
結局バンドはうまくいかなくなり、やがて解散。しかし、京都のライブハウスが主催するライブにひとりで出演することになった主人公に、こんな言葉をかける女性が現れます。
「誰かが言ってたんだけどね、比喩って古くなるんだって。どんなに優れたものでも必ず。時代の中で古くなっていくんだって。あなたの詞は比喩が多いでしょ? 一度聴いただけですぐわかる程に。(中略)素直にまっすぐに、っていうのは基本じゃない? 何をするにしても。だからね、どうしてもそうしたいなら、ある程度音楽でやってから、小説でも書けばいいじゃない。どこかの編集者にそそのかされて勘違いして、好きなだけ比喩を使って、小説でも書けばいいのよ」
物語の終盤、自分だけの世界を追い求めてもがく主人公の姿は、それまでの情けなさや苦しみ、怒りを背負ったままでいながらも、冒頭の人物とはどこか変化しているように見えます。それを成長とは呼べずとも、主人公は前に進むことを決めたのだ、と予感させるような爆発力のあるシーンで本作は幕を下ろします。
荒削りでありながらも、尾崎世界観らしい生々しくえぐみのある表現を味わうことのできる傑作です。
ユーモアたっぷりに日常をさらけ出す。エッセイ集『苦汁100% 濃縮還元』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4167914964/
『苦汁100% 濃縮還元』は、尾崎世界観が2017年に発表したエッセイ集『苦汁100%』に、コロナ禍に襲われた2020年2月の最新日記を書き下ろしとして収録した1冊です。
彼らしい、日常を包み隠さず赤裸々に描く筆致は、本作のなかでも遺憾なく発揮されています。たとえば、小説『祐介』を上梓した2016年の夏の日記には、
舞い上がったまま、いつも通っているあの本屋へ。『祐介』がどこに置かれているかの確認へ。前は3冊、サブカルコーナーにぽつんと置かれていた。でも、テレビや雑誌で何度か取り上げて貰った今なら、きっと。そう信じて見たけれど無い。文芸のコーナーに置いていない。サブカルコーナーを見てみると前よりも増えている。おまけに奥の人気の無い音楽書籍コーナーにも追加で大量に並んでいて、絶対に文芸と認めないという書店側の意地を感じた。
と、思わず笑ってしまいそうになる文章で『祐介』をめぐる書店と著者との攻防が描かれています。
また、ライブ前後の心境を綴った日記のなかでは、
鹿児島でのライブ。屋上に建てたプレハブ小屋のような楽屋。外に出ると室外機だらけで、見渡すと周りはビルだらけ。その隙間から顔を出す桜島。下を覗くと、早めに集まっているお客さんが何人か見えて、どこからか風に乗ってブラスバンドの音が流れてくる。あの曲は『君の瞳に恋してる』だ。
なんか凄く居心地が良い。昨日からずっと気分が良い。リハーサルを終えて、本番。ステージに上がると満員のお客さん。ライブ中、お客さんが勢いよく来てくれるんだけど、嫌な感じが全くない。好きな人に、食べたり飲んだりしている物を「ひと口ちょうだい」と言われるときのような感じ。
と、多幸感あふれる描写が光ります。
書き下ろしとして収録された2020年2月の日記では、予定していたライブが延期・中止になり、やりきれない気持ちを抱えながらも、それでもなんとか前を向こうとしている自身や周囲の人々の様子が嘘偽りのない言葉で書かれています。書き手としてもミュージシャンとしても素顔で世の中を見つめようとする尾崎世界観を知ることができる、必読の1冊です。
おわりに
自身の創作活動の根源には、いまも昔も“怒り”があると尾崎世界観は語っています。
もともと昔から、創作の根源には怒りがあって、今も純度100%であります。
──『母影』発表時の日刊スポーツによるインタビューより
その“怒り”が常に沸点に達し、いままさに吹きこぼれんばかりにぐつぐつと煮えているようなエネルギーが、彼の作品の大きな魅力です。小説、エッセイに限らず、今後も尾崎世界観が発表していく文章作品から目が離せません。
初出:P+D MAGAZINE(2021/01/25)

