詩人・萩原朔太郎の“スゴい詩”4選

「日本近代詩の父」と呼ばれる詩人・萩原朔太郎。『月に吠える』『青猫』といった傑作詩集は読んだことがなくとも、名前を教科書などで聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。今回は、萩原朔太郎の“スゴい詩”を、その背景や鑑賞のポイントとともに紹介します。
生涯を通じて深い孤独や絶望、無力感を抱えながらも、『月に吠える』『青猫』といった傑作詩集を次々と世に出した詩人・萩原朔太郎。大正期、口語による新しい詩の世界を開拓し、近代詩の礎を築き上げた彼は、「日本近代詩の父」とも呼ばれています。
今回は、萩原朔太郎の詩を初めて鑑賞するという方、あるいは萩原の詩にあまり馴染みがない方に向けて、代表的な詩やその魅力が伝わる詩を、背景の解説とあわせて4作品紹介します。
光る地面に竹が生え、青竹が生え──『竹』
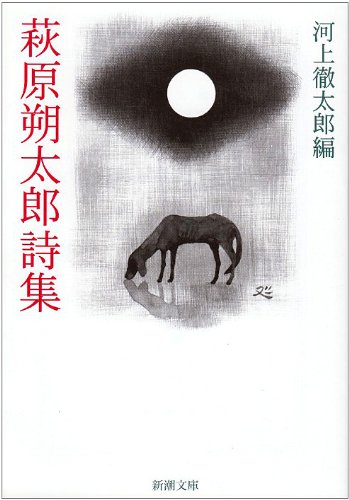
https://www.amazon.co.jp/dp/4101197016/
“光る地面に竹が生え、
青竹が生え、
地下には竹の根が生え、
根がしだいにほそらみ、
根の先より繊毛が生え、
かすかにけぶる繊毛が生え、
かすかにふるえ。かたき地面に竹が生え、
地上にするどく竹が生え、
まつしぐらに竹が生え、
凍れる節節りんりんと、
青空のもとに竹が生え、
竹、竹、竹が生え。”
『竹』は、萩原朔太郎が1917年に発表した第1詩集、『月に吠える』に収録された詩です。それまでの詩の伝統を打ち破り、口語抒情詩の新たな地平を切り拓いた作品として有名な本作を、学生時代に国語の教科書などで目にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
この詩の1連目では地下に伸びる竹の根に目が向けられ、2連目では対照的に、地上から空に向かって伸びる竹に目が向けられています。1連目、地下に伸びる竹の根のイメージは「根がしだいにほそらみ」「かすかにけぶる繊毛」「かすかにふるえ」──などと繊細そのものですが、一方の2連目では、「するどく」「まっしぐらに」「りんりんと」といった言葉から、雄渾で力強い竹の姿が浮かび上がってきます。さらには、幾度も繰り返される「竹(take)」「生え(hae)」といった脚韻が独特のリズムをもたらし、驚くべきスピードで生長していく竹の生命力をも表しているように感じられます。
この詩を発表した当時の萩原は、思春期から続いていた強い精神的苦痛に悩むとともに、キリスト教会に出入りし始め、原罪や贖罪といったテーマについてしばしば考えてもいました。25歳のときに知人に宛てて書いた手紙の中では、
“生を憧憬する心と、生をいとう心とこの二つの矛盾がいつまで私の心で戦をつづけているのであろう、私はいつも明るい方へ明るい方へと手をのばして悶えながらかえってますます暗い谷底へ落ちて行くのである”
と綴っています。この『竹』の1連目と2連目の対比はまさに、「明るい方へ」手を伸ばそうとしながらも地下へ向かって下降していくことを止められない萩原自身の心象が、詩の表現として結晶化したものだったのでしょう。
よせくる、よせくる、このしろき浪の列はさざなみです──『春夜』
“浅蜊のようなもの、
蛤のようなもの、
みじんこのようなもの、
それら生物の身体は砂にうもれ、
どこからともなく、
絹いとのような手が無數に生え、
手のほそい毛が浪のまにまにうごいている。
あわれこの生あたたかい春の夜に、
そよそよと潮みずながれ、
生物の上にみずながれ、
貝るいの舌も、ちらちらとしてもえ哀しげなるに、
とおく渚の方を見わたせば、
ぬれた渚路には、
腰から下のない病人の列があるいている、
ふらりふらりと歩いている。
ああ、それら人間の髪の毛にも、
春の夜のかすみいちめんにふかくかけ、
よせくる、よせくる、
このしろき浪の列はさざなみです。”
『春夜』は『竹』と同じく、萩原の第1詩集『月に吠える』に収録されている詩です。一読して、その妖しげで美しいモチーフの連続にうっとりとしてしまいます。
アサリや蛤といった海の生き物たちが淡い空気の春の海岸で無数にうごめいているという、ややグロテスクでありながらも幻想的なイメージは、詩の半ばで“腰から下のない病人の列”に唐突に接続し、見る者をはっとさせます。しかし、ぬらぬらとうごめく貝類たちと幽霊のような病人たちにはどこか近しい匂いも感じられ、全体として、春の夜のおぼろげな空気が見事に形象化されていると言える詩です。
この詩に出てくるような“腰から下のない病人”のイメージは、同時期の萩原の他の詩にも見られるものです。萩原は『内部に居る人が畸形な病人に見える理由』という詩の中でも、
“わたしは窓かけのれいすのかげに立って居ります、
それがわたくしの顔をうすぼんやりと見せる理由です。
(中略)
じっさいのところを言えば、
わたくしは健康すぎるぐらいなものです、
それだのに、なんだって君は、そこで私をみつめている。
なんだってそんなに薄気味わるく笑っている。
おお、もちろん、わたくしの腰から下ならば、
そのへんがはっきりしないというのならば、
いくらか馬鹿げた疑問であるが、
もちろん、つまり、この青白い窓の壁にそうて、
家の内部に立っているわけです。”
と、実在感の薄い、幽霊のような「わたし(あるいはわたくし)」を描いています。
萩原の生涯の友でもあった詩人の室生犀星は、『月に吠える』の巻末に付された文章の中で、萩原のこのような詩世界を、“歯痛のごとき苦悶”によって生み出されているものと綴っています。
“これらの詩篇によって物語られた特異な世界と、人間の感覚を極度までに繊細に鋭どく働かしてそこに神経ばかりの仮令へば歯痛のごとき苦悶を最も新らしい表現と形式によったことを皆は認めるであろう。”
室生の言葉通り、萩原の詩世界には常にこの、歯痛のようにきりきりと神経を悩ませる“苦悶”が横たわっていたのです。
およぐひとのからだはななめにのびる───『およぐひと』
“およぐひとのからだはななめにのびる、
二本の手はながくそろえてひきのばされる、
およぐひとの心臓はくらげのようにすきとおる、
およぐひとの瞳はつりがねのひびきをききつつ、
およぐひとのたましいは水のうえの月をみる。”
『およぐひと』は、『月に吠える』に収録された、5行から成る短い詩です。
ひらがなの多用が印象的なこの詩。加えて、繰り返される「およぐひとの」というフレーズ、そして「のびる(nobiru)」「すきとおる(sukitoru)」「ききつつ(kikitsutsu)」という脚韻の効果によって、どこか間延びした、スロー映像のようなイメージが頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。そのイメージは、水泳をする人の手足がゆっくりと水をかきながら前進していく様子に重なります。
詩の前半では「からだ」と「二本の手」に向けられていた視線は、後半で「心臓」「たましい」といった、目に見えないものへと移っていきます。注目すべきは、「およぐひとの瞳はつりがねのひびきをききつつ」というフレーズ。ここで「つりがねのひびき」を聞いているのが耳ではなく「瞳」であることからもわかるように、詩の主体は「つりがねのひびき」を音として聞いてはいません。この人物が水中にいることを考えると、おそらく、周囲は無音であるはずです。それでも、スローに引き伸ばされた動きの中で「瞳」が遠くの音を捉えてしまうという表現からは、萩原らしい、研ぎ澄まされた神経が感じられます。
萩原は、詩歌論『詩の原理』の中で、
“およそ詩的に感じられるすべてのものは、何等か珍しいもの、異常のもの、心の平地に浪を呼び起すところのものであって、現在のありふれた環境に無いもの、即ち「現在してないもの」である。故に吾人はすべて外国に対して詩情を感じ、未知の事物にあこがれ、歴史の過去に詩を思い、そして現に環境している自国やよく知れてるものや、歴史の現代に対して詩を感じない。すべてこれ等の「現在しているもの」は、その現実感の故にプロゼックである。”
と述べています。「現在しているもの」には詩性を感じないという萩原は、だからこそ目の前にあるもの以上の景色を幻視し、その存在を新たな位相で描き出すことができたのでしょう。
かくして蛸は、彼の身体全体を食いつくしてしまった──『死なない蛸』
“或る水族館の水槽で、ひさしい間、飢えた蛸が飼われていた。地下の薄暗い岩の影で、青ざめた玻璃天井の光線が、いつも悲しげに漂っていた。
だれも人人は、その薄暗い水槽を忘れていた。もう久しい以前に、蛸は死んだと思われていた。そして腐った海水だけが、埃っぽい日ざしの中で、いつも硝子窓の槽にたまっていた。
けれども動物は死ななかった。蛸は岩影にかくれて居たのだ。そして彼が目を覚した時、不幸な、忘れられた槽の中で、幾日も幾日も、おそろしい飢饑を忍ばねばならなかった。どこにも餌食がなく、食物が全く尽きてしまった時、彼は自分の足をもいで食った。まずその一本を。それから次の一本を。それから、最後に、それがすっかりおしまいになった時、今度は胴を裏がえして、内臟の一部を食いはじめた。少しずつ他の一部から一部へと。順順に。
かくして蛸は、彼の身体全体を食いつくしてしまった。外皮から、脳髄から、胃袋から。どこもかしこも、すべて残る隈なく。完全に。
或る朝、ふと番人がそこに来た時、水槽の中は空っぽになっていた。曇った埃っぽい硝子の中で、藍色の透き通った潮水と、なよなよした海草とが動いていた。そしてどこの岩の隅隅にも、もはや生物の姿は見えなかった。蛸は実際に、すっかり消滅してしまったのである。
けれども蛸は死ななかった。彼が消えてしまった後ですらも、尚お且つ永遠にそこ(・・)に(・)生きていた。古ぼけた、空っぽの、忘れられた水族館の槽の中で。永遠に──おそらくは幾世紀の間を通じて──或る物すごい欠乏と不満をもった、人の目に見えない動物が生きて居た。”──『死なない蛸』
『死なない蛸』は、萩原が晩年にあたる1939年に発表した自選詩集、『宿命』に収録された1篇です。
水族館の忘れ去られた水槽の中で自らの身体を食い破っていき、しまいには跡形なく消えてしまいながらも、人の目に見えない姿で“永遠にそこに生きていた”という蛸を描くこの詩。グロテスクさと官能性が同居する本作からは、萩原の生涯を貫いていた、ひりひりとした飢餓感や渇望感が見てとれます。
詩集『宿命』は、萩原が過去に発表した詩集の中から複数の散文詩と抒情詩を選出して編んだものですが、それに加え、前半部の末尾では作者による「散文詩自註」というかたちで、詩の制作背景や表現論が書き添えられています。
詩人・フランス文学者の山田兼士は、『宿命』の収録作である『触手ある空間』という詩と「散文詩自註」の双方に注目し、
“『宿命』散文詩群にはショペンハウエルの言葉として「宇宙は意志の表現であり、意志の本質は悩みである」という巻頭言が付されているが、これに詩集表題を重ねて考えれば『宿命』の中心主題が「意志」と「宿命」の葛藤にあることは概ね想像できるだろう。(中略)
二十二年間の詩人生活を振り返り凝縮し意味付けた七十三篇の散文詩は、詩人の宿命とともに詩そのものの宿命──近代日本における自由詩の宿命といってもいい──を最も根源的な層において描き出してもいる。なぜなら、「触手ある空間」とはあらゆる存在へと手を伸ばしながらついに実体に届き得ない〈詩〉の根源的不可能性の喩であるからだ。
──『現代詩手帖』2011年10月 「萩原朔太郎『宿命』再考」より
と評しています。
さらに萩原は「散文詩自註」の中で、自らの詩人としての「宿命」を嘆いてこう綴っています。
“詩人として生れつき、文学をする人の不幸は、心に休息がないということである。(中略。家に居る時も、外に居る時も、読書してる時も、寝そべってる時も、仕事してる時も、怠けている時も、起きてる時も、床にいる時も、夜も昼も休みなく、絶えず何事かを考え、不断に感じ、思い、悩み、心を使ひ続けているのである。眠れない夜の続く枕元に、休息のない水の流れの、夜更けて淙淙という音をきく時、いかに多くの詩人たちが、受難者として生れたところの、自己の宿命を嘆くであろう。”
『宿命』の主題が「意志」と「宿命」のあいだで切り裂かれる詩人の葛藤にあるとするならば、この『死なない蛸』という詩からも、死に抗い、生に執着しようとする意志と、受難者として生まれ、疲弊し続けている心身を休ませてくれる死(=宿命)のあいだでさまよう詩人の心情が、伝わってくるように思えるのではないでしょうか。
おわりに
萩原朔太郎は、生涯にわたって強い孤独と絶望感に悩まされ続けた詩人でした。随筆『僕の孤独癖について』の中では、医者であった父親との確執や強迫観念に襲われ続けた青年期について振り返りながら、自身の孤独についてこう綴っています。
“町へ行くときも、酒を飲むときも、女と遊ぶときも、僕は常にただ一人である。友人と一緒になる場合は、ごく稀れに特別の例外でしかない。多くの人は、仲間と一緒の方を楽しむらしい。ただ僕だけが変人であり、一人の自由と気まま勝手を楽しむのである。だがそれだけまた友が恋しく、稀れに懐かしい友人と逢った時など、恋人のように嬉しく離れがたい。「常に孤独で居る人間は、稀れに逢う友人との会合を、さながら宴会のように嬉しがる」とニイチェが言ってるのは真理である。”
“「孤独は天才の特権だ」といったショーペンハウエルでさえ、夜は淫売婦などを相手にしてしゃべって居たのだ。真の孤独生活ということは、到底人間には出来ないことだ。友人が無ければ、人は犬や鳥とさえ話をするのだ。畢竟人が孤独で居るのは、周囲に自分の理解者が無いからである。天才が孤独で居るのは、その人の生きてる時代に、自己の理解者がないためである。即ちそれは天才の「特権」でなくて「悲劇」である。”
萩原はこの随筆を、最近は大人になり、「次第に常識人の健康を恢復してきた」という言葉で締めくくっていますが、実際には天才の“悲劇”であるところの孤独は終生、萩原を囚えて離さなかったのではないかと思えます。
絶望感や渇望感に満ちながらも、同時に音楽的な軽やかさも感じさせる萩原の詩。教科書で読んだことしかなかったという方もぜひこの機会に、気に入った詩を見つけてみてください。
※参考文献……
・萩原朔太郎『萩原朔太郎全集』(筑摩書房)
・久保忠雄『萩原朔太郎論』(塙書房)
・高橋順子 選『萩原朔太郎 ふらんすへ行きたしと思えどもふらんすはあまりに遠し』(小学館)
初出:P+D MAGAZINE(2022/11/30)

