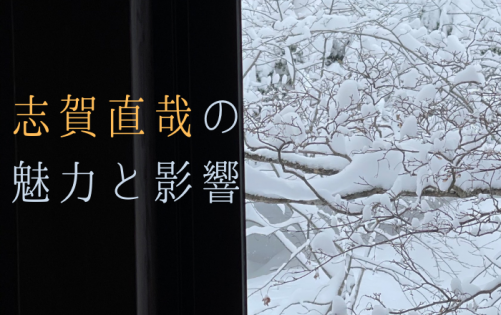【没後50年】小説の神様・志賀直哉って何がスゴいの? その魅力を徹底解説
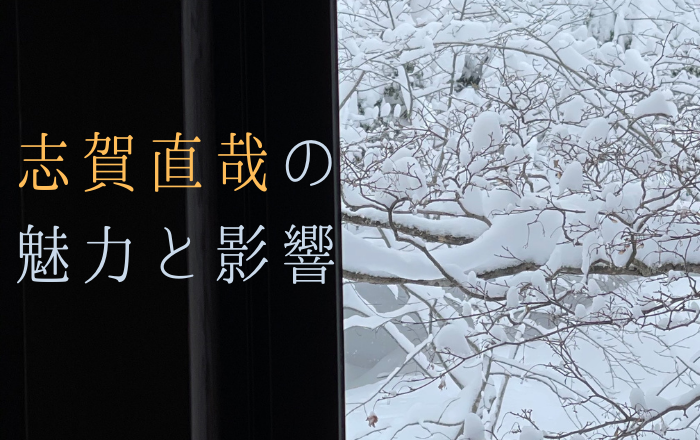
白樺派を代表する作家のひとりで、”小説の神様”とも呼ばれた文豪・志賀直哉。志賀の代表作品のあらすじと読みどころを紹介しつつ、志賀の文章の“スゴい”ポイントを詳細に解説します。
2021年に没後50年を迎える志賀直哉。志賀は白樺派を代表する作家のひとりで、“小説の神様”と呼ばれた文豪です。その平明で簡素かつ写実的な文体は文章のお手本とされることも多く、後世の作家にも多大な影響を与えました。
今回は、そんな志賀直哉の代表作品のあらすじと読みどころを紹介しつつ、志賀の文章の“スゴい”ポイントを詳細に解説していきます。
『城の崎にて』
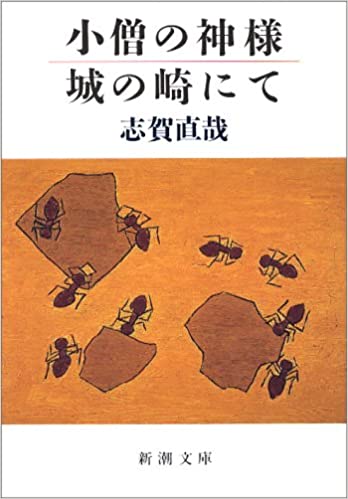
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101030057/
【あらすじ】
1917年、白樺派の同人誌『白樺』にて発表された短編小説・随筆作品。山手線に跳ね飛ばされる交通事故に遭い、兵庫県の城崎温泉にて療養していた志賀直哉自身の経験をもとに書かれている。
事故に遭い、城崎温泉を訪れた「自分」が、生活や散歩のなかで蜂、鼠、イモリという3匹の生き物の死に偶然立ち会い、命拾いした自分の生を省みる。
【ここがスゴい】徹底して無駄のない、“実用的”な描写
のどかな温泉街で療養生活を送っている主人公が、3匹の小さな動物の死を偶然目にしてしまう──。まとめてしまえばたったそれだけの小説ですが、『城の崎にて』は“無類の名文”と評されることの多い作品です。その最大の理由は、なんと言っても志賀の観察眼が遺憾なく発揮された、無駄のない明瞭な文体にあります。
たとえば、「自分」が滞在中の部屋の窓から蜂の巣を眺め、そのなかでせわしなく働いている蜂たちを見つめている場面。
虎斑の大きな肥つた蜂が天気さへよければ朝から暮近くまで毎日忙しさうに働いてゐた。蜂は羽目のあはひから摩抜けて出ると一ト先づ玄関の屋根に下りた。其処で羽根や触覚を前足や後足で丁寧に調べると少し歩きまはる奴もあるが、直ぐ細長い羽根を両方へシツカリと張つてぶーんと飛び立つ。飛び立つと急に早くなつて飛んで行く。
或朝の事、自分は一疋の蜂が屋根で死んで居るのを見つけた。足は腹の下にちぢこまつて、触覚はダラシなく顔へたれ下がつて了つた。他の蜂は一向冷淡だつた。巣の出入りに忙しくその脇を這ひまはるが全く拘泥する様子はなかつた。忙しく立働いてゐる蜂は如何にも生きてゐる物といふ感じを与へた。その脇に一疋、朝も昼も夕も見る度に一つ所に全く動かずに俯向きに転がつてゐるのを見ると、それが又如何にも死んだものといふ感じを与へるのだ。それは見てゐて如何にも静かな感じを与へた。淋しかつた。他の蜂が皆巣に入つて仕舞つた日暮、冷たい瓦の上に一つ残つた死骸を見る事は淋しかつた。
生きている蜂が飛び立つまでの詳細な描写はもちろん、死んだ蜂を見ていて湧き上がってくる「自分」の心境が、非常に細やかに、それでいて無駄なく描かれていることがおわかりいただけると思います。
文豪・谷崎潤一郎は、文章指南本『文章読本』の冒頭で、「文章に実用的・芸術的という区別はないと思う」と自身の見解を述べています。明治時代までは「美文体」という実用から遠く離れた華やかで美しい文章が重宝されることがあったけれど、現代はもはや、生活に密着した、喋り言葉とそう変わらない“実用的”な文章だけで小説を組み立てることができる、と谷崎は言うのです。そして、『城の崎にて』の文章は“実用的”かつ“明瞭”な文章の手本のようだと書いています。
「他の蜂が皆巣に入つて仕舞つた日暮、冷たい瓦の上に一つ残つた死骸を見る事は云々」のところも、普通なら「日が暮れると、他の蜂は皆巣に入ってしまって、その死骸だけが冷たい瓦の上に一つ残っていたが、それを見ると、」と云う風に書きそうなところですが、こんな風に短く引き締め、しかも引き締めたために一層印象がはっきりするように書けている。(中略)簡にして要を得ているのですから、このくらい実用的な文章はありません。
──谷崎潤一郎『文章読本』より
『城の崎にて』は、志賀の文章の最大の特徴である、透徹な目による明晰な描写を堪能することのできる不朽の名作です。
『暗夜行路』
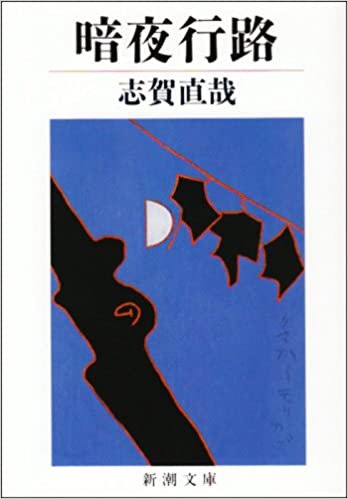
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101030073/
【あらすじ】
雑誌『改造』で1921年から1937年にわたり、断続的に発表された志賀直哉唯一の長編小説。
祖父と母との過失によって生まれ、両親に愛された記憶のない青年・時任謙作を主人公に、彼が妻・直子の不倫といった不幸を背負いながらも人を赦し、強い意志の力で幸福を掴み取ろうとするまでを描く。近代文学の最高峰と呼ばれることもある志賀の代表作。
【ここがスゴい】“無我”の境地に達した、飾り気のない詩情
特に初期における志賀文学の最大のテーマは、“父と子との不和”です。志賀は、実業家として巨万の富を成したものの、金に執着し文学に価値を見出すことのなかった父と長年対立していました。ようやく父と和解を遂げた1917年以降には親子の対立の解消や赦しを描いた作品を続けて発表しており、『暗夜行路』もその系列に属する作品です。
本書の主人公・時任謙作は、心の混迷を深めるたびに、転居を繰り返し、日本全国のさまざまな場所に足を運びます。東京を離れたあとは広島県・尾道に赴き、京都に引っ越し、物語の終盤では鳥取県の大山を訪れます。『城の崎にて』の項でも述べたリアリスティックで明晰な描写は、本書における風景や生き物の描き方にもありありと表れています。
石の上で二匹の蜥蜴が後足で立上ったり、跳ねたり、からまり合ったり、軽快な動作で遊び戯れているのを見、自らも快活な気分になった。
加えて本書では、志賀の透徹なまなざしがさらに洗練され、ある種の“無我”の境地に到達しています。たとえば、謙作が相次ぐ不幸に見舞われ、心身ともに疲れ切ったなかで大山登山をするシーン。
自分の精神も肉体も、今、この大きな自然の中に溶込んで行くのを感じた。その自然というのは芥子粒程に小さい彼を無限の大きさで包んでいる気体のような眼に感ぜられないものであるが、その中に溶けて行く、──それに還元される感じが言葉に表現出来ない程の快さであった
ここで描かれているのは、景色を見ている自己が消失し、風景と一体になってしまったかのような陶酔感です。評論家の小林秀雄は、このような描写は、志賀自身の“見ようとはしないで見ている眼”によって成立していると指摘します。
私に恐ろしいのは決して見ようとはしないで見ている眼である。
物を見るのに、どんな角度から眺めるかという事を必要としない眼、吾々がその眼の視点の自由度を定める事が出来ない態の眼である。志賀氏の全作の底に光る眼はそういう眼なのである。
恐らく氏にとっては、見ようともしない処を、覚えようともしないでまざまざと覚えていたに過ぎない。これは驚くべき事であるが、一層重要な事は、氏の眼が見ようとしないで見ているばかりでなく、見ようとすれば無駄なものを見てしまうという事を心得ているという事だ。氏の視点の自由度は、氏の資質という一自然によってあやまつ事なく定められるのだ。
──小林秀雄『作家の顔』より
どこをどのように切り取って描写すれば文学的になるか──という作為のない、どこまでも“自然”な眼。文豪・芥川龍之介は、この自然な描写の才に加えて、志賀には“東洋的伝統の上に立つた詩的精神”があると述べています。芥川は、自身の随筆のなかで、『暗夜行路』のなかの
彼は然し、女のふっくらとした重味のある乳房を柔かく握ってみて、云いようのない快感を感じた。それは何か値うちのあるものに触れている感じだった。軽く揺すると、気持のいい重さが掌に感ぜられる。それを何と云い現わしていいか分からなかった。
「豊年だ! 豊年だ!」と云った。
そう云いながら、彼は幾度となくそれを揺振った。何か知れなかった。が、兎に角それは彼の空虚を満たして呉れる、何かしら唯一の貴重な物、その象徴として彼には感ぜられるのであった。
という描写を、
ゴム球のやうに張つた女の乳房に「豊年だ。豊年だ」を唄ふことは到底詩人以外に出来るものではない
──芥川龍之介『文芸的な、余りに文芸的な』より
と非常に高く評価しています。
『小僧の神様』
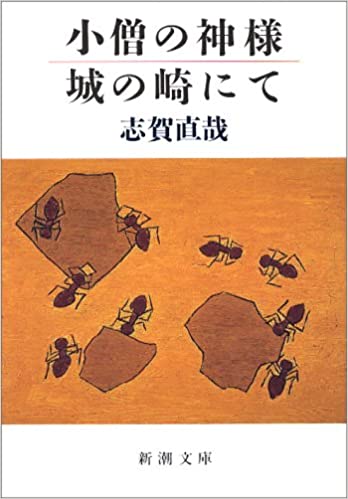
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101030057/
【あらすじ】
1920年、雑誌『白樺』にて発表された短編小説。本作がきっかけで志賀の作家としての知名度は大きく上がり、中心的存在になった。
本作の主人公は、神田の秤屋で奉公をしている仙吉という名前の“小僧”。美味しいという番頭たちの噂を聞いてひとりで屋台の寿司屋に立ち寄ったものの、金が足りずにすごすごと帰ることになった仙吉の姿を見ていた貴族院の男・Aが、後日、秤屋で仙吉に偶然再会し、寿司をおごってやる。Aの正体がわからない仙吉は、彼のことを“神様”ではないか、と考え始める。
【ここがスゴい】あまりにも爽やかな読後感と、道徳的な“純粋さ”
草花や動物や虫や、総じて自然が好きだったが、同じように、人間の生き方としても、自然なのを一番よしとしていた。
うしろに一本強い倫理的なすじが通っているのは事実だが、その倫理性潔癖性が、堅苦しく硬直したかたちで作品の上にあらわれることは、まず無かった。
──阿川弘之『志賀直哉の生活と芸術』より
志賀の生き方や作風をそう評したのは、弟子として彼の生活をいちばん近くで見ていた作家の阿川弘之です。『小僧の神様』は、この“強い倫理性”や“潔癖性”、そして“自然さ”が色濃く表れた作品と言えます。
その傾向を端的に表しているのが、本作の最後の描写です。『小僧の神様』では物語の終盤、“作者”である志賀自身が突如現れ、
実は小僧が「あの客」の本体を確かめたい要求から、番頭に番地と名前を教えて貰って其処を尋ねて行く事を書こうと思った。小僧は此処へ行ってみた。ところが、その番地には人の住いがなくて、小さい稲荷の祠があった。小僧はびっくりした。──とこう云う風に書こうと思った。然しそう書く事は小僧に対し少し惨酷な気がして来た。それ故作者は前の所で擱筆する事にした。
と述べるのです。この風変わりな箇所の意義については評価が分かれるところですが、志賀の倫理観の強さがよく表れている部分であることは間違いありません。近代文学者の高田瑞穂は、本書の解説のなかでこの箇所について、
直哉における美的関心と人間的関心との微妙な関連の暗示である。直哉は美的ではあり得ても耽美派ではなかったのである。
と記しています。芥川も“人生を清潔に生きてゐる作家”と評している(『文芸的な、余りに文芸的な』より)ように、志賀の道徳的な純粋さと人道主義に基づいた人間観を知ることのできる、非常に爽やかな1篇です。
おわりに
志賀の類まれな描写力と鷹揚な人柄は多くの文人に慕われました。芥川龍之介や小林多喜二、阿川弘之といったさまざまな文豪が、志賀による多大な影響を受けていることを公言しています。
また、志賀の文章に惚れ込んだ芥川が、夏目漱石に「どうしたらああいった文章が書けるのか」と尋ねたところ、
「文章を書こうと思わずに、思うまま書くからだろう。おれもああいうのは書けない」
と答えたというエピソードからもわかるように、志賀の作為のない、自然で美しい文章は、文豪たちからも職人芸のように捉えられていました。
志賀の文章にはどれも物語らしい物語がなく、平坦で退屈と称されることも少なくありません。しかし、その無駄のない活き活きとした描写は、読むことの純粋な喜びを読者に呼び起こしてくれます。学生時代に国語の教科書で『小僧の神様』や『清兵衛と瓢箪』を読んだきりという方も、ぜひ、大人になったいまこそ志賀作品に手を伸ばしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/02/22)