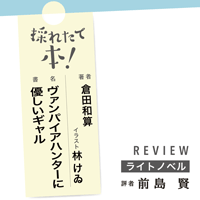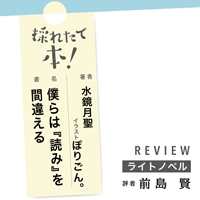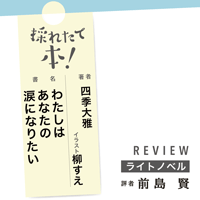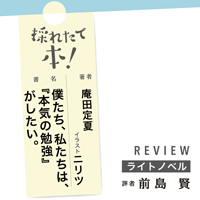採れたて本!【ライトノベル#08】

突然の寒冷化に覆われた世界。神奈川県では9月に降りはじめた雪が浜辺を覆い尽くした。高校生の天城幸久は、たったひとりで別荘に引っ越してきた同級生・真瀬美波と雪かきの手伝いをきっかけに付き合い始めたが、授業さえリモートで行われるような状況では、外出先など軒並み閉鎖されている。それでもふたりは冬にあらがうようにデートを重ねるが、続く異常気象と否応ない社会の変化が若いふたりを翻弄し始める。『冬にそむく』は、そんな冬に閉じ込められた世界の恋人たちを描いた青春小説だ。
著者の石川博品は、架空の共産圏風国家が舞台の異文化交流ラブコメ(?)『耳刈ネルリ御入学万歳万歳万々歳』(ファミ通文庫)で2009年にデビュー。独自の発想と文体を武器にしつつ、地下アイドルがテーマの『メロディ・リリック・アイドル・マジック』(ダッシュエックス文庫)や、VRがテーマの『ボクは再生数、ボクは死』(KADOKAWA)など、しばしば現代的なテーマに取り込んできた作家だ。
本作もまた、突然の「冬」の訪れを、コロナ禍の比喩と読むことは容易だろう。突然のパンデミックにより友達や恋人と過ごすはずの場所と共有するはずだった様々な経験……掛け替えのない十代の時間を突然に奪われ、どこにも行けずに閉じ込められることが、若い世代にとっていかに理不尽で残酷なことだったか。評者は、幸いにも影響が軽微だったせいもあって、本書を読むことで今更ながらにそれを思い知らされた。おそらく登場人物と同世代の読者には、コロナ禍の三年間に抱えていた思いを代弁してくれる一冊になっているのではないか。あるいは、気候変動や天災に翻弄される幼い恋人たちを描いた作品という点においては、『天気の子』などの新海誠作品などと接続することも可能だろう。
しかしながら、そうした現代性・同時代性はもちろんのこと、評者は本書『冬にそむく』を端的に若い恋人たちが冬にそむく小説として読んだ。視点が高校生ということもあって、文中に使われる語彙はあくまで日常的な、素朴と言ってさえいいものだ。そんな等身大の言葉でもって、本書は、若者たちを押し潰そうとする理不尽な世界に向かい合い、克明に描写していく。その真摯な筆致から否応なく伝わってくる、登場人物たちの切実な姿にこそ、評者は強く心を打たれた。
そういう意味で本書は、コロナ禍の表象であると同時に、十代の閉塞感という普遍的な主題を描いた作品になっていると思う。是非ともジャンルや世代を、ひいては時代を超えて読まれてほしい。
〈「STORY BOX」2023年6月号掲載〉