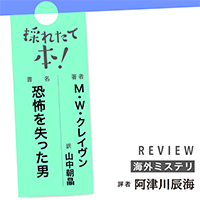採れたて本!【海外ミステリ#22】

フランスの作家、リリア・アセンヌの『透明都市』(早川書房)は、SFや文芸作品の範疇に属すると捉えられる作品だろう。事実、本作は「フランスの高校生が選ぶルノードー賞」を受賞している。しかし、これはミステリ好きもぜひとも読むべき作品である。2022年に刊行されたエルヴェ・ル・テリエ『異常(アノマリー)』を思わせるタイプの作品、と言えば、同作のファンにはリーチするだろうか。
2029年、フランスで新革命が起きた。あるインフルエンサーの男性が性暴力加害者を告発し、さらに、自らの手で殺害したのだ。彼を巻き込んだ騒動は「市民による透明性」運動へと発展、ある建築家が透明な家によって閉じた空間を一掃する構想を立てる。
それから20年が経った2049年、ガラス張りの家が立ち並ぶ相互監視の街で、一家が忽然と姿を消した。一体、どうやって。そして、なぜ? 元警察官のエレーヌ・デュベルヌは、事件の捜査を通じて、自らの社会に疑念を抱くようになるのだが……。
さながら「メアリー・セレスト号事件」を思わせる不気味な人間消失である。といって、ミステリらしく、トリック(ハウダニット)が謎解きのメインになるわけではない。むしろ、なぜ一家は消えてしまったのか、というホワイダニットの部分が肝要な作品といっていいだろう。改行や一行空きを多用してなお、240ページに収めているため、かなり短めの作品だ(この短さや、心理描写のねちっこさが、やはりフランスミステリの特徴だと思う)。手際よく点描されていく街の様子とそこに生きる人々の言動から、ディストピアSF風の気味の悪さがじわじわと漂ってきて、ゾワッとくる。その「ゾワッ」が最高潮に達するのは、恐ろしく、哀しい真相が明かされる瞬間である。異様で不気味な街の姿を描いたからこそ、説得力を持つ真相だろう。
透明なガラス張りの家を受け容れない人々は、別の地区に住んでいるが、そこはスラム街のようになっている、など、本作の設定は多岐にわたっているが、作品の短さゆえか、十全に活かされているとはいいがたい。それでも、本作の設定にリアリティーを感じるのは、本作の設定が、SNSを通じた「怒り」の共有という、とても身近な景色を起点としているからだろう。常に怒りに溢れ、炎上のリスクに怯えるが故軽い皮肉や嫌味も吐けなくなった、窮屈な相互監視のバーチャル空間は、この「透明な都市」と何が違うのか。そう思えるからこそ、本作の真相は物悲しいのだ。あり得ないなんて、決して言い切れないから。
評者=阿津川辰海