聖夜がくるのが怖くなる。クリスマスを舞台にしたホラー小説3選

街が華やぐクリスマスシーズン。この季節になるとどことなく気分が浮かない……、という読書家の方は少なくないのではないでしょうか。今回はそんな方の気分に合わせ、クリスマスがくるのが怖くなるような良質なホラー小説を3作品ご紹介します。
綺麗なイルミネーションや幸せそうな家族・カップルたちの姿で街が華やぐクリスマスシーズン。この時期になるとなんとなく気分がウキウキするという方もいれば、反対に、理由もなく沈鬱な気持ちになる──という方もいるのではないでしょうか。
今回はそんな後者のタイプの方々のために、クリスマスイブやクリスマスシーズンを舞台にした、とっておきのホラー小説を3作品ご紹介します。皮肉たっぷりなショートショートから本格派のゴシックホラー、サイコスリラーまで、さまざまなジャンルの怖さをお楽しみください。
『最後のクリスマス』(筒井康隆)
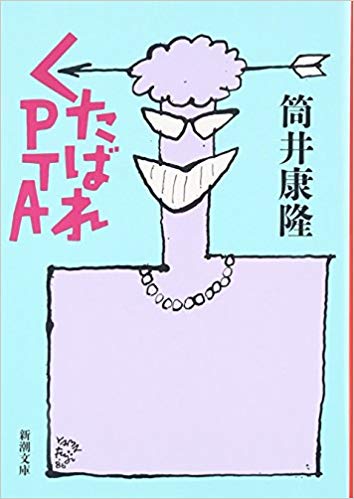
『最後のクリスマス』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/410117119X/
『最後のクリスマス』は、SF小説の大家・筒井康隆による短編作品です。物語は、“クリスマスがだいきらい”な主人公・“おれ”が芽里(通称メリー)という名の恋人とサンタクロースについての話をするところから始まります。
おれはクリスマスが大きらいだ。
第一に下品だ。第二には騒々しい。
金のある連中は酒を飲んで酔っぱらい、女を抱いたり何かして歌をうたい、ごきげんである。だが、おれには金がない。おれがクリスマスを嫌いな第三の理由──それは金がなくて、クリスマスを楽しめないからである。
しかしそんな“おれ”とは対照的に、メリーはクリスマスイブが待ち遠しいと語ります。それは、イブになると毎年サンタクロースが家の煙突から入ってきて、メリーに直接プレゼントをくれるからだと言うのです。
そのサンタクロースの正体はメリーの父親だと言って呆れる“おれ”。しかし、メリーには父親がいないことを思い出します。
「だけど、サンタなんていないんだよ」
「いるわよ」
彼女はムキになって言いかえしてきた。「このダイヤの指輪だって、去年のクリスマスにもらったのよ」
彼女の突き出した白い指にはまっている指輪を見て、おれはびっくりした。もしダイヤだとすれば、充分三カラットはある大粒のダイヤなのだ。
サンタクロースはここ数年、メリーを“大人あつかい”して指輪やネックレスをくれるようになったと彼女は語ります。大人あつかいとはなんだ、と“おれ”が問いただすと、メリーは2年前からサンタクロースと関係を持っているということを明かすのです。
“おれ”は激昂し、クリスマスイブに友人から借りたライフルを持ってメリーの家に乗り込みます。“おれ”が待ち伏せをしていると、なんとメリーの話どおり、絵本で見るような姿のサンタクロースがトナカイのひく橇に乗って現れたのでした。
サンタクロースに掴みかかるようにしてメリーと関係を持った理由を聞く“おれ”。すると彼は、イギリスがクリスマス島でおこなった水爆実験の影響で、自分もトナカイたちも放射能を浴びてしまった、いまのうちに子孫を残さないと一族が途絶えてしまう──という事情を語るのです。よく見ると、サンタクロースの顔の半分はケロイドでただれ、トナカイたちも奇形のものばかりでした。
サンタクロースからプレゼントを取りあげ、空へと追い返した“おれ”ですが、そのあとには誰もがゾッとするような意外な結末が待っていました。筒井康隆らしいシニカルさを存分に味わえる、短いながらも読み応えのある短編です。
『ホートン・ミア館の怖い話』(クリス・プリーストリー)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4652080050/
『ホートン・ミア館の怖い話』は、イギリスのイラストレーター・漫画家として長年活躍してきたクリス・プリーストリーによる長編小説です。プリーストリーは2000年に小説家デビューして以降、子どもの頃に読んで夢中になったというホラー小説のスリルを求めて、『モンタギューおじさんの怖い話』、『船乗りサッカレーの怖い話』といった良質なホラー作品を数多く発表してきました。
本作の舞台は、19世紀のイギリス。父と母を亡くし孤児になった少年・マイケルが、自身の後見人であるスティーブン卿を訪ねて彼の住むホートン・ミア館に向かうところから物語は始まります。マイケルは軍隊にいた父の死に関係しているというスティーブン卿を憎んでいたため彼と会うことを嫌がりますが、クリスマスシーズンはホートン・ミア館で過ごしなさいと弁護士のジャーウッドに説得され、仕方なくそのとおりにするのです。
ホートン・ミア館行きの馬車の中で、マイケルは恐ろしい光景を目にしてしまいます。
頭を窓の内側にもどす。外よりはいくぶん暖かい。ランタンの明かりは外にはあまり広がらず、せいぜい道の端くらいまでしか照らしていない。ところがその瞬間、おそろしいものがみえた。闇の中に女の顔が浮かびあがったのだ。
馬車のほうに伸ばした両手。血走った目。青白い肌。大きく開いた口。なにか叫んでいるのだろうが、馬車の車輪の音にかき消されて、なにもきこえない。外は凍てつく寒さなのに、着ているのは薄いスリップのようなものだけ。しかもずぶ濡れになっている。
マイケルは馬車に同乗していたジャーウッドに「女の人が助けを求めている」と訴えますが、道を探してみても誰の姿も見当たりません。薄暗いお化け屋敷のようなホートン・ミア館に着いてからも、マイケルは夜がくるたびに誰かの足音を聞いたり、女の人がすすり泣く声を聞いたりするのでした。
ホートン・ミア館には、いつも黒い服に身を包み、青白い神経質そうな顔で館を歩き回っているスティーブン卿と、甲斐甲斐しく彼の世話を焼く妹のシャーロット、そしてたくさんのメイドや召使いたちが住んでいました。
いつも笑顔で明るいのはシャーロットだけで、他の人物たちは皆、マイケルを見ると顔をそむけたり、どこかよそよそしく接したりしてきます。この館は何かがおかしい、何かを隠している──と感じたマイケルは、怪現象に耐えながら、館の秘密を探ろうとします。
闇の中で音がきこえるときはたいていそうだが、音の出所がわからない。ベッドに体を起こして上掛けを折りかえし、耳をそばだてた。床板のきしむ音がする。呼吸みたいな音もする。まちがいない。ドアの外にだれかが立っている。それを裏づけるかのように、ドアノブがゆっくりまわる音が聞こえた。
「だれ?」ぼくは声をかけた。「だれなんだ?」
本作はイギリスの伝統的なクリスマスの雰囲気を存分に味わえる作品であるとともに、児童文学という形式をとってはいますが、中身はまったく子供だましではない本格的なゴシックホラーです。読者をただ驚かすような怖さではなく、じわじわと背後から何かが忍び寄ってくるような怖さを味わいたい方には、特におすすめの1冊です。
『マークハイム』(スティーブンソン)
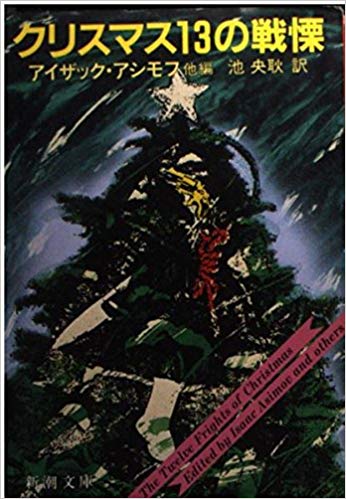
『マークハイム』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4102186050/
『マークハイム』は、『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』といった冒険小説・怪奇小説の名作を数多く生み出したスティーブンソンによる短編小説です。
物語は、マークハイムという名の男がクリスマスの夜、金に困って行きつけの骨董屋の店主を殺してしまうというシーンから始まります。
主人が体を起こそうとする刹那、マークハイムは後ろから襲いかかった。焼き串に似た刃渡りの長いナイフが閃めいた。店の主人は締められた雌鶏のように身をもがき、陳列棚に
顳顬 を打ちつけて床にくずおれた。
金目のものがないかと店内を物色するマークハイム。すると突然、彼の前にひとりの見知らぬ男が現れ、マークハイムと対話をし始めるのです。男はマークハイムのことをよく知っており、マークハイムが骨董屋の店主を殺すシーンも目にしていた、と語ります。しだいにマークハイムはこの男のことを、“悪魔の化身”だと感じるようになっていきます。
「俺に言わせれば、人殺しは何も特別な罪ではない」悪魔の化身は言った。「人生が戦いであるのと同じで、すべての罪はつまるところ人殺しだ。俺が見るところ、人間どもは筏に乗って漂流する餓えた水夫の一団と変りない。腹を空かした仲間の手からパン屑を奪い取る。お互いに、他人の命を食いものにする。俺は罪が犯される瞬間よりも、それから後を見届けることにしているのだ。人間、行き着くところは死でしかない」
男の言葉を聞いていたマークハイムは、なぜかだんだんと自分の犯した罪が恐ろしくなると同時に、良心の呵責に耐えられなくなってしまいます。そしてついには、
マークハイムは微かに頬をほころばせて小間使いの娘を戸口に迎えた。
「警察を呼びなさい」彼は言った。「私はおたくの御主人を殺した」
と自白をするのです。
男の前に突如現れた見知らぬ男は、彼の“もうひとりの自己”であると言ってよいでしょう。本作は殺人犯である男が自分自身と対話をするというシンプルなストーリーでありながらも、許されざる罪を犯してしまった若者の心境や、その精神状態のゆらぎなどを非常に緻密に描いています。『マークハイム』を発表した翌年にスティーブンソンが『ジキル博士とハイド氏』を執筆していることから、本作は二重人格の男を描く『ジキル博士とハイド氏』の土台になった作品のひとつでもあると言われています。
『マークハイム』は、幽霊やモンスターが登場するホラーではなく、人間の弱さをじっと見つめ直すようなサイコスリラー作品が読みたい方には一押しの作品です。『マークハイム』が収録されているアンソロジー短編集『クリスマス13の戦慄』の中にはほかにも、ギャスケル夫人による『老いたる子守の回想』やラヴクラフトによる『祭祀』など、クリスマスを舞台にしたホラーの古典的名作が数多く収録されています。
おわりに
クリスマスはカップルや家族があたたかな時間を過ごす季節であるとともに、悪霊や殺人鬼が活躍する季節でもあるのです。ホラーにつきものの赤い血は、クリスマスイブに輝くツリーや白い雪によく映える──と言っても、ホラー好きの方になら頷いていただけるでしょう。
今回ご紹介した作品はどれもただ闇雲に“怖い”だけでなく、シニカルな読後感やゴシックホラーの雰囲気、サイコスリラーの風格などを感じることができる名作ばかりです。クリスマスの夜を迎えるのが憂鬱だという読書家の方は、今年はぜひ家にこもって、これらの名作のページを開いてゾッとしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2019/12/11)

