東大卒の落語家がいま語ること 他人ではない自分を生きるのみ 「源流の人」第2回:春風亭昇吉(落語家)
時代に流されず、 常に新たな価値観を発信し続ける人々を追う、本の窓の連載「源流の人」。第2回は初の東大卒の落語家・春風亭昇吉。東京大学在学中の2006年に第三回全日本学生落語選手権・策伝大賞で優勝し、翌年には春風亭昇太に入門。今年の2月『マンガでわかる落語』を刊行したばかりの異色落語家に、学生時代と入門後のこと、人生の切り拓き方など、お話を伺いました。
連載インタビュー 源流の人 第2回
時代に流されず、 常に新たな価値観を発信し続ける人々を追う
東大卒の落語家がいま語ること
他人ではない自分を生きるのみ
春風亭昇吉
落語家(40歳)

インタビュー・加賀直樹 Photograph: Matsuda Maki
これは日本人特有なのか、それとも世界じゅうが同じなのか。ひとは、どうしても肩書きで相手を見たがる。名誉、地位、出自、財力。特にわが国においては、好むと好まざるとに拘らず、最高学府である「東大卒」という肩書きにとても弱い。偉業を成し遂げれば「さすが東大卒」と褒めたたえ、失態を演じれば「東大卒がなぜ」と蔑み落とす。その肩書きは、ときには錦の御旗に、ときにはトドメの
そんな宿命を背負った一人が落語家の
「『ありがとう』『申し訳ありません』。それ以外の言葉はすべて胸の内にしまう──。ひとえにそう念じながら、この世界で生きてきました」
二〇〇七年、東大経済学部の卒業と同時に、「笑点」(日本テレビ系)でおなじみの落語家・春風亭昇太のもとに弟子入り。入門当時は「初の東大卒の落語家」として大きな話題になった。それから十三年の時が過ぎ、歯切れ良い語り口と、機転の利いたコメント能力を買われ、現在は高座だけでなくクイズや情報番組にも活躍の場を広げている。キャリアからして真打も近いだろう。実力を着実に積み重ねた人気
「うちの師匠からも言われたことがあるんです。『お前、東大卒じゃなかったほうが良かったね』って。僕自身、そう思ったことも昔はありましたよ」
昇太師匠とのエピソード、例えばこんなことがあった。
楽屋
「師匠は『ラクするな』と言いたかったのだと思います」
昇太師匠はどちらかと言えば放任主義で、けっして理不尽なことを口にしない。だが、落語の世界自体には、先輩が黒と言えば白いものでも黒であるという空気が流れていることも知った。どんな不便で非効率であっても、言われた通りにしなければいけない世界だと悟った。
いま、昇吉には、東大卒の後輩落語家が二人いる。そのうちの一人に会って伝えたのは、「理や知が
だから、生意気を言うんじゃないぞ。「ありがとう」と「申し訳ありません」。この言葉が大切だ。昇吉は何度もそう語りかける。自らにも言い聞かせるように。
通信添削で全国一位に輝く
生まれ育った岡山で小学校生活を送った昇吉は、とにかく周囲になじめなかった。教室では「静かにしなさい」と先生が怒鳴っているのに、なぜ周りの子たちは静かにしないのだろう。なぜ、全員でフォークダンスを踊らされるのだろう。頭が混乱してくると、彼は学校を脱走した。人見知りの性格で、正面から相手の顔を見られない。文化祭にも体育祭にも参加せず、集団生活を毛嫌いした彼にとって、唯一の心の癒やしはテレビアニメだった。
「『さすがの猿飛』ってご存じですか。あれにハマったんです」。昭和五十五(一九八〇)年、『増刊少年サンデー』(小学館)で連載が始まった作品で、主人公・肉丸とその恋人・魔子ちゃんが、なぜか最終回には敵となり戦うというストーリーだ。そして人気作品『ハイスクール! 奇面組』にも傾倒した。いずれも共通しているのはギャグ満載で話が進むのに、最終回はシリアスでシュールな展開になる。そんな物語が、幼い頃は大好きだった。
中学生になって、落語界の異端児・
高校卒業後、地元の国立大学に入学。ところが、友達と酒を飲むほかは、ほぼ引きこもりの生活に突入してしまう。坂口安吾、尾崎
「あなたの声がきれいだった」に導かれて
赤門をくぐってみて初めて気がついた。「みんなと
それにしても他人の顔を真正面から見ることもできないほど内気だったのに、なぜ落研に? そう問いかけると、彼は笑いながら答えた。
「そもそも、落語は僕にぴったりなんです。だって、左右に顔を振って話すでしょう。観客の顔を見なくても済むんですから」
彼にはもう一つ、衝撃的な出来事があった。それは四年生の時、ボランティアで都内の盲学校を訪ねた時のことだ。この頃の昇吉は、都内のホスピスや医療少年院、高齢者施設などを回っては、自ら志願して一席設けさせてもらっていた。
「披露する前、盲学校の先生からは『落語は子どもたちには難しいかもしれない』と言われたんです。ところが、始まってみると全然違った。ものすごくウケたんです!」
落語には「
「見えない人こそ楽しめる文化もあると知りました。日本のお笑いの文化、ひょっとすれば海外の人にも伝わるかもしれない。そんなものをつくりたいと思うようになったんです」
盲学校の生徒の一人は後日、感想を寄せてくれた。「声がきれいで聞きやすかったです」。その一言は、彼が落語家として生きていく原動力となった。卒業間近の三月、東京・町田で開かれた昇太師匠の落語会に出向き、弟子入りを
自分の人生を生きるだけ

普段持ち歩くカバンの中身は、財布、筆ペン、落款用の判子にデンタルフロスも。奥のポーチと市松模様の名刺入れはご贔屓の方にいただいた富山の織物。
「東大を出てなぜ落語家に?」
「これまでの蓄積を捨てる覚悟が、落語家の道を選ぶにあたって必要だったのでは?」
昇吉は、内心憤りを覚えていました、と振り返る。どれだけ落語家をバカにしているのか、と。彼の著書にこんな一節がある。
「自分で選んだ道、どんな結果も自分の責任である。その結果に後悔が出ないよう、僕は前だけを見て、これからも自分の芸を磨いていきたい」(『東大生に最も向かない職業』)
今となっては、当時のような偏見に満ちた質問は受けなくなった。それはきっと、彼の落語にかける情熱や実績が、周囲の口を黙らせたのだろう。もっとも、本人自身は謙虚な姿勢を崩さない。
「私は自分の人生を生きているだけです。他の東大生がどう生きるべきか、とか、他人に対してどうとか、意見は持っていません」
幸せになる方法なら知っている
コロナ禍で寄席は一時閉鎖され、高座に上がる機会はなくなった。死生観、人生観について問い直すひとは世界中に
「自分がやりたいことを僕はやっているだけです。そもそも、東大を出たとか、どこかの社長になったとか、芥川賞を獲ったとか、そういった『地位財』を求めると、ひとは幸せになれないと思うので」
地位財とは、周囲と比較することで満足を得られる財のこと。所得や財産、社会的地位を得たとして、その幸福感は長続きしない。そして彼は言葉を繋いだ。
「その代わりに、幸せになる方法なら分かりますよ。それは『感謝すること』です。一日に八回は『ありがとう』と言うんです。日々が変わってきますから」
今年二月、落語を分かりやすく解説した『マンガでわかる落語』(誠文堂新光社)を刊行した。「芝浜」「目黒のさんま」「明烏」など名作を紹介し、知識がなくとも落語に親しみ、寄席の醍醐味が味わえる構成にした。「僕は勉強が大好きなんです。本を読んで研究し、江戸のことをひたすら調べました。そうしたら、本に載った原稿の三十倍の分量になってしまいました」。屈託なく笑う。
故郷・岡山で経済番組の司会を務める彼は、新幹線の車内読書が日課だ。これまでも斎藤環、和田秀樹、春日武彦ら精神科医の著作を読みあさったという。「春日さんの『不幸になりたがる人たち 自虐指向と破滅願望』(文春新書)は興味深かった。集中し過ぎて周りが見えない。幸せになると不安になる人たちの話です」。新書は岡山までの片道で読破し、番組でトークの糧にしていく。
どこか自らを俯瞰し、客観視する。そんな印象を彼に感じた。そう告げると、真っ直ぐな眼で彼はこう答えた。
「死んだら終わりなんですよ。他人様は関係ないんです。僕は自分の人生を一所懸命、生きていくだけです」
新しい風が古典芸能の世界にも吹き始めている。

春風亭昇吉(しゅんぷうてい・しょうきち)
一九七九年、岡山県生まれ。東京大学在学中の二〇〇六年、第三回全日本学生落語選手権・策伝大賞で優勝。〇七年の卒業時に東京大学総長大賞を受賞。同年、春風亭昇太に入門。一一年、二ツ目に昇進。一二年から三年連続でNHK新人演芸大賞ファイナリスト。現在、クイズ番組や経済番組でも活躍中。著書に『東大生に最も向かない職業』(祥伝社)、『マンガでわかる落語』(誠文堂新光社)がある。
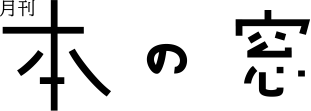
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
初出:P+D MAGAZINE(2020/05/23)

