見殺しにされる文化芸術を新たな力で支え、守り抜く 「源流の人」第4回:大高健志(「MOTION GALLERY」代表)
時代に流されず、 常に新たな価値観を発信し続ける人々を追う、本の窓の連載「源流の人」。第4回は「MOTION GALLERY」代表の大高健志。飲食店、小売業と、個人事業主を救うことに冷淡なこの国で、文化の世界はさらに支援の視野にすら入っていない。荒廃した世の中でいつも人々の心を救ってくれたのは映画であり、音楽であり、書籍であり、一幕の演劇だったのではないか。その火を消してはいけないと立ち上がった起業家がいた。
連載インタビュー 源流の人 第4回
時代に流されず、 常に新たな価値観を発信し続ける人々を追う
見殺しにされる
文化芸術を
新たな力で支え、守り抜く
大高健志
「MOTION GALLERY」代表(37歳)

インタビュー・加賀直樹 Photograph: Matsuda Maki
ステイホーム、ソーシャル・ディスタンス。たった数か月前までは知りもしなかった、こんな言葉によって、私たちの世界がこれほどまでに変わってしまうとは、いったい誰が予想しただろう。外国への渡航はおろか、隣県への移動にも白い目を向けられ、巣ごもりをお願いされた私たちは、感染者数や医療現場の緊迫を伝える報道を、不安と絶望を抱きながら眺め続けるしかなかった。寛解の兆しを見せたかと思えば、再び事態は悪くなり、ほぼすべての人々の人生に影響が及ぶなかで、とりわけ絶体絶命のピンチに陥っているのが、映画や演劇、音楽、書籍などといった文化芸術の業界だ。迅速な補償も行き渡らぬまま「不要不急」というレッテルを貼られ、長期休業を余儀なくされた挙句、とうとう閉館を決めたり、存続危機に
「いま、この数か月を守り切れなければ、取り返しのつかないことになってしまう」
そんな焦燥感から、困窮する全国の小規模映画館を救うべく立ち上がった人物がいる。
そもそも大高が取り組む「クラウドファンディング(クラファン)」とは何か。簡単に説明すると、インターネットを使って不特定多数の人々から資金調達を行い、商品開発や事業などを達成する仕組みのことだ。クラウド(群衆)とファンディング(資金調達)の二つの言葉を掛け合わせている。「ミニシアター・エイド基金」は、国内クラファン史上で最高額を記録したほか、それを追うようにして始めた「ブックストア・エイド基金」では全国の書店・古書店を、「小劇場エイド基金」では舞台の灯火を守るべく、共に多くの賛同金を集めた(各プロジェクトはいずれも終了)。
最近、とみに耳にするようになった新語「クラファン」だが、大高自身は約十年も前に、「
「大学院で映画や現代アートを勉強していた時、制作の現場を見ていくなかで、痛感したからです。『日本のクリエイティブ業界の未来、これは厳しいぞ』と」
東京藝大では、世界的に著名な作家や映画監督らが教授陣に名を連ねている。ところがそんな多忙な彼らが休まずに授業を続けているという。新学期が始まる時、教授の多くが「今年は企画が通るから僕はもう授業に来られなくなる」と言っているにもかかわらずだ。聞けば、「企画が飛んだ」ということらしい。
このように、若手だけでなく、世界的に高い評価を受けているベテランたちも、充分な金銭面の支援が得られていない現状を大高は悟った。
大学院一年次で交換留学生としてフランスへ。そこで大高は、美術に対する日仏の価値観の差をまざまざと見せつけられた。
「まず、米国など規模の大きな英語圏マーケットでは、お金を派手に使って新たな才能をどんどん開花させます。これに対し、マイナー言語であるフランス語で闘う彼らは、英語圏のルールでは勝てないことに気付いている。だから、国の助成金を後ろ盾に、ハイブランド戦略の闘い方をしているのです」
売れるか否かはどうでも良い。映画やアートで独自ルールを構築すべく、エッジの効いた作品をつくっていく。映画で言えばカンヌ国際映画祭といったように、芸術の評価はフランスが決める。そんな強い自負さえ感じた。
「お金ならば何とかなる、という雰囲気でした。仕事がなくとも芸術家として認められれば、生活の保障がある。これは強い。同じ芸術分野に従事しているとは思えないほど、土壌があまりに違い過ぎると思いました。これって、個人の才能の有無の話ではない。そう思いました」
『カメ止め』を生んだ映画との間違った出会い
ひとが、ひとらしく生きていく。その多様性や、社会全体の公益性を育んでゆく時には、採算を度外視してでも生み出すべき作品があるはずだ。表現とは本来、長い目で考えていくものである。ところが、そうした視線を日本で保ち続けることは、じつに難しいことであると、日本に戻ってきた大高は痛感するようになった。
「バブル期ならまだしも、企業が支えるのも、一発当てたお金持ちが支えるのも厳しい。フランスのように文化助成が手厚くはならないし、むしろ削減されていく」

映画、写真、アート作品──。サイト内にはさまざまな支援プロジェクトがある。例えば「目標額を達成すれば出版が決まります」という本のクラファン。「欲しい」と思った本の出版を願う人たちが、例えば三千円、一万円、一万五千円など、懐に応じて可能な範囲の額を出資し、期限内に目標額に達すれば、そこから本の制作が始まり、完成した本と共に額に応じた特典が届けられる仕組みだ。不成立の場合は支援者に(又は出資者に)返金される。ここで重要なのは「売れそうな」本ではなく、「欲しい」本を支援者が選んでいるということだ。
「『売れる』本ではなく、『欲しい』本にお金が集まって企画に青信号が
そうして大高は、これまでに三十億円を超えるクラファンを実現させてきた。二〇一五年度にはグッドデザイン賞も受賞。何と言っても極め付きは、二〇一八年に大ヒットした映画「カメラを止めるな!」だろう。映画の制作費の半分が、大高のもとで集められたのだった。
「まだ当時は、監督も役者も全国的に有名な状況ではなかったので、一般的な製作委員会方式で作ろうとしてもお金は集まりません。おもしろさや熱量で支援金を集め、興行収入は三十億円を突破した。そんなシンデレラストーリーができました」。大高は目を細める。
「カメラを止めるな!」だけに限らず、大高にとって映画には特別な思いがある。それは中学二年生の時のことだ。友人と久々に映画館で「ドラえもん」を
「人気俳優のブラッド・ピットが出てくるし、どうせハッピーエンドだろうな、とタカを括っていたら、まるで違っていたんです。皮肉と批判が盛り込まれたバッドエンドの話。いきなり見せつけられ、『すごく面白い!』って感動したんです」
以来、銀幕の世界にのめり込み、多彩な世界が広がっていることを知った。「上映時間二時間のうち、一時間五十分は
最近流行しているネット配信の映画では、こうした類の作品ではラストを待たずに変えられてしまうだろう。視聴形態の変化は、演出を刺激的に変えたり、集中力を失わせないテクニックへと制作者の目的を変えていく。それはもはや映画ではなくて、新しい娯楽商品ではないのか。
「『ドラえもん』の代わりに観て感じたような、『間違った出会い』こそ大事。無防備な状態で観て、そこから何かを考える人が出てくる可能性が映画にはある」。大高はこう力説する。
そんな映画への熱い
「主催者は『寝ても良いですよ』って。映画館で寝るのって気持ち良い。寝ても良い前提で小難しい映画を観るという企画だったんです。ところが誰も寝ずに最後まで観ていたという」
もともと各地で行われてきた自主上映会とは、世代や趣味
第三者だからこそ動くことができた
全国に感染拡大が広まっていった、ある日。
大高のスマートフォンを、二人の気鋭の映画監督が「それこそ一時間ほどの時間差で」鳴らした。一人は、かつて「MOTION GALLERY」でクラウドファンディングを行った映画「ハッピーアワー」を世に送り出した
「全国一律でミニシアターを救うクラファン基金を立てられないか」
各地のミニシアターは、存続の危機にさらされていた。良作を上映することに人生をかけているオーナーたちだが、いずれも観客が多いとは言えない。しかし一度無くなれば、再び映画館を建てるなどもはや不可能な時代である。それは誰もが気付いていたことであろう。
この時、大高はある種の運命を感じたという。社会的に、物理的に、分断がみるみる広がっていくなか、連帯を呼び掛ける旗を立て、ミニシアターという文化を皆で助けたい。全国の小規模映画館に一括で分配する仕組みをつくりたい。ネットを活用できない老経営者も多いはずだ。そんな彼らを除いてしまうとそれもまた分断になる。手分けして連絡した。記録的なスピードで支援金が集まり、分配に至るまで駆け抜けた。後に実施した書店、小劇場のクラファンも含め、全国の経営者たちからはその後、こんな声が寄せられたという。

「そもそも、こんな方法を知らなかった」
そして最も多かったのは、こんな声だったという。
「自分たちでは言えなかったことだから、良かった」
大高は言う。
「今回、第三者の者たちが、代わりに起案するということが重要だった気がしているのです」
この
「当人ではない僕らが、心から必要だと思っているものを、分断や選別なく取りまとめ、助けたいという声を上げる。それにより公共性を帯びてくると思います。コロナの状況において、それがある種の正当性を確立できたような気がします」
誰もが皆、傷を負っている。自分だけが助かれば良いと思っているわけではない。文化自体の土壌を守りたい。そんなメッセージを大高らは発信し続けた。
□文化に冷淡な国でも、
支える市井の人びとがいる
約十年前、大学院生の時に滞在し、その後の人生の方向性を照らしてくれた欧州。低成長の段階に入った彼らの国々には、国際競争力として功を奏するものとは何かを考えた時に、文化やアートへの投資が長期的に重要であるとの価値観がしっかり根付いているのを実感した。
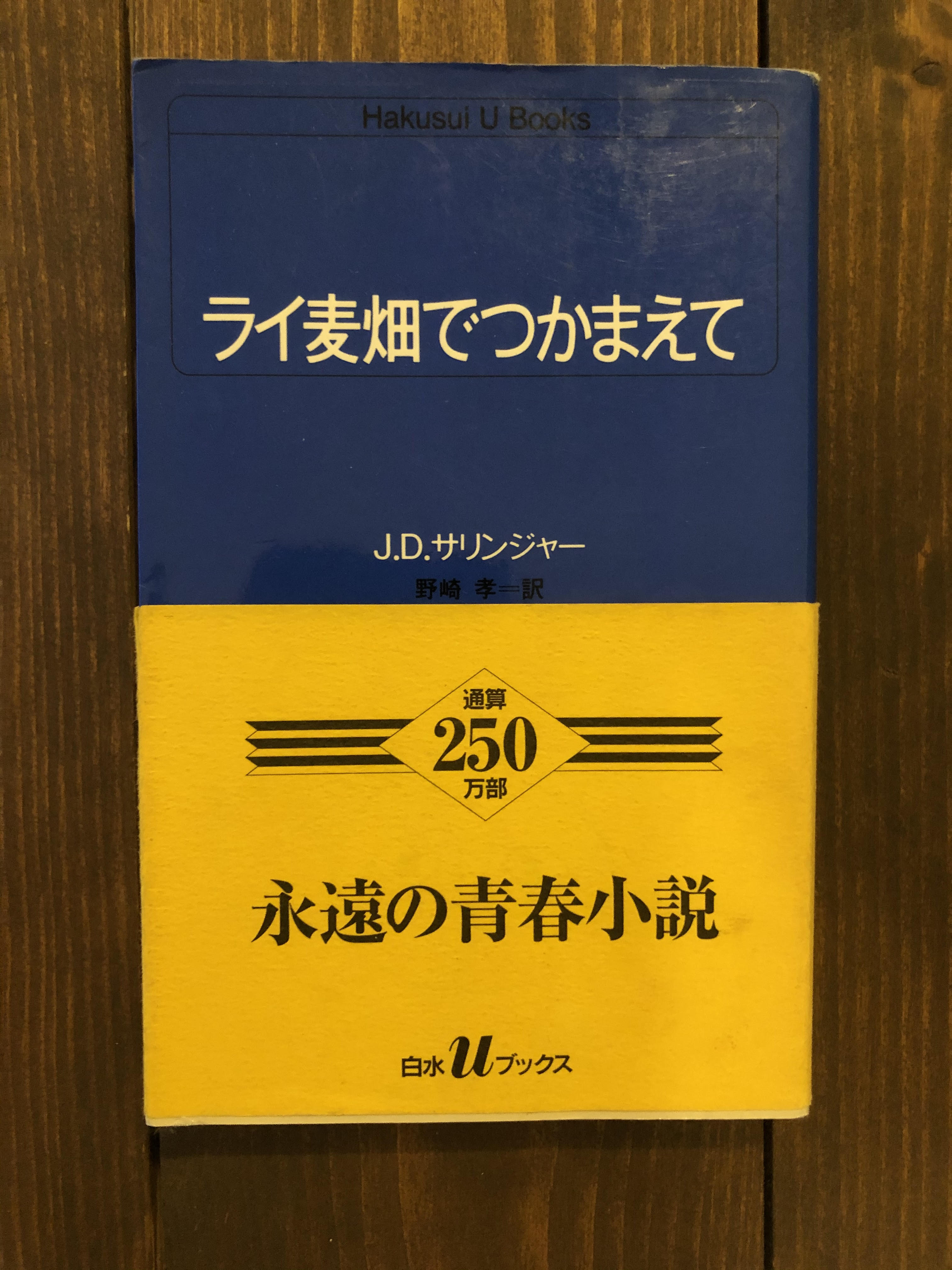
愛読書『ライ麦畑でつかまえて』との出会いは中学2年生の時。思春期に見る社会の景色と心情を的確に抉っている小説だと実感。以来この作品の影響を受けた映画やアートに惹かれてしまうのだそう。
「そもそも、文化庁には対策予算がないと聞いています。なので、この非常時になぜ文化を救わないのか、というよりも、従来の文化芸術の社会的位置付けが
「
「人生について考える指針になるもの、だからですかね」
今後は、感染拡大のリスクに最大限の注意を払いながら、地方都市での映画上映イベント再開を模索したい。また、ドライブインシアターのような、ソーシャル・ディスタンスと大人数での共通体験が両立可能なプロジェクトのサポートも考えている。大高は言う。
「安全のもと、皆で映画を観るということを浸透させたい。長い目で見ても大事だと思うんです。だって、せっかく映画館が再開しても、お客さんが戻らず『ネットで観れば良いじゃん』となってしまうと厳しいですから」
今回、「ミニシアター・エイド」などを通じて得た経験は、この国に住む人々が文化を支えようとする心意気がまだまだ健在であることを教えてくれた。大高は「今も驚いています。そして感激しています」と話す。顔を合わせることはできなくても、同じ思いを抱く人が日本中にいる。ディスタンスは保ちつつ、心は
ミニシアター、書店、小劇場。今日は必要ではないかも知れない。しょっちゅう行けないかも知れない。けれども、いつまでもそこにあってほしい。だから支えていく。「不要不急」のものこそが、生きる糧となっていく。

大高健志(おおたか・たけし)
一九八三年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、二〇〇七年、外資系コンサルティングファーム入社。その後、東京藝術大学大学院に進学。制作に携わるなかで、二〇一一年、クラウドファンディングプラットフォ ーム「MOTION GALLERY」設立。以降、二十億円を超えるファンディングをサポート。二〇一五年度、グッドデザイン賞「グッドデザイン・ベスト」受賞。二〇一七年、誰でも自分のまちに映画館を発明できるプラットフォーム「POPcorn」設立。二〇二〇年「さいたま国際芸術祭」キュレーター就任(新型コロナ感染症拡大のため当面開催延期中)。
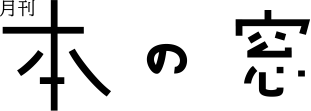
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
初出:P+D MAGAZINE(2020/07/24)

