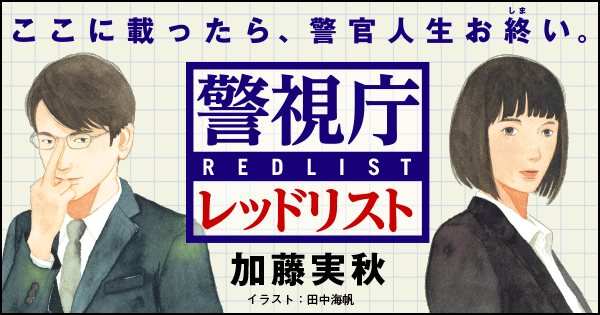〈第12回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

みひろは違和感を覚える。
CASE3 ゴッドハンド:神にすがる女刑事(4)
11
「二〇一〇年? なにそれ。本当?」
苦笑して問いかけ、柿沼はコーヒーを飲んだ。頷き、みひろは答えた。
「本当です。賞味期限の日付まで覚えてますから」
「河元は人はいいけど、大雑把なところがあるからね。お客さんに売っちゃったり、中身を鈴木さんにあげちゃったりしたら大変だから、私から言っておくよ」
「よかった。ずっと気になってたんです」
ほっとして、みひろはお皿の上のパンケーキをフォークで刺し、口に運んだ。ふんわりした口当たりのパンケーキに、シロップとして使われたエスプレッソの香りと苦み、上に載ったバニラアイスの甘みと冷たさがミックスされ、絶妙なバランスだ。思わず、
「おいしい~!」
と声を上げると、柿沼がコーヒーカップをテーブルに置いてこちらを見た。
「よく昼ご飯に、そんな甘いものを食べられるね。おやつならわかるけど」
信じられないといった口調と眼差しだ。みひろの隣に座る慎の前にもパンケーキのお皿が置かれ、半分食べ終えている。ナイフとフォークを置いて前髪を搔き上げ、慎は言った。
「おっしゃることはわかりますが、パンと名のつくものは別です」
みひろもこくこくと頷き、柿沼は不思議そうに「へえ」と返した。
スーパーことぶきから、奥多摩駅近くのキャンプ場の中にあるこのカフェに来た。みひろは昨日の朝奥多摩署に行くと知るとすぐにこの店を調べ、パンケーキを食べようと決めていた。柿沼は「キャンプ場は知ってたけど、カフェがあるとは知らなかった」と珍しそうにウッディーで山小屋風の店内を眺めている。
「聞き込みを終えて、いかがですか?」
慎が話を変え、柿沼は表情を引き締めてこちらに向き直った。
「板尾の印象が、私と土橋先生たちとでは違うね。ただ出家信者はみんな訳ありだし、板尾は小さなケンカはしても、命を奪われるようなトラブルは抱えていなかったと思う」
「しかし波津の口ぶりからすると、出家信者たちは防犯カメラの死角を知っていたようです。そうなると信者は施設を事実上自由に出入りでき、外部の人間も死角の件を知っていれば同様ということになります。何らかの理由で板尾を含む出家信者の誰かが外部の人間と接触し、それが今回の事件につながったとは考えられないでしょうか」
「確かに。他の出家信者を洗い直してみるよ……三雲さんは? 波津さんに案内してもらってる間、何か言いたそうな顔をしてたよね。聞かせてよ」
見られてたのか。さすがは元敏腕刑事。驚き感心し、みひろは切り出した。
「波津さんって、歳は違いますけど園田さんと似てますよね。園田さんは土橋さんの側近って感じだし、波津さんも土橋さんとは近しい間柄でしょう? それってつまり──すみません。板尾さんの事件とは関係ないと思いますけど」
口に出したものの気まずくなり、みひろは頭を下げた。しかし柿沼は動じず、あっさりこう言った。
「ああ。愛人かどうかってこと? なら、合ってるよ。一年ぐらい前までは、波津さんが施設の本館の三階で土橋先生と暮らしてた。そこに園田さんが入信して来て、波津さんは三階を出たんだ。でも代わりに教団の金庫番っていう、先生の絶対的な信頼が必要な仕事を与えられた。波津さんは信者としてより高いステージに行ったって、みんなに羨ましがられてるよ」
「ははあ」
相づちを打ちながらも、「やっぱりそうか。土橋さん、好みがわかりやすすぎ。あと手切れ金代わりの出世を『より高いステージに行った』と思わせるって、やっぱりやることが詐欺師」という新たな突っ込みが浮かぶ。こちらの気配を察知したのか、柿沼はさらに言った。
「また何か考えてるでしょ? その野次馬根性、いいと思うよ。警務部より刑事部が合ってるんじゃない?」
「ありがとうございます」
言葉のチョイスは微妙だが、褒めてくれているし自分に興味も持ってくれているようだ。そう確信し、みひろは一番訊きたかったことを訊いた。
「柿沼さんは、なぜみのりの道教団に入信したんですか?」
「奥多摩署に赴任してすぐに、あそこを教団の施設にするしないの騒動が起きたんだよ。民事不介入の原則はあるけど、田舎の警察は住民の協力なしにやっていけないからね。相談に乗ってるうちに教団の人とも話すようになって、ってのがきっかけ。知ってるだろうけど私は若い頃がんを患って、治りはしたんだけど疲れやすくなっちゃってね。でも先生に施術してもらって農作業を手伝うようになったら、ウソみたいに楽になったんだよ」
みひろは曖昧に頷き、隣を見た。しかし慎は、知らん顔でパンケーキをぱくついている。呆れながらも、彼は調査対象者の心情や身の上に無関心なのを思い出した。
こちらの沈黙を批判と受け取ったのか、柿沼はこう続けた。
「言いたいことは想像がつくよ。知り合いには、『ミイラ取りがミイラになった』って言われたし。でもね、私は土橋日輪って人が信じられるし、救われもしたんだ。がんになったのは刑事としてこれからって時だったからショックで後悔もして、ずっとその気持ちを引きずってた。でも土橋先生は、『柿沼さんは刑事として人の悪意を浴び続けてきた。がんも疲れやすいのも、全部それが原因。あなたは悪くない』って言ってくれたんだ。あとは単純に、施設のみんなと畑で汗を流すのが楽しい。私は子どももいないし、悪人の悪巧みをぶっ潰す、みたいなことばっかりやって来たでしょ? 何かを作ったり、成長を見守るのがこんなに楽しいなんて、入信して初めて知ったんだ。それに土橋先生の信者を愛人にしちゃうようなところも、人間臭くて逆に信用できるしね」
最後は笑い話にして、柿沼はまたコーヒーを飲んだ。相手が刑事なら土橋はそう言うだろうなとみひろは思ったが、それ以上突っ込む気にはならなかった。
「今一度確認です。柿沼さんは自身がみのりの道教団の信者であると認め、板尾の件の捜査が済み次第、その旨を監察係に報告することを承諾しますね?」
ようやく慎が口を開いた。パンケーキを完食し、柿沼と向き合っている。面倒臭そうに、柿沼は返した。
「だから、昨日そう言ったでしょ」
「わかりました。では処分については捜査終了後、追って通達します」
「あっそう。ところでこれ、もったいないから食べてくれない?」
平然と返してから、柿沼はテーブルの上を指した。白く丸いお皿に、彼女が注文したピザが載っている。みひろは問い返した。
「いいんですか? 一切れしか食べてませんけど」
「夏バテみたいで、食欲がなくてね。先生には『柿沼さんに溜まった悪意を浄化しきるには一生かかる』って言われてるから、そのせいかも。とにかく片付けちゃってよ」
「じゃあ、遠慮なくいただきます」
勢い込んで、みひろは向かいに手を伸ばした。が、横から伸びて来た手に目当てのピザの一切れを奪われてしまう。隣を見ると、慎が当然という顔でピザを囓(かじ)っていた。
- 1
- 2