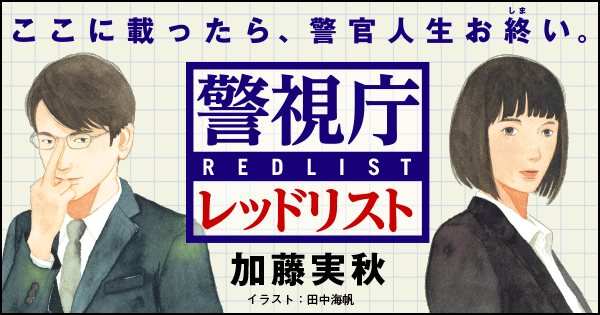〈第12回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

みひろは違和感を覚える。
12
賑やかな気配があって、若いカップルが二組、売り場から出て来た。階段には向かわず、傍らの壁際に置かれているベンチに歩み寄る。
「あ~、疲れた」
「ヤバい。もうフラフラだよ」
ロングヘアでデニムのミニスカートを穿いた女と、ショートカットにメガネで花柄のワンピースを着た女がそう言ってベンチに座り、肩にかけたアパレルブランドのショッピングバッグを下ろした。連れの男たちも「買いすぎなんだよ」「時間もかけすぎ」とぼやいてベンチに座り、女たちに持たされたと思しきショッピングバッグを下ろす。その様子を、慎は階段を挟んで反対側の壁際のベンチから眺めた。
ここは、新宿のデパートの二階にある婦人服売り場だ。日曜日の今日はバーゲンセールが行われており、混み合っていた。
「でも、すごく得した。とくにこれ」
そう言って、ロングヘアの女がショッピングバッグの一つを持ち上げた。他のバッグは紙かビニール製だがそれだけが黒い布製で、中央にブランドロゴらしき銀ラメの英語の文字が入っている。
「だよね。朝から並んだ甲斐があったよ」
頷き、メガネの女も同じバッグを摑んで中から何か取り出した。ブランドロゴのステッカーのようだ。それを見て、男の一人が呆れる。
「そんなもん買ってどうするんだよ。しかも、一枚千円って。訳わかんねえ」
「違うよ。欲しかったのはステッカーじゃなく、このエコバッグ。人気があるんだけど、普段は服とか高いものを買わないと、これには入れてもらえないの」
「そうそう。ステッカーはどうでもいいの」
女たちは反論したものの、男は「もっと訳わかんねえ」と顔をしかめ、もう一人の男も頷く。関心は皆無だったが慎は念のためにカップルたちのやり取りを聞き、売り場の様子に目を配った。腕時計を覗くと、午後四時五十五分。間もなく約束の時間だ。
慎のパンツのポケットでスマホが振動した。液晶画面に表示された発信者は、「三雲みひろ」。無視しようかとも思ったが、緊急連絡の可能性があるので通話ボタンをタップしてスマホを耳に当てた。
「はい。阿久津です」
「三雲です。休日に申し訳ありません」
あまり申し訳なくなさそうに、みひろが告げる。売り場を注視したまま、慎は応えた。
「いえ。どうしました?」
「いま柿沼さんから電話があって、板尾さん以外の出家信者を調べましたが、手がかりは得られなかったそうです。河元さんについても、板尾さんと揉めていた形跡はありません。ただ板尾さんが施設を抜け出した夜、河元さんは『実家に顔を出したり、細々した用事を片付けていた』そうでアリバイなしです」
「アリバイなし」というフレーズを口にできるのが嬉しくて仕方がないといった気配を感じ、慎は小さくため息をついた。
教団の本部施設と河元の店を訪ねたのは、二日前。昼食の後、柿沼は「聞き込みに行く」と車で走り去り、慎とみひろは奥多摩署で署員たちに、表向きの訪問理由である職場環境づくりのための聞き取り調査を行った。
みひろから聞いた情報を頭の中で整理し、慎は返した。
「わかりました。しかし、板尾の捜査は柿沼に任せましょう。加えて、柿沼と個人的に連絡を取り合うのは問題です。彼女は非違事案の調査対象者で、捜査に同行しているのは行動確認の一環だということを忘れないで下さい」
「でも柿沼さんが宗教活動をしているのは休日だけみたいだし、奥多摩署の人も柿沼さんの入信を知らない様子でしたよね。調査を始めた日に室長が言ってた『常識の範囲内』じゃないですか?」
「それを判断するのは、我々ではありません。三雲さんはみのりの道教団の資料を読み、その印象を『微妙』と述べましたよね。実際に教団の施設を見学し、教祖の土橋に会ってどうでしたか?」
慎が問いかけると考え込むような気配があり、みひろはぼそりと答えた。
「もっと微妙」
「同感です」
満足し、慎は頷いた。しかしみひろは納得がいかないらしく、さらに言った。
「でも人が一人亡くなってるんだし、警察官として捜査に協力するのは当然でしょう? 私、やっぱり板尾さんは殺されたと思います。理由はお金か愛。世の中の殺人事件の八割は、そのどちらかが原因です」
「八割というデータの出典は? 警察庁の警察白書? あるいは、法務省の研究部の報告ですか?」
「いえ、『実話ハッスル』。コンビニの成人向け雑誌コーナーで立ち読みしました」
はきはきと返され、慎はうなだれた。前髪を搔き上げ、気を取り直す。
「それはデータではなく、限りなくでっち上げに近いですね」
「ですか……なによ。『情報収集を行うべきかと』って説教したのはそっちじゃない」
頭の「ですか」以外は独り言めかした、というより口に出したことに気づいていない様子だ。慎はきっぱりと言い渡した。
「僕の言う情報とは新聞やニュースの報道で、ゴシップ誌の記事ではありません」
「えっ!? ……すみません。私、頭に浮かんだことを知らないうちに声に出しちゃうクセがあるみたいで」
「知っています」
間髪を入れずに返すとみひろは恐縮して「すみません」と重ねて謝罪し、こう続けた。
「でも板尾さんは殺されたと思うし、河元さんは怪しいです」
「しかし、動機は? 一昨日の柿沼の話では、河元が借金や浮気をしている可能性は低い。三雲さんの言う、お金にも愛にも該当しないということです」
「わかってます。だけど」
みひろが言いかけた時、慎の前に誰かが立つ気配があった。はっとして視線を上げると、新海弘務がいた。
「すみませんが、切ります。続きは明日」
早口で告げ、慎は通話を打ち切ってスマホをポケットに戻した。その間に新海は周囲を確認し、慎の隣に腰掛ける。
「中森と抜き取ったデータの所在地は?」
挨拶抜きで、慎は問うた。こちらに目を向けず、新海は答える。
「探っているが、不明のままだ」
先月、初めてコンタクトを取った二週間後に慎が舟町(ふなまち)テクノリサーチのビルのトイレに行くと新海は現れず、代わりに洗面台の底に「五日後の午後二時。荻窪(おぎくぼ)中央病院の会計待合所」と書かれたメモが貼り付けてあった。メモの通りに病院に出向いた慎の前に地味なワイシャツにスラックス姿の新海が現れ、「盾の家では電話の使用は禁止で、放射線の研究に必要な器具や資料を入手するという口実で研究所から外出し、公安課の捜査員と接触している」と話した。今後は慎ともそのタイミングで会うこと、日時と場所は新海が定期的に訪れる舟町テクノリサーチのビルのトイレにメモを残すことを決め、その日は別れた。そして先週、慎がトイレをチェックすると、今日の約束が記されたメモがあった。病院の会計待合所もバーゲン会場も、混み合ってはいるがそれぞれ目的があり、慎たちに注目する人はいない。密談にはもってこいで、先日の佐原皓介の居酒屋といい、刑事課や公安課の捜査員は常日頃からこういう場所をリサーチしているのだろう。
さっきの若いカップルたちがはしゃいだ声を上げ、新海は反対側の壁際のベンチに目をやった。その横顔に、慎は訊ねた。
「神奈川県相模原市に、盾の家の施設または研究所はありますか?」
「相模原? 俺は知らないが、なぜだ?」
こちらを振り向き、新海は問い返した。今日も地味なワイシャツにスラックス姿で、ベンチの端に大きく膨らんだビジネスバッグと、書店の手提げ紙袋を置いている。
慎は自分の今の職務を打ち明け、中森がかけてきた内通と柿沼への電話、みのりの道教団について説明した。
「それなら簡単だ。盾の家は、みのりの道教団を監視している」
新海は即答した。「監視?」と問うた慎に新海は頷き、話を続けた。
「盾の家の代表である扇田鏡子(せんだきょうこ)と、みのりの道教団教祖の土橋日輪は二十年ほど前、同じ自己啓発セミナーの生徒だったんだ。短い期間だし二人とも経歴から抹消しているが、扇田と土橋は男女の関係だったらしい。だが土橋が同じセミナーの若い女に手を出して二人は破局し、扇田はセミナーを辞めて盾の家を始めたんだ」
「そうでしたか」
「しかし扇田の怒りは収まらず、盾の家のメンバー相手に土橋を『エセ教祖』『詐欺師』と糾弾する一方、在家信者にスパイを潜り込ませてみのりの道教団の動きを報告させてる。恐らく中森は、その報告で柿沼って職員の入信を知ったんだ。盾の家には、メンバーであることを隠して活動に協力する人間がいる。その協力者が相模原にもいて、中森を匿っていた可能性が高い。協力者は世間に溶け込むために携帯電話を持っているはずだから、中森はそれを使って内通電話をかけたんだろう。とは言ってもとっくに別の隠れ家に移動してるし、携帯電話も処分済みだぞ」
「わかりました。しかしなぜ中森は内通し、僕の来訪を柿沼に伝えたんでしょうか」
「知るかよ。あんなやつのことは、考えたくもない。それに、あんたの部下だろ?」
顔をしかめ言葉も尖らせた新海に、慎は「元部下です」とだけ返し前を向いた。
中森が盾の家の思想に感化され、メンバーになった可能性は? それなら警察職員の入信を知って内通し、みのりの道教団の活動を妨害しようとしたと考えられる。ならばなぜ、柿沼に我々の来訪を知らせた? そもそも、中森がどうやって職場環境改善推進室の職務を知ったのかという、根本的な疑問の答えが見いだせていない。
甲高い笑い声と複数の足音がして、慎は思考を止めた。反射的に振り向くと、若いカップルたちがベンチを離れ、売り場に戻って行くところだった。視線を戻そうとして、慎はベンチの上のものに気づいた。それが二枚のステッカーだと認識するのと同時に、慎の頭にさっきの女たちの会話が蘇った。
エコバッグだけを持ち帰って、ステッカーは棄てていったんだな。中身よりも、それを包んで保護するためのパッケージが大切ということか。矛盾した価値観だな。ふとよぎり、慎は胸に引っかかりを覚えた。それどころではないと思う一方、無視してはいけないとも感じ、慎は頭を猛スピードで回転させた。
「お菓子とかカレールーとか、少しでも外箱が潰れたりキズが付いたりすると売り物にならないんだって。そういうのの中身だけを貯めておいてくれるのよ」。蘇ったのは、二日前にスーパーことぶきの外で会った初老の女性の姿と言葉。続いて同じ女性の「あそこの娘と母親は。旦那を締め付けるばっかりで、何にもやらないんだから」という発言も再生された。そこに賞味期限切れのカレールーの箱を掲げて見せるみひろの姿と、河元を評した「とてもいい方ですよ」という波津の言葉、その波津が園田と顔を並べて土橋の後ろに控える光景、彼女が河元に生活用品の代金を支払った封筒の映像が、時間を遡るかたちで浮かんだ。そして慎の記憶の再生を締めくくったのは、「理由はお金か愛。世の中の殺人事件の八割は、そのどちらかが原因です」という、「実話ハッスル」出典による、さっきのみひろの発言だった。
そういうことか。仮説が確信に変わり、頭は次にすべきことを考え始める。
「おい。どうした」
新海に問いかけられた。慎は振り向いてベンチから立ち上がり、答えた。
「すみませんが、別件で急用です。引き続き中森とデータを追って下さい。連絡事項はあのトイレに」
- 1
- 2