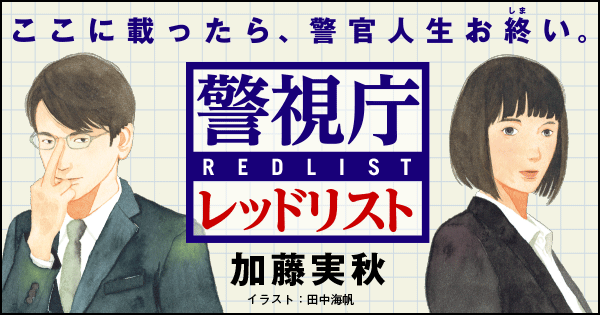〈第2回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」
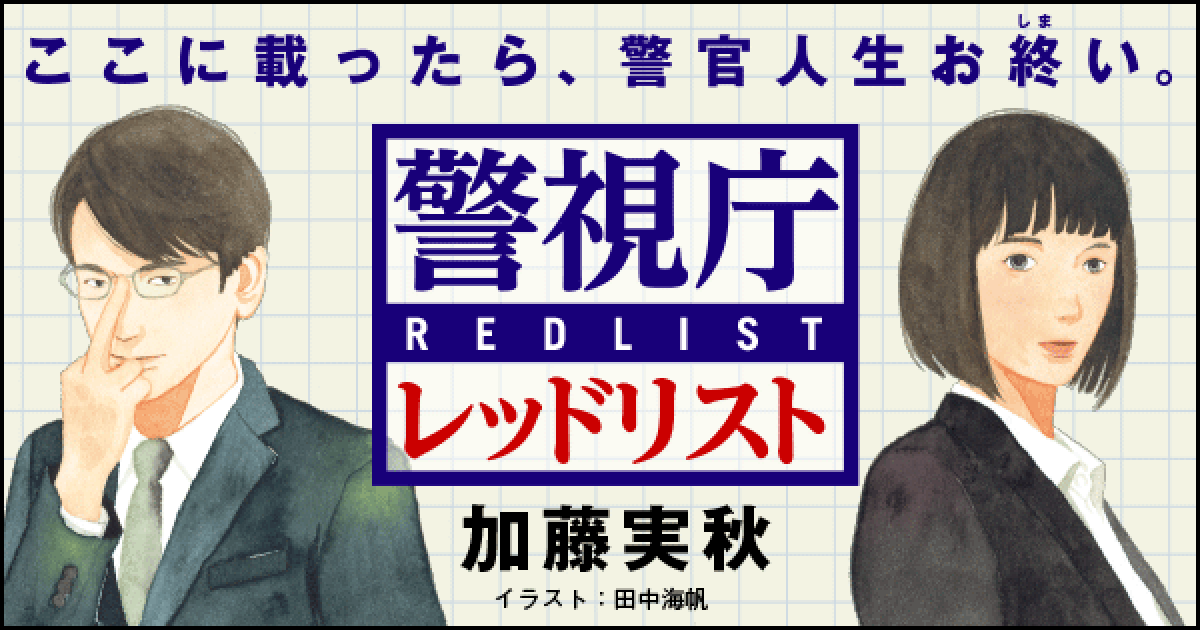
身内の警察官を調査する
新部署での仕事がはじまる。
6
「ガーリックトーストと、ナンドッグちょうだい」
片手を挙げてみひろが言うと、カウンターの向こうの摩耶(まや)ママは醒めた声で返した。
「うちはパン屋か。酒を飲みなさいよ」
「だって、おいしいんだもん。お酒だって飲んでるし。ほら」
下げた手で中身が半分残ったハイボールのグラスを持ち上げ、みひろは主張した。
「あんた、ここに来てすぐにホットドッグも食べてたけど……エミリちゃん。よろしく」
無表情に煙草(タバコ)をふかし、ママは横を見た。「はあい」と力の抜けた返事をして、エミリがカウンターの端の厨房に向かった。みひろと同年代。ライトブラウンにカラーリングした長い髪の先を巻き、胸元が開いた花柄のドレスを着ている。
「次、みひろちゃんの番。なにを歌う? aiko? それともPerfumeか」
呼ばれて、みひろは後ろを振り向いた。深紅のベルベッド張りのソファとローテーブルが置かれたボックス席があり、ソファの中央に腰掛けたジャージ姿の中年男がカラオケのリモコンを掲げている。中年男の隣には、アロハシャツを着た初老の男・森尾(もりお)と白いドレスを着た若い女・ハルナも座っていた。
「パス。吉武(よしたけ)さん、先に歌っていいよ」
みひろが答えると吉武は「了解」と返し、背中を向けた。ソファの向かいには小さなステージが設えられ、傍らの壁に歌詞字幕の映像用の液晶ディスプレイが取り付けられている。
スナック流詩哀(ルシア)、それがこの店の名前だ。みひろが暮らす警察の独身寮にほど近い商店街にあり、ランチ営業をしていたので入ってみたところおいしく、ママとも気が合ったので仕事帰りに立ち寄るようになった。今では常連で、近隣の商店主が中心の他の常連客とも顔なじみだ。店内は五人座るといっぱいのカウンター席と、ボックス席が一つ。壁には演歌歌手のポスターが貼られ、人工大理石のカウンターの上には胡蝶蘭の鉢植えとお湯割り用のポット、タワー状に積まれた灰皿とボックスティッシュが置かれている。
「で、どこまで話したんだっけ?」
前に向き直り、みひろは問うた。ママの後ろには、酒のボトルがずらりと並んだ大きな棚がある。
「公務員は、規則が厳しくて自由がないってグチ。もう何十回も聞かされてるけど」
表情を動かさずに、ママは答えた。エミリ同様ロングの巻き髪だが、鋭角的に整えられた細眉とごってり塗られたワサビ色のアイシャドーに時代を感じる。シワとたるみの目立つ四角い顔には、ファンデーションが白浮きするほど厚く塗られていた。
「そうそう、そうなの。あれはダメ、これは禁止って締め付けるクセに勤務時間は不規則、サービス残業当たり前。給料だってよくはないし、部署によっては危険もある。ブラックもいいところよ」
みひろは訴え、片手でグラスを口に運んでもう片方の手でカウンターをばしんと叩いた。鼻から煙草のけむりを吐き、ママは言った。
「でも、異動になったんでしょ? 新しい部署はどうなのよ」
「微妙。しかも、よりによって──なんでもない」
口を閉ざし、グラスをテーブルに戻す。
ちょっとした言葉や仕草から相手の気持ちと状況を読み取り、役に立って気持ちが楽になるアドバイスをする。それは好きだし、地味で平凡な自分に与えられた貴重な能力なのかもとは思う。しかしその能力を、常日頃鬱陶しく感じていた警察の規則のために使うのは躊躇するし、釈然としない。と、全部ぶちまけてしまいたいのだが、それこそ守秘義務という重大な規則に違反することになるのでできない。
「だからって、辞めようなんて考えちゃダメよ。三流大学出のフリーターが区役所の正規職員に、なんて今どき夢みたいな話なんだから。規則ならその辺の会社にだってあるんだし、適当に合わせておけばいいのよ」
「そうだけど。でも、その辺の会社は」
「不倫の疑いぐらいで、相手ともども身辺調査なんかされないでしょ」とこれまたぶちまけたいが、もちろんできない。この店に通い始めた一年ほど前、ママに「仕事は何してるの?」と訊かれた。正直に答えると色々面倒なので「公務員」とだけ返したところ、いつの間にか区役所の職員ということになり、店の他の女の子と常連客もそう思い込んでいるようだ。
「ところで、班長だか室長だかいう男はどうなの? 独身?」
ヒョウ柄のドレスに包まれた小柄小太りの体を乗り出し、ママが訊ねた。みひろはカウンターに頰杖をつき、「知らない。結婚指輪はしてなかったけど」と返した。大して飲んでいないのに、呂律(ろれつ)が上手く回らない。異動初日から慣れない仕事をした上、署に戻ってからその仕事の報告書を書かされ、慎に提出すると丁寧かつ冷静にダメ出しをされまくり、何度も書き直しをしたので、もうぐったりだ。
「ていうか、十歳も上のおじさんだし。思ってたよりは感じのいい人だけど、いまいち摑み所がないっていうか。なにげに上から目線だし」
そう続けて口を尖らせると、ママは鼻を鳴らして身を引いた。
「上司なんだから上から目線で当たり前じゃない。エリートなんでしょ?」
「元エリート。あれは訳ありだね。絶対そう」
「三十六年生きてりゃ、誰だって訳の一つや二つあるわよ。それにあんただって、あっという間に三十六よ。悪いこと言わないからその元エリート、ぱくっと捕まえちゃいなさい」
「なんでそうなるのよ」
みひろが返すとやり取りが聞こえていたらしく、エミリが厨房から顔を出した。
「みひろちゃんがいらないならその元エリート、私がもらう」
食パンにナイフでガーリックバターを塗りながら告げ、それに反応してボックス席の男たちが、
「元エリートって、俺のこと?」
「いや、俺だろ。もらってくれるの? 妻子持ちだけど」
と騒ぐ。脱力するのと同時に明日からのことを考えると気が重くなり、みひろはグラスに手を伸ばしてハイボールを飲んだ。