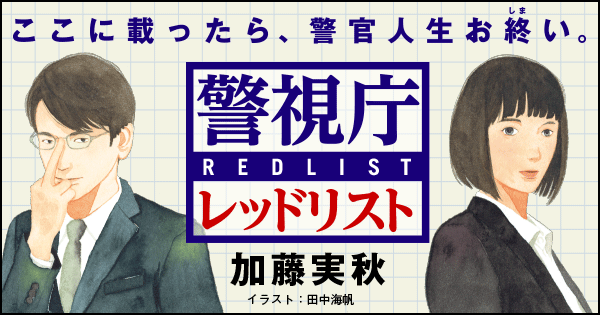〈第4回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

かと思われた事案は、
再調査で思わぬ結末に。
12
排気ガスの臭いと湿ってまとわりつくような空気に息苦しさを覚え、慎は咳払いをしてネクタイを少し緩めた。腕時計を覗くと、午後九時過ぎ。今日はみひろと水天宮から本庁に戻った後報告書を作成し、豆田に提出した。ここは警視庁から二キロほど離れたオフィス街の地下駐車場だ。天井に等間隔で並んだ蛍光灯が照らし出す場内は昼間のように明るいが、車が並んでいるだけで他に人影はない。
と、エンジン音がして通路を銀色の車が近づいて来た。車が駐車スペースの一つに入るのを確認し、慎は柱の陰から出た。周囲を確認してから、助手席のドアを開けてセダンに乗り込む。
「待たせたな」
エンジンを止め、運転席の佐原皓介(さはらこうすけ)が言った。小柄で童顔だが引き締まった体つきで、目つきも鋭い。ダークスーツのジャケットの襟には、「S1S mpd」という金文字が入った赤く丸いバッジ。警視庁捜査一課の捜査員だけが装着できるものだ。
「SSBCの動きは?」
挨拶抜きで問いかけ、慎はもう一度周囲を確認した。SSBCとは警視庁刑事部の捜査支援分析センターの通称で、防犯カメラやパソコンなど電子機器の情報解析と犯罪者のプロファイリングなどを行っている。
「三次元顔画像識別システムで中森の関係先と全国の主要ターミナル駅、空港などの防犯カメラの画像を解析したが、収穫なしだ。中森は持井事案のデータを抜き取った日に警視庁を出て、桜田通りを徒歩で虎ノ門方向に移動。以後の足取りは不明だ」
「都内に潜伏しているのか。共犯者(レツ)がいるのかもな。失踪前の交友関係は?」
「お前の方が詳しいんじゃないのか。直属の部下だろ」
慎はまず「元部下だ」と訂正し、佐原が呆れたようにこちらを見るのを感じながら続けた。
「失踪前、中森は体調不良による欠勤や早退が増えていた。『風邪が治りきらない』と言い、咳やくしゃみをしたり薬を飲んだりする姿も見たので信用していたが、実際は心療内科に通院していた。主治医には、『辛い』『なにもかも滅茶苦茶にしたくなる衝動にかられる』と話していたらしい。その片鱗は事件前の中森の言動にも現れていたはずだが、俺は見逃した」
「だから責任を感じて中森を追っているのか? 持井さんに『新部署への異動と赤文字リスト入りのどちらかを選べ』と突きつけられて、新部署を選んだんだろ? リスト入りして飛ばされれば、事件を嗅ぎ回れなくなるからな」
薄笑いを浮かべ、佐原は問うた。慎とは同期入庁で警察学校でもともに学んだ。しかし学科、実技、武道と常に首席だった慎を卒業まで一度も抜くことができず、いまだに根に持っている。
慎が黙っていると、佐原はさらに言った。
「しかし責任感だけでそこまでやるか? ああ、市民への罪悪感もあるのか。持井案件のデータが公になれば、大騒ぎになるからな。何しろあれは――」
ふいに言葉が途切れた。振り向いた慎が腕を伸ばし、佐原のジャケットの襟を摑んで引き寄せたからだ。とっさに顎を引き、佐原は目を見開いた。それを見返し、慎は告げた。
「お前の妹の息子。高校でいじめに遭って以来、引きこもり状態らしいな。最近じゃ、妹やその夫に暴力を振るうようになったそうじゃないか。捜査一課(ソウイチ)の管理官目前の身としては、是が非でも隠し通したい醜聞だな」
「それをどこで……脅すつもりか? お前、どうしちまったんだ。そこまでして、あのデータを守りたいのか?」
怯えや焦りよりも戸惑いの色の濃い眼差しを、佐原が慎に向ける。目をそらさず、慎は即答した。
「誤解するな。俺は責任感も罪悪感も抱いちゃいないし、データなんかどうだっていい。ただ、自分にふさわしいポストに戻りたいだけだ。何が何でも、監察官として返り咲いてみせる。そのために新部署での仕事は完璧にこなすし、お世辞や作り笑顔もお手のものだ」
顔を強ばらせ、佐原は「わかった」と頷いた。慎は彼を解放し、今後も中森の追跡捜査で動きがあれば報告することを約束させ、車を降りた。車は走り去り、慎もコンクリートの通路を出入口に向かって歩きだした。
俺は必ず、這い上がってみせる。そして俺を陥れた者たちよりも高い場所に立つ。
心の中で呟くと、脳裏にみひろと豆田の顔が浮かんだ。しかし胸を突き上げる強く激しく、同時に氷のように冷たい想いの前に二人の顔は一瞬で、なんの躊躇も感じずに消し去られた。
まっすぐ前だけを見て迷いのない足取りで、慎は通路を進んで行った。