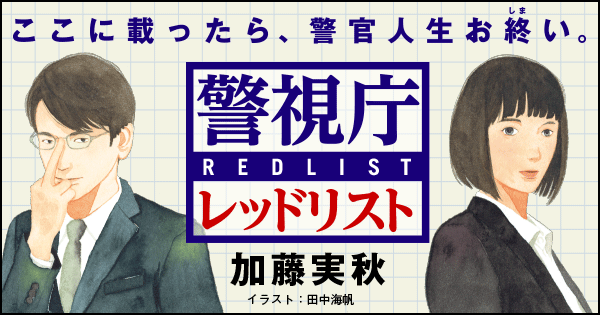〈第4回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

かと思われた事案は、
再調査で思わぬ結末に。
11
水天宮は、みひろが思っていたより狭かった。ビルとビルの間にあり、縦長の敷地に屋根が銅板葺(どうばんぶき)の本殿や朱色に塗られた柱や階段が印象的な弁財天、その脇には安産の祈禱を受けに来た人のための待合室もある。最近建て替えられたらしく、建物も参道も新しい。境内を一回りして、お産の予定はないが子宝いぬと安全子育河童の銅像を撫でたら、気持ちが少し収まった。
星井の次に黒須を会議室に呼び、改めて話を聞いた。過去にもその場限りの浮気の経験はあった黒須だが星井には本気で入れ込み、歯止めが利かなくなっていたらしい。慎が星井が副業を認めたと伝えると黒須は、「彼女を守りたい一心で副業を隠し、自分が関係を強要したと話しました」とうなだれて話した。その後みひろたちは日本橋署を出たが、慎は「小用があります」と車を停め、どこかに行ってしまった。目の前に水天宮があるのに気づき、みひろも車を降りて入ってみた。
ついでにお守りか絵馬でも買おうかと思っていると、「三雲さん」と呼ばれた。振り向いたみひろの視界に、出入口の方から歩み寄って来る慎の姿が映る。買い物をしたのか、手に白いレジ袋を提げていた。
「ここにいたんですか。お待たせしてすみません」
「いえ。今度こそ調査終了だし、次にいつこの街に来るかわからないので、入ってみました……真相が明らかになっても、黒須の処分は変わらないんですよね」
本殿の前の参道に立ち、みひろは慎を見上げた。頷き、慎は返す。
「ええ。規則は規則ですから。むしろ、星井をかばったことで処分が重たくなる可能性があります」
「じゃあ、星井は? 赤文字リストに名前が載っても、退職してしまえばお咎めなしですよね」
つい感情的になって問うたが、慎は動じずに答えた。
「そうなりますね。納得できませんか?」
「はい。でもそれ以上に、自分の至らなさっていうか認識不足を痛感しています」
「と言うと?」
メガネの奥の目を動かし、慎がこちらを見下ろす。促され、みひろはさっきから抱えていた思いを一気に言葉にした。
「規則で職員をがんじがらめにした上、行動を監視したり行き過ぎた処分をしたりする警察の体制に、疑問と不満を抱いていました。でも、そういう体制を利用して自分の目的を果たそうとする職員がいるなんて、考えてもみませんでした。腹が立つし、悔しいし、怖いです」
「規則は守られているかだけではなく、その守られ方が正しいかを見定めなくてはなりません。そのために監察、ひいては我々の存在が必要なんです。背後で目を光らせている者がいるからこそ、警察職員は緊張感とモチベーションを維持し、社会悪と対峙できるのです。それが、昨日の三雲さんの『警察って規則はすごく大事にするけど、人の気持ちを無視するのは平気なんですね』という言葉への答えです」
「はい」
警察組織への疑問と不満が消えた訳ではないが、今回の調査を振り返れば慎の言うとおりだ。みひろが素直に頷いたのに気を良くしたのか、慎はさらに続けた。
「それに、そう卑下する必要はありません。三雲さんは行動確認に於いては初心者で、圧倒的に経験値が足りない。至らないのも認識不足も当然で、職務に励み研鑽(けんさん)を重ねれば自ずと解決されます。加えて、今回の調査。星井の副業に気づいたのは僕ですが、きっかけは昨日の三雲さんの発言です」
「えっ。本当ですか?」
「ええ。三雲さんには人の話を聞いて心に寄り添う才能があり、それは我々の仕事に役立つ。先日僕が言った通りでしたね」
そう話をまとめて微笑み、慎は前髪を搔き上げた。
結局自慢? キザ全開だし。ていうか、上から目線の割になんでいつまでも敬語なの?
突っ込みは浮かんだが褒められたのは嬉しく、みひろは返した。
「ありがとうございます。正直、この職務を続けていけるか自信はないです。でも、このまま終わるのはしゃくだし、次は納得のいく仕事をしたいと思います」
「その意気です……ところで、本庁に戻る前にこれを食べませんか?」
言いながら、慎はレジ袋を開いて何かを取りだした。見ると、ラップフィルムにくるまれたホットドッグ用のパン。中央の切れ込みの中に、ちくわが丸々一本挟まれている。
「ちくわパンだ! そうか。これを売ってるお店って、この近くにあるんですよね」
「よく知っていますね。グルメサイトによると、『ちくわとツナマヨネーズソース、ふわふわのパンの食感のハーモニーが最高』だそうです。僕はパンに目がなく情報収集も完璧なんですが、今回はうっかりしていました。報告書の作成中に日本橋人形町という住所にピンと来なければ、食べ損ねるところでした」
「すごい偶然。私も大のパン好きです。休みの日に、あちこち食べ歩くのが趣味で」
驚いて語りだしたみひろをスルーし、慎は歩きだした。ほっそりとした白く長い指で、ちくわパンのラップフィルムを剝がす。
「えっ。それ、私にくれるんじゃないんですか?」
問いかけながら、みひろも歩きだした。ちくわパンに向けられた慎の顔はこれまでになく輝き、活き活きとしている。
この人、変。やっぱり訳ありだ。でも威張り散らさないし、やさぐれてやる気ゼロでもない。今はそれでよしとして、次の調査案件を待とう。じきにボーナスも出るし。
そう思い、気持ちが明るくなるのを感じながらみひろは慎のダークスーツの背中を追った。