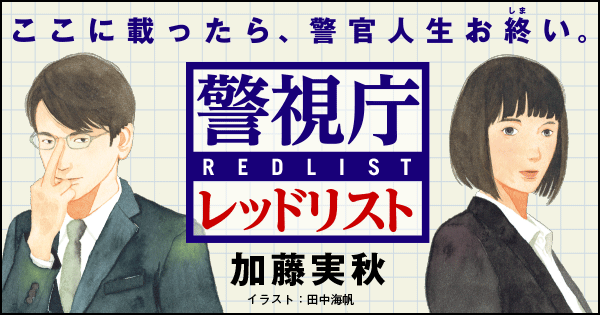〈第5回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

第一自動車警ら隊用賀分駐所へ出動する。
CASE2 ローン、アローン:借金警察官の涙(1)
1
深く下げていた頭を上げ、監察係首席監察官の持井亮司(もちいりょうじ)は身を翻した。部下の柳原喜一(やなぎはらよしかず)理事官が開けたドアから警視総監室を出て廊下を歩きだす。
「射撃訓練の時期と重なっていなかったのが、不幸中の幸いでしたね」
警視総監室から十分離れた頃合いを見計らい、後ろから柳原が語りかけてきた。
「ああ」
前を向いたまま、持井は返した。折田晴一(おりたせいいち)警視総監と相対した緊張感が、まだ残っている。持井と柳原が警視庁本庁舎十一階の警視総監室に入ったのは、二十分ほど前。部下である中森翼(なかもりつばさ)警部補のデータ抜き取りと失踪事件の現状報告のためだ。自席に着いた折田の傍らには人事一課長の日山真之介(ひやましんのすけ)もおり、主に発言したのは彼だった。日山が最も気にしていたのが、今はごく一部の関係者しか知らない中森の事件が外部、とくにマスコミへ露呈することだ。
警察組織の中では事務方の監察係だが、一年に一回実包射撃訓練が義務づけられている。通知を受けた係員は警護課の金庫室で自分の拳銃と弾丸を受け取り、江東(こうとう)区新木場(しんきば)にある警視庁術科(じゅつか)センター内の射撃場で訓練を行う。事件がこの訓練と重なり、中森が拳銃と実弾を所持したまま失踪していれば市民に危険が及び、公表は避けられなかった。監察実務の現場を仕切るのは持井だが、部署の顔は、警察庁から出向したキャリア官僚で警視長の人事一課長。よって非違事案発表会見が開かれれば記者たちの追及を受けることとなり、これを恐れる日山は常日頃から身内の不祥事は極力穏便に、可能な限り表沙汰にせずに済むよう腐心している。
「くれぐれも、二階に動きを気取られるな。広報課にも目を光らせるように伝えろ」
持井が命じ、柳原は「はい」と頷く。
新聞社や通信社の記者が詰める通称・警視庁記者クラブは警視庁本庁舎の二階にあり、同じフロアに広報課も入っている。記者たちが目当ての捜査員や係官の経歴や自宅の場所を知っているように、広報課の課員も記者たちの学歴、職歴、犯罪歴、学生運動歴、趣味などを把握している。報道発表やイベントの企画、警察音楽隊の運用などのイメージが強い広報課だが、最大の職務は記者クラブの監視とコントロールだ。
「警視総監も案じておられましたが、中森の目論見が読めませんね。事件発生当時はネットへの流出と拡散かと思いましたが、今のところWinny、WikiLeaksなどのネットワークにそれらしき気配はありません」
深刻な口調で、柳原は続けた。恐らく表情も深刻で、将棋の駒を思わせる四角い顔の眉間には深いシワが刻まれているのだろう。間もなく五十歳を迎える柳原だが、短く刈り込んだ髪は半分以上が白くなっている。前を向いて歩き続けながら、持井は返した。
「加えて、事件発生から二カ月以上経つが犯行声明、金銭の要求といったアクションもない。別の計画があり、データの抜き取りはその一部にすぎないという可能性もあるな……外事三課に行くぞ。海外の情報機関との連携状況を聞く」
「はい」
柳原が再度頷く気配があり、二人は足を速めた。公安部外事三課は国際テロ犯罪を扱う部署で、本庁舎の十五階にある。時刻は午前十時前だ。
エレベーターホールに着き、柳原が上りのボタンを押した。持井が外事三課との合議事項をシミュレーションしようとした時、
「そうそう。今どき恋愛禁止なんて会社、あり得ないって」
と、後ろで声がした。振り向くと、廊下を女が近づいて来る。歳は二十代半ばだろうか。淡いグレーのスーツを着て片手に茶封筒、もう片方の手にスマホを持って耳に当てている。
「だって、人間の感情は止められないじゃない。それに、恋愛ってダメと言われれば言われるほど燃えるのがお約束だし……やだ。『萌える』じゃなくて『燃える』だってば」
なにがおかしいのか顎を上げてけらけらと笑い、女は持井たちの隣で立ち止まった。小柄細身で、黒い髪を襟足の長さでまっすぐに切り揃えている。
「そもそも規則を振りかざすのは、何も考えてない証拠よ。見直したり、止めたり、変えるのが怖くて、続けることが正義ってすり替えてごまかしてるだけ。ルールを守るのは大切だけど、時と場合ってものがあるでしょ。車が一台も通らない真夜中の横断歩道の赤信号を、延々待ってる。律儀と取るか、間抜けと取るか。微妙だよね」
テンポよく語り、また顎を上げて笑う。その態度より話の内容が看過できず、持井は女に向き直った。ジャケットの胸にIDカードを付けているので警視庁の職員には間違いないが、茶封筒で隠れて氏名や部署名は確認できない。持井の表情を読み、柳原がうろたえだす。なにも気づかず、女はさらに言った。
「それに、規則で人を縛り付けるやり方なんて長続きしないから。そんなのちょっと考えればわかるんだけど、わからないのがいかにもオヤジ、バブル世代って感じ? 定年退職した翌年の正月に届いた年賀状の激減ぶりで、初めて己を知る訳よ」
「オヤジ」「バブル世代」が自分と合致することもあり、持井は黙っていられなくなった。焦った柳原が先に女に何か言おうとした矢先、チャイムが鳴ってエレベーターが到着した。
「あ、切らなきゃ。じゃあまたね」
ドアが開くと女はあっさり電話を切り、エレベーターに乗り込んだ。勢いをそがれた形になりながら、持井と柳原も後に続く。
ドアが閉まりエレベーターが動きだすと、持井は奥の壁際に立つ女に問いかけた。
「きみ。名前は? 部署はどこだ?」
弄っていたスマホから顔を上げ、女が初めてこちらを見た。小さな顔に作りの小さなパーツ。髪型といい、子どものようだ。
「職場環境改善推進室の三雲(みくも)みひろ巡査です」
きょとんとしている女に代わり、柳原が早口で答える。驚いてからもろもろ合点がいき、持井は首を縦に振った。
「きみが例の。なるほど」
言いながら胸に優越感と蔑みの気持ちが湧き、口元が緩むのを感じた。きょとんとしたままの女に、柳原が戒めの口調で告げる。
「こちらは、監察係首席監察官の持井警視正だ」
「監察係?」
訊き返してから何かに気づいたように「ああ」と呟き、女は、
「失礼しました。三雲です」
と一礼した。それを見下ろし、持井は話しだした。
「型破りだとは聞いていたが、それ以上だな……今のきみの電話だが、聞き捨てならない。赤信号を待つのは律儀だからでも間抜けだからでもなく、規則だからだ。道路交通法第七条に『道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない』と明記されている」
「すみません。友だちの相談に乗っていて、つい。以後気をつけます」
恐縮してみひろは再度頭を下げたが、持井はさらに続けた。
「きみは規則について一家言あるようだな。友だち相手とはいえ、庁舎内で就業時間中に堂々と語っていたんだ。『何も考えてない』だの『すり替えてごまかしてる』だのは、警察組織に対してのきみの考えと判断されても仕方がないぞ」
知らず、圧をかけるような口調と眼差しになる。「申し訳ありません」と俯いたみひろだったが、次の瞬間顔を上げてこう返した。
「警察が『何も考えてない』とも『すり替えてごまかしてる』とも思いません。でも、『規則で人を縛り付けるやり方は長続きしない』と感じることはあります」
こちらに向けられた眼差しにためらいはなく、自信と信念に溢れている。とっさに持井は言葉を失い、柳原は表情を険しくして口を開こうとした。片手を挙げてそれを止め、持井は話を変えた。
「職場環境改善推進室は開設早々結果を出しているようだな。日本橋署の非違事案の報告書は、私も読んだ。大活躍だったそうじゃないか」
「その件ですが、三雲巡査というより、阿久津(あくつ)の機転で」
なんのつもりか元部下のフォローを試みた柳原を遮り、持井は続けた。
「部署の発案者として心強い。これからも職務に励んでくれ……ところで、きみは何階に行くつもりだ?」
「あ、ボタンを押し忘れてました。別館との連絡通路に行きたいので六階──えっ。このエレベーター、上り?」
壁のパネルの階数ボタンを見て、みひろが騒ぐ。慌てて十四階のボタンを押し、到着すると「失礼します」と一礼してエレベーターを降りて行った。ドアが閉まり、エレベーターは再上昇する。
「大変申し訳ございません。出過ぎた発言でした」
流れる沈黙を怒りと受け取ったのか、柳原が頭を下げた。しかしそちらには目を向けず、持井は呟いた。
「『規則で人を縛り付けるやり方は長続きしない』だと? あの上司にして、この部下ありだな」
再び、胸に優越感と蔑みの気持ちが湧いた。が、同時に中森の事件に関する慎(しん)への憤りと怨嗟も蘇りそうになり、持井は口を引き結んで自分を鎮めた。
「三雲みひろ。要注意だな」
呟きが聞こえたのか柳原が顔を上げ、こちらの表情を確認するなり怯えたようにまた頭を下げた。