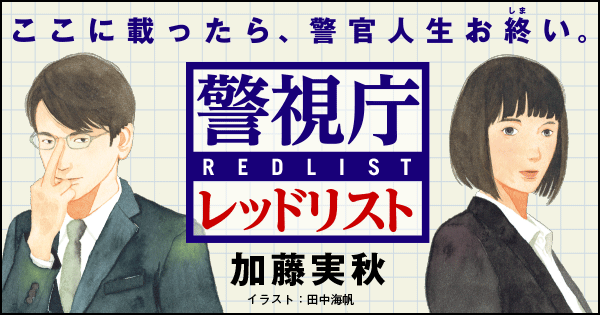〈第5回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

第一自動車警ら隊用賀分駐所へ出動する。
2
みひろが職場環境改善推進室に戻ると、慎は自分の机でノートパソコンに向かっていた。
表情のない顔も、絶え間なく流れるキーボードを叩く音も、三十分前に部屋を出た時と変わらない。
「お帰りなさい。制度調査係はどうでしたか?」
手を止めず、ノートパソコンの液晶ディスプレイに目を向けたまま慎が問うた。椅子を引いて向かいの席に座り、みひろは返した。
「遅くなりました。みんな元気で変わりなく──そう言えば、帰りのエレベーターで」
伝えようとして、持井とのやり取りが蘇った。高圧的な態度と説教は「ザ・警察幹部」という感じだったが、みひろが慎の部下だと知るなり浮かべた意味深な笑みと、こちらを評価もしているようなことを言いながら、慎の名前を一度も口にしなかったのが気になる。慎が監察係からここに来た理由と関係しているんだろうなとは思ったが、面倒臭そうなので話題を変えた。
「いえ、なんでもないです。それより、制度調査係に呼ばれた理由。何かと思ったら、これですよ」
言いながら、抱えていた茶封筒から長方形の白い台紙を取り出す。扉を開いて薄い和紙を捲(めく)り、台紙に収められた縦二十五センチ、横二十センチほどの写真を向かいに見せた。写真に写っているのは、スーツ姿の三十代前半の男。小太りで髪を角刈りにしている。
「お見合いですか」
手を止めてメガネのレンズ越しに写真を見て、慎が言う。みひろは頷いた。
「ええ。『結婚なんてまだ考えてない』って言ったんですけど、無理矢理渡されちゃって。かわいがってもらっていた先輩の旦那さんの後輩で、会計課の人だそうです。いい人っぽいけど、今どき角刈りって」
「これからも見合いや縁談を勧められますよ。警視庁の女性警察官の割合は九・八パーセント。うち何パーセントが独身かは不明ですが、貴重な存在なのは間違いありません」
表情を動かさず、淡々と語る。みひろは写真を引っ込め、扉を閉じた。
「そう言えば、警察官って職場結婚が多いですよね。しかも上司や先輩からの紹介ってパターンが多くて、職場ぐるみで奨励してる感じ」
「同業者だと、公務に理解を得やすくなります。警察職員なら身元も確かですし」
「警察職員以外の相手は、身辺調査をするんですよね。本人だけじゃなく、親族に前科や特定政党・宗教とのつながりがある人がいても『結婚するな。したければ辞職しろ』って言われるとか。あと、外国人もNGらしいとも聞きました。そういう規則なんですか?」
「いえ。結婚に関する規則はありません。身辺調査は事実ですし、相手のバックボーンに職務に支障を来す要素があると判断した場合は再考を促します。とはいえ強制力はないので、いま三雲さんが挙げたような相手と結婚した職員もいますよ」
「でも、赤文字リスト入りですよね?」
勢い込んで迫ったが、慎は「そうですね」と当然のように頷く。鼻を鳴らし、みひろは胸の前で腕を組んだ。
「規則がないのは、支障の根拠を証明できないからでしょう? それなのに圧力をかけて従わないと制裁を下すって、規則で縛るより問題なんじゃないかなあ。で、その問題の象徴が、赤文字リストっていう……本当に赤い文字で書いてあるんですか? 表紙も赤くて、白で『RED LIST』って書いてあるとか」
後半は好奇心が不満に勝り、身を乗り出して問う。ため息をつき、慎は目を伏せて右手の人差し指でメガネのブリッジを押し上げた。
「『DEATH NOTE』に影響されすぎですね。まあ確かに、マンガも映画もよく出来ていましたが」
「えっ。室長、マンガを読むんですか? でも、『よく出来て』ってなにげに上から目線」
みひろが問いかけつつ突っ込んだ時、ノックの音がしてドアが開いた。
「おはようございます。いや~、暑いね。梅雨も明けたし、夏本番だ」
ハンカチで汗を拭き拭き捲(まく)し立て、豆田益男(まめだますお)が部屋に入って来た。七月に入り、気温三十度に迫る日が続いている。この部屋も北側なのにエアコンを入れていても暑く、みひろは私物の卓上扇風機をフル稼働させている。加えて湿気もすごいので部屋のあちこちに大きさと形の違う除湿剤が置かれていて、それを見た豆田は「魔除けか呪いの儀式みたいだね」とコメントした。
みひろと慎が挨拶を返す中、豆田は机に近づいて来た。
「また監察係から調査事案が届きました。第一自動車警ら隊の用賀分駐所(ようがぶんちゅうしょ)」
そう告げて、慎にファイルを差し出す。受け取った慎はファイルから書類を出し、読み始める。みひろは訊ねた。
「自動車警ら隊っていうと、『警察24時』ことテレビの警察密着番組でお馴染みの?」
「なにそれ」
豆田が脱力し、書類に目を落としたまま慎は言った。
「警察職員としていかがなものかと思いますが、イメージ的には間違っていません。三雲さん、出動です」
「はい」
見合い写真を放り出し、みひろは急いで身支度を始めた。