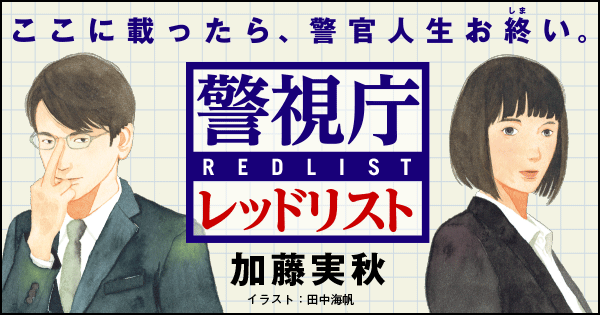〈第5回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

第一自動車警ら隊用賀分駐所へ出動する。
3
第一自動車警ら隊用賀分駐所は、警視庁用賀署内にあった。みひろと慎は署長と分駐所のトップである中隊長に会い、訪問の趣旨を説明して隊員への聞き取り調査の許可を得た。その後、今回の調査対象者がパトロールに行っていると聞き、みひろたちも分駐所を出た。
車を環状八号線の道の端に寄せ、慎はエンジンを止めた。助手席のシートベルトを外して窓の外に目を向け、みひろは言った。
「やってますねえ」
中央分離帯を挟んだ反対車線の歩道寄りに、車が二台停まっている。環状八号線を行き交う車の間から見ると一台は黒いミニバンで、もう一台はパトカーだ。ミニバンの向こうに見える歩道には、タンクトップにハーフパンツ姿の若い男と警察官が立って話している。警察官はもう一人いて、ミニバンの荷室を調べていた。職務質問、警察用語で言う「バンかけ」だ。パトカーが今回の調査対象者が乗車しているものであることは、屋根に記された「135」の番号でさっき確認した。この番号は「対空表示」と呼ばれ、パトカーのフロントとリヤウィンドウにも記されている。対空表示にはいくつかの種類があるが、自動車警ら隊、通称・自ら隊の場合は所属する隊と車両の通し番号の組み合わせだ。つまり「135」は、第一自ら隊の35番目のパトカーということになる。歩道の奥は砧(きぬた)公園で緑が広がり、遊歩道なども見える。
「スモークガラスを貼った改造車。運転している人は平日の真っ昼間にあの恰好で、金髪メッシュ。私でも職質したくなりますけど、実際に薬物とか、持ってちゃダメなものが見つかって検挙できる割合ってどれぐらいなんでしょうね」
男とミニバンを眺め、みひろは問うた。男は所持品検査を受けている様子で、ふて腐れた顔で警察官に財布を渡している。運転席から同じ方向を見て、慎が返す。
「平成二十九年中の職務質問による検挙数は、約四万件。そのうち自動車警ら中の検挙は約一万五千件と、トップです」
「へえ。さすが、『警察24時』に取材されるだけありますね」
「『警察24時』の何が『さすが』かはさておき、薬物以外にも『持ってちゃダメなもの』はあり、最近増えているのがナイフやハサミなどの刃物です。銃刀法で定められた長さを超えるものは検挙の対象となりますが、所持に対する正当な理由があれば問題ありません。逆にマイナスドライバーや大量のヘアピンなど、法規制の除外物でも正当な理由なく所持していると、署に任意同行を求められる可能性があります」
「なんでマイナス限定? プラスドライバーならOKなんですか? あと、ヘアピンでできる犯罪って」
「どちらもピッキング犯罪に使われるんです。ああいう所持品検査では、偽造クレジットカードや振り込め詐欺で奪われたキャッシュカードが発見されるケースも増えています」
「なるほど。室長って、警察に滅茶苦茶詳しいですね。そんなに好きなんですか?」
感心しつつ訊ねると慎は呆れた様子で「好き嫌いではなく、職務上の常識です」と答え、話を変えた。
「調査対象者は、男と話している方です。里見洋希(さとみひろき)巡査長、二十八歳。『職場の仲間から度々金を借り、返済が滞っている』と内通がありました」
「借金ですか。内通者はお金を貸した人かも。自分で『返して』って言えばいいのに……言えない理由があるってことか」
「早速分析ですか。頼もしいですね」
やり取りしながら、二人で里見に目を向けた。ひょろりとして、黒縁のメガネをかけている。身につけているのは、半袖のスカイブルーのワイシャツに濃紺のベストとスラックスという制服。通称・活動服の夏服で、制帽も夏用だ。ミニバンの荷室を調べている方は三十代半ばで、小柄だががっしりした体つきをしている。
所持品検査と車内検査では何も見つからなかったらしく、里見たちは男を解放した。不機嫌そうにミニバンに乗り込んで走り去る男を、脱帽し頭を下げて見送る里見が印象的だった。
続いて里見たちは、歩道を通りかかった中年男に声をかけた。ミニバンの男とは逆に長袖長ズボン姿で、痩せていて顔色が悪い。薬物の所持を疑ったのだろう。里見たちは「背中のリュックサックの中を見せて欲しい」と乞うたようだが、男は怒りを露わにして首を横に振った。たちまち押し問答になったが、よく見ると里見が所持品検査を求め続ける一方、小柄な警察官は笑顔で男の訴えを聞き、なだめている。いわゆる「良い警官と悪い警官」という役割分担で、刑事課の取り調べで用いられているのはみひろも知っていたが、職質の現場でも行われていたとは驚きだ。
二十分以上ゴネてから男は所持品検査に応じたが、里見がリュックサックを調べている間中、小柄な警察官は男と話し続けていた。男の返事の仕方や顔色、目の動きなどで薬物の隠し場所や中毒の有無などをチェックしたのだろう。
しかしまたもや何も見つからず、里見たちは男を解放するとパトカーに乗り込み、走り去った。
「行っちゃいましたよ」
みひろは告げたが慎はあっさり、
「大丈夫。じきに戻って来ます」
と返した。
その自信の根拠はなに? 訝しみ、みひろが通りを眺めていると、本当に五分ほどで里見たちのパトカーは戻って来た。反対車線の歩道側をのろのろ走っては停まり、を繰り返している。
「なんで? こんな公園じゃなく、駅前の繁華街とか怪しい人がいそうな場所に行けばいいのに」
パトカーを目で追いながら、みひろは疑問を呈した。慎が答える。
「そういう場所は、別の隊員がパトロールしていますよ。それに公園の近くというのは、一見治安がよさそうでも実は駐車場が多い、長時間車を停めていたり、うろうろしていても怪しまれないなど、犯罪の温床になりやすいんです」
「確かに。でもそれなら、私服で覆面パトカーの方が検挙しやすくないですか?」
「逆です。制服とパトカーは、挙動不審者を浮上させる最強のアイテムです。普通は『ああ。警察だな』と思うだけですが、後ろめたいことのある者は目をそらす、車のスピードを上げるなど不自然な反応をします。それを運転中でも見逃さないのが自動車警ら隊で、いわばバンかけのスペシャリストです。地域課や交通課の警察官・パトカーと混同されがちですが、配属されるのは、人を見抜く目と運転技術の双方に長けた者だけです」
「つまり、すごい精鋭部隊ってことですね。そんな人が、なんで借金なんか……そろそろ里見に声をかけませんか?」
疑問と興味を胸に覚えみひろは促したが、慎は前を向いたまま素っ気なく返した。
「我々が行かずとも、向こうから来てくれますよ」
意味がわからず訊き返そうとした時、みひろたちの車の後ろに赤色灯を回転させたパトカーが停まった。驚く間もなくパトカーのドアが開き、里見と小柄な警察官が降車する。みひろたちの車に歩み寄って来た里見が、こんこんと運転席の窓をノックした。助手席の外には小柄な警察官が立つ。慎が運転席の窓を開けると、里見は身をかがめた。
「こんにちは。どうしました? ずっと停まったままですよね」
明るく問いかけつつも、メガネの奥の細い目は慎、みひろ、ダッシュボードと動く。小柄な警察官も、頭を低くしてこちらを窺(うかが)っているのがわかった。
「失敬。こういう者です」
涼しい顔で告げ、慎はスーツの胸ポケットから警察手帳を出して開いた。下にバッジ、上に顔写真と階級、職員番号が記されたカードが収められている。階級の「警部」を確認したらしく、里見はたちまち神妙な顔になって身を引き、
「失礼致しました!」
と敬礼をした。小柄な警察官も警察手帳を確認したようで敬礼し、「お疲れ様です。本庁の方ですか?」と訊いてきた。
「はい。人事一課です」
慎の返答に里見の顔色が変わり、小柄な警察官も黙る。二人を見て微笑み、慎は続けた。
「そう警戒しなくとも。人事一課ですが、監察係ではなく雇用開発係の職場環境改善推進室です。よりよい職場の環境づくりのための聞き取り調査に協力していただくと、聞いていませんか?」
「ああ。さっき中隊長から無線で聞きました」
小柄な警察官が表情を緩め、里見もわかりやすくほっとする。
借金疑惑のある里見はともかく、もう一人までこんなに態度が変わるなんて、人事一課ってどんだけ恐れられてるのよ。驚き呆れる一方、自分たちが見張るのと同時に、里見たちも反対車線からこっちをマークしていたんだなと感心する。目が合ったので、
「よろしくお願いします」
と極力明るく微笑むと、里見も笑顔になって会釈した。