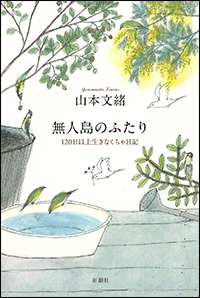吉川トリコ「じぶんごととする」 11. 優しい自己責任論者のためのエンディングノート
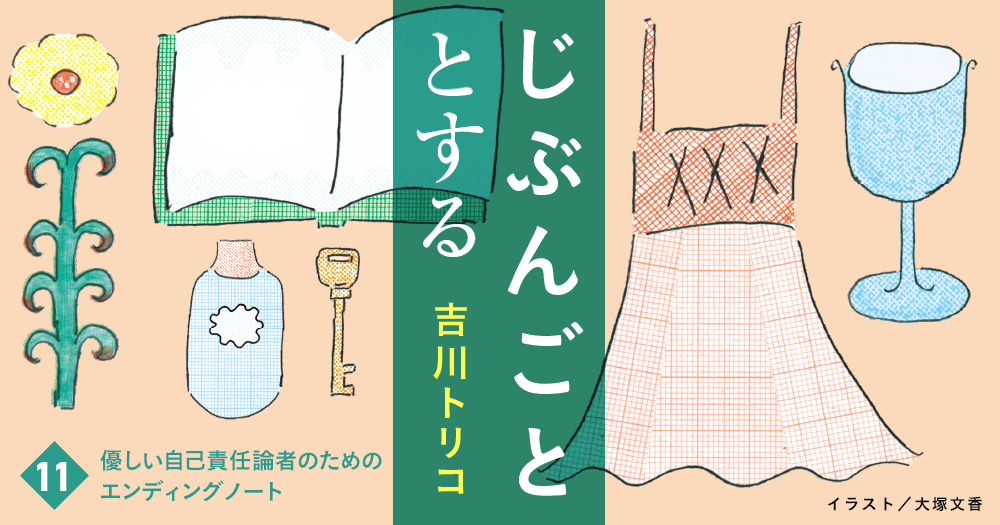
だからというわけでもないけれど、つい先日エンディングノートを書いた。
できることなら死んでもだれにも迷惑をかけたくないが、死んでしまったらどうしようもないから、なんとかその迷惑を最小限に抑えられるように生きているうちにどうにかしておくしかない! といまだ自己責任論者養成ギプスをバキバキにきめながら私なりに考えた次第である。
遠い将来(ゆ)に迷惑をかけることも恐ろしいが、いま私が突然死んだりしたら夫がさぞかし困るだろう。銀行口座やSNSのアカウントやなんやかんや、なにひとつ情報を共有していないし、出版社に連絡しようにもどこのだれに連絡していいのか、わからないにちがいない。そのことがずっと気がかりだった。
さいわいと言っていいかは微妙なところだが、イラストレーターの早川世詩男くんは夫の幼なじみなので、「私になにかあったら、まず世詩男くんに連絡するように」とは前々から言いわたしてあった。ポプラ社から出した本の装画を世詩男くんに描いてもらったことがあったので、ポプラ社の担当(こ)氏に世詩男くんから連絡してもらえば、(こ)氏が各社の担当に連絡してくれるはず——といったようなことを、(こ)氏にはなんの許可もとらずに勝手に算段していた。(こ)氏からしたらいい迷惑である。目先のだれかに迷惑をかけないようにするあまり、遠くのだれかにそのしわ寄せがいってしまうなんて、元も子もあったものではない。
しかし、いざ市販されているエンディングノートを書店で手に取ってみたら、「幼少期の思い出」とか「実績・経歴」とか「大切な人へ伝えたい思い」といった項目がずらずら並んでいて、なんだかげんなりしてしまった。いつごろからか、葬儀場でとりおこなわれる葬式がやたらと感傷的なメモリアル演出を加えてくるようになったが、まさにあの世界観である。この社会にはだれが決めたのかもわからない「あるべき姿」の雛形が無数に存在するけれど、あのノートの項目を埋めていくことによって、「さまざまな功績を世に残し、遺された人々への感謝をしたためて死んでいった美しく清らかな故人」みたいな物語に押し込められてしまうかんじがしてぞっとしなかった。
そんなふうに斜にかまえていられるのも、自分がまだ死なないとどこかで高を括っているからかもしれない。緩和ケア病棟のルポなどを読んでいると、残された時間の中で自分史を書き記すことに精を出す患者も多いというし、いざ自分が余命いくばくもないと告げられたら、なにか書かずにはおれないとも思う。そのときなにを書くかはまだわからないけれど、うまく書こうとか、最後に一発、とんでもない傑作をものしてやろうとか、自分が死んだ後にこれを読んだ読者はどんな顔をするだろうとかいった煩悩まみれでなにかを書いている気はする(つまり、いまとそう変わらない)。
もしかしたらそのときになっても、「大切な人へ伝えたい思い」なんてかんたんに言葉にできたら苦労しねえよ〜とくだをまいているかもしれない。これまで原稿用紙何枚分の原稿を書いてきたのか、ちゃんと数えたことがないからわからないけれど、仮に一万枚だとしても、それだけの枚数を費やしたってぜんぜん足りない気がする。
ところで、市販のエンディングノートはほっこりしたかんじの淡い色彩のものが多く、それはそれでかわいらしいんだけど、おしゃクソ的にはもうちょっとバリエーションがほしいと思ってしまう。シンプルかつ洗練されたデザインで、クールにドライに実務的な項目をたんたんと埋めていく、そんなおしゃクソによるおしゃクソのためのエンディングノートがあれば飛ぶように売れるんじゃないだろうか。うしろのほうにフリースペースをたくさん取っておけば「幼少期の思い出」とか「実績・経歴」とか「大切な人へ伝えたい思い」とか書きたい人は書けるだろうし、エンディングノートは折々更新していくものだから、同じ項目のシートを最低でも十枚ずつ綴じ込んでおきたい。どうでしょう、どこかの会社でこのアイディアを買ってくれたりしませんかね……?(とにかく老後の資金が不安なんです!)
山本文緒先生が亡くなってから一年後に刊行された『無人島のふたり 120日以上生きなくちゃ日記』には、文緒先生ががん告知を受けてから亡くなるまでの半年のあいだに、さまざまなものに別れを告げ、少しずつ死へと向かう準備を進めていく様子が仔細に記されている。最初のほうでは、王子(※文緒先生の夫さん)の助けを借りなければ暮らしていけないこと、自分で自分の終いをやり遂げられそうにないことをぼやいていたが、終わりに近づくにつれ、素直に王子に甘えられるようになれたことを、先生ご自身が喜んでいるというか、ほっとしているように読めた。もしかしたら先生も病気になるまで自己責任論者ギプスをバキバキにきめていたのかなあ、なんて。
刊行されたばかりのときは、いろんな感情でぐちゃぐちゃになってとても冷静に読めなかったが、いまこのタイミングで読みかえしてみたら、やっぱりめちょめちょのべそべそになって、先生がこの本を遺してくれたことに対する感謝の気持ちで胸がいっぱいになった。
病気がわかってから、依頼をもらうたびにちいさな噓を重ねてお断りしなければならなかったことを先生は日記の中で謝っていたが、ほんとうにどこまでも文緒先生らしい心遣いだと思う。『余命一年、男をかう』の刊行時、パブリシティの一環として、「もし余命一年だったら」というテーマで何人かの作家に競作エッセイを書いてもらったことがあるのだけれど、実は当時の担当(あ)氏と相談し、文緒先生にも原稿を依頼していたのだ。体調を崩しているから今回はご遠慮させてくださいという返事がきて、残念だけどしょうがないね、先生の体調が心配だね、早くよくなるといいね、なんて話していたことを覚えている。あとから思うと、なんと能天気で、なんと無神経だったんだろう。知らなかったとはいえ、余命宣告をうけた渦中の人にそんな依頼をしてしまうなんて。そのことを私はずっとうしろめたく思っていた。おそらく(あ)氏もそうだったんじゃないかと思う。
日記の中で先生は、『余命一年、男をかう』をとりあげ、「面白かったです」とわざわざ記してくださっていた。もしかしたらこれは先生からの配慮だったんじゃないかと勝手に私は思っている。先生が亡くなったことを知ったら、きっと私や(あ)氏が気に病むだろうと先回りして考えて、大丈夫、大丈夫だから気にしないで、と先生が言ってくれているのではないかと。
やさしすぎるほどやさしい。先生がそういう人であったことを私はよく知っているし、私だけでなく熱心な山本文緒の読者ならおそらくだれもが知っているだろう。この本で先生はいろんな人たちにメッセージを送っていたけれど、私たちにもそのやさしさをわけてくれたのではないかと思えてならない。そうじゃなかったとしても、そう思うことをどうか許してください。
遺された者たちは、こんなふうに勝手に故人の言葉を享受する。わずかな言葉のその奥にこめられた思いを血眼になって読みとり、どうにか対話を試みようとする。「大切な人へ伝えたい思い」なんて原稿用紙一万枚でも書ききれる気がしないといったそばから矛盾するようだけれど、「面白かったです」というたった一言が、こんなにも雄弁にさまざまなことを伝えてくれるなんて思ってもいなかった。
だけど、よくよく考えてみたら、そもそも山本文緒という作家がそういう作家だったじゃないか。なんということもない平易な言葉の積み重ねなのに、一文一文の切れ味といったらすさまじく、これまでどれだけゆたかなことを読者に伝えてくれただろう。
見あげると、ずっと先まで、道しるべのように点々と光る石が続いている。その軌跡は決してまっすぐではなく、よろよろとあっちへいったりこっちへいったりしているけれど、そのあけすけなほどの右往左往っぷりが、なによりあとに続く者たちへのエールになる。
私にとって、山本文緒とはそうした作家であった。文緒先生が最後に書き記したこの本も、遠くのほうでひときわ強い光を放っている。よりよく生きて、いずれ死んでいく。きっと、その指針になるだろう。
- 1
- 2