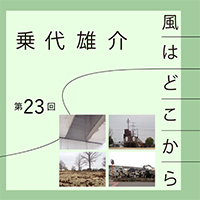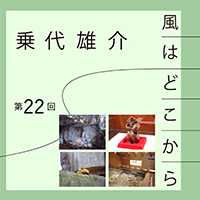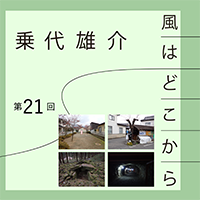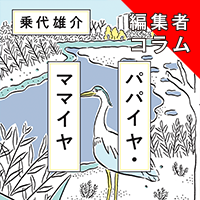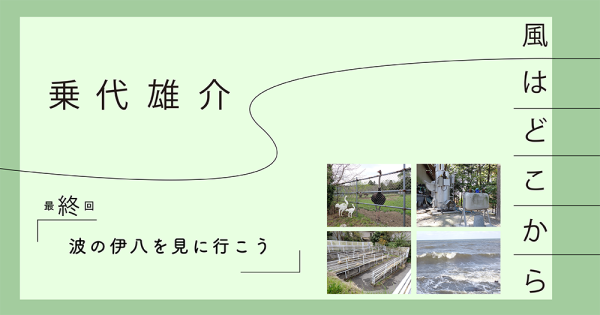乗代雄介〈風はどこから〉最終回

最終回
「波の伊八を見に行こう」
千葉県茂原市、JR茂原駅の東口を右に出ると、線路沿いに遊歩道が延びている。しばらく歩くと阿久川に突き当たり、渡る前に曲がって右岸の道に入る。尾崎紀世彦の「また逢う日まで」を聴き始めたのは、阿久悠作詞だからである。前方に大きなガスホルダーが見えた。ガスタンクではなくガスホルダーが正式名称らしい。薄緑色をした球体の曲面には「天然ガスと七夕のまち もばら」と書いてある。
千葉の大部分、東京、神奈川、埼玉、茨城の一部に分布している南関東ガス田には、約3685億立方メートル、日本の年間消費量で計算すると3年分という量の天然ガスが埋蔵されている。採掘に伴う地下水の汲み上げが地盤沈下を引き起こすため採掘と供給は一部に限られており、その中心が茂原市なのだ。茂原市の都市ガスにはこの地産ガスが用いられており、国際価格の変動に影響されないという。
このガス田の発見については諸説あるが、1891年の千葉県大多喜町に残されている話が実用化のきっかけのようだ。醬油醸造業者の山崎屋太田卯八郎が井戸を掘っていると、泡を含んだ茶褐色の塩水ばかりで真水が出ない。がっかりして吸っていた煙草を投げ込んだら、青白い炎が上がってそこにいた皆が驚いたという。今だったらそんな工事の折に喫煙もポイ捨てもしないし発見されないかも、とか十数年前は思いもしない感想を抱いてしまう。
阿久川はやがて一宮川に合流した。護岸工事の真っ最中で、法面にコンクリートを積んでいっている様子がよくわかる。その最先端、次の工事区域にあたる土でナノハナやナズナが花を咲かせていた。
その先には、さっきから白いローゼ橋が見えている。ローゼ橋は、アーチの下に道路がある下路アーチ橋の一つで、アーチ部と路面部の材の厚みが同じくらいの橋のことをいう。ほほえみ橋という名らしいが、下路の横に似たような太さの天然ガス輸送管がくっついていて見所の多い橋だ。せっかくなので左岸から右岸へ渡ってみると、こちらの方が堤との高低差があって、自転車用スロープ付きの階段が住宅の並ぶ道へと続いていた。それとは別に車椅子用のスロープがあり、十数メートル四方の空間でつづら折りに四度曲がって上下をつないでいる。一見してぎょっとする場の取り方でたくさん写真を撮っていると、傍らの看板に説明があった。
「このスロープは交通バリアフリー法等の法令に基づいてつくられたものです。傾斜は5%勾配といい100mの間に5mの高さを上る(下る)程度の坂道となっています。」
車いすが無理なく自走できる上限が5%勾配とされている。塾講師をしている時に車椅子ユーザーの生徒を長く見ていた時期があったのでこういうことを知らないわけではないのだが、大小の川沿いにつながるこのくらいの階段をさんざん上り下りしてきたというのにこんなスロープは初めて見たし、意識したのも初めてだった。

上から眺めつつ、もっと効率のいい方法はないかと考えてみたが、これくらいの傾斜ではどうしたって道を重ねられない。3mもない高低差と思うが、それを一人で上り下りするためにはこのくらいのスペースが必要なのだとまざまざと見せつけられて、しばらく物思いにふける。そのうち、学年にばらつきのありそうな小学生集団が、ちょっとこちらを警戒しながら自転車用スロープを上っていった。
その後ろ姿を追いかけるように私も歩き始める。中の島公園の桜は昨日までの雨もあってほとんど散り、歩道はしばらくピンク色に染まっている。右岸は川沿いの道がなくなるので、民家の間の道を行く。家の前ですやすや寝ている小麦色の犬をにこにこ見ていたら、その後ろの物陰に隠れていた別の犬に吠えられて驚いた。
南に進むと、細い川に当たった。鶴枝川というらしく、一宮川と合流する一帯にはその名を取った鶴枝遊水公園が広がっている。堤防の下に行くと、湿地ではカジカガエルの大合唱だ。日頃から水が入っているところなのだろうか。歩けるようになっているところも、雨の影響なのだろう、刈られたままに横たわった枯れ草を踏みしめると底から水がにじみ出てくる。傍らの小さな流れは、緑っぽい体のヌマエビが目視できるほど透き通っていた。防水カメラを水中に突っ込んで小さな姿を撮影するなどしていたら、腰が痛くなった。
道が悪いので一宮川の堤防に上がって下流に向かったが、その先が工事中で通れない。大きく回り道をして一宮橋を渡っても、川沿いの道はなお通行止めだ。一つ離れた道を行くと、七井圡西部土地改良組合による立派な竣功記念碑があって、しばし読みふけった。
「古来道は狭く曲折多く人馬の歩行に足りる程度にして畑地は僅少なり、山辺は多量の冷湧水で腰を没し、川辺は常時畑地と化す強湿過乾田が混在する、加うるに降雨ともなると何時しか河川が氾濫して一夜にして耕地一面泥海と化し作物は枯死寸前となること屢なりにもかかわらず先人は秋の実りを夢想して春ともなれば鍬先に意欲を託し難渋に耐へるを宿命として日夜農耕に勤しまれたり……」
平成二年三月吉日、組合長理事の髙仲精一撰文とある。約四十年前においくつであったかはわからないが、文語体を扱える人が普通にいる最後の世代であったかもしれない。読みやすい碑文も見てきたが、こういう格調を意識したものを今も続く河川工事のそばで読むと、土地も文も変わりゆくものだとしみじみする。少し歩くと髙仲家のお墓があったが、墓誌にお名前は見当たらなかった。
はっきりしない天気の中をしばらく行くと、木々の間に覗いたフェンスの奥にダチョウが数羽見えた。混乱して確認したグーグルマップには〈長生 ダチョウ牧場〉とある。外から見られるように植栽にいくつかの隙間ができているのだが、ひときわ大きな一羽は人に興味があるのか、私がそこに現れるたびに目の前にやって来た。首をフェンスの上までぴんと伸ばし、凜々しい顔で遠くを見つめている。The Creation「Ostrich Man」を聴きながら、古代ローマの博物学者プリニウスの間違いのせいで、ダチョウが多くの言語で「現実逃避」と結びついていることを気の毒に思う。

このあたりでも河川工事に伴う通行止めが続いており、県道85号を南下して埴生川まで行き、その川沿いの道を通って再び一宮川に戻るというルートを取った。工事をやっていること自体知らなかったが、これほど広範囲で通行止めになっているとは思わずのんびりしていたので、想定の時間よりもだいぶ遅れている。私はこのあたりで、上総一ノ宮駅から電車に乗ることを決めた。
というのも、この連載は今回が最終回なのだが、私には締めくくりとして是非とも行こうとしている場所があるのだ。いすみ市にある飯縄寺である。本当なら、一宮川に沿って海に出て九十九里浜を南に向かう予定だったが寺は16時に閉まるそうで、このままでは間に合うかわからない。時間を調べて、最短距離を小走りで駅へ向かう。それでも、駅付近までは一宮川沿いの楽しい道だった。一面の小麦畑が清々しい。

急いだら若干の余裕ができたので、玉前神社に参拝し、参道にある〈御菓子司 角八本店〉でどら焼きを購入。外房線の安房鴨川行に乗れば、二駅で太東駅に着く。駅から県道229号を東へしばらく歩く。私は海に向かって歩いていると広末涼子の「summer sunset」を聴いてしまうのだが、この数日前に逮捕されたという状況でも普通に聴いたので、今後もずっと聴く気がする。
私は年に一度、飯縄寺を訪れている。そこには武志伊八郎信由の欄間彫刻「天狗と牛若丸」と「波に飛龍」がある。欄間というのは鴨居の上にある口を開けた部分のことで、元々は採光や通気目的だったところに装飾が施されるようになった。伊八は彫刻師として五代目まで続いたが、最も知られるのが初代の信由で、房総を中心に五十ほどの作品を残した。「波の伊八」と呼ばれるほど波の表現に秀で、関西の彫刻師たちの間で「関東に行ったら波を彫るな」という噂が立っていたとか、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」の画風に影響を与えたとか、様々な逸話がある。私はこの人を好きになって作品を見て回り、作品を小説の材にもしたが、最も感銘を受けたのは「天狗と牛若丸」だ。
朱塗りの仁王門は萱葺き屋根である。写真を撮っていたら、警察官が通るのを待ってくれた。お礼を言い、その後に続いて門をくぐると、警察官はお寺の関係者と思しき方々と合流し奥にある本堂へと向かうようだ。何かあったにしては急ぐ様子もない。三列の石畳がまっすぐ続く参道を、少しの距離を取ってついて行く。低い木々が広く囲んだ境内は苔むしたように斑に生えた芝に陽光が当たって緑に輝き、四度目の来訪だがいつ来ても気持ちがいい。そういえば、いつの間にか晴れている。
一行は、何人かが先を指差しながら本堂の裏の林に入って行った。追うわけにもいかず、私は本堂の前で止まった。1797年に再建されたここが目的地である。初代伊八はこの再建にあたって約10年間滞在し、金2000両余りで彫刻をはじめ総合的に関わったという。
私の作法としては、靴を脱いで本堂に上がってもまだ欄間を見上げず、拝観料として求められている300円を賽銭箱に納めて合掌する。そうして参拝を済ませたあと、数歩引いてから上を見る。そこに「天狗と牛若丸」がある。ケヤキの一枚板に彫られたこの大きな彫刻についてはまだ描写する言葉も気力も持たないし、撮影も禁止されているので、何も書けないし見せられるものもない。調べればネット上に許可を得て撮られた写真も見つかるけれど、生で対峙すると、言い様のない鬱蒼とした奥行きや物々しさが全く違うので、左右にある「波に飛龍」と併せて、ぜひ見に行ってもらいたい。
私は芸術家として初代伊八を尊敬しており、毎年ここに来ておみくじを引いて、一年の創作についての運勢をうかがうことにしている。今回は大吉で「する事なすこと幸の種となって 心配事なく嬉しい運ですからわき目ふらず一心に自分の仕事大事とはげみなさい」とあった。はげもうと思い、それからまた「天狗と牛若丸」を目に焼きつけようと、30分ほど見上げていた。首が痛いのはいつものことだが、やる気に満ちてくるのもいつもと同じだ。そして私はやっぱりいつものように、寺を後にして太東の浜へと向かい、打ち寄せる波を見た。
初代伊八は、生まれ故郷の鴨川でも、飯縄寺の本堂再建の仕事を始める前も、駆っていった馬を海に入れ、崩れる波をじっと観察していたという。伊八のように世界を見て、探って、表せたら。そう願いながら色んな土地を歩いてきたし、これからも歩くのだろう。なんとなく見返したおみくじは、強い海風を受けてずっと震えていた。

写真/著者本人
(連載はこれで終わります。長らくご愛読いただきありがとうございました)
乗代雄介(のりしろ・ゆうすけ)
1986年北海道生まれ。2015年「十七八より」で第58回群像新人文学賞を受賞しデビュー。18年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞を受賞。21年『旅する練習』で第34回三島由紀夫賞を受賞。22年に同作で第37回坪田譲治文学賞を受賞。23年『それは誠』で第40回織田作之助賞を受賞し、同作の成果により24年に第74回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。ほか著書に『最高の任務』『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』『パパイヤ・ママイヤ』『二十四五』などがある。