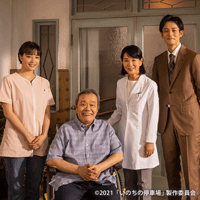現役医師・南 杏子の新刊『ヴァイタル・サイン』 冒頭ためし読み!
ステーション奥の師長席に歩み寄った。でっぷりした体型の美千代は、やや不機嫌な面持ちで書類を眺めていた。
デスクの正面に立ち、そのままの姿勢で美千代の言葉を待つ。
「資格取得のことだけど」
師長の言葉に、鼓動が速くなるのを感じる。先月、認定看護師の資格を取らせてほしいとリクエストした件だ。
認定看護師は、「ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有する者」の証だ。日本看護協会が定めた講習を受け、審査に合格した看護師に与えられる資格だった。昇給にも結びつく。ただし、取得には約百万円の受講費用と半年以上におよぶ受講期間中の身分保障が必要だ。もし病院から支援を受けられるのであれば、ぜひ挑戦してみたかった。
「……難しいわね」
師長は口元を引き締め、上目づかいで素野子をにらむように見た。
「講習費を病院が負担する出張扱いでは無理よ」
歌謡界の大御所に似ていると皆が言う表情が、そこで少し和らぐ。
「だけど、自己啓発のための研修扱い、という形なら検討してもらえることになったの。それでも堤さん、がんばる気はある?」
手にした書類をデスクに置き、師長が正面から見つめてくる。
研修扱い──つまり受講費用はすべて自己負担だが、勤務は免除され、給与の一部が支給されるという意味だ。ゆとりはないが、貯金をはたけば何とかなる。
反射的に、素野子は激しくうなずいた。
「はい、お願いします」
給与が全額出なくても、半年くらいなら持ちこたえられる。その後の給与はアップが期待できるから、トータルではいい条件だ。
「認定看護師の制度はスタートしてまだ日が浅いし、本格的な評価はこれからだけど、勉強したいっていう意気込みはとってもいいと思う」
師長の大きな目を飾る長いまつげが盛んに上下した。小さな風に乗せてエールを送られたような気持ちになる。
「ありがとうございます!」
認知症看護認定看護師、あるいは糖尿病看護認定看護師、がん性疼痛看護認定看護師、それとも摂食・嚥下障害看護認定看護師……。
二十一の専門分野のうち、どの専門に照準を合わせて勉強しようか。考え出すと、先ほど以上に脈打つ音が速まるのを感じた。
「あなたの希望をすぐに認める、とはならないわね。理事会の議論と決定を待って、追っかけ詳しい学習計画書と申請書を書いてもらう。そんな感じだからコースの受講開始は、早くて来年かな?」
それでいい。却下されるのでなければ。
先週の金曜日に素野子は三十一歳になった。来春は三十二。まだ遅くはない、と思う。
この年齢で学び直しを図り、専門知識をさらに吸収させてもらえるというのは、願ってもないチャンスだ。体の震えが抑えられないほどうれしかった。
「もちろんです。よろしくお願いします」
すぐに母に知らせたかった。元看護師の母は、職場での成長を誰よりも願っているはずだから。
師長はデスクの上からもう一枚の紙を引き寄せて言った。
「私から堤さんにもう一つ。前にも言った通り、今年度から田口主任の補佐をやってちょうだい。それと、来週から新しい看護助手が入職するから。大原桃香さんに加えて、そっちの教育係もよろしく」
「二人の教育係、ですか」
年度始めに新人教育のタスクが回ってくるのは珍しくはない。けれど、一人が一般的だった。一人と二人の指導では、業務負担が違ってくる。ようやく桃香が慣れてきてくれたと思った矢先だった。認定看護師の研修許可と業務負担のセットは、まるでアメとムチのようだ。
「大原さんは仕事の辞め癖がついているから、扱いが難しいでしょ。でも、あなたが支えてくれて、ひとまずこの一年はもっている。そこを見込んで、なのよ」
桃香に対する指導を評価してくれている。おだてられているだけかもしれないが、自尊心をくすぐられた。
とはいえ、気を緩めるわけにはいかない。慢性的な人手不足の中、目下の者が辞めると教育係が責任を問われる空気が、この職場にはある。
「分かりました。新しい方は、どのくらいの経験の持ち主でしょうか」
「経験なしの男性。もともとサラリーマンで、ハローワーク経由。資格なし。最初は使い物にならないと思うけど、ゼロから戦力レベルにまで引き上げてやってよ。まあ男だから、それなりに力はあるでしょうけど」
病棟看護師の勤務スケジュールは、師長がチームを組み、シフト表に落とし込む。メンバーの年次や経験によって、仕事の負担も変わってくる。師長は、新人の看護助手を中堅どころの素野子にかませることでバランスを取ろうとしているのだ。それは理解するが、負担が増えるのは確かだ。
「分かりました」
思いがけず沈んだ声になってしまった。
「堤さん、この病棟で教育係に求められることは何かしら?」
師長が謎をかけるような言い方をしてきた。
「若手の知識と技術を確かなものにして、一日も早く病棟の戦力になってもらうこと──でしょうか?」
素野子の答えに草柳師長は大きくうなずき、その直後に首を左右に振った。
「若い子を辞めさせないで、とにかく働き続けてもらうこと──まずはそこ」
看護職の絶対的な不足、三百六十五日続く不規則勤務、民間病院の経営環境、価値を増す若年労働力……。普段はあまり考えたことのない院長講話のテーマが、素野子の頭の中をぐるぐる回る。
「あなた、うちに来てどれくらいだっけ?」
「……十年です」
師長ほどのベテランでもないが、さりとて新人でもなく、「もう」とも「まだ」とも形容し難かった。
「なら、仕事が増えるのも当然ね。たんぽぽの花で浮かれてるヒマはないと覚悟して──」
皮肉の一打を受けて、冷や汗が吹き出す。やはり桃香の指摘した通り、目立ちすぎだったか。どこかからバチンという金属板の音が聞こえたような気がした。
一礼して草柳師長のもとを離れた素野子は、東療養病棟の中央にあるナースステーションを後にした。キャリア・アップの道に差し込んだ細い光だけが、素野子の心を少しだけ軽くしてくれる。
二子玉川グレース病院のルーツは、もともと「ほどこし」だったと聞いたことがある。大正時代、目黒にあった旧藩主の地所に造られた「養育院」が始まりで、浮浪者、今で言う路上生活者や貧しい病人の収容が主目的だった。それが昭和初期に、目黒から現在の地に移転し、病院へと組織替えが図られた。今では二子玉川駅の周辺にある高級ショッピングセンターがにぎわうように、二子玉川グレース病院も富裕層の患者であふれかえっている。
「おはようございます。いいお天気ですね」
廊下の窓に春の空が広がっていた。ソメイヨシノが多摩堤通りに並び咲いている。
「おはようございます。けさは本当に気持ちがいいですね」
療養病棟は、こうしたスタッフの声かけに反応できない患者も少なくない。認知症の患者が六割強に上るためだ。
それでもスタッフはていねいにあいさつを繰り返し、体温や血圧などヴァイタルの測定を進める間も患者に優しく声をかけ続ける。
患者を人として尊重する──それは、素野子が誇りに思う二子玉川グレース病院のポリシーであった。
病院の最上階に位置する四階の療養病棟は、エレベーターホールで東西に分かれ、それぞれ五十一床を擁する。入院患者は認知症をはじめ糖尿病、慢性心不全、脳血管障害、慢性関節リウマチ、パーキンソン病といった複数の疾患を抱える七十歳代以上が大勢だ。
東病棟と西病棟の患者については、病気や容態に特段の違いはない。広い病棟を便宜上二つに区切り、二つの看護チームで担当しているだけだ。いずれも長期の療養が必要な患者たちで、入院のタイミングとベッドの空き状況次第で東西どちらの病棟に回るかが決まる。
このため、死期が目前に迫った患者や重度の認知症患者など、より手厚い看護が求められる患者が東あるいは西の病棟に集中し、もう一方の病棟には症状が軽くてケアする側の負担の小さい患者の入院が続くようなことが起こりうる。
素野子の二つ年下の恋人、市川翔平は、そうした事情をトランプのゲームになぞらえた。
「ギャンブルだよね。持ち札によって業務負担が極端に違ってくるなんて」
トランプで最初に札を配られたとき、手元にどんなカードが来るかどうかは、まったくの運次第。不吉なスペードのカードばかりが届いて手札が真っ黒になる場合もあれば、優雅なクイーンやキングが顔をそろえることだってある。ただ、高位のカードが来ればラッキーなのか、小さい数の方が楽なのか。素野子は翔平の言うゲームのルールがつかみきれない。
「トランプの四種類のスートは春夏秋冬、季節を意味するんだよ。一組が五十二枚で、一年の週の数になっていて、すべてのカードの数字を足し合わせると三百六十四になるんだ。おもしろいでしょ」
素野子はまだピンとこなかったが、翔平が自分を楽しませようと一生懸命に説明してくれているのがうれしくて、目の前で動く翔平の唇を眺めたのを思い出す。
翔平の雑学好きは、多忙のせいかもしれない。別の病院で整形外科医として働き、緊急手術や患者管理で常に呼び出しを受けるハードな生活をしている。唯一の息抜きは隙間時間に雑学を仕入れたり、ゲームやパズルをやることらしい。最近はまっているのは数独だが、付き合って半年たった今も、素野子にはどこがおもしろいのか分からない。
「分かる? 一年なのに三百六十四なんだよ」
素野子はそこでようやく気づいた。
「一、足りないってこと?」
素野子が指摘すると、翔平は満足そうにうなずいた。
「そう。でもトータルは三百六十五になる。最後にジョーカーが加わるからね」
「わあ、怖い。ジョーカーを加えて一年が成立するって、なんか、不吉」
「人間の運命には、最初から鬼札が組み込まれているということかもな」
単なるゲームの話かと思って油断していると、突然、奥深いものが見えてくる。翔平の話の、そんなところも好きだった。
──大丈夫、今のところ東病棟にジョーカーはいないから。
翔平と交わした会話の最後に、そんなことを言った記憶がある。
午前九時半少し前、病棟の中ほどにある機械浴専用の浴室に向かった。
【好評発売中】
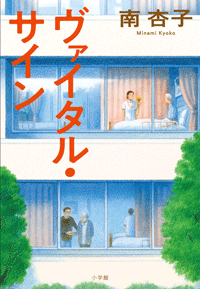
『ヴァイタル・サイン』
南 杏子