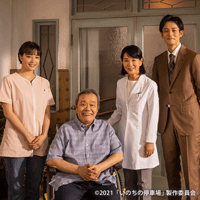現役医師・南 杏子の新刊『ヴァイタル・サイン』 冒頭ためし読み!
この日、素野子にあてがわれた日勤業務は、入浴介助から本格的にスタートする。体の自由のきかない入院患者を一人ずつ順番に風呂に入れる役割だ。
辞書で「看護師」を引くと、「厚生労働大臣の免許を受け、傷病者などの療養上の世話または診療の補助をすることを業とする者」などと書かれている。
実際のところ、この病棟での看護師の仕事は「診療の補助」よりも「療養上の世話」が圧倒的に多い。入浴介助は、白衣の職場のイメージとは異なり、そのユニフォームを脱いで取り組む重労働だ。
「よし!」
素野子は自分に気合いを入れ、脱衣所から浴室に通じるスライドドアを引き開けた。
ムッとした湿気が押し寄せてくる。入浴介助の補助を担当するパート職員、細内勇子が風呂の湯を張り、室内も暖めておいてくれていた。
「細内さん、よろしくお願いしまーす」
湯けむりの先に向かって声を張り上げる。
Tシャツ姿の勇子は右手で湯をかき混ぜながら「お湯の温度、ばっちりですよ」と左手を高く掲げた。
ここは、自力で立ったり歩いたりするのが難しい患者のための特別な浴室だ。浴槽は一人用だが、室内にストレッチャーを運び入れても介助者が動けるよう二十畳ほどの広い造りになっている。ストレッチャーの昇降機によって、患者は横になった状態のまま湯に入ることができる。
「女性患者十人の予定です。ゆっくり確実に、今日も無事故でいきましょう」
「はーい、よろしくお願いしまーす」
勇子は明るい声を返してくれた。「あたし、この仕事でこんなに腕が太くなっちゃったわヨ」が口癖の四十四歳のベテランで、素野子にとっては頼もしい存在だ。
素野子はいったん脱衣所に引っ込み、さっとTシャツと短パンに着替えた。大きなエプロンを付けてはいても、湯や泡が大量に飛んでくる。自分自身も汗だくになり、入浴介助の作業が終わるころにはいつも全身がびっしょり濡れてしまう。
「患者さん、入りまーす」
浴室の入り口で同僚看護師の声がした。
タオルケットにくるまれた裸の患者が、ストレッチャーに乗ったまま浴室に運び入れられる。
関節が硬くなった患者の服を脱がせるのは相当に時間がかかる。このため患者は、あらかじめ病室で衣服を脱がされ、病棟の廊下を、すっぽりとタオルケットに包まれた裸体で通る格好になる。
浴室での作業効率を維持する必要から作られた手順だが、「患者を人として尊重する」というポリシーとせめぎ合う側面もあり、他の患者となるべくすれ違わないコースを移動する配慮がなされている。
脱衣所の扉が開いた。ストレッチャーの上で高齢の女性患者が不安そうに周囲を見回している。四〇三号室の内田佐枝子だった。
「内田さん、大丈夫ですよ、ご安心くださいね」
ゆっくりやさしくを心がけつつ、素野子は声をかけた。
裸にさせられる、ストレッチャーで移動させられる、他人の手で体をこすられて温水をかけられる、それから寝たまま入浴台に乗せられ、浴槽に沈められる──患者の側からすれば、怖いことだらけだ。
素野子自身、美容院で髪を洗ってもらうときですら緊張する。それを思えば、裸にされた患者がおびえるのも当然だ。
「さあ、きれいになりましょうね」
そうっとタオルケットを剥いだ。ただし羞恥心への配慮から、小さなタオルをかけておく。まずは佐枝子の頭をシャンプーし、シャワーで温めながら体を洗う。せっけんを使わない「湯洗い」が中心だ。洗いすぎると皮膚が乾燥しやすくなるため、手足や首、陰臀部のみ泡の洗浄剤を使う。
続いて体が滑らないように気を配りながら、横になったままの佐枝子をストレッチャーから入浴台に移動させる。
ここが最も危険で、細心の注意が必要になる。骨の変形によって背中が丸い患者が転がり落ちそうになったりするからだ。かといって、骨や皮膚の弱くなっている患者に無理な力はかけられない。
入浴介助の時間は一人当たり十二分。
ていねいに作業しなければならないが、あまりゆっくりもしていられない。事故防止のため、二人以上での介助が原則だ。
佐枝子は脳出血で左半身に重い麻痺が残っていた。左手足が屈曲した状態で硬直している。
入浴台に佐枝子が確実に移ったのを確認して、ボタンを押す。細かい穴の開いた入浴台が徐々に下がり、佐枝子の体は浴槽内に沈んでいく。その間も寒くないよう、肩のあたりはシャワーで湯をかけ続ける。そこから三分ほどぬくもる時間を取る。
「ふぁあ、気持ちいい」
佐枝子はとろけるような声を出した。
このときの患者の表情を見ると、仕事の疲れが吹き飛ぶ。いくら重労働でも、そんな瞬間があるから入浴介助は好きだ。
「ありがとうねえ」
感謝の言葉をかけてくれる患者には、ケアにも熱がこもる。
佐枝子の硬直した左手足を少しずつ伸ばしてあげた。痛くないように、けれど拘縮がわずかでも改善するように。佐枝子の表情と手足の緊張を確かめながら、微妙に力加減を調整する。
佐枝子が入院してきたときは、ひどい衛生状態だった。家族がおらず、一人では入浴が難しかったのだ。特に首回りは、ボンドを何度も塗り重ねたように薄茶色い垢が層を成していた。
そういう垢は、一度や二度の入浴では落ちない。しかも、あまり強くこすると八十四歳の皮膚は簡単にむけてしまう。週に二回の入浴日に優しく洗い進め、一か月ほどでようやくきれいな肌になった。
「なんだ内田さん、本当は色白だったんですね」
佐枝子とそんな軽口をたたきながら喜び合ったのを覚えている。
時間となり、入浴台を上げる。タオルで体を拭き上げてから、移動用のストレッチャーに慎重に戻した。
「ああ、気持ちよかったわあ」
素野子はほほ笑みつつ、少し残念にも思う。本当は、もっともっと気持ちよくなってもらいたい。けれど、こうも短い時間では、できることは限られていた。
「お肌が乾燥しないように、保湿しますね」
最後に佐枝子の肌にクリームを塗る。周囲にいい香りが漂った。
「まるでお花畑。本当にここは天国ね」
満足顔になった佐枝子を新しいタオルケットで包み直し、「お疲れさまでした」と声をかける。
「ありがとう。ホント、気持ちよかった」
ストレッチャーの上で佐枝子は何度も礼を言ってくれる。
浴室の外で待機しているスタッフに佐枝子を託し、入れ替わりで次の患者を受け入れた。
「やめろ! 人殺し!」
四〇六号室の蜂須珠代だった。認知症の症状が重く、入浴を極度に嫌がる。浴室に入る前から大声で乱暴な言葉を投げつけてきた。
「いじわる! 虐待よ!」
傍らで勇子が小さなため息をつく。スタッフの重荷となるのは、肉体的なきつさよりも、こうした介護への拒絶反応だ。
患者は認知症のため自分の置かれた状況を把握するのが難しく、不安や恐怖を極度に感じやすい。そのせいで暴言を口にしてしまう。スタッフの誰もがそれを学び、理解はしている。ただ、実際に目の前で怒声を浴び、激しい抵抗を受けると、自分が本当に正しいことをしているのかどうか──と悩んでしまう者も少なくない。
「心が折れそうだわ」
いつだったか。入浴拒否を続けた患者をなんとか風呂に入れた後、勇子がそんなことをポツリと言うのを聞いた。
この日の珠代は、いつも以上に激しく抵抗した。
患者本人がどうしても介助を受け入れない場合、入浴を中止するという判断も当然ありうる。けれど珠代は、このところ五回連続で入浴をキャンセルしており、乳房の下があせもで赤くなっていた。今日は入ってもらいたい。
「お風呂で気持ちよくなりましょうね、蜂須さん。お体、楽にしてください」
素野子は珠代の緊張をほぐそうと、必死で声をかける。珠代の振り回すこぶしの力が少し弱まった。
ほっとしたのもつかの間、珠代がいきなり右手を大きく払い、勇子の顔をたたいた。眼鏡が吹き飛び、向こうの壁にぶつかる固い音を立てる。
「いった〜い。泣いちゃいますよ〜」
勇子の口調は冗談めいていたが、表情はこわばっている。
「今回は洗身だけにしましょうか」
シャンプーは、あまりにも抵抗が激しそうであきらめる。
「了解です。欲張らない方がよさそうだもんね」
勇子が患者の腕を押さえて、洗身の態勢に入った。その間に素野子は脇や胸の下に泡をつけて素早くこする。続いて全身をシャワーで洗い流し、ようやくほとんどの泡がなくなるところまでたどり着く。
素野子は仕上げに珠代の腕に湯をかけた。一瞬、珠代を押さえていた勇子の力が緩む。
「やめろ! 人殺し!」
珠代は再び激しく叫び、自由になった手でホースを振り払った。シャワーヘッドが跳ね上がり、素野子の額を直撃する。
「痛っ」
思わず声が出た。クロムメッキを施した重いシャワーヘッドを拾い直し、再び珠代に声をかける。
「温泉ですよ〜。蜂須さん、草津温泉って知っていますか? ほらほら、草津よいとこ〜」
珠代の気をそらしながら、ストレッチャーから入浴台にさっと移す。床面からの高さは約一メートル。患者が暴れて落ちるのを防ぐため、介助者は自分の体を柵にする。
たとえ患者にひっかかれようが殴られようが、柵になりきり、じっと耐え続ける。落下事故を起こすことに比べれば何でもない。
だがすぐに珠代は興奮し始めた。
「もう無理ですね」
入浴台を上げ、珠代をタオルで手早く拭き上げる。
「堤さん! おでこから血が出てる!」
勇子が教えてくれたが、気にしている暇はなかった。珠代をストレッチャーに移す。
ふいに目がしみた。血液か汗が目の中に入ったようだ。腕で顔をぬぐうが目を開けられなくなった。
「ちょっと顔を洗わせてもらいますね」
水道の水で顔を洗う。職員事故の報告書を書く仕事が増えたと少し憂うつに思いながら。それからペーパータオルで押さえつけるように顔を拭く。額の部分は圧迫止血も兼ねて、しっかりと。ペーパーにはそれほど血液が付着せず、ほっとする。
【好評発売中】
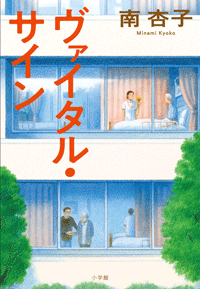
『ヴァイタル・サイン』
南 杏子