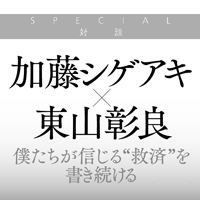加藤シゲアキ × 逢坂冬馬【SPECIAL対談】いま、僕たちが戦争を書くということ─前編─

いま、僕たちが戦争を書くということ ─前編─
過去の戦争について知ることが未来を切り開いていくことに繋がる
逢坂
僕はあまりテレビを見ないものですから、NEWS の加藤さんとしての活動は全く存じ上げていないんです。僕にとって加藤さんは、作家の先輩です。
加藤
実は、2023年で11年目なんです(笑)。逢坂さんはデビュー作の『同志少女よ、敵を撃て』で本屋大賞を受賞されて、あっという間に世間に認知されましたよね。僕の周りでも、普段あまり本を読まない人たちがこぞって読んでいた。第二次大戦の、しかも外国で起きた戦争について真正面から描いた作品がベストセラーになったという状況は、素晴らしいなと思いました。今回の『歌われなかった海賊へ』は、二作目ですね。
逢坂
一発屋だと思われないよう、デビュー作から二年以内になんとか本を出したくて頑張りました(笑)。加藤さんの『なれのはて』は、一人の作家が現時点での全てを出し切り、戦争という題材に限らずあらゆる面に力を入れて書いた小説だと感じました。作家の人生において、そういう作品って何度も書けるものではないんですよね。
加藤
そうですね。もしかしたら、デビュー作の『ピンクとグレー』以来だったかもしれない。
逢坂
読んでみて、対談の企画が来た理由がなんとなくわかったんです。『なれのはて』と僕の『歌われなかった海賊たちへ』という作品は、見た目や雰囲気は全然似てないんだけれども、構造が似ているのではないかなと。
加藤
それは、僕も思いました。
逢坂
どちらも現在から入って、過去の戦争について振り返っていく構造なんだけれども、過去を検証して終わりではないんですよね。過去を振り返った結果が、現代にも影響を与えていく。過去を知ることが未来を切り開いていくことに繋がる、という点が共通していると思います。
加藤
戦争があった過去と現在は地続きなんだ、という意識は時代を経るごとにどうしても薄くなりますよね。過去と現在を接続させるような構造が、小説の中にも必要だと思ったんです。逢坂さんも同じアプローチだったので、「おおっ!」となりました。
逢坂
僕の場合、前作で結構評価されたポイントの一つが、エピローグなんですよ。あれがあったことによって、本編で描いた第二次大戦の独ソ戦が、現代と地続きであると示すことができた。今作では、その構造を冒頭から押し出していったかたちです。市民社会において、レッテル貼りとしてではなくて、ナチズム的な要素が現代にも持続せざるを得ないとしたら一体何なのか。そこを書かないことには結局、「過去にこういう話がありました」で終わりになってしまいかねないんですよね。
加藤
戦争に関するノンフィクションだったり、著名な戦争文学は既にたくさん存在しているわけです。そんななかで、戦争の小説を自分が今書く意味はどこにあるのか。現代の視点を通さなければ、新しいものにはなり得ないんじゃないかとも考えました。
広島、長崎、東京、沖縄……だけではない戦争を取り上げる
逢坂
現在日本のフィクションが、過去の日本の戦争についてよく取り上げる素材は、東京大空襲であり、原爆投下であり、零戦に戦艦大和に特攻隊。僕は裏で「五大パターン」と言っているんですが、そういった繰り返し再生産される表象で戦争を語ろうとすると、そこで語り得ないものは見えなくなってしまう弊害があるんです。加藤さんは今回、秋田の土崎空襲というマイナーな題材を扱っていますよね。素晴らしい着眼点だなと思ったんですが、どういった経緯でこの題材を選ばれたんでしょうか。
加藤
僕は、生まれが広島なんです。五歳までしかいなかったので当時の記憶はあまりないんですが、広島のメディアの方に声をかけていただいて、戦争関連のお仕事をよくさせてもらっているんです。そのたびに、広島の戦争について小説で書いてほしい、語り継いでほしい、という声をいただくんですね。ただ、広島や長崎を題材にした優れた作品はあまりにもたくさんあるので、新たに自分が書く意味があるんだろうかと感じていたんです。それにいま語られていない地域にも、戦争の傷はあったはずだとも思いました。そんな時に、そういえば母の出身である秋田にはどんな戦争被害があったのかなと検索してみたら、土崎空襲のことが出てきたんです。終戦前日に起きたことから、「日本最後の空襲」と言われていると知って衝撃を受けました。終戦があと一日早ければ、とみんな思ったはずなんです。

逢坂
あと一日早ければという思いは、現代パートにおけるパブリックドメインの問題と反響しているんですよね。画家の死亡した日が一日違うだけで、著作権が20年延長されるか否かが決まる。だから、主人公たちは画家の死をめぐる謎を解かなければならない……という設定は説得力がありました。
加藤
もともと、権利を題材にしたミステリーにしよう、というアイデアが先行していたんです。そこに、土崎空襲が結び付いていったんですよね。小説にも書きましたが、なぜ空襲を受けたかというと、石油が出たから。土崎という地域に、大きな製油所があったからです。石油が出なければ爆撃もなかったけれど、石油のおかげで経済的に潤ったという恩恵もあった。そういった「引き裂かれる思い」は、小説で書きたいと思うポイントの一つです。ここ数年の SDGs に関する個人的な興味も、この題材ならば取り上げることができると思いました。
逢坂
ストーリーとしては一枚の絵画を巡るミステリーであると同時に、石油で成り上がった一族の興亡記でもありますよね。石油とは人間の欲望の対象であり、それゆえに戦争の時には資源と化し、かたや、それが人の命を奪う戦争の標的にもなっている。一つのモチーフから幾つもの意味やイメージを取り出して書かれている点が、小説として本当に魅力的でした。
加藤
ありがとうございます! めっちゃ嬉しいです。
「気に入らない」という不良マインド。「死にたくない」という動機
加藤
僕は人々の記憶から薄れてしまっている戦争被害もあるはずだ、と調べていったところで、秋田の土崎空襲の存在を知り、『なれのはて』という作品ができていきました。逢坂さんは『歌われなかった海賊へ』で、エーデルヴァイス海賊団という少年少女たちの視点から、ナチ・ドイツについて書かれていますね。
逢坂
ナチ・ドイツの青少年と言えば、たいていヒトラー・ユーゲント(※ナチ党の青少年団)のことを思い浮かべますよね。ヒトラー・ユーゲントは時代の変遷の中で末期には軍事化していって、最後には戦闘に加担していきました。そちらの角度から見ていくと、これまでに再生産されてきた戦争のイメージを補強する役目しか果たさないんですよね。でも、エーデルヴァイス海賊団はあまり知られてない。
加藤
僕も知らなかったです。
逢坂
本国でも1970年代あたりまで忘れ去られていた存在だったんですが、彼らはヒトラー・ユーゲントをぼこぼこにぶん殴っていたんです。「うるせえ、おれたちに指図するな」と。あるいは、これは僕の考えたフィクションですが、自分たちが暮らしている辺境の街に鉄道が引かれたんだけれども、ここが終点であるはずなのに、レールが先まで延びているのはおかしいだろう。レールの先にあるものを自分たちの目で確かめて、なんだったらぶち壊す。彼らは特に高邁な政治思想に燃えているわけではなく、「気に入らない」からという理由だけでナチスに歯向かっていった。迎合することによってファシズムは完成するわけですから、反迎合主義の不良たちの言動は、世の中にちょっと風穴を開ける。そういった不良マインドの重要性を描きたかったんです。

加藤
小説ではエーデルヴァイス海賊団を全肯定しているわけではないですよね。彼らも間違えているところもあっただろうし、という部分も書かれている。そこがいいんです。結局、戦争は誰も救わないってことがちゃんと描かれている。
逢坂
彼らの勝利ではなく、敗退の歴史にしなければウソになると思ったんです。さらに言えば、「どうして日本ではなく、ドイツを舞台にした小説を書いたのか?」とよく聞かれるんですが、日本を舞台にしたらこの小説は絶対に成り立たないんですよね。戦時下の日本には、こういう子たちがいなかったんですから。
加藤
日本にはいなかったんですか、不良たちは。
逢坂
エーデルヴァイス海賊団のような不良集団はいなかったようです。もちろん、個人としてはいました。誰々は戦争をサボタージュしていた、みたいな話はよく聞きますよね。徴兵逃れ、というやつです。動機としてはだいぶ違いますけれども。
加藤
反体制的な動機ではなく、「死にたくない」が動機ですよね。
逢坂
そうですよね。でも、よく考えたら、特攻隊を美化するよりも、「死にたくない」って思いで徴兵から逃げ回ってる人の話を書くほうが、健康的じゃないかと思う。
加藤
僕はそちら側を書きたいんです。『なれのはて』に出てくる猪俣勇という人物は、戦争に行きたくないし、死にたくない。「お国のためなら死んでもいい」といった自己犠牲精神に頼ってストーリーを描くのは、危ないことなのではと思っています。「死にたくねえよ!」と、ともすれば情けなく見える人間の姿を描いたものの方が、戦争の恐ろしさが伝わると思うんです。
逢坂
昭和ファシズム下でおしつけられた自己犠牲精神を、家族のためとか、愛する人のためという現代人にも理解可能な形式に置き換えることで、例えば特攻隊を肯定してしまうようなお話を作るのは本当にタチが悪いなと思います。でも、そういうものの方が受け入れられやすい。
加藤
自己犠牲精神を美化しすぎているのではないか、戦争を美しく書いてはいけないだろう、みたいな気持ちは常に持っておきたいと思います。
逢坂
それって作り手も受け手も、戦争を消費して気持ちよくなってるだけじゃんって。
加藤
そう感じてしまいますよね。
逢坂
そうではなくて読者を、それから書いている自分もえぐっていかなければいけない。世界の国で今まさに起きている絶え間ない戦争について注意を促すのは、本質的にはジャーナリズムの役割でもあるかもしれないけれども、報道に心を痛めても、そこで起きていることは距離的にも心理的にも遠いものだっていうふうに受け止めざるを得ないんです。でも、小説は違う。ナチ・ドイツ体制下のドイツの少年たち、あるいは独ソ戦に参加したソ連女性兵士たちの物語を追いかけていくうちに、本当の自分の知り合いのように感じていくんですよね。彼らの命が奪われていく、あるいは精神が変容していく姿を間近で見ながら、「もしも自分だったら? この場面に自分が居合わせていたら?」と自分に問いかけていく。そうすることで、戦争の悲惨さを真に実感することができると思うんです。
*対談は「後編」につづきます
加藤シゲアキ(かとう・しげあき)
1987年生まれ。大阪府出身。NEWS のメンバーとして活動しながら、2012年『ピンクとグレー』で作家デビュー。21年、『オルタネート』で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞。『なれのはて』が第170回直木賞にノミネート。
逢坂冬馬(あいさか・とうま)
1985年生まれ。埼玉県出身。2021年にデビュー作『同志少女よ、敵を撃て』がアガサ・クリスティー賞大賞を受賞し、「キノベス!2022」1位に。翌年には同作で第166回直木賞候補となり、本屋大賞、高校生直木賞を受賞。