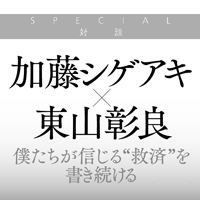加藤シゲアキ × 逢坂冬馬【SPECIAL対談】いま、僕たちが戦争を書くということ─後編─

いま、僕たちが戦争を書くということ ─後編─
「前編」はこちら
戦争の反対にあるのが、文化。戦争は、文化から殺していく
逢坂
過去の戦争を検証するきっかけとして、文化というものが出てくるところも共通点だと思うんです。僕は歌で、加藤さんは絵画です。どういう考えで絵画を取り上げたのか、お伺いできたらと思うんですが。
加藤
僕自身が好きというのももちろんあるんですが、絵の良し悪しは本来、判断がつきづらいものですよね。ただ、今のアートの評価は文脈や歴史、背景といった情報が評価基準になっている部分もあるんです。そういった情報が一切なく、ただ純粋に「すげえ!」となる絵があったとしたら、そこで初めて「誰がこの絵を描いたんだ?」という謎が生まれる。話の大枠としてはミステリーにしたかったので、そのための装置として絵を考えましたね。逢坂さんが今回、歌を題材に取り入れたのはどうしてだったんですか。
逢坂
エーデルヴァイス海賊団の資料を読んでいると、必ずといっていいほど、彼らが作った歌というのが出てくるんです。小説で出したものは僕の創作ですが、実際の歌詞も一部残っている。ところが、メロディはわからないんですよね。ヒトラー・ユーゲントが当時歌っていたようなものはメロディも残っているんですが、エーデルヴァイス海賊団は反体制側でしたから、受け継がれないまま歴史から取りこぼされてしまった。その距離感をちょっと味わってほしかったんです。
加藤
戦争の反対にあるのが、文化ですよね。戦争は、文化も殺していく。最近も公文書館と図書館が燃やされてしまいました。それは文化がいかに強いかということの表れでもあるんですよね。
逢坂
そうですね。一方で、加藤さんの作品の中には、文化というものは利用される、プロパガンダになっていくという側面も取り込まれている。去年の今頃かな、東京で岡本太郎の大規模な展覧会に行ってきたんですよ。「すごいな」と「よくわからないけど、すごいな」の繰り返しを堪能できたんですが、一点だけ、「師団長の肖像」という写実的な肖像画があったんです。それは岡本太郎が戦争で中国へ行っている時に、仕事として描いた上官の肖像画で、誰がどう見てもうまいんです。だけど、つまらない絵なんです。どうしてかというと、この絵の中に岡本太郎の言いたいことなんてみじんもないから。文化が体制側に利用されるツールとなったら、文化のありようが失われる、その怖さを改めて感じたんですよね。『なれのはて』でプロパガンダ絵画のことが言及されていて、そのことを思い出しました。
加藤
不思議ですが、プロパガンダの絵は、すぐ分かりますよね。
逢坂
分かりますね。悲しいほど分かる。文化というものは、常に政治と密接な関わりを持たざるを得ません。今、イスラエルでヒットチャートのナンバーワンを記録しているラップ(*)が「ガザを殲滅しろ」って曲だという話を聞いて、恐ろしい気持ちになったんです。そうやって少しずつ少しずつ、価値観が市民に反映されていく。そういうことがこれから日本にも訪れるかもしれないというよりも、本屋さんへ行って人文系の棚の前を通る時に、ヘイトとか陰謀論丸出しのものを見ずに帰ってくることができたら、奇跡じゃないですか。決して今の日本と無縁じゃない、ということは言っておきたいです。
*Ness and Stilla「Harbu Darbu」
社会問題や現実の出来事に関する質問が来るのは自分の書いた小説が普遍性を言い当てた証
加藤
僕が『なれのはて』で戦争という題材を初めて扱ったきっかけの一つは、同世代の作家たちが戦争についての小説を次々と発表していたからなんです。具体的に言えば、『地図と拳』の小川哲さんであり、『同志少女よ、敵を撃て』の逢坂さん。もともと、いつか書きたい題材ではありましたが、自分もその流れに連なっていきたいと思ったんですよね。
逢坂
みんなそれぞれアプローチが全然違うんだけれども、作品の中に「忘却にあらがう」というエピソードが出てこざるを得ないのは、同世代の作家に共通する問題意識なんじゃないかなと感じます。僕自身の話をすると、自分が唯一持っている戦争との生々しい接点は、祖父が戦争体験者だったということです。前線には行かなかったんだけれども、軍港へ行って悲惨な目に遭って帰ってきてから、人間性が変わったと祖父は話してくれました。大学生の頃、同級生たちと「自分たちは戦争の体験を聞ける最後の世代じゃないか」という話をしたことも覚えています。それからさらに時代が流れて、現実的な接点を持った小説家として戦争を書く、という行為もいよいよ限界が来ている。自分たちが何かしなければという思いが、無意識下で共有されているのかもしれません。

加藤
年齢的に、戦争を直接体験した方々が少なくなってきていますよね。去年、広島で90代の被爆体験者の女性に1000問ぐらい質問して、その答えをAIに記憶させることで、戦争被害を語り継ぐという番組に出演させていただきました。ビデオに証言を残すこともできるんだけれども、それだとやっぱり、見返すのが難しい。だからAIと対話できる装置を作ることで、記憶を継承しようというプロジェクトなんです。そういったプロジェクトを経験したことも、作家として戦争を語り継ぐことができないか、という思いが募るきっかけになりました。
逢坂
興味深いです。
加藤
逢坂さんの『同志少女よ、敵を撃て』は、ロシアのウクライナ侵攻が起こる前に書かれたんですよね。
逢坂
本を出した3ヶ月後に、ロシアがウクライナに攻め込んだんです。そのことは広く読まれるきっかけにもなったんですが、心が分裂しそうになりました。「俺、戦争で儲けてるの?」みたいな気持ちになったんです。作品に無用な色が付いてしまうことになったかもしれない、と呪いのように感じることもありました。インタビューなどでも、現実の戦争についてのコメントを求められるんです。加藤さんも、同じような状況になっているんじゃないですか?
加藤
そうですね。戦争のこともそうですし、報道や正義という題材も小説の中で描いていたので、所属事務所の問題とリンクしてしまったところもありました。
逢坂
それを答えていくのはしんどいですよね。ただ、最近わかってきたんです。もしも書いている時に想定していなかった社会問題や、現実の出来事に関する質問が自分に浴びせかけられるとしたら、それは自分の書いた小説が普遍性を言い当てたことの証なんですよ。
加藤
なるほど。
逢坂
それを自分に対しても言っているのは本来おかしいですが、もう腹を括りました。というのも、『歌われなかった海賊へ』の取材でも、作品外の現実についての質問をたくさんもらったんです。僕にせよ加藤さんにせよ、もしもただ単にナチズムから逸脱する少年の話、あるいは土崎空襲や石油の話のみに終始している作品であれば、そういう現象は起きなかったんじゃないか。歴史上の固有の事象にアプローチしてはいるんだけれども、固有の事象を越えて、現実の社会構造のいびつさと繋がるものや普遍的なものを描けたから、そういう質問が来るんだと思うんです。そう考えるのが精神衛生上、一番いい(笑)。
加藤
例えば戦争についてどう思うかと聞かれても、そんな簡単には答えられないし、分からない。分からないからこそ、書きたかったんです。書くことで知りたかったし探りたかったという気持ちがあるから、その問いに本音で答えるとすれば「小説を読んでください」になってしまうんですよね。
逢坂
それは僕もまったく同じですね。戦争とは何か、戦争を生きた人々はどんなことを考えていたのか。それを整理するためには、小説というかたちにしなければ本当の意味で理解できない。架空のキャラクターになり変わってその世界を生きることで、初めてエーデルヴァイス海賊団は何を考えていたのか、あるいは、当時のドイツ市民は何を考えていたのかがやっと分かるようになるんです。
体制に迎合し戦争に加担する側の加害性。「悪の凡庸さ」について
加藤
これは『なれのはて』を書き終わった後の話なんですが、先日亡くなられた脚本家の山田太一さんのドラマで、登場人物たちが戦争について語り合っているシーンの動画を見たんです。そこでの若者のセリフが印象的だったんです。ざっくり説明すると「大人たちが戦争をちゃんと怖く語れよ。そうじゃないと、おれたちは怖いと思わなくなるだろう。戦争はそんなに大したことないと思っちゃうだろう」という会話。フィクションで戦争を扱うならば、戦争をむごくグロテスクに描く責任があるのではと僕も思うんです。それと同時に感じたのは、戦争は書いてみると自然と筆が高揚してしまうものなんですよね。それはそれでイヤだったんですよ。
逢坂
その感覚、よく分かります。
加藤
もし戦争に行ったら誰もが興奮せざるを得ないのかもしれない。そうすることで生き延びようとするのかもしれません。戦争ってそういうものなんだな、自分の中にもそういう部分があるのかもしれないと、小説を書きながら考えてしまいました。
逢坂
今のお話とちょっと繋がるかなと思うんですが、僕がどうして『歌われなかった海賊へ』をこのタイミングで書いたのかというと、『同志少女よ、敵を撃て』の時にやり残したことがあったんです。その一つが、兵士の側ではなく、市民の側が帯びている加害性の問題でした。戦争において市民は常に被害者の側から語られますが、それだけじゃないんですよね。エーデルヴァイス海賊団に視点を取ることで、そこも書くことができると思ったんです。
加藤
一般的な人であっても体制側、ファシズムの側に行ってしまう可能性がある。終盤は読んでいて苦しかったし、切なかったですね。哲学者のハンナ・アーレントが、ユダヤ人を強制収容所に送ったナチ・ドイツの役人アイヒマンについて形容した、「悪の凡庸さ」という言葉を思い出しました。
逢坂
アーレントの思想はそれ自体がテーマに取って代わりそうなので執筆中は意図して参照しなかったのですが、どうしても連想はしますよね。作中の彼らは特に、悪い人だってわけではないんですよね。善良さを持ったまま、許されないことをしていた。ひょっとしたら加藤さんにしろ僕にしろ、もしも次に戦争の小説を書く場合は、体制に迎合し、戦争に加担する側の加害性がより大きな課題になってくるのかもしれないですね。
加藤
逢坂さんは今後、日本の戦争を書く構想もあるんですか?
逢坂
可能性としてはいろいろ考えています。とりあえず、近代ヨーロッパの戦争もので3本やるのはないかなと思っています。戦争を書くのってやっぱりしんどくて、精神的にもたないんです。『同志少女よ、敵を撃て』を書いた後も相当ボロボロになったんですが、『歌われなかった海賊へ』も書き終わった瞬間、咽頭炎になって二週間寝込みました。次は一旦離れようかな、と。ただ、作家としての自分と戦争は切り離せない部分があるから、どこかのタイミングで戻ってくることになるとは思います。加藤さんは?
加藤
まだわからないです。今回のような強烈な出会いがあれば、戦争についてまた書くことはあると思います。でもこればっかりはわからない。とはいえ、次作についても考えなきゃダメなんだけど、今はさすがにちょっとのんびりさせてほしい(笑)。
逢坂
いやぁ、これからもっともっと忙しいことになると思いますよ(笑)。
加藤シゲアキ(かとう・しげあき)
1987年生まれ。大阪府出身。NEWS のメンバーとして活動しながら、2012年『ピンクとグレー』で作家デビュー。21年、『オルタネート』で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞。『なれのはて』が第170回直木賞にノミネート。
逢坂冬馬(あいさか・とうま)
1985年生まれ。埼玉県出身。2021年にデビュー作『同志少女よ、敵を撃て』がアガサ・クリスティー賞大賞を受賞し、「キノベス!2022」1位に。翌年には同作で第166回直木賞候補となり、本屋大賞、高校生直木賞を受賞。