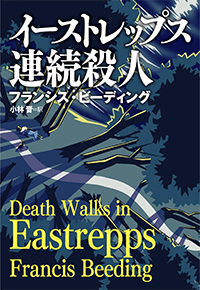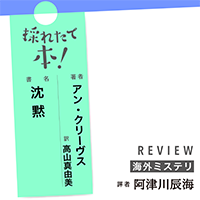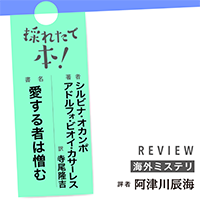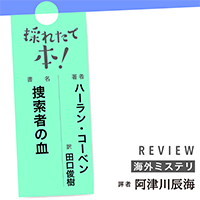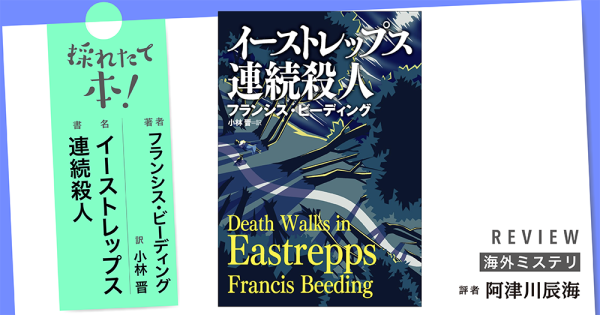採れたて本!【海外ミステリ#31】
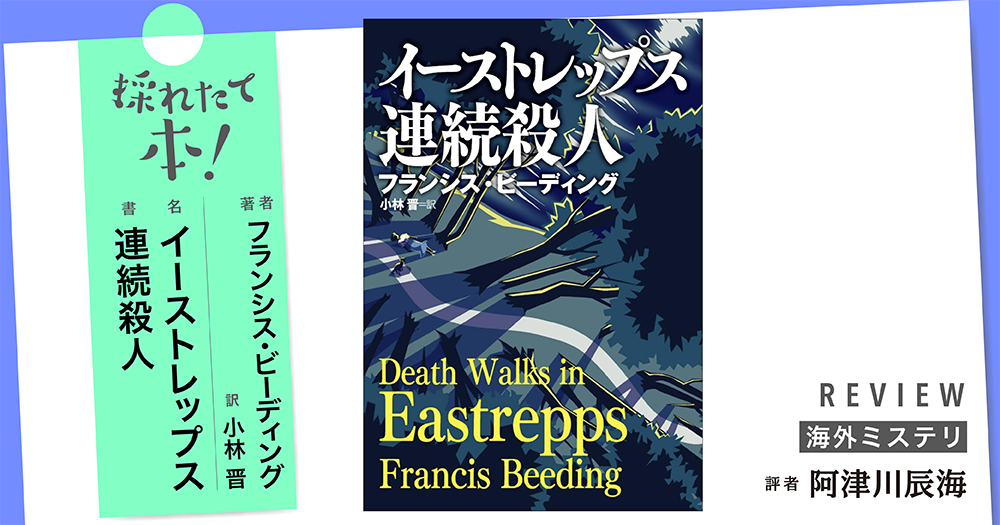
「幻の名作」を発掘、という言葉には夢がある。とはいえ同時に、一抹の不安を感じる人もいるのではないだろうか。擦れた読書家ほど、「幻の名作」には、「幻」になるだけの理由があると知っているからだ。とはいえ、長らく評価されなかった理由が、その作品の先進性にあるのならば、「幻の名作」は「今読むのが最も面白い作品」とイコールになる。
フランシス・ビーディング『イーストレップス連続殺人』は、一九三〇年代に発表されたシリアル・キラーサスペンス×本格ミステリである。訳者は小林晋で、扶桑社ミステリーにおいて古典名作を発掘、紹介し続ける姿勢には頭が下がる(この「採れたて本」でも以前ロバート・アーサー『ガラスの橋 ロバート・アーサー自選傑作集』を紹介した)。シリアル・キラーものだから先進性がある、早すぎた、というわけでは決してない。一九三一年にイギリスで初版が出版されたというから、この時点でクリスティーの『ABC殺人事件』(一九三六年)より早い。早いのだが、一九三一年の前後に連続殺人ものは多くの作例があることは、塚田よしとの解説でも明瞭に言及がある。
では、この作品の何が先進的なのかといえば、凄まじくトリッキーな構図である。
ノーフォーク海岸沿いの保養地、イーストレップスで老婦人が殺害され、以後、同じ手口で殺人が繰り返される。巻頭には図版としてイーストレップスの地図が挿入され、六つの殺人が起こることが分かってしまうが、殺人の起こる地点が分かるだけで、状況も被害者も分からないので、スリルは保たれている(なお、この地図は訳者あとがきによればイギリス版の初版から収録したもののようで、海外でも図版があるバージョンとないバージョンが混在しているらしいから、かなり貴重なものだ。眺めているだけで面白い地図なので、ぜひ見てみてほしい)。
複数の視点を切り替えるリズムや、脇役まで含めてキャラクター像が分かりやすく立っているところなど、エンターテインメントの要件も十分に備えており、まさかの法廷劇まである。被害者を繫ぐミッシング・リンクや凶器の謎など、脇筋を固めるネタの提示もスマートだ。サービス精神満点の作品である。
結末に至って、事件全体の構図が明らかになる瞬間の手つきはまさに圧巻だ。捻りに捻りすぎていて、一九三一年時点の状況では凄みが伝わらなさそうなのだが、今読むとその構造の異常性がよく分かる。あの作家や、あの作家が試みたことの先取りをしているのだ。ある種の「名犯人」小説と言ってもいいかもしれない。
それでいて、こうした「幻の名作」にありがちな「飛び道具」的な臭いが強くないのも嬉しい。正攻法で、技巧的に、しかしあり得ない方向に突き抜ける。そこが美しい。
評者=阿津川辰海