坂本 葵 著 『食魔 谷崎潤一郎』に見る「料理的」な作品の秘密…山内昌之が紹介!
「料理は藝術。美食は思想」という哲学を生涯貫き、この世のうまいものを食べ尽くした谷崎は、「食魔」とも称された美食経験を持ったことで有名。明治大学特任教授の山内昌之が、かつてない谷崎論を読み解きます。
【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】
山内昌之【明治大学特任教授】
「料理的」な作品の秘密は書生時代の日々の暗い思い出
食魔 谷崎潤一郎
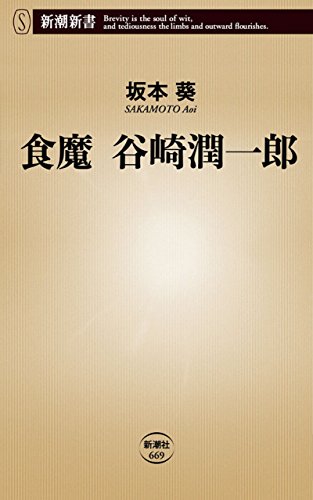
坂本 葵 著
新潮新書
760円+税
谷崎潤一郎は、三日に一遍は美食をしないと、仕事が手につかなかったという。三島由紀夫ではないが、谷崎の小説は読んでいても美味しいのである。
坂本葵氏は、谷崎の作品が「料理的」である秘密を、少年期に裕福だった家が没落し、築地精養軒の経営者の家に家庭教師兼書生として住み込んだ日々の暗い思い出に求める。何しろ主人一家は仕出し屋のコック料理を毎日食べているのに、自分ときては沢庵やひじきの粗食が出されるだけだった。
食い意地は谷崎を生涯文学に駆り立てる原動力であり、料理を通して母の思い出をたどるエンジンのようなものだった。
著者は、谷崎が多食の女には淫奔な婦人が多いと指摘した点に着目する。確かに、悪女・妖婦系の『痴人の愛』のナオミや、『卍』の光子たちは揃いも揃ってよく食べるのだ。一見すれば、多食と多淫は結びつかないようにも思える。しかし、彼女たちは文学的に目に見えないものを象徴的に貪り食う存在なのだ。ナオミが一日ビフテキを三皿平気で平らげるのは、谷崎が食を通してエロチシズムを比喩的に表現しようとしているからだ。
谷崎作品の不気味さは美食小説によく現れている。『美食楽部』では、会員たちの肥満体は東坡肉やフォアグラにたとえられ、主人公の伯爵がようやくテーブルについても素材のよく分からない料理が出てくる。会長なるコックの手にかかればどんな物でも料理の材料になってしまう。「上は人間から下は昆虫に至るまでみんな立派な材料になるのです」と。
それでいて、これといった事件が起こるわけでもなく、客が食した中身が何であったのか、正体を解き明かすこともない。
スタンリー・エリンの『特別料理』のような仕立てよりも、はるかに洗練されているのだ。谷崎は、料理を作る人、食べる人の境界さえ判然とさせず、読者にも何も食べなくても食べたような境地にさせるのだ。これこそ食の美学を求めた谷崎文学の極致だと、著者は結論づけたいのだろう。
(週刊ポスト2016年6.10号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/06/21)





