雫井脩介著『望み』が語る、家族とは何か。著者にインタビュー!
「あの子は殺人犯なのか、それとも被害者なのか。」揺れ動く父と母の思い――。どこか不穏な空気感と、深く濃密な心理描写が秀逸な一作。執筆時、著者が最も悩み、苦しんだという渾身の力作の創作の背景を、著者にインタビュー。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
家族とは何か。心に深く突き刺さる比類なき心理サスペンス
『望み』
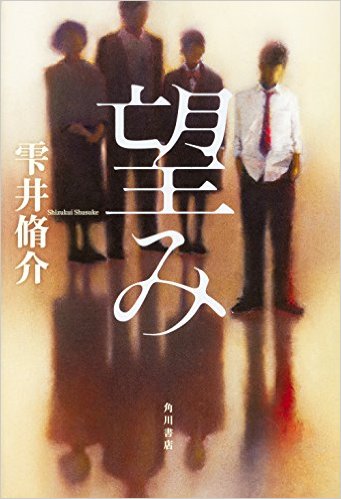
KADOKAWA 1600円+税
装丁/高柳雅人装画/牧野千穂
雫井脩介
●しずくい・しゅうすけ 1968年愛知県生まれ。専修大学文学部卒。出版社勤務等を経て、2000年に第4回新潮ミステリー倶楽部賞受賞作『栄光一途』でデビュー。05年『犯人に告ぐ』で第7回大藪春彦賞。同作は週刊文春ミステリーベスト10第1位等に輝き、映画化もされた。他に『虚貌』『火の粉』『クローズド・ノート』『ビター・ブラッド』『犯罪小説家』『銀色の絆』『検察側の罪人』『仮面同窓会』等、ベストセラーや映像化作品多数。160㌢、56㌔、A型。
実人生でなかなか出会えない新しい感情が読む人の経験になれば僕が書く意味もある
まさに究極の選択である。
ある日、遊びに出たまま帰らない息子の友人が遺体で発見され、現場付近では慌てて逃げる2人の少年の姿が目撃された。埼玉県、〈戸沢市〉郊外で起きた少年リンチ殺人事件である。
未だ消息不明の関係者は3名。そのうち高校1年生の息子〈規士〉は被害者なのか、それとも加害者なのか―。市内で建築事務所を営む父親〈石川一登〉と校正者の母親〈貴代美〉は、まさに2つに1つの可能性に身を引き裂かれてゆく。
父は息子の無実を、母は生存を信じる。しかしそれは、前者であれば規士の死を、後者は息子が殺人犯であることを同時に意味した。その致命的な『望み』の違いに崩壊寸前となる家族の、どちらに転んでも〈望みなき望み〉の行方を見事描き切った、雫井脩介氏、渾身の一大傑作である。
*
先ごろドラマ化もされた『火の粉』や、『犯人に告ぐ』『クローズド・ノート』等、圧倒的なリーダビリティや心理描写で定評のある雫井氏。その彼が「最も自分を追い込み、最も悩み抜いた作品」が、本書だという。
「この小説は、父親と母親それぞれの視点で進みます。息子を大事に思っているのは同じでも、事件の捉え方、考え方は違う。ただ、対照的に見えても、そこにはそれぞれ葛藤が生じ、変化も起こります。そんな複雑な心理を、どう表現すればいいかということに悩み、執筆の体感時間がいつもより何倍にも感じられました。
両親や妹〈雅〉にすれば規士が犯人でも被害者でも救われず、各自守りたいものが違うだけで、誰の望みも正しいわけです。しかもマスコミが押し寄せる中、受身を強いられた一家の揺れ動く心理を、僕自身息をつめて拾っていきました」
一登自ら設計した自慢の家に一家4人が暮らす石川家。規士は練習中の事故でサッカー部をやめて以来、塞ぎがちだが、有名私立をめざす中3の雅と仲もよく、一登たちは子供たちと何でも話し合ってきたはずだ。
しかし夏休みのある日、規士は顔に痣を作って帰宅し、数日後、今度は貴代美が彼の机からナイフを発見する。ナイフは一登が預かるが、その後、家を出た規士は〈いろいろあってまだ帰れない〉とメールを寄越したきり、姿を消したのだ。
折しも市道に乗り捨てられた車から男の死体が発見されたとニュースは報じ、夫妻は警察に相談。しかし刑事は被害者〈倉橋与志彦〉との関係を一方的に訊ね、規士を疑う風ですらある。
「警察が何も教えてくれない一方、報道やネットには噂話の類が流出する。子供の詳細な交友関係まで親も把握し切れていないし、被害者か加害者かも分からない状況下にあっては、自分たちが動いて真相を探るというのも無理があります。ただ見守るしかない中で、少しずつ表に出てくる情報に一喜一憂する。その静かな揺れ動きをドラマとして捉えることができればと思いました」
具体的な台詞で心理を形にする
本書ではひたすら息子の無事を願う母と、我が子を信じる父の対立構造が他人事とは思えぬ緊張感を醸し、〈犯人だったら困る〉と、父親にだけ打ち明ける雅に、貴代美は女の小狡さを感じていた。そして規士が犯人だった場合、社会的立場を失う夫を〈あなたは、世間体第一で考えてるのよ〉と罵る彼女自身、最も恐れる事態から目を背けたくて、その望みに縋るかのようだ。
「2人とも反対の可能性は重々承知しつつ、そう望むことで何とか自分を保っているんですよね。一方雅は子供ならではの本音を言える部分があって、それが一つの波風にもなる。妹であろうと家族である限り、無関係では済まされないわけです」
そんな貴代美を心配して、実家から手料理を手に駆けつけた老母が、〈幸せなんて感じなくたってね、本当に失ってはいけないものを守っていくのが大事なの〉と諭すシーンや、それを聞いて〈自分の子どもが、この先不幸になるとしても、母はそれを許してくれるという〉〈ならば、自分は何でもできると思った〉と貴代美が腹を括るシーン。さらに覚悟を決めた彼女が、息子を信じる中学の親友〈涼介〉と町で再会するシーンが秀逸だ。涼介は規士を脅していた不良一味の情報を仲間と集め、今から通報に行くという。しかし貴代美は〈そんなことしてどうなるの?〉〈規士にまで、その真っすぐなところを押しつけるのはやめて〉と言い放ち、涼介を絶句させるのだ。
「わが子を悪者にしてまで守る理不尽さは自覚しつつ、その壁を突き崩すほど覚悟した人間は『こんなことを言うのか!』と周囲がたじろぐシーンを書くのが、たぶん僕は好きなんです。その豹変すら厭わない凄味にドラマを感じるし、特に女性は強いと思います」
心理描写と言うは易しだが、それを雫井氏は具体的なシーンや台詞で形にする。そして通り一遍な解釈から零れ落ちたまだ見ぬ感情に言葉を与えるのも、小説家の仕事だと言い切るのだ。
「実人生ではなかなか出会えない新しい感情に出会うことも、僕は一種のエンターテインメントだと思う。人間は一つの感情で括れるほど単純じゃないし、その初めて知る感情が読む人の経験になれば、僕らが書く意味もあるのかなって」
つい自分ならどうか、と思わずにいられない本書は、身を捩るほど過酷な経験を読む者に強いる。だが読んだ前と後では明らかに何かが違い、自己愛も家族愛も全て曝け出した彼らの残像がいつまでも脳裏にこびりつく、今季最大級の収穫だ。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年10.14/21号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/10/19)

