私小説作家・車谷長吉を支えぬいた、高橋順子による回想『夫・車谷長吉』
作家・車谷長吉を支えた妻が振り返る結婚生活。その魂の交流を描いた一冊『夫・車谷長吉』。その創作の背景を著者にインタビュー。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
直木賞受賞、強迫神経症の発症―異色の私小説作家を支えぬいた詩人の回想
『夫・車谷長吉』
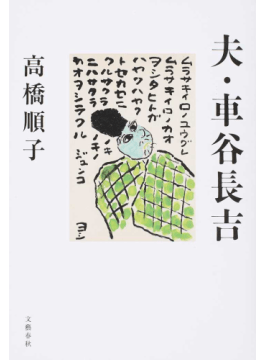
文藝春秋 1600円+税
装丁/関口聖司
高橋順子

●たかはし・じゅんこ 1944年千葉県飯岡町(現旭市)生まれ。東京大学文学部卒。出版社勤務を経て、87〜98年書肆とい主宰。98〜05年法政大学非常勤講師。90年『幸福な葉っぱ』で現代詩花椿賞、97年『時の雨』で読売文学賞、2000年『貧乏な椅子』で丸山豊記念現代詩賞、14年『海へ』で藤村記念歴程賞と三好達治賞。他にエッセイ集『水のなまえ』や小説『緑の石と猫』等。162㌢、O型。「長吉はA型だったと聞いています」。
「書きたいものがある限り死なない」―命を削るように書いた夫は約束してくれた
無粋ながら、東京千駄木の、作家の夫と詩人の妻が慎ましく暮らす家に、読んでいるこちらまでが上がり込んでいる気分になった。
夫は『赤目四十八瀧心中未遂』(98年)等で知られる直木賞作家・車谷長吉氏。妻は詩人・エッセイストとして活躍する高橋順子氏。15年5月、誤嚥性窒息死で急逝した夫の三回忌に合わせ高橋氏が書き下ろしたのが『夫・車谷長吉』である。
後年は強迫神経症や脳梗塞を患い、ふさぎこむことも多かった長吉は、かつて恋文ともとれる〈絵手紙〉を唐突に送りつけ、11通目から4年後に2人は結ばれた。長吉48歳、順子49歳の時だった。そんな出会いのいきさつや、取材や講演に夫婦で連れ立った旅のこと。真っ先に作品を見せ合ったという表現者同士の絆を、著者は22年分、自身の日記を元に克明に記してゆく。
折々に詠んだ詩句を交え、事実だけを坦々と追う抑えた筆致からは、創作や病に苦しみ、そのくせお茶目でもあった故人の横顔がかえって偲ばれ、かくも端正な詩人の言葉に見送られて、この作家はつくづく幸せだ。
*
「先日もね、長吉はちょうど今の時期に咲くドクダミの白い花が好きだったから、忌日を十薬忌にしてはどうかという人がいたんです。十薬は歳時記にもあるドクダミの別名で、確かに彼は毒にも薬にもなった人かもしれないなあって(笑い)」
〈車谷嘉彦と署名のある絵手紙をもらったのが、最初だった。一九八八年九月十二日、東京本郷の消印〉
青土社時代の元同僚から手渡されたその絵手紙には、〈青い空っぽのガラス壜〉が描かれ、〈ただならぬ気配のたちこめる肉太の字で、余白がびっしり埋められていた〉。文面には〈高橋順子詩集、三冊を借りて読んだ。孤独な生い立ちの木〉などとあったが、高橋氏はその後届いた手紙にもほとんど返事をしていない。
「当時は面識もありませんし、独り言みたいな手紙も多いから返事の書きようがなくて。絵の方も後に長吉の本の表紙になるほど味のあるものだったのに、私も目のない女です(苦笑)」
その後は自身が主宰する「書肆とい」のPR誌や詩集を送るなどしたが、高橋氏が花椿賞の授賞式に招いた時も、長吉は彼女を遠巻きに眺めるだけだった。
「私は『そろそろ顔を見せなさいよ』というつもりで招いたんですけどね。普段の長吉は傍若無人なおしゃべりで、平気で嘘も書くわりに、女性には臆病でした」
そしてその年の大晦日、彼と彼女は初めて会う約束をする。〈赤い自転車が停まっており、その前にその人がいて会釈した。ほっそりした坊主頭の人だった〉と描写される場面はまるで映画のようだ。
やがて長吉は小説集を自費出版したいと言って原稿と手付金を託し、本が出来たら京都で雲水になるなどと言うが、一時は芥川賞候補にも上りながら30代を放浪にやつした彼の文学は、既に圧倒的だった。そうこうして『新潮』に掲載された『鹽壺の匙』が三島賞等を受賞。この時の愛の告白ともとれる受賞の言葉が背中を押し、93年秋、2人は結婚。〈この世のみちづれにして下され〉という長吉との生活が始まった。
白洲正子さんも怖がる程の殺気
直木賞受賞前後の狂騒や、いつからか執拗に手を洗うようになった長吉の神経症発覚まで、高橋氏は〈水道料金〉の増え方など、あくまで客観描写に徹している。
「日記には『包丁3本隠す』なんてことが書いてあって、つらかった記憶ほど鮮明でしたけど、やはり個人的な感傷は邪魔になりますから。
私自身、彼のことが知りたくてこれを書いたものの、今でもわからないことだらけなんですよ。長吉はとにかく謎や揉め事の多い人で、あの白洲正子さんが『彼は怖い』と言うくらい、殺気走った感じもあったので」
絵手紙に始まって、〈どくだみを踏んでキスする男女かな〉と初デートで長吉が詠んだ句など、この2人はことごとく書かれた言葉で結ばれていた印象を受ける。
「本人も『書かれたものが全てだ』とよく言っていて、困るのは私の友達の話でも何でも書いちゃうんですね。『織田作之助の女房は亭主のためにご近所の噂を蒐集したもんだ』なんて言って。
千駄木の次に住んだ今の家では2階の北の3畳間が長吉、1階の南が私の書斎で、彼はその狭〜い部屋を自分で選んだくせに、『順子さんは南の広い部屋をとり、私には3畳間があてがわれた』と書く人なんですよ。嘘ではないけれど、あてがわれたなんて、ねえ(笑い)」
一見強面の長吉は順子のJを取って〈UNKOちゃん〉と呼ぶなど、関西弁で言う〈甘え太〉でもあった。
「私は私で長吉を悪たれの〈くうちゃん〉と呼び、横縞が嫌いな彼の前では横縞の服は着ないとか、ちょっと甘やかしすぎましたね。
彼が病気になってからも逃げようとは思わなかったな。お遍路に出たりピースボートで南半球を一周した時は症状も多少改善していたし、常に命を削るようにして書いていた彼は書きたいものがある限り、死なないと約束してくれたので」
だがその日。ビール代の300円をねだり、散歩から一足先に帰宅した長吉は、翌日大根と煮るつもりだった生のイカを喉に詰まらせ、唐突に逝ってしまうのだ。
「最期のことはお話ししたくありません。ここに書いたことが全てですから……」
と、俄かに表情を硬くした高橋氏は、その最期の場面を「手にお数珠を巻いて」どうにか書き上げたという。書くことで結ばれた2人は、やはりこの2人でなければならなかったのだ。
●構成/橋本紀子□
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2017年7.14号より)
初出:P+D MAGAZINE(2018/03/05)

