夏の夜によく冷えたビールを。小説のとっておきの“飲酒”シーン10選
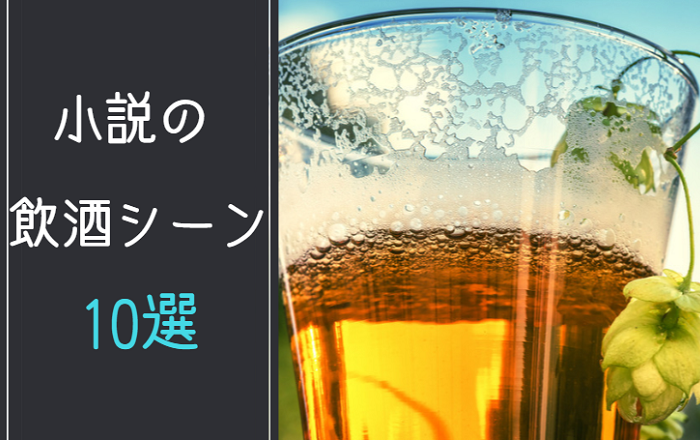
お酒が好きな人にとっては、キンキンに冷えた生ビールが恋しくてたまらない夏。今回は国内外の小説の中から、読んでいる自分までお酒を飲みたくなってしまうようなとっておきの“飲酒シーン”を集めました。
夏本番がすぐそこに迫り、徐々に、夜もクーラーなしでは寝苦しいほどになってきました。酒呑みの人にとっては、キンキンに冷えた生ビールが恋しくてたまらない季節ですね。
今回は、国内外の小説の中から、読んでいる自分までお酒を飲みたくなってしまうようなとっておきの“飲酒シーン”を集めました。夏の夜に飲みたいお酒No.1であるビールを中心に、さまざまなシチュエーションで飲み交わされるすばらしいお酒の数々を、ぜひ、お好きなアルコールを用意してお読みください。
1.しゅわわわ、という音が耳をくすぐる──『ランチのアッコちゃん』

出典:http://amzn.asia/glILljO
「ビールを頼む」
(中略)
玲実は嬉しそうに、腰に下げているカップの一つを取ると、腰を屈めてチューブからビールを注いだ。しゅわわわ、という音が耳をくすぐる。小憎らしいことに、液体八割に対して泡は二割。ビールの黄金分割と言ってもいい、完璧なバランスだった。
雅之は受け取ったカップをしげしげと見つめる。ビニールのカップではあるが、よく冷えた泡が唇に心地好い。ほろ苦い黄金色の液体が喉を通り過ぎると、世界が急に彩りを取り戻した。──柚木麻子『ランチのアッコちゃん』第四話 ゆとりのビアガーデン より
キンキンに冷えたビールはどんなシチュエーションで飲んでも美味しいものですが、中でもビアガーデンで飲むビールは格別、と思われる方は多いのではないでしょうか。
柚木麻子による連作短編集『ランチのアッコちゃん』の中の1編、『ゆとりのビアガーデン』は、出来の悪い会社員だった“ゆとり世代”の佐々木玲実が、その人懐っこさと行動力を活かしてオフィスの屋上にビアガーデンを作るというストーリーです。
屋上で玲実が注いだビールを苦々しい気分で飲む雅之は、玲実がかつて勤めていた会社の社長。玲実が部下であった頃はその“使えなさ”に日々頭を悩ませていた雅之ですが、ビアガーデンで働く玲実は意外にも商才を発揮し、新しい職場で生き生きとしていました。
一九五三年、大阪で始まったんです。(中略)ビアガーデンの誕生の地となったのが、大阪第一生命ビル屋上。もともとはそのビルの地下でレストランを経営していた黒須定七さんという男性が、オートバイの展示会のプロデュースを頼まれ、屋上を借り切ってパーティーしたことが始まりなんですって。
ビアガーデンの発祥について滔々と語る玲実のペースに、雅之は知らず知らずのうちに飲まれてしまいます。ビアガーデンの開放的な描写を楽しむのはもちろん、スカッとする小説を読みたい方にはうってつけの1冊です。

2.「そういうビールは、グラスで飲む方がいいんじゃないの?」──『儀式』

出典:http://amzn.asia/4dAjUUU
私は台所のテイブルについて、ビールをらっぱ飲みしていた。「ピルズナァ・ウーアクウェル。金持ちの愛人でもいるのか?」
「あなたが飲んでみたがるんじゃないかと思ったの」
私はまた一口飲んだ。「うまい」
(中略)私はビールを飲み干して、もう一本取りに冷蔵庫へ行った。一本取り出したあと、まだ十本あるのを見ると、深い満足感が急速に胸中に広がった。
「そういうビールは、グラスで飲む方がいいんじゃないの?」
「まったく同感だ」──ロバート・B・パーカー『儀式』より
『儀式』は、アメリカのボストンを舞台にした、私立探偵スペンサーが活躍するハードボイルドな長編小説「スペンサー・シリーズ」の第9段です。
引用した一節は、スペンサーが恋人・スーザンの家でくつろぎながら、新しい探偵の仕事の依頼について相談しているシーン。スーザンが簡単な食事を用意している間、スペンサーは瓶ビールで喉の渇きを潤します。
ここでスペンサーが飲んでいる“ピルズナァ・ウーアクウェル”(ピルスナー・ウルケル)は、チェコを代表する伝統的なピルスナースタイル(※)のビール。日本でもマニアに人気のこの高級ビールが恋人の家の冷蔵庫に入っているのを見たスペンサーは「金持ちの愛人でもいるのか?」と軽口を叩きながらも、その味に「うまい」と舌鼓を打ちます。
(※…淡色の下面発酵ビールであり、ホップの苦みを特長とする)
ビールを1本飲み終えて冷蔵庫を見ると、まだ10本ものビールが残っている……。そんな光景は、ビール党の方の目には夢のように映るのではないでしょうか。

3.「ひやして置きましたけど、お飲みになりますか?」──『おさん』
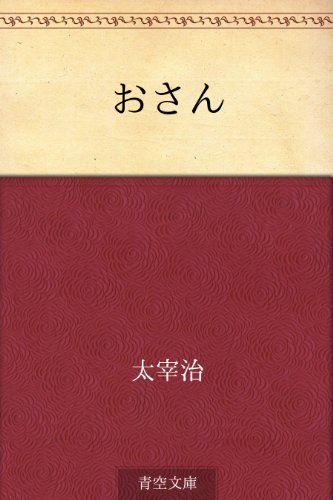
出典:http://amzn.asia/3kHpDpw
「暑かったでしょう? はだかになったら? けさ、お盆の特配で、ビイルが二本配給になったの。ひやして置きましたけど、お飲みになりますか?」
夫はおどおどして気弱く笑い、
「そいつは、凄いね。」
と声さえかすれて、
「お母さんと一本ずつ飲みましょうか。」
見え透いた、下手なお世辞みたいな事まで言うのでした。
「お相手をしますわ。」──太宰治『おさん』より
この、どこか不穏な香りのする夫婦のやりとりは、太宰治による短編小説『おさん』の中の一節です。
主人公である「私」は、戦時中の疎開先であった青森で被災し、子どもを連れて東京に戻ってきたばかり。それまでは優しく穏やかであった夫がこそこそと落ち着かない挙動をするようになったのを見て、「私」は、夫が自分のいない間に不倫をしていたことに気づくのです。夫はやがて、不倫の罪悪感に耐えられなくなり、自ら命を絶ってしまいます。
この痛ましい小説は、太宰治が愛人の女性と入水自殺をする約半年前に発表されました。『おさん』は女性の語り口を借りた、太宰による自己批判的な作品と捉えられています。
太宰はかつて“酒”について、自らの随筆の中で
酒を呑むと、気持を、ごまかすことができて、でたらめ言っても、そんなに内心、反省しなくなって、とても助かる。”
──『酒ぎらい』より
と語っていたこともあり、つらく不安定な気持ちを紛らわす特効薬のように“酒”を飲んでいたことが窺えます。

4.まるでお腹の中が花畑になっていくようなのです──『夜は短し歩けよ乙女』

出典:http://amzn.asia/9cwYnJ4
偽電気ブランを初めて口にした時の感動をいかに表すべきでしょう。偽電気ブランは甘くもなく辛くもありません。想像していたような、舌の上に稲妻が走るようなものでもありません。それはただ芳醇な香りをもった無味の飲み物と言うべきものです。本来、味と香りは根を同じくするものかと思っておりましたが、このお酒に限ってはそうではないのです。口に含むたびに花が咲き、それは何ら余計な味を残さずにお腹の中へ滑ってゆき、小さな温かみに変わります。それがじつに可愛らしく、まるでお腹の中が花畑になっていくようなのです。飲んでいるうちにお腹の底から幸せになってくるのです。
──森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』より
ここで少し、ビール以外のお酒もご紹介しましょう。
明治時代に生まれたブランデーベースのカクテル“電気ブラン”をご存じでしょうか。これは、東京・浅草でいまでも続く老舗「神谷バー」の創業者が考案したカクテルで、ブランデーにジンやワインといったさまざまな酒類、そして薬草をブレンドしたもの。高いアルコール度数と、ほんのり甘い風味が特徴です。
森見登美彦の『夜は短し歩けよ乙女』には、そんな電気ブランを真似て作られた“偽電気ブラン”なるアルコール飲料が登場します。偽電気ブランは、電気ブランの製法がまだ明かされていなかったころ、なんとかその味を再現しようと企てた人々によって発明された、と作中では説明されています。引用した一節は、“偽電気ブラン”をある夏の一夜に初めて飲んだ黒髪の乙女(主人公の想い人である大学生)が、その感想を語るシーン。このシーンのあとには、
偽電気ブランはまるで私の人生を底の方から温めてくれるような味であったのです
という夢のような独白が続きます。偽電気ブランの製法は作中では明かされていませんが、人生で一度は味わってみたい、と思わされる1杯であることは間違いありません。

5.「まぐろ納豆。蓮根のきんぴら。塩らっきょう」──『センセイの鞄』

出典:http://amzn.asia/cHm9mGG
「まぐろ納豆。蓮根のきんぴら。塩らっきょう」カウンターに座りざまにわたしが頼むのとほぼ同時に隣の背筋のご老体も、「塩らっきょ。きんぴら蓮根。まぐろ納豆」と頼んだ。
趣味の似たひとだと眺めると、向こうも眺めてきた。
「キミは女のくせに一人でこういう店に来るんですね」センセイはさらしくじらの最後の一片にしずしずと酢味噌をからめ、箸で口に持っていきながら言った。
「はあ」ビールを自分のコップにつぎながら、わたしは答えた。高校時代の先生だったことは思い出したが、名前が出てこなかった。
よくも一生徒の名なぞ覚えているものだとはんぶん感心、はんぶん困惑しながら、ビールを干した。──川上弘美『センセイの鞄』より
川上弘美による長編小説『センセイの鞄』は、主人公・ツキコが馴染みの居酒屋で高校時代の国語の教師である“センセイ”に出会うシーンから始まります。
ツキコがまぐろ納豆や蓮根のきんぴらといった酒のアテを注文したとき、まったく同じものを頼んでいた“センセイ”。ふたりはこの店での再会をきっかけに、時々会っては酒を酌み交わす仲になっていきます。ある休日に一緒に近所に出かけた際は、ビールを巡って
「喉がかわきませんか」センセイが聞いた。
「でも、夕方にビール飲みますから、それまでは何も口にしません」答えると、センセイは満足そうに肯いた。
「よくできました」
「テストだったんですか」
「ツキコさんは酒にかんしてはできのいい生徒だ。国語の成績の方はさっぱりでしたが」
といったユーモラスなやりとりが交わされるなど、着実にその距離を近づけてゆくふたり。60代と30代、歳の離れたセンセイとツキコですが、ふたりは共通の趣味であるお酒を通して次第に惹かれ合っていくのです。

6.「春、乾杯をしようじゃないか」──『重力ピエロ』

出典:http://amzn.asia/5O5eEOe
私は手に持った缶ビールを見た。そのうちの一本を右手で持つと、思い切り振った。しゃかしゃかしゃかと上下に揺する。二階を見上げ、「春、乾杯をしようじゃないか」と声をかけた。
(中略)何度も振ったほうの缶ビールを、屋根の上にいる春に向かって投げた。春がそれを受けとめる。
蓋を開けたらビールが吹き出すのを、私は期待し、笑いを堪えながら、「さあ、乾杯だ」と高らかに言った。
すると、春は缶をじっと見つめたままで、なかなか蓋に手をかけない。どうやら私の悪戯に気がついたようだ。
「兄貴、これ振っただろ」
「いや」空とぼけた。
「なら、缶を交換してよ」と春は笑った。そして、屋根から身を乗り出すようにすると、下を眺めて飛び降りた。
春が二階から落ちてきた。──伊坂幸太郎『重力ピエロ』より
ビールを思い切り振って渡すというチャーミングな悪戯を描いたこのシーンは、伊坂幸太郎の代表作、『重力ピエロ』のラストです。春と「私」は、血の繋がっていない弟と兄。春たち家族は今でこそ仲良しであるものの、過去には母親をめぐる辛い出来事を経験していました。
実はこの“乾杯”は、「私」の父親の葬儀の日、立ち上る火葬場の煙を近くの小屋の屋根の上から眺めつつ交わされています。異常な状況ではありますが、春と「私」はまるで競馬の応援のように、屋根の上から
「行け。行け」
と煙に向かって声をかけるのです。
一見、仲のよい兄弟のただのふざけ合いのようにも思えるこの場面。しかし、『重力ピエロ』を最初から読んでいけば、このラストシーンには思わず心を動かされることでしょう。これから本作を読まれる方は、この爽やかな“乾杯”の裏にある兄弟たちの葛藤や別れを、ぜひじっくりと味わってください。
(合わせて読みたい:
独特な言葉選びが印象に残る、伊坂幸太郎の名言10選。
【読みやすく、多くの層に人気!】伊坂幸太郎のオススメ作品を紹介)

7.一夏中かけて、25メートル・プール一杯分ばかりのビールを飲み干した──『風の歌を聴け』

出典:http://amzn.asia/cuZTGEX
一夏中かけて、僕と鼠はまるで何かに取り憑かれたように25メートル・プール一杯分ばかりのビールを飲み干し、「ジェイズ・バー」の床いっぱいに5センチの厚さにピーナツの殻をまきちらした。そしてそれは、そうでもしなければ生き残れないくらい退屈な夏であった。
──村上春樹『風の歌を聴け』より
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」
……かの有名な1文で始まる村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』は、「僕」が海辺の街に帰省した1970年の夏を描いた物語です。「僕」は夏の間、家の近くの酒場“ジェイズ・バー”に足繁く通い、友人の“鼠”を始めとするさまざまな人々と再会し、そして別れます。
ジェイズ・バーで「僕」と鼠は、いつも決まってビールを飲んでいます。バーテンダーのジェイはその様子を呆れたように見ながらも、何も口出しはしてきません。
ジェイズ・バーのカウンターには“二匹の緑色の猿が空気の抜けかけた二つのテニス・ボールを投げあっている”ように見える絵がかかっており、それが何を象徴しているのかと「僕」がジェイに聞くと、こんなクスリとくるやりとりが交わされるのです。
「左の猿があんたで、右のがあたしだね。あたしがビール瓶を投げると、あんたが代金を投げてよこす。」
僕は感心してビールを飲んだ。
作中で「僕」と鼠は、楽しいときも辛いときも、事あるごとにお酒を飲みます。洒脱でありながらもどこかほろ苦い登場人物たちの会話は、夏の夜にひとり、冷えたビールを飲みながら味わうのにぴったりです。

8.大きく開いた喉に、鋭く細やかにとげを立てて液体が流れ込む──『今夜、すべてのバーで』
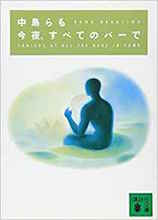
出典:http://amzn.asia/hnxwsLY
「お飲みものは」
「ビール」
言ってしまってから、おれは、“はてな”と面妖な気になった。(中略)
考える間も、悔やむ間もない間に、おばさんがビールの大壜とグラスを運んできて目の前に置き、一杯目をついでくれた。
「ごゆっくりどうぞ」
グラスもていねいに冷やされていたのだろう。しっとりと外側に汗をかいている。少し冷やし過ぎなのか、泡の厚みが薄かった。
おれは、約三秒ほどそのグラスを見つめていた。それから、手に取って、口へ持っていった。(中略)
大きく開いた喉に、鋭く細やかにとげを立てて液体が流れ込む。おれは息が苦しくなるまで、ごくごくとビールを流し込んだ。──中島らも『今夜、すべてのバーで』より
思わず喉が鳴るようなこのワンシーンは、中島らもの長編小説『今夜、すべてのバーで』からの一節です。主人公の小島容はアルコール依存症で病院で治療を受けている身でありながら、ある夜、アルコールの誘惑に負けてしまい、病棟を抜け出して近くの蕎麦屋に駆け込みます。
ビールの最後の一杯を注いだところで、奥の厨房から、天ぷらを揚げる威勢のいい音が聞こえてきた。それを聞きつけた他の客が、こっちも天ぷら盛りふたつとわめいた。
そばが運ばれてきた。机の半分がた埋まるくらいの大仰な角盆に、天ぷら、そば、つゆ、薬味が乗っている。きつね色に揚がった天ぷらを見ていると、おれの中でうずくものがあった。
「ビール、もう一本」
あろうことか容は、美味しそうな蕎麦を前に我慢ができなくなり、ビールを追加注文してしまいます。蕎麦とビールを存分に味わった容に翌日待っていたのは、二日酔いと、アルコール依存症治療薬による激しい副作用でした……。
『今夜、すべてのバーで』の中で、容は自分と同じ“アル中”に悩まされるさまざまな登場人物に出会います。中でも、断酒を諦めている福来という人物は、容に
「メザシ食って長生きしようと思っても、台風で看板が飛んできて、そいつに当たって死ぬかもしれないじゃないか。私なんか、それでびくびくして暮らすくらいなら、今晩酔っ払って眠れる方を選ぶね。明日の朝目がさめるかどうかなんて、知ったこっちゃない」
と語ります。本作は、刹那的な登場人物たちの生きざまに、アルコールとの付き合い方を考えさせられるような1冊でもあります。

9.ビヤホールにゆき、ミュンヘンの黒ビールを飲みながら新聞を読んだ──『武器よさらば』

出典:http://amzn.asia/igsWhg0
ぼくはビヤホールにゆき、ミュンヘンの黒ビールを飲みながら新聞を読んだ。(中略)広告欄はぜんぶ黒く塗りつぶされていたが、これはおそらく、その欄を利用して敵と交信するのを防ぐための措置なのだろう。新聞を読んでも気分は晴れなかった。事態はどこでも悪化の一途をたどっていたからだ。黒ビールの重いジョッキを手に隅の席にすわり、プレッツェルの光沢紙の袋をあけて、塩気のある香りと、ビールを引き立ててくれる味わいを楽しみながら悲惨な記事を読んだ。
──ヘミングウェイ『武器よさらば』より
ヘミングウェイの『武器よさらば』は、第一次世界大戦下のイタリアで恋に落ちた青年フレドリックと看護師キャサリンの運命を描いた、長編小説の名作です。
作中で主人公・フレドリックは、戦いの合間やキャサリンとのデート、待ち合わせまでの時間など、さまざまなシーンでアルコールを口にします。登場するお酒はビールだけでなく、赤ワインやグラッパ、ウイスキー、グリュー・ワインなど実にバリエーション豊か。
どの“飲酒シーン”も美味しそうな食事とお酒がセットで描写されており、思わずこちらまで飲みたくなってしまうこと請け合いですが、その背景には常に戦争の冷たい影がぴたりと寄り添っています。美味しそうなお酒の描写やフレドリックとキャサリンとの軽妙な会話を楽しむのはもちろん、戦時中のイタリアの文化を知り、当時の空気を体感するのにもおすすめの1冊です。

10.御月さま今晩はと挨拶したくなる。どうも愉快だ──『吾輩は猫である』

出典:http://amzn.asia/fHQyDF0
吾輩は我慢に我慢を重ねて、一杯のビールを飲み干した時、妙な現象が起った。始めは舌がぴりぴりして、口中が外部から圧迫されるように苦しかったのが、飲むに従ってようやく楽になって、一杯目を片付ける時分には別段骨も折れなくなった。もう大丈夫と二杯目は難なくやっつけた。ついでに盆の上にこぼれたのも拭うがごとく腹内に収めた。
それからしばらくの間は自分で自分の動静を伺うため、じっとすくんでいた。次第にからだが暖かになる。眼のふちがぽうっとする。耳がほてる。歌がうたいたくなる。猫じゃ猫じゃが踊りたくなる。主人も迷亭も独仙も糞を食えと云う気になる。金田のじいさんを引掻いてやりたくなる。妻君の鼻を食い欠きたくなる。いろいろになる。最後にふらふらと立ちたくなる。起ったらよたよたあるきたくなる。こいつは面白いとそとへ出たくなる。出ると御月様今晩はと挨拶したくなる。どうも愉快だ。──夏目漱石『吾輩は猫である』より
これはかの有名な『吾輩は猫である』の最後、主人公の猫である「吾輩」が飼い主たちの飲むビールに手をつけ、前後不覚になるシーンです。
「吾輩」は、飼い主である中学教師の苦沙弥先生を始めとした個性豊かな登場人物たちの一挙一動を猫の目で見つめながら、次第に人間の運命の無情さに思いを馳せるようになります。
どうせいつ死ぬか知れぬ命だ。何でも命のあるうちにしておく事だ。死んでからああ残念だと墓場の影から悔やんでもおっつかない。思い切って飲んで見ろ
そんな退廃的な気分になってビールを飲んだ猫に待っていたのは、大きな水がめに落ちて死んでしまうというあっけない最期でした。作者である夏目漱石はかつて、新聞に掲載した随筆の中で
酒を飲んで、気分の變る人は何だか險難に思はれて仕様がない。日本では、酒を飲んで眞赤になると、景気がつくとか、上機嫌だとか言ひますが、西洋では、鼻摘みですからね。
──武田勝彦『あらゆる冒険は酒に始まる』より
と語っています。下戸であった漱石は、お酒を飲んで人が変わったように陽気になる人のことを、どうやらあまり快く思っていなかったようです。
しかしながら、ビールを飲んでほろ酔いになったとき、「吾輩」の言うように“御月様今晩はと挨拶したくなる”気持ちには、覚えがある酒呑みの方も多いのではないでしょうか。

おわりに

蕎麦屋での1杯からビアガーデンでの1杯、そして猫が飲む1杯まで。さまざまな“飲酒シーン”の饗宴、お楽しみいただけたでしょうか。
もしも、今回ご紹介した飲酒シーンをきっかけに気になる小説ができたなら、夏の寝苦しい夜にぜひ、その1冊を肴にじっくりとお酒を味わってみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2018/07/23)






