子どもの頃に憧れた未来は、すべて反転してしまった──穂村弘『水中翼船炎上中』インタビュー

今年、17年ぶりの最新歌集『水中翼船炎上中』を発表した穂村弘氏。著者インタビューを通じて、収録作品の背景や穂村氏の創作術に迫りました。
2018年5月に、17年ぶりの最新歌集『水中翼船炎上中』を発表した歌人の穂村弘氏。自分自身の“過去”と“現在”をモチーフに328首を収録した今作には、大きな注目が集まっています。
今回は著者インタビューを通して、収録作品の背景や短歌が生まれる瞬間について、じっくりとお話を伺いました。
【プロフィール】
穂村弘(ほむら・ひろし)
1962年生まれ。1990年『シンジケート』で歌集デビュー。歌論集『短歌の友人』、エッセイ集『鳥肌が』など著書多数。2018年5月に最新歌集『水中翼船炎上中』を発表。
『水中翼船炎上中』
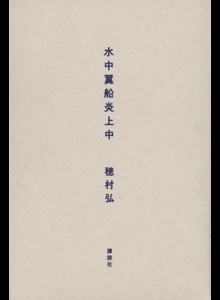
講談社/出典:http://amzn.asia/d/44ncdl8
いまの自分の体感に合うものを入れたら、“夜の歌ばっかり”に

──『水中翼船炎上中』は、前作『手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)』から17年ぶりの歌集ということで話題になっています。新作を今年発表されたのはなぜだったのでしょうか。
穂村弘氏(以下、穂村):ずっと出さなきゃ出さなきゃと思ってたんですけど、歌集をつくるのって大変なんですよね。どの歌を入れてどれを落とすのかとか、並べ方とかを考えなきゃいけないというのもそうですし、タイトルひとつとっても、その歌集というひとつの小宇宙を完全に示すタイトルをつけたいと思っているので、緊張度がすごく高くて。
今年出したのには、平成が終わるということも少し意識にありました。昭和のことを書きたいという気持ちがあったので、それならやっぱり平成のうちには、というか。編集には1年くらい時間をかけたんですが、編集しているあいだに、現在から始まって現在に戻るっていう構成がいいかなと思って、そういう形にしています。
──『水中翼船炎上中』に収録されている短歌は、『出発』という連作を除けば、短歌雑誌などで穂村さんが2000年代に発表されてきた作品を再編したものですよね。『出発』はこの歌集のために書き下ろされたんですか。
穂村:『出発』のなかの短歌もすごく古いものは25年ぐらい前に書いたもので、つい最近つくったものもあるし、ばらばらなんですよ。25年前に書いたものも、現在を表す『出発』の章のなかに入れたときに凸凹感がないようにしたかったので、いまの自分が読んで、現在の自分の体感とあまりずれていない歌を選んで入れたつもりです。ただ、そしたら夜の歌ばっかりになっちゃった(笑)。
──たしかに夜の歌が多かったです。それから、今回の歌集には「メモ」という名前で、歌集の構造を表す見取り図のようなものがついていましたよね。これまではあまり、歌集のなかで短歌が詠まれた背景を補足するということはされてこなかったと思うのですが、今回はどうしてこういう形をとられたんですか。
穂村:今回の「メモ」みたいなものを入れるっていうのは、短歌の世界では不評なんですよね。でも、広く読まれたいという気持ちがあるので、それがあるのとないのじゃ全然違うだろうなと思って。自分が初めて短歌の本を読んだときの“読めなさ”を覚えているので、やっぱりそういうガイドがあったほうがいいだろうなと。あとは、僕は装丁が好きで執着があるので、装丁が全部で9パターンあるというのも細かく説明したかったのが大きいですね。
科学に代表される未来のビジョンはみんな反転してしまった
──さきほどお話しされたように、今回の歌集は現在から過去を遡っていってまた現在に戻ってくるという、自分史のような形をとられていますよね。この形をとった理由について、「この半世紀で時空間の匂いや色が変化した感覚があって、その感覚を留めておきたかった」と穂村さんがおっしゃっていたのを拝見しました。
穂村:そうですね。たとえば、僕が子どもの頃は味の素を食べると頭がよくなるって言われてて、何にでも味の素をかけることを推奨されてたの(笑)。それから、マーガリンも「未来のバター」っていう位置づけだったりして。一方で、いまはラーメン屋さんなんかに行くと「無化調系」とか書いてあって、化学調味料を使っていないことが売りとされている。マーガリンなんて、いまは「狂ったバター」って呼ばれてたりして(笑)、摂取することを強く推奨されてはいないものですよね。
──たしかに、いまはすべてそれらの位置づけが変化してしまいました。
穂村:原発も、僕が子どもの頃は未来のお城みたいなイメージだったんだけど、いまはそうではない。だから、科学に代表される未来のビジョンはみんな反転してしまったんですよね。
僕は30歳ぐらいまで、戦争体験のある人や学生運動の経験がある人に代表されるような、「自分の中の価値観が破壊されて反転した経験」を持たない最初の世代に自分たちがなると思ってたんですよ。でもそのあと、オウムの事件や震災、それにともなう原発事故とかが発生して、自分たちはもっと内出血みたいにそれを味わうことになった。僕らには別に敗戦のような絶対的な経験はひとつもなかったのに、気がついたらいろんなことが反転していたという感覚があって、それを早く書きたいと思ったんですよね。
──たしかに少年時代を歌った短歌のなかには、ノスタルジーを感じさせると同時にどこか不吉で、平穏な日常がいつかなくなってしまうという予兆のようなイメージもあるものが散見されます。「大晦日の炬燵布団へばばばっと切り損ねたるトランプの札」といった歌にも、そんな予兆を感じました。
穂村:そうですね。反転したイメージの究極がやっぱり原発で、僕、子どもの頃に原発は素晴らしいって書かれたチラシをもらった記憶があるんですよね。そのなかの“安全性”という欄に数字が書いてあって、「99.999999……%」って9がずっと続いてたのを覚えてるんですよ、こんなの計算できるんだって思ったから(笑)。つまりこれは絶対安全ってことだって当時は思ったんだけど、いまは「嘘つかれた」って感想になってる。
あれが仮に「78%」とか書かれてたら僕は別に怒ったりしなかったと思うんだけど、99.999999……%ではない、残りの0.00000……1%のことがあの震災で起きたとは思わないから、やっぱり嘘だったんだなって。実際の現象とは別に、嘘をつかれたという気持ちのほうが意識のなかでは大きいんですよね。
──それも非常に大きな“反転”ですね。
穂村:マーガリンも原発もだけど、僕たちが子どもの頃に聞かされていた夢は誰も追えなかったんだ、って感覚があって。当時の未来予想図では、もういまぐらいの時代には火星には行ってて、木星か金星くらいを目指してるって想定だったんじゃないかなあ。『2001年宇宙の旅』とかそういう話でしたよね。だけど現実ではもう月にも行かないんだ、とか思いますよね。
子どもの頃のユートピア感と、大人になってからのディストピア感

──いま「火星」という言葉も出ましたが、『火星探検』はお母様の死をテーマとした連作だと書かれていました。穂村さんは以前から「母親の無償の愛情」というものが恐いということを繰り返しおっしゃっていたように思うのですが、この『火星探検』は穂村さんのなかでどういった位置づけなのでしょうか。ターニングポイントのような意識はありましたか?
穂村:子どもの頃は母親の無償性や愛情って、絶対必要なものですよね。でもあるときから邪魔になってきて。これは何回も話してきたことなんだけど、僕、生まれてからバレンタインデーにチョコレートを1個ももらえない時期が長かったんです。それで中学生ぐらいになってバレンタインデーがくると、学校では1個ももらえないんですけど、家に帰ると必ず「母より」っていうチョコレートが置いてあるんですよね。で、それにすごい殺意を覚える(笑)。
つまり八百長じゃないですか、家族の評価なんて。その八百長から脱しない限り最初の本物のチョコレートっていうのは手に入らないわけですよね。その後は生命保険のおばさんしかくれなかったんですけど、八百長だよね、両方とも(笑)。母親は血縁という八百長だし、保険のおばさんは下心っていう八百長ですよね。
──穂村さんは、血縁よりももっと遠いものに対する愛情のほうが本質的だとよくおっしゃっているイメージがあります。
穂村:自分が生んだ子どもがかわいいって八百長じゃん、と思うんですよね(笑)。まあ、必要悪というか。愛情の無償性が他人に向かうほうがよくて、動物や無生物に向かうのはもっといいっていう考え方ですね。
──個人的には、『火星探検』のなかの「髪の毛をととのえながら歩きだす朱肉のような地面の上を」という歌がとても好きです。お母様が亡くなった直後の歌だと思うのですが。
穂村:これは葬式的なイメージですね。葬式って一応ネクタイ締めたり髪を整えたりはするんだけど、忙しくてメンタル的にもそんな余裕ないんですよね。実感としてはとてもふわふわしていて、そういう感覚を書いています。
あと、「真夜中に朱肉さがしておとうさんおかあさんおとうさんおかあさん」って短歌もあるけど、朱肉ってハンコや肉親つまり血縁のイメージが強いですよね。これは、なにかで朱肉が必要になったけど見つからないことがあって、母がいるときは母に聞けば場所がわかったんだけど、全然見つからないとパニックになるというか。もう誰も自分を助けてくれないんだ、という感覚の歌ですね。
──最後に収録されている連作『水中翼船炎上中』は、もともと発表されていた収録歌を、歌集にされる際にすべて入れ替えられたと聞いています。これはどうしてだったのでしょうか。
穂村:最後にやっぱり“夜ではない”現在を書かなくてはいけないと思ったんだけど、それがすごく難しくて。「海」と「引っ越し」のイメージで、現在の希望のようなものを書きたいとは思ったんですが。
──最後の一首、「海に投げられた指環を呑み込んだイソギンチャクが愛を覚える」はたしかに希望を感じさせますよね。
穂村:でもそれも、見方によっては希望だけじゃなくて。人類滅亡後に地球をどの種が支配するかみたいなことってよく言われますよね。イカだっていう説をわりと聞くんだけど(笑)、その短歌のなかではイソギンチャクにしていて。人類は種としては滅亡してるんだけど、指環をイソギンチャクがたまたま食べて、愛という概念を無意識に引き継ぐみたいなイメージですね。でもそこには人間はいないから、ユートピアとディストピアの両方みたいな。
この連作には、人間は自分たちがつくったイデオロギーや兵器とともに滅びて終わり、みたいなイメージもちょっとあります。自分が人間だからということを除くと、別に人間がいなくなってもイカやイソギンチャクがいるからいいじゃん、みたいなことも言えなくはないというか。
──全体を通して見ると、穂村さんの歌集ではこれまで「青春」や「恋愛」が大きなモチーフになっていることが多かったように思うのですが、今回はそういった匂いは非常に薄いですよね。それらのモチーフは、今回は意図的に封印したのでしょうか。
穂村:つくりとしてはそういう感じですよね。ひとつの短歌をつくる上では意図のようなものってほとんど通用しない……、つまりコントロールが難しいので、編集するときになってそういうものは意図的に排除しましたね。子どものときのユートピア感と現在のディストピア感の対比でつくろうと思ってたので、キラキラした青春みたいなものは邪魔かなと思って。
実はひとつ前に出した歌集、『手紙魔まみ』の時点で、青春みたいな感覚は自分のなかにあまりなかったと思うんですよね。だからあのときは、自分よりも若い、性別の違う女性のキラキラした感覚を輸血するというか憑依するような感覚で、一種のコラボレーションみたいにして作っていましたね。
短歌をつくるときに外している“社会的なフィルター”

──今回の歌集以外のことも少しお伺いしたいのですが、穂村さんは書評やエッセイ、絵本など、短歌以外にもさまざまな創作活動をされていらっしゃいますよね。頭の切り替えが非常に大変なのではとも思うのですが、そういった多種多様な活動をされるモチベーションってどんなところにあるのでしょうか。
穂村:散文でも韻文でも、自分のなかの作業としては、出力するときのジャンルの振り分けが違うだけという感覚なんですよね。だから、一番ズレるのは車の運転とかするとき。
大人になると、車の運転に象徴される、社会的に有益な情報をフィルタリングすることを身につけるじゃないですか。パッと見たときに、社会的に重要な情報とそうでない情報を見分けてキャッチするという能力が現実をサバイブするには必要だと思うんだけど、僕はその能力はもともと低くて、なかなかそのフィルターが構築できなかった。だから、そうでない別のフィルタリングを職業化したっていう感じですかね。
──一般的には、韻文よりも散文のほうがよりロジカルに書かれると思うのですが、そのふたつの切り替えも自然にできますか。
穂村:そうですね。本質的には非論理的だと思うけど、僕はもともとある種、理屈っぽい書き方をするほうだと思うので。でもその理屈は社会に通用するようなものじゃ全然なくて、会社員時代はまったく何が起きてるのかわからないみたいなことがよくあった。株主総会とか、本当にまったく何が起きてるのかわからなくて(笑)。それで当時の会長に「お前は何もわからないんだな!」って怒鳴られたことがあったけど、わかる人はわからない人のことがわからないから……。
でもたとえば、スポーツがまったくわからない人って一定数いるじゃないですか。そういうのは他人でも、すごく面白くて。知人に、野球を見ると「ピッチャーが攻めてるんだ」って言い張る人がいるんです。いやピッチャーは守ってるんだよって教えても、いや、どう見ても攻めてるじゃんって言う。でも言われてみると、たしかにあんなボールなんかを相手にぶつけようとしてるわけで、どう見てもピッチャーが攻めてるんですよ(笑)。バッターは棒1本で必死に身を守ろうとしてて。
──その感覚は少しわかります(笑)。
穂村:ですよね。スポーツというフィルタリングを取り払った目で見ると、ピッチャーが攻めているっていうのは、たしかにまったくそのとおりで。僕は「異化」ってよく言うんだけど、短歌をつくるときにはそのフィルターをわざと外すんですよね。
「それぞれの夜の終わりにセロファンを肛門に貼る少年少女」っていう短歌があるんだけど、これはぎょう虫検査のことを歌っていて。でも、「ぎょう虫検査」っていう社会的に意味のあるフィルタリングを外すと、世にも奇怪な儀式みたいになって、急に“異相”が見えてくる。僕はさっき話したように、そのフィルターが外すまでもなくもともと外れかかっているので(笑)、それをそのまま書くという意識ですね。
──穂村さんが昔書かれた、『呼吸する色の不思議を見ていたら「火よ」と貴方は教えてくれる』という短歌もそうですね。
穂村:あれもそうですね。ぎょう虫検査とか火とか言わずに、いちいちそれを辞書的な定義の次元に解体していたら生活できないんだけど、ある種の官能性みたいなものはそこに宿る。
たとえば、火をふたりで見つめているときに、“火”というフィルターを外して、原始人が初めてつくりだした火を見ているようなシーンであるほうが、より官能的なわけじゃないですか。花火とかでも、どちらかの火をどちらかに渡すみたいな行為のなかにある強いシンパシーとかね、そういうものをフィルターを外して見たいなと思うんです。もちろん、生活する上では社会的なフィルターも必要なんだけど。
──ここまでのお話をお聞きしていると、もうすでに穂村さんの次の歌集が待ち遠しい、と思ってしまいます。次回作の構想はすでにあるのでしょうか。
穂村:次の歌集まではそんなに長い時間を空けないでつくりたいなと思ってますね。イメージはもうなんとなくあって……なんか、かわいいやつ(笑)。“極東のアリス”とか、“パニックバンビ”みたいな感じのイメージです。
──予想がつかないですが、楽しみにしています。
<了>
初出:P+D MAGAZINE(2018/09/16)

