月刊 本の窓 スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 第14回 中山和美
リオデジャネイロ・パラリンピックにも出場した、車いす陸上の第一人者は、なぜこれほどまでに、人の心を惹きつけるのだろうか。

「車いすになったことに後悔はありません。どんなことにも後悔しないがモットーなので。車いすになったのは、しょうがないこと。まだ走ってる途中ですけれど、好きなことをやってきましたから!」と中山。その爽やかな笑顔と心根の逞しさは多くの人を魅了する。
中山和美(35歳)
(車いす陸上選手 アクセンチュア所属)
Photograph:Yoshihiro Koike
久しぶりに会った彼女の両腕は、一回りは大きくなっていた。日々の鍛錬の成果だろう。驚きながら、そう伝えると、彼女は笑顔をみせつつも、納得のいかない表情を隠さないまま「えー、本当ですか?」と応えた。
車いす陸上のパラリンピアン中山和美。私の自慢の友人の一人だ。改めて溯ってみると、出会って十年が経つ。パラリンピックを目指し、日本でトップを走り、世界のレースに挑んできた姿を陰ながら応援してきた。リオデジャネイロ・パラリンピックの大舞台では、彼女が走る姿を見て、涙がこぼれた。
彼女が所属するアクセンチュアで、私たちは短期間だが仕事仲間だった。彼女の初出勤日には、「すごい美人のアスリートが来る!」と社内がざわついた。そうして一緒に働いてみると、業務の飲み込みは早いし、黙々と働いて切り上げ、颯爽と車を運転してトレーニングに行く。同僚たちが彼女を見る目は、美人に対するそれではなく、イケメンを見つめる眼差しになった。
たしかに美人だが、とにかく“男前”でもある。今、三十五歳になった彼女は、パラ陸上チームのリーダー格だ。コーチとも、時に激論を交わし合うほど逞しい。頼りになる「姉御」のように、若い選手たちをもり立てる。これまでも自分で道を切り拓き、人生を輝かせてきたのだ。彼女に憧れて、車いすレースを始めた二十歳の女の子は、ため息まじりに「カッコいい……」と目をキラキラさせる。まるで少女漫画の世界だ。
スポーツ万能少女の夢は「スッチー」
実現するも脊髄梗塞で車いす生活に……

ポジティブに邁進する原動力は、「勝ちたい気持ち一心でやってきたから。でも、いろいろな人に支えられてきたおかげです」と中山。練習熱心は周囲が認めるほどだが、「ちゃんと息抜きもしてますよ。映画を観たり、買い物に行ったり、ダラダラ過ごしたり。みんなと同じように気分転換します」。
中山は、四つ上の兄と七つ上の姉を持つ末っ子。幼い頃からスポーツが好きで、何にでもチャレンジしたという。「小学校や中学校でも、いつもリレーの選手に選ばれてたんですよ」。高校生まではバスケットボールに夢中になったが、スキーもスノーボードもサーフィンもこなした。そんなスポーツ万能少女が憧れた職業は、当時スチュワーデスと呼ばれた客室乗務員。「スッチーになりたいって言って、早く働きたいから専門学校を出て、最初はホテルで勤務してました。それから転職でチャレンジしたら合格できた」。面白いこと、やると決めたことに挑戦する若者だった。
ただし、憧れの職業で空を飛んだのは一年ほど。「せっかく業務にも慣れたっていうのに、休みでハワイに遊びに行ったら大事件ですよ」と笑い飛ばす。中山は、そのハワイでのサーフィン中に突如、脊髄梗塞を発症したのだった。いわゆる脳梗塞の脊髄版で、脳梗塞と比べると遙かに発症例の少ない症例という。血栓で脊髄の血管が詰まり、周囲の神経が壊死した。二十四歳、両下肢麻痺になって車いす生活を余儀なくされた。
落ち込んだのは、最初の一か月ほど。「なんでだろう」「どうして私が」と苛んだが、支えてくれた母の「しょうがないじゃない」の一言で、後は切り替えた。それに、病室でじっとしていることが耐えられなかった。「早くもとの生活がしたいって思って、リハビリの病院に転院してからは、早かったと思います。三か月ぐらいかな。リハビリが嫌になることもなかった。私、運動神経いいから、案外なんでもすぐできちゃうんで」とまた笑うのだ。
中山も含めて、パラ陸上の選手たちは、実に明るい。競技を、今を楽しんでいるのが、まざまざと伝わってくる。それにどこか大らかな雰囲気もあるので取材もとても楽しい。きっと想像を超える苦しみを経験した選手もいるはずだが、一方でそうじゃない選手もいるのだという。「実際、面白い話も多いんですよ。子どもの頃、逆立ちしたら病院送りで(下肢不随に)なったとか」と笑いながら語る。そう言われてもすぐに笑えないのだが、当人や仲間は「逆立ちが原因だなんて恥ずかしい」とネタにしているほどだ。
「たぶん、そういうメンタルじゃないと、この競技はできないかもしれないです。みんな手がなくても、足がなくても、全然気にしてないんだと思います。そういうコじゃないと続けられないってのもあると思う」と語る。実にさまざまな人が活躍できる開かれた場所だから、私も好きなのかもしれない。
走る楽しみから日本記録樹立へ
T53とは? 世界で戦うために必要なこと
中山は、リハビリの一環で車いすレースに出会った。「最初は、ただ何かをやりたかった」と、さまざまなスポーツに取り組んだという。車いすバスケットボールも試したが、これまでの経験から、逆に違和感が拭えなかったのでやめた。まずは「楽しく走れれば」と車いすマラソンに取り組んだ。そのうちに、いろいろな人と出会い、トラック競技に転向。みるみると頭角を現し、今では百メートル、二百メートル、四百メートル、八百メートルで日本記録を持つ。
パラ陸上では公平に競い合うことができるよう、障害の種類や程度に応じてクラス分けがされている。中山のクラスは、T53。TはTrack(トラック)の頭文字で、競走種目と跳躍種目が含まれる。なお、FはField(フィールド)で投てき種目を意味する。最初の数字の5は障害の種類、次の3は障害の程度を表し、程度は数字が小さいほど障害が重い。例えば、T54の選手は腹筋が利くが、それより障害の重いT53は腹筋が利かない。「でも、中には53の選手でも54の選手より速いこともあります」と中山。そのため、この二クラスは八百メートルまでは別々だが、それ以上の距離では一緒に走ることになる。
中山がトラック競技にのめり込んだのは、結果が出せたからということも大きい。「やるからには何か達成したい」と日本記録を次々と樹立したのだ。今年ついに百メートルの記録は破られてしまったが、今は東京パラリンピックでの、メダル獲得に向けての調整と強化に必死だという。リオ大会では、四百メートル、八百メートル、千五百メートルに出場したが、いずれも予選敗退に終わった。「日本ではトップでも、海外に行くとビリ同然なんです。海外の選手は骨格からして違う。だから、技術をあげていかないと」
日本パラ陸上競技連盟の副理事長で陸上車いすのコーチを務める花岡伸和氏は言う。「実際にパラリンピックは、オリンピック以上に元々の体型や体格差で決まることは多いです。また、海外のトップ選手のほとんどは、先天性の障害を持っているから大きな身体でも、使わない部分は成長してないので“軽い”んですよ。でも、大人になって脊髄を損傷して車いすになると、使わない部分も成長していて全部重りになってしまう。だから、いかに今持っているものだけで技術を磨いていくかが大事になります」。中山が“技術”を強調するわけである。

車いすのトラック競技では、今のF1のように“マシン”による差はあまりない。アスリートの体力とパワー、そして技術がレースの勝敗を左右するという。中山が専門にする800mは、レース中のスピードのアップダウンも激しく、いつ仕掛けるかの駆け引きも見どころだ。
カギは身体改造と熟練のテクニック
師弟関係は「花ちゃん」「中やん」
幸いにも車いすレースの現役寿命は意外と長い。「個人差はありますが、ピークは三十代前半から五年ぐらいじゃないかと思います」と花岡コーチは言う。いわく、「体力のピークと技術の熟練度は成長カーブが同じじゃないですから。体力が落ちてきても、技術が後から追いついてくるところが、競技者としてのピークではないかなと思うんです」。
「今が技術的にも体力的にも、ちょうどバランスが取れたところだよね」と花岡コーチが中山に語りかけると、「いや、技術がもうちょっと欲しいですし、(冬の間に筋肉をつけたが)身体ももうちょっと大きくできる」と中山。そう言いつつも、この二週間で痩せてきてしまったという。だから、再会して大きくなったと印象を語っても表情が陰ったのだ。連盟の強化指定選手として、栄養指導も仰いできた。だが、そもそも女性は筋肉がつきにくく、落ちやすい特性がある。中山が「ちょっと不安です」とこぼすと、「まあ張りが取れると、見た目は細く見えるから。でも実際のパワーはそんなに変わらへん(ない)」と花岡コーチは励ました。
花岡コーチは、元パラリンピアン。二十年ほど現役で活躍したが、「世界でやれてたのは十年。アテネは行けたけど、北京に行けなかった」と振り返る。すると、中山がすかさず突っ込んだ。「何で行けなかったの?」。「もがき苦しんでしまった。運のめぐりも良くなかった」と同コーチは苦笑いした。
世の中には、いろいろな人間関係があるが、この師弟関係も実にユニークだ。まず、二人は言いたいことを言い合う。「花ちゃん」「中やん」と呼び合うほど親しく、中山も気になることがあれば何でもコーチに尋ねる。その一方で、納得のいかないことは譲らない。ある時は、酒席ながら議論がいわゆる“水掛け論”になったところ、本当に中山がコーチに“水を掛けた”のだという。そんな話も「花ちゃん」こと花岡コーチは、ニコニコしながら何でもないといった風に、「大事なことだから僕も引かない。でも、これでもだいぶ遠慮してるんですよ」。そうすると、「遠慮しなくていいです。言いたいことあったら、言ってください」と中山がまた返すのだった。
その後も、中山と花岡コーチは、選手たちが定期的に受けている心理テストやメンタルトレーニングの話、自身のレースの総括などを率直に「あれはどうなの?」「それは違うと思う」と、やはり活発に議論を戦わせていた。
「迷いを経ての今がある」と意志を貫く
東京パラリンピックで納得して終わりたい
東京パラリンピックに向けて、中山は今も日々試行錯誤をしている。「あと二年しかない。この二年もあっという間でした」と振り返る。車いすレースは、レーサーと呼ばれる特別仕様の車いすに乗ってタイムを競い合うが、中山は今年、関東選手権とその後のジャパンパラ陸上競技大会とで、別のレーサーに乗った。ジャパンパラではフレームの短いものに乗り、取り回しをよくすることを狙ったという。これに花岡コーチは「迷いが出てしまう」と反対したが、中山は「迷いを経ての現在がある」と聞かなかった。
フレームが短いと、左右に振りやすくなる。中山が挑む八百メートルでは、百メートル以降はオープンレーンになるため、位置取りが重要になってくるのだ。「集団で走っててスパートをかけられた時に、どうしても私は後れをとってしまうので、これで早く反応しようと思ったんです」。だがジャパンパラでは、期待したような手応えは得られなかったという。それでも「まだ十回もこれで走ってないので、もう少し走り込んでみようと思います」と中山は決断を語った。
ハンドリムを漕ぐために、手にはめるグローブも一新した。今使用しているのは、男子車いすの樋口政幸選手が使用しているグローブを、3Dプリンターでコピーしてリメイクしたもの。「実は前の自分のグローブで手首を痛めたんです。一年ぐらい前からこれを使ってるけど、最初は全然走れなくて。それが、今やっと前と同じような感覚で走れるようになったんですよ」
自分の走りも、映像で繰り返し復習するという。「でもなかなか理想の走りにたどり着けない」と嘆く。花岡コーチに中山の一番の強みを尋ねると、「真面目さ。繊細すぎるところもあるのですが」と返ってきた。中山はそれも、わかっている。「でも迷った結果、これで行くっていうのを一つずつクリアしないと気が済まない。誰かに言われた通り、素直にハイって言える性格ならラクだったのかもしれないですけども」と語るのだ。
ジャパンパラ大会では、四百メートルのスタート直前、彼女は何度も大きく深呼吸をしていた。「ヒー、フー、ハー」。か細い声が聞こえてくる。私は思わず息を飲んだ。彼女は言っていた。四百メートルは車いすレースで最も苦しいけれど、途中で息が乱れたら勝てないのだと。終始セパレートレーンで走る、いわば“自分との闘い”だと。中山は結局、スタートからゴールまでトップを走りきった。タイムは納得の行くものではなかった。だが大舞台を目指し、伸びしろも気持ちもある。二〇二〇年、私はきっとまた泣いてしまうだろう。
※本連載は、今回で最終回となります。
ご愛読ありがとうございました。
プロフィール

中山和美
なかやま・かずみ
車いす陸上選手。1983年生まれ、身長160cm、体重46kg。千葉県松戸市出身。子どもの頃からリレー選手やバスケットボール部のキャプテンなどを務めたスポーツ万能女子。24歳の時、サーフィンをしていて脊髄梗塞を発症し、両下肢麻痺に。リハビリ中に車いす陸上に出会い、車いすマラソンに挑戦。27歳からトラック競技をメインに本格的にレースへ参戦すると、100m、200m、400m、800mで日本記録を樹立。2014年のアジアパラリンピックでは、200mと400mで銀メダルを獲得。2016年のリオ・パラリンピックでは、400m、800m、1500mに出場した。
松山ようこ/取材・文
まつやま・ようこ
1974年生まれ、兵庫県出身。翻訳者・ライター。スポーツやエンターテインメントの分野でWebコンテンツや字幕制作をはじめ、関連ニュース、書籍、企業資料などを翻訳。2012年からスポーツ専門局J SPORTSでライターとして活動。その他、MLB専門誌『Slugger』、KADOKAWAの本のニュースサイト『ダ・ヴィンチニュース』、フジテレビ運営オンデマンド『ホウドウキョク』などで企画・寄稿。
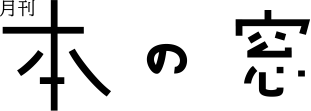
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。ページの小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激します。
スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 連載記事一覧はこちらから
初出:P+D MAGAZINE(2018/08/22)






