認知症介護から、妊娠中絶まで。昭和の女性作家が描いた壮絶な“社会”

昭和の中期、「才女時代」と称された、社会派の女性作家が多く活躍した時代がありました。今回は、昭和を代表する3名の社会派女性作家について、その代表的な作品とともに紹介します。
社会派の作家──と聞くと、松本清張や城山三郎といった男性作家をイメージされる読者の方も多いかもしれません。しかし昭和の中期には、「才女時代」と称された、社会派の女性作家が多く登場し活躍した時代がありました。
「女性だからジェンダーの問題を描く」「女性だから親子の問題を描く」といった紋切り型の価値観ではなく、彼女たちはその鋭い目で、医学界の腐敗や介護問題、人工妊娠中絶といった社会課題に真正面からメスを入れました。
今回は、そんな“社会派”を代表する3名の女性作家について、代表的な作品を解説しつつご紹介します。
医学界を描いた、社会派小説の金字塔──山崎豊子『白い巨塔』
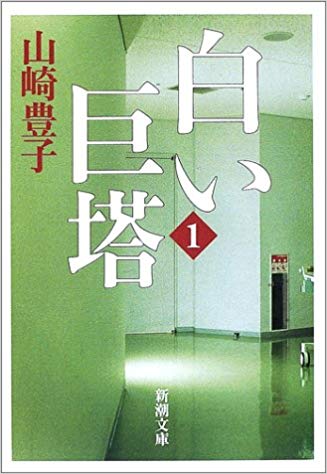
出典:http://amzn.asia/d/016Lbwi
社会派の女性作家──と聞けば、まず最初に山崎豊子の名前を思い出す方も多いのではないでしょうか。
山崎は旧制京都女子専門学校(現在の京都女子大学)を卒業後、新聞記者としてそのキャリアをスタートし、1958年、吉本興業を創業した吉本せいをモデルにした『花のれん』で第39回直木賞を受賞したことをきっかけに専業作家となりました。
初期の作品は自身の生まれ育った大阪を舞台にした小説が多かったものの、次第にその舞台を広げ、作家人生をかけて、戦争や社会の腐敗といった普遍的なテーマを描くようになります。
中でも、山崎の中で大きな転機ともなったと言える代表作が『白い巨塔』。さまざまな陰謀の渦巻く大学病院を舞台に、医学界の腐敗を鋭い目で追及した長編小説です。1966年には田宮二郎主演で映画化、2003年には唐沢寿明主演でテレビドラマ化されるなど、時代を超えて愛され続ける作品で、2019年には5夜連続で新たにテレビドラマが放映されることが決定しています(主演はV6の岡田准一)。
『白い巨塔』では、権力を得ようと奮闘する有名外科医・財前五郎と、患者のことを第一に考える誠実な内科医・里見脩二という対象的な二人を通し、医学界のいびつさや権力を望む人間の狡猾さがリアルに描かれます。
権力者には徹底的に媚び、そうでないものには横柄に接する悪辣な財前の姿は「悪役」としては異例なほど大きな反響を呼び、1967年には読者からの熱心な声を受けて、『続・白い巨塔』が発表されたほど。
また、この作品を契機として、東京大学を中心とした研修医の待遇改善運動(通称、東大紛争)が勃発したことも知られています。山崎は『白い巨塔』及びその続編について、のちに
小説的生命を全うしようとすれば、既に完結した小説の続編は書くべきではなく、作家としての社会的責任を考えれば、小説の成果の危険をおかしてでも書くべきであると考えた。この選択の難しさは、作家になってはじめて経験した苦悩であったが、最後は小説的生命より、社会的責任を先行させ、続編に取り組んだ
『大阪づくし私の産声─山崎豊子自作を語る2』より
と語っています。
認知症の介護をめぐる苦悩と葛藤──有吉佐和子『恍惚の人』
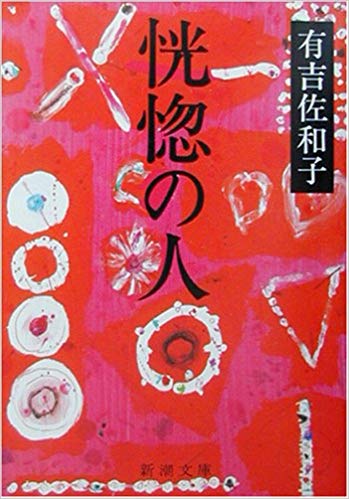
出典:http://amzn.asia/d/3jkazeD
有吉佐和子は1956年、25歳で『地唄』が文學界新人賞候補、ついで芥川賞候補となり、文壇デビューを果たした女性作家です。大学在学中は演劇評論家を志望し、最初期には『断弦』など古典芸能・伝統芸能を題材にした作品に取り組みました。
作品を発表するごとにそのテーマは“社会派”的な色を濃くしてゆき、1966年に発表した『華岡青洲の妻』では嫁姑問題、1974年の『複合汚染』では環境問題を描いて注目を集めました。
そんな有吉作品の中でも特に世間から多大な関心を集め、社会現象を呼ぶきっかけにもなった長編小説が『恍惚の人』(1972年)です。認知症の義父を介護する主人公・明子の視点で人間の“老い”を見つめた本作は、190万部以上を売り上げる大ベストセラーとなりました。
『恍惚の人』で有吉は、当時はまだ「痴呆」という名称が一般的だった認知症の症状やその介護の難しさを、丁寧に描きました。本作の中で、かつて明子を意地悪くいびっていた義父・茂造は、認知症が進行するにつれて穏やかな“恍惚の人”となっていきます。
彼はよく笑うようになった。口は開けず声も出さず、眼許だけで微笑するのだが、こんな表情は明子の知る限りの茂造にはないものであった。(中略)
神になった茂造は天衣無縫で、便所などという汚れた所へ行かなくなった代り、排泄は時と所を選ばない。おむつは常時当てておかなければならなくなった。
若い頃、働きながら一人息子の世話をする明子を見て「職業婦人」(※)と古い言葉で嫌味を言い続けていた茂造は、認知症が進むと一転、食事や排泄の世話まで明子に頼りきりになります。実の父のそんな様子を目にした明子の夫の信利は、茂造が自分の未来の姿であるように思え、介護の一切を放棄して明子に任せてしまいます。
『恍惚の人』の発表を契機として、介護問題に対する世間の関心は一気に高まりました。老年学の学者である森幹郎は、本作の解説の中で、『恍惚の人』が老人福祉の推進にもたらした影響をこのように語っています。
人々の心の中には、親の介護ぐらい子供がするのはあたりまえではないかという考え方が強かった(中略)。こうした社会規範の中で、介護の社会システム化への途は非常にけわしかった。
本書が出たのは、そんなときである。本書の爆発的な売れ行きの中で、老人福祉の推進に対する世論は高まり、関係者の合意はとにもかくにも得られたと言ってよい。
本作は間違いなく福祉の未来に新しい道を切り拓きましたが、それでもなお、作中で描かれた共働きの家庭における介護や高齢者の医療費負担といった社会課題は、深刻化の一途を辿っています。そんな今の時代だからこそ、『恍惚の人』は改めて広く読み返されるべき意義のある作品だと言えるでしょう。
(※……社会に出て職に就いている女性がまだ少なかった時代に、職に就いている女性をいった語)
「中絶」をめぐる命の尊厳──曽野綾子『神の汚れた手』
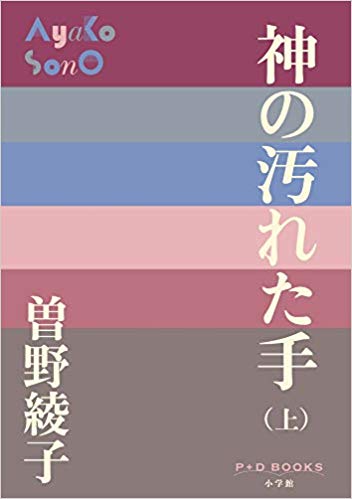
出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352353
曽野綾子は、『遠来の客たち』(1954年)や『木枯しの庭』(1976年)といった代表作品を持ち、87歳を迎えた今もなお現役で作品を発表し続けている女性作家です。中でも、中絶手術という題材を通して“人間の尊厳”について問いかけた『神の汚れた手』(1979~1980年、朝日新聞掲載)は、発表当時、文壇のみならず世間にも大きな衝撃を与えました。
『神の汚れた手』の舞台は、三浦半島の小さな産婦人科医院です。主人公で産婦人科医の野辺地貞春は、医師として出産に立ち会い続ける一方、中絶手術も請け負う人物。貞春のもとには、新しい命の誕生を待ちわびる患者から、望まない妊娠をして堕胎を希望する患者まで、さまざまな女性が次々と訪れます。
曽野綾子自身は熱心なカトリック教徒ですが、作中では“中絶”という行為が一方的に非とは決めつけられず、終始フラットに描かれています。貞春は、自身が中絶という行為をどのように捉えているかについて、友人の筧とその知人である神父の宗近に、こんな風に語ります。
「筧さんはいつか、僕がアウス(中絶)の手術をよく平気でするって非難めいたことを言われたけど、僕には全く、生命を絶っているっていう実感はないね」(中略)
「どうしてかしらね」
「どうしてって言われても困るけど、なぜか、ない。もちろん、二、三カ月までの話だけど。なぜ、我々にそういう感じを与えないようになっているか、神さまという存在があるんなら聞いてみたいね」
「本当になぜかしらね。あなたは決して鈍感な人じゃないのにね。手術中は何を考えてるの?」
「どんなに、うまく鮮かにやってのけられるか、っていうことだけ」
淡々と手術をこなしながらも時折自分の仕事の是非について自問自答し、葛藤を覗かせる貞春という人物を通して、読者は“命の尊厳”について考えさせられることになります。曽野自身は、この作品のあとがきで
私はカトリックの学校に幼稚園から大学まで学び、幼い時から、生と共に死に馴れしたしむことを教わった。(中略)この作品の中に、科学的な苛酷な状況が少しも手加減なく書かれているとすれば、それは私が小さい時から抱いた、誰にも一つずつ平等に与えられている死についてのみは、労る必要はない、むしろ私たちは誰もが頭を垂れてその運命を正視しなければ、我々はこの短い生涯を本当に生きたことにならない、という根本的な発想から生まれているというほかはない。
と述べています。彼女はその静かな筆致を通して、すべての生死は例外なく尊厳を持って扱われるべきであるというメッセージを私たちに投げかけます。
おわりに
社会問題をリアルに描いた小説は、その課題と向き合うことを、読み手にも否応なく要求します。今回ご紹介した作品も、腰を据えないとなかなか読み進められない、重厚かつシリアスなものが多いかもしれません。
しかし同時に、これらの作品は、普段は目をそむけている社会のいびつさに真正面から憤り、問題提起をする勇気を私たちに与えてくれます。3名の勇気ある女性作家の作品をきっかけに、“社会派小説”の扉を開いてみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2019/01/03)

