「石牟礼道子の宇宙」6選

代表作『苦海浄土』が日本文学史上に残る名作のひとつと言われ、『池澤夏樹=個人編集 世界文学全集』(河出書房新社)にも、唯一の日本文学として収録された、石牟礼道子。人間以外の様々な生類の視点にも立ち、美しい言葉で土地の人々や自然を描く彼女の作品には、日本文学から世界文学へと宇宙のように広がる、驚くほど豊穣な世界が。パーキンソン病を患い2018年2月に亡くなるまでに描かれた中から、お薦めの6作品を紹介します。
はじめに
熊本の天草で生まれ、水俣で育った石牟礼道子は、主婦を経て文筆活動を始め、90年に渡って地元の水俣病と向き合いながら、人間と自然が溶け合うような、どこか懐かしい世界を生み出し続けてきました。様々な問題を告発するだけにとどまらない彼女の作品は、現代を生きる私たちが抱える様々な問題についても、考えるきっかけをきっと与えてくれます。
戦後文学の傑作/『苦海浄土 わが水俣病』
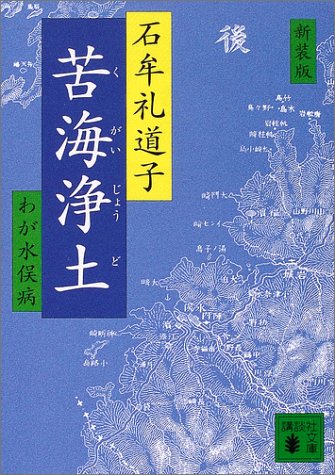
https://www.amazon.co.jp/dp/4062748150/
この日はことにわたくしは自分が人間であることの嫌悪感に、耐えがたかった。釜鶴松のかなしげな山羊のような、魚のような瞳と流木じみた姿態と、決して往生できない魂は、この日から全部わたくしの中に移り住んだ。
自分の体に二本の足がちゃんとついて、その二本の足でちゃんと体を支えてふんばって立って、自分の体に二本の腕のついとって、その自分の腕で櫓を漕いで、あをさをとりに行こうごたるばい。うちゃ泣こうごたる。もういっぺん 行こうごたる、海に。
水俣病を描いたこの『苦海浄土』は、戦後日本文学における最高傑作のひとつとして知られています。チッソによって流された工場廃水で起きたとされる水俣病は、その土地に住む人々の生活や命、風土を破壊しました。作者はこの作品で、そのような破壊されたものたちの声を聞き、自らが彼らの代わりとなって言葉を記しました。水俣病患者たちの声なき声を聞き、方言を織りなすようにして、彼らの以前の豊かな生活が描写されます。動くことができなくなった女性が思い出す海での幸せな日々、木の棒で野球の真似をし続ける少年など、病の中に映る夢のような情景が、この作品をより魅力的なものにしています。
公害告発の書という枠に止まらない、人間の尊厳の物語が、この作品にはあります。
また、単なるルポルタージュではないこの作品の力強さは、石牟礼道子という人間が受難の物語として、彼らの苦しみを自らの苦しみのように描いたことにあるのです。他者の苦しみを自分のことのように感じること。それによって、近代とそれ以前という対立だけではない複雑な世界のあり方が浮かび上がってきます。現在の我々が読むと、福島第一原子力発電所の事故など、様々なことを想起させます。文明や化学とどのように付き合っていけば良いのか。自然とはそもそも誰のものなのか。様々なことを考えさせてくれる作品です。
失われた故郷の記憶/『椿の海の記』

https://www.amazon.co.jp/dp/4309412130/
春の花々があらかた散り敷いてしまうと、大地の深い匂いがむせてくる。海の香りとそれはせめぎあい、不知火海は朝あけの靄が立つ。朝陽が、そのような靄をこうこうと染あげながらのぼり出すと、光の奥からやさしい海があらわれる。
この作品には、幼少期の石牟礼道子、「みっちん」が見た様々な風景が記されています。盲目のおもかさま(祖母)や父など多様な人々と共に、意識を世界に張り巡らして、みっちんは自然を感受し自らと語っていきます。自然と共に生きること、神様の存在など、現代日本が失ってしまった世界がそこに立ち現れます。印象的なのは、彼女が五感で感じている自然と、彼女自身が溶け合っていくような描写です。自分は何の生まれ変わりなのだろうと問うたり、疎外された人々のことを思ったり、様々なことを内省する彼女の心にはいつも自然が映し出されています。自分は人間という以上に生類の一部なのだという視点は現代の私たちが改めて取り戻さなければいけないのかもしれません。ゆっくりと、時には声に出して読んでみることでこの作品の奥深さをさらに知ることができるでしょう。言葉では完全には表せない世界がそこには広がっています。
だまって存在しあっていることにくらべれば、言葉というものは、なんと不完全で、不自由な約束ごとだったろう。
神さまになりかけている人々の物語/『あやとりの記』

https://www.amazon.co.jp/dp/4834024156/
犬の仔せっちゃんになるとか、ヒロム兄やんやぽんぽんしゃら殿になるとか、それから、めくらのおもかさまのようになるとか。そういう人間たちにぜんぶなってしまわなければ、とてものことに迫んたぁまになれるとは考えられません。
ごーいたごいた/ごーいたごいた/今日の雪の日/鋸曳く者はよ/なんの首曳く/親の首曳く/ごーいたごいた/ごーいたごいた
この作品も、みっちんとおもかさまが登場する石牟礼道子の自伝的な作品です。世界から外れてしまっているような人たちに出会いながら、みっちんは土地の精霊たちと交流していきます。決してわかりやすいあらすじがあるわけではなく、それぞれの章が独立した物語のように読むことができます。犬の仔せっちゃんやヒロム兄やん、仙造さんなど、「神さまになりかけている人々」を通して、みっちんは「あの衆」と言われる神様たちの気配を感じていきます。片目であったり片足であったり、登場する人物は皆どこかこの世の外の世界にいるような人々です。そのような人々と同じように、みっちんもまたどこか世界の外を彷徨っている精霊となるのです。疎外された人こそあの衆と言われる神さまと話すことができるのかもしれないと読者に思わせる、どこか懐かしいような不思議な世界がこの作品には広がっています。
原初からのメッセージ/『水はみどろの宮』

https://www.amazon.co.jp/dp/4834082512/
千年狐のごんの守といっしょに、穿の宮の湖の底へおこもりをしてから、お葉には山の声が聞こえるようになった。爺さまを手伝って舟をあやつっていたとき、ちょっと咳ばらいをするような、山のしゃがれた声がしていた。
水はみどろの/その奥に/まことの花の/咲けるかな/いざ一息に/身をば投げえーい/六根清浄/ええーいっ
この作品は、千本松爺と共に暮らす7歳のお葉が犬のらんに連れられて山に彷徨い、千年狐のごんの守や黒猫のおノンといった精なるものたちと出会っていく物語です。山の中の泉に千年狐とおこもりしてから、お葉には山の声が聞こえるようになり、鐘の中から“巨きな鯰”が出てきたり、最後には地震が起きたりと、まるで神話のような世界の中で動物や風景と心を通わせる敏感な少女の姿が描かれています。時間の流れが曖昧で、何が起こっているのかさえも不確実なこの世とあの世の合間の世界がそこには広がっています。亡き母を思う心や、自然や風土に対する感度の高さをお葉の目線で感じながら、読者もその世界の中に彷徨うことができるでしょう。また、他の作品に比べて比較的優しく読みやすい文章でありながら、美しい詩で溢れています。子供向けに作られた話ではありますが、大人が読んでも十分楽しめるものとなっています。
民衆の記憶の物語/『西南役伝説』

https://www.amazon.co.jp/dp/4062903717/
「わし共、西郷戦争ちゅうぞ。十年戦争ともな。一の谷の熊谷さんと敦盛さんの戦は昔話にきいとったが、実地に見たのは西郷戦争が初めてじゃったげな。それからちゅうもんひっつけひっつけ戦があって、日清・日露・満州事変から、今度の戦争–。西郷戦争は思えば世の中展くる始めになったなあ。わしゃ、西郷戦争の年、親達が逃げとった山の穴の中で生れたげなばい。」
西郷隆盛が新政府に対して挙兵したとされる西南戦争を扱ったこの物語は、時代に翻弄されながらも生き抜いた農民や漁民たちの語りで構成されています。直接的ではなく間接的に戦いを経験した人々の暮らしが、聞き書きという形を持って豊かに描かれ、このようなフィクションとノンフィクションの間の物語の形は、『苦海浄土』に通ずるところがあると言えるでしょう。
切支丹の乱と弘化一揆をつなぐ赤い糸が見えてくる気がする。長岡、永田らいやいや夥しい者たちの血の色において。水俣被害民らの魂を通して。このような魂たちの依り代は異教や一握りの土地や海であった。その寄るべを失う者たちを放棄したまま近代は始まるのである。
特徴的なのは、歴史的な資料と民衆の語りという対極にあるような文章が併存していることで、より語りが強く浮かび上がってくることです。明治維新の際に全てを新しくしていった中で取り残された人々。命を繋ぎ止めてきた人々。教科書で書かれる歴史の裏に隠された、生活を巡る記憶の物語です。
信仰と生活が交差する『春の城』
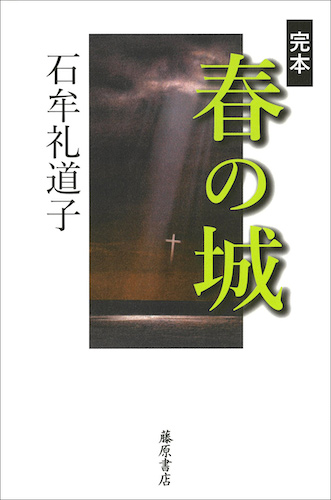
https://www.amazon.co.jp/dp/4865781285/
「天国はこの世のものではありませぬ。天国に生れ替るは神の計らい。それをおのれの計らいのごとく口にすることはできませぬ。わたくしの思うておりますのは、この世の境界を超えたところに、いまひとつのこの世が在るということでござります。」
天草四郎時貞を総大将としてキリシタンの人々が幕府と戦ったとされる、天草・島原の乱を描いたこの作品は、十数年をかけた取材を基に生まれた壮大な大河小説です。多様な人物が登場しながら一つの戦いへと向かう姿を描いたこの力作は、読むものをその場に立ち会っているかのような感覚にさせてくれます。また、この作品はただ戦いを描いたものではなく、婚姻の儀式に始まり、食事の場面など、戦いの記録の中にある民衆の生活や信仰を描いています。
顔を見たことのない殿さまや、代官所の役人たちがどのくらいの人間だか知らぬが、わが身を使って働いたことのない者が、百姓の丹精しあげた作物を、紙切れ一枚で取り上げようなどとは、とんでもない心得ちがいだ、
ここで見えてくるのは、島原の乱は食えないがために立ち上がったもの、言わば、キリスト教徒と権力者の戦いというよりも、民衆と権力者の戦いなのだということです。そのような立ち行かない生活と信仰が矛盾しながら交差して、民衆は天草四郎を筆頭に戦います。必ず死ぬと分かっていながらも戦う民衆は、石牟礼の言う“もうひとつのこの世”を目指しているかのようです。権力に翻弄されながらも、自らの魂の為に戦った人々の歴史を是非その目で確かめてみてください。
おわりに
石牟礼道子の作品は、物語の才能に溢れながら、文学という枠だけでは語れない魅力を持っています。多様に読み取れるその言葉は、現代を生きる私たちにとって非常に重要な意味を持ちます。災害や自然との向き合い方、命の問題、利便性を求める世の中など、様々な事柄を読むものに問うことになります。彼女は他にも詩歌やエッセイなど様々な文芸作品を書いていて、ここで紹介したのは彼女の作品宇宙の本の一端に過ぎませんが、まずはその豊穣な世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2019/07/17)

