【「クリスマス・キャロル」ほか】チャールズ・ディケンズのおすすめ作品

『クリスマス・キャロル』や『デイヴィッド・コパフィールド』といった数多くの代表作を持つイギリスの国民的作家、チャールズ・ディケンズ。これからディケンズを読んでみたいという方のために、おすすめの作品を4作品ご紹介します。
貧しくも善良な人々の姿を起伏に富んだストーリーとともに描いたイギリスの国民的作家、チャールズ・ディケンズ。2020年は、ディケンズの没後150年にあたります。
映像化も数多くされた『クリスマス・キャロル』や『デイヴィッド・コパフィールド』を始め、さまざまな代表作を持つディケンズ。今回はそんなディケンズを初めて読む方に向けて、おすすめの作品を4作品ご紹介します。
『クリスマス・キャロル』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4102030093/
『クリスマス・キャロル』は、ディケンズが1843年に発表した中編小説です。世界でもっとも有名なクリスマスのお話と言っても過言ではない本作は、イギリスのみならず全世界で愛読され続けている名作です。
物語の主人公は、強欲な守銭奴として人々から嫌われている老人・スクルージ。その性格は、どんなにどしゃ降りの雨でさえも彼ほどに頑固ではない、と描写されるほどに冷徹でした。
外部の暑さも寒さもスクルージには何の影響も及ぼさなかった。どんな暖かさも彼をあたためることはできず、どんなに寒い冬の日も彼をこごえさせることはできなかった。どんなに吹きすさぶ風も彼ほどにきびしくはなく、どんなに降りつのる雪も彼ほど一徹ではなく、どんなにどしゃ降りの雨も彼ほど頑固にいっさいをはじき返すことはしなかった。
そんなスクルージはあるクリスマスイブの晩、かつて仕事上の相棒だったマーレイの亡霊と対面します。マーレイはスクルージに“お前さんのところへ3人の幽霊が来ることになっている”と予言を告げ、消えてしまいます。その次の日から、スクルージの家には予言通り3人の幽霊がひとりずつ現れて、スクルージは幽霊とともに過去のクリスマス・現在のクリスマス・未来のクリスマスを旅するのです。
冷徹だったスクルージの心は、自分自身がまだ純粋だった過去の記憶や快活にクリスマスを楽しむ人々の姿を見せられることによって、すこしずつやさしさやあたたかさを取り戻していきます。スクルージはやがて、“行く手に横たわる「時」が自分のものであり、埋合わせをつけられる”ことに気づき、心を入れ替えた彼のことを街中の人々が慕うようになります。人間らしい心を取り戻したスクルージが、「クリスマスおめでとう!」と街の人々に声をかけるシーンは非常に感動的です。
あたたかなヒューマニズムに満ちた本作は、本国・イギリスでも、クリスマスの晩には決まって大人が子どもに読み聞かせをする伝統的な作品となっています。ディケンズも自身を世界的な小説家にしたこの作品を愛しており、クリスマスシーズンには好んで公開朗読をおこなっていました。
『オリヴァー・ツイスト』
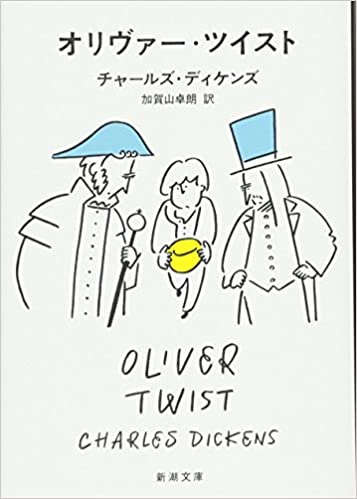
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4102030077/
『オリヴァー・ツイスト』は、ディケンズ初期の代表的な長編小説です。主人公の孤児・オリヴァーがさまざまな辛苦を経験し、何度も悪に染められそうになりながらも、ひとりの立派な青年として成長していくまでの姿を描いています。
イギリスの片田舎で生まれ、劣悪な環境の救貧院で育ったオリヴァー。彼はある日、飢えの限界に達した仲間の孤児たちとの間でおこなわれたくじ引きの結果、給仕係にお粥のお代わりを要求する役目を担うことになってしまいます。
子供ながらに空腹のため絶望し、みじめで捨て鉢な気分になっていたオリヴァーは、机から立ち上がり、ボウルとスプーンを手に給仕係のところまで歩いていくと、自分の無謀さにいささか驚きつつ言った──。
「お願いします、お代わりをください」
給仕係は太った健康な男だったが、とたんに真っ青になった。びっくり仰天して、小さな反逆者を数秒見つめたあと、よろめいて竃の縁に手をかけた。(中略)
「お願いします」オリヴァーはくり返した。「お代わりをください」
給仕係はオリヴァーの頭に杓子の一撃を加えると、羽交い締めにし、上ずった大声で教区吏を呼んだ。(中略)
「ミスター、リムキンズ、たいへん申しわけございません。オリヴァー・ツイストがお代わりを要求しました!」
このシーンは、本作の中でももっとも有名な場面のひとつです。ただお粥のお代わりを要求したというだけでオリヴァーは異端者扱いされ、役人たちから虐待同然の扱いを受け、しまいには町の葬儀屋に売られることとなってしまいます。オリヴァーはその後、過酷な環境に耐えきれずに夜逃げをし、放浪していたロンドンで窃盗団の一味に取り込まれるなど憂き目に遭い続けますが、彼はどのようなときでも善良な心を忘れず、すこしずつ成長していきます。
ディケンズの出世作でもある本作ですが、『クリスマス・キャロル』や『デイヴィッド・コパフィールド』といった彼の他の作品と比べると、ストーリーがご都合主義的である、キャラクターが戯画的すぎる──といった難点も見られます。しかし、推理作家として有名なイギリスの小説家、G・K・チェスタトンは本作の解説の中で、ディケンズが初めて恐ろしいものや超自然的なものに筆力を示した点、そして当時のイギリス社会に蔓延していた社会的抑圧をはっきりと批判している点は素晴らしいと評しています。
『デイヴィッド・コパフィールド』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4003222814/
『デイヴィッド・コパフィールド』は、ディケンズが1849年から1850年にかけて雑誌で発表した長編小説です。主人公であるデイヴィッドは母親の再婚をきっかけに、継父とその姉から虐待されるなどさまざまな困難を経験しますが、逆境を乗り越えて成長していき、やがて作家として身を立てるようになります。
勧善懲悪が貫かれるストーリーのわかりやすさ、皮肉交じりのユーモアの面白さももちろんですが、本作の最大の魅力は登場人物たちの個性豊かさです。たとえば幼少期のデイヴィッドが通う学校、セーラム学園では、学生たちは支配的で冷酷な校長のもとで怯える日々を過ごしていますが、デイヴィッドとともにそこに通う年上の利発な少年・スティアフォースと、いつも貧乏くじを引かされる役目ながら明るく正義感の強い同級生・トラドルズとの出会いが、デイヴィッドの運命を変えていきます。
ほかにも、弁護士事務所の書記を務め、一見とても腰の低い人物でありながら実は大悪人のユライア・ヒープや、美しいけれど世間知らずですぐに拗ねてしまうデイヴィッドの妻・ドーラなど、本作には一度読んだら忘れられないような魅力的な人物が多数登場します。
デイヴィッドが貧しい家の育ちであることや法律事務所で働くことなどはディケンズ自身が実際に経験したことでもあり、作者の自伝的要素も多いとされる本作。ディケンズは、自身でも本作を“全著作の中で一番気に入っている”と綴っています。
本書が、小生の全著作の中で一番気に入っています。小生は、自分の想像力が生んだどの子供たちにも甘い親であり、小生をおいてそういう家族のことを心から大切に思える人間は他にはいないということは、容易に納得していただけるのではないでしょうか。それでも子供に甘い多くの親の例に漏れず、小生にも心ひそかに可愛い子というものがあります。その子の名前はデイヴィッド・コパフィールドです。
──『デイヴィッド・コパフィールド(1)』より
本作は全5巻(岩波文庫版)の長大な物語ではありますが、終始波乱万丈で、読者を飽きさせないストーリーとなっています。ささやかなシーンがすべて伏線となり、最後の大団円につながっていくダイナミックかつ緻密な展開も読みどころです。
『二都物語』
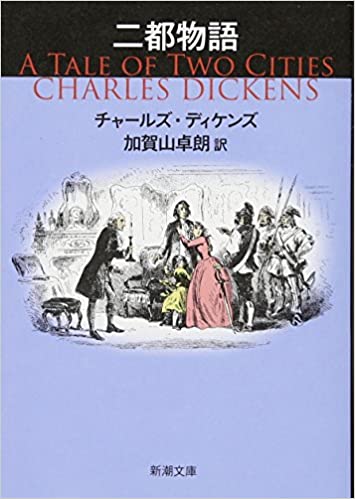
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/410203014X/
『二都物語』は、18世紀、フランス革命前後の時代のフランス・パリとイギリス・ロンドンというふたつの都市を舞台とする物語です。1859年に発表された本作は、ディケンズ後期の代表作のひとつとされています。ディケンズは、イギリスの歴史家であるトーマス・カーライルの『フランス革命史』に影響を受け、歴史小説として本作を記しました。
物語は、少女ルーシー・マネットの父であるアレクサンドル・マネット医師がフランスでの18年にわたる収監から解放され、イギリスに帰るシーンから始まります。その帰途で、マネット父娘はフランス人の亡命貴族・ダーニーと知り合います。
ダーニーは、仕事で英仏を行き来していたことを理由にスパイの嫌疑をかけられてしまいますが、ダーニーの弁護士はカートンという名のダーニーと容姿がよく似たイギリス人の青年を引き合いに出し、見事、無実を勝ち取ります。その裁判にマネット父娘が証人として召喚されたことをきっかけに、ダーニー、カートン、マネット父娘に交流が生まれます。そして、よく似たふたりの青年・ダーニーとカートンは、やがてともにルーシーに恋をしてしまうのです。
本作の主要なテーマは、フランス革命前後の、貴族と市民の階級間の壮絶な対立です。本作の中で、ダーニーは自分の身分を捨てイギリスで身を立てたにも関わらず、旧貴族階級であるという理由だけでフランス市民たちから虐げられ、“すべての貴族に死を”と憎悪を向けられます。ディケンズは常に弱者の側に立ち、貴族ではなく労働者階級に寄り添うような作品を終世書き続けましたが、本作ではダーニーのような特権階級の人物を追い詰める一市民の狂気やたくましさも同時に描いています。
フランス革命時の狂乱を描いた歴史小説としても読める一方で、ルーシーという愛らしい女性をめぐって男性たちが奮闘する、エンターテインメント性の高い恋愛小説としても楽しめる作品です。
おわりに
ディケンズの描く波乱万丈な物語とチャーミングなキャラクターは世界的に愛され続けてきましたが、20世紀初期の芸術至上主義的な文壇の空気の中では、“稚拙で楽天的”、“古臭い”と批判を受けることもありました。しかし現在は、人間への洞察力や明るい道徳観が再評価され、ふたたび世界的作家としての地位を取り戻しています。
翻訳家・児童文学作家の村岡花子は、ディケンズの作品をこのように評します。
彼は笑いの中に涙の露を光らせる。彼の作品を構成するものは涙と笑いである。光と影が交錯している。ディケンズの人物の持つ哀感(ペーソス)は時としては余りにも芝居がかって来ることもある。が、つまるところ、彼は役者であり、彼の演劇の終局の目的はヒューマニズムであったのだ。
──『クリスマス・カロル』解説より
ディケンズの終局の目的はヒューマニズムであった、という言葉には、頷かれる方も多いのではないでしょうか。常に、弱い立場に立たされながらも尊厳と愛を忘れない人々の姿を描いたディケンズ。人生の節目節目で作品を読み返し、そのあたたかさに触れたくなるような作家です。
初出:P+D MAGAZINE(2020/05/26)

