【SM・バラバラ殺人】傑作推理小説のモデルになった昭和の犯罪事件簿

あの傑作推理小説は実際の事件をモデルにしていた!?ドキドキハラハラが止まらない、昭和の犯罪事件とミステリー作品との関係を探ります。
都市空間の成立と探偵の誕生
デパートのショーウィンドウやカフェ、ダンスホールやレビュー、モダンなファッションに身を包んだ人々の雑踏…。1920年代から30年代にかけての東京では、21世紀の現在にまで続くきらびやかな都市文化が花開きます。
ただし、こうした表向きには光り輝いてみえる都市空間は、その裏面に〈性〉や〈犯罪〉といった闇の部分も抱え込んでいました。また、そこに行き交う人々も、表面上はふつうに見えていても、裏ではどんなことをしているのかわからない・・・・・・。このような都市に生きる人々のあいだに生まれた不安はまた、その裏面に隠された秘密を覗いてみたいという欲望をビリビリと刺激するものでもあったでしょう。
その欲望は、同時代に大ブームを巻き起こすことになる「推理小説」というフィクションスタイルの中で、探偵の姿に具現化されていきました。ここでは、都市文化の成立と密接な関係にあった推理小説・探偵小説を、モデルとなった実際の事件とともに紹介します。

江戸川乱歩『D坂の殺人事件』と小口末吉SM殺人事件
まず始めに、日本でもっとも有名な名探偵・明智小五郎の初登場作品である江戸川乱歩の『D坂の殺人事件』。作品の冒頭、語り手の「私」は次のように述べます。
それは九月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。私は、D坂の大通りの中ほどにある、白梅軒という、行きつけの喫茶店で、冷しコーヒーを啜っていた。当時私は、学校を出たばかりで、まだこれという職業もなく、下宿にゴロゴロして本でも読んでいるか、それに飽きると、当てどもなく散歩に出て、あまり費用のかからぬ喫茶店廻りをやるくらいが、毎日の日課だった。
この「私」のように、大学を卒業したにもかかわらず、定職にも就かずぶらぶらしている若者のことを、当時の言葉で「遊民」といいました。明智小五郎もまた「私」と同様の遊民であり、二人は時折このD坂(=団子坂)のカフェで顔を合わせる仲でした。
事件は、いつものようにカフェで犯罪談義をしていた二人が、大通りを隔てた向かいの古本屋の異変に気付き、店の奥に細君の絞殺死体を発見したことから発覚します。その状況を「私」は次のように述べています。
表の大通りには往来が絶えない。声高に話し合って、カラカラと日和下駄を引きずって行くのや、酒に酔って流行歌をどなって行くのや、しごく天下泰平なことだ。そして障子ひとえの家の中には、一人の女が惨殺されて横たわっている。なんという皮肉だろう。
ここには、障子一枚によって隔てられた〈表〉と〈裏〉の世界がまるで異なった姿をあらわすという、都市空間の構造が見事に言い表されています。
明智はそこから、「被虐色情者」(=マゾヒスト)であった古本屋の細君と、「ひどい惨虐色情者」(=サディスト)であった隣の蕎麦屋の主人とが、互いの「病的な欲望」を満たすために行った性的遊戯が行き過ぎたため起こった「合意の殺人」であったという、「人世の裏面」に潜む「陰惨な秘密」を暴き出していくのです。
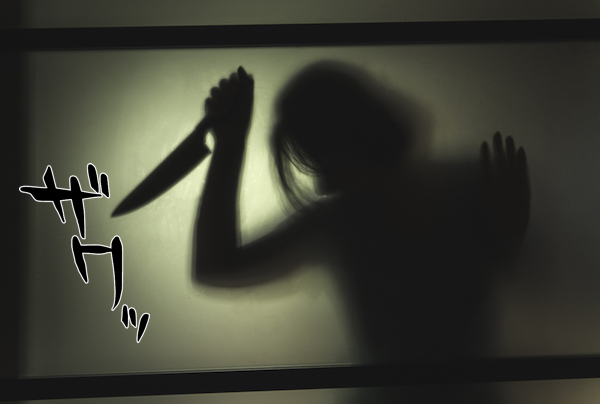
実はこの小説に描かれた事件は、実在の事件をモデルとしていると言われています。それは1917年、浅草裏にあった「しもた屋」で、小口末吉によってその内縁の妻である矢作よねが殺された事件です。
よねの死体には、全身に痛々しく化膿した切傷や火傷があり、手足の指が何本も切断され、背中や腕に「小口末吉」と焼け火箸で刻印されていました。警察はすぐに現場にいた内縁の夫である末吉を逮捕しますが、調べが進むうち、全身の傷や焼印などは、性的な快楽を得るために、嫌がる末吉によねが強要してつけさせたものであったことがわかります。よねは稀代のマゾヒストだったのです。
乱歩は、この実際のSM殺人事件に都市と探偵というモチーフを加え小説化するのですが、そこには、犯罪を暴き正義に資するだけではない、「いかがわしさ」をあわせ持つ存在として、探偵が描かれていたことも見逃せません。
そもそも、明智と「私」の探偵行為は、カフェからは見ることのできない古本屋の障子の奥を覗き見たいと思い立ち、そこに「侵入」することから始まっていました。物語の途中で、明智が「私」に犯人ではないかと疑われるのも、その「いかがわしさ」を示すエピソードであったといえます。
このように探偵とは、清廉潔白な「正義のヒーロー」であるように見えて、実は、一般には理解しえない欲望を抱え、それを実行に移してしまうという点で、「実行犯」ともパラレルな関係にあるような存在なのです。

探偵小説家と猟奇犯罪
1930年代に入ると、エロ・グロ・ナンセンスと呼ばれた時代相を象徴するような猟奇的な事件が頻発します。
そのなかでも、日本で最初に「バラバラ殺人」という呼称が使用されたことでも有名な、1932年に起きた玉の井バラバラ殺人事件は、とりわけセンセーショナルでした。東京の向島・玉の井にあった私娼窟のまわりを流れる、通称「おはぐろどぶ」と呼ばれた側溝の中から、切断された身許不明の男の胸部、腰部、頭部が発見されると、新聞紙面には「怪事件」「猟奇」「グロ」といった見出し語が踊り、「探偵小説的興味」をひきおこす事件として大々的に報道されます。
事件直前には乱歩が、殺人淫楽者の盲人による連続女性バラバラ殺人事件を描いた『盲獣』(1931‐1932)を連載していたという奇妙な一致もあり、人々は探偵小説を読むように現実の事件の「謎解き」に狂奔していくことになるのです。

さらに当時の新聞には、江戸川乱歩のほか、浜尾四郎、甲賀三郎、正木不如丘、森下雨村、牧逸馬といった売れっ子の探偵小説家たちがたびたび登場し、この玉の井バラバラ殺人事件に対する「推理」が行われていました。
現在のテレビのワイドショーでのコメンテーターの先駆けともいえそうですが、このように当時の探偵小説家は、読者の代表として、まさにフィクションさながらの「探偵」役として駆り出されてもいたのです。
しかしその一方で、同時期には、探偵小説を読んだことから起こしたとされる犯罪事件がしばしば報道され、その犯罪誘発性が真剣に議論されてもいました。玉の井バラバラ殺人事件の場合も例外ではなく、探偵小説の影響が盛んに議論され、「犯人は江戸川乱歩である」という投書が、警視庁に送られてきたことが報じられてもいたほどでした。
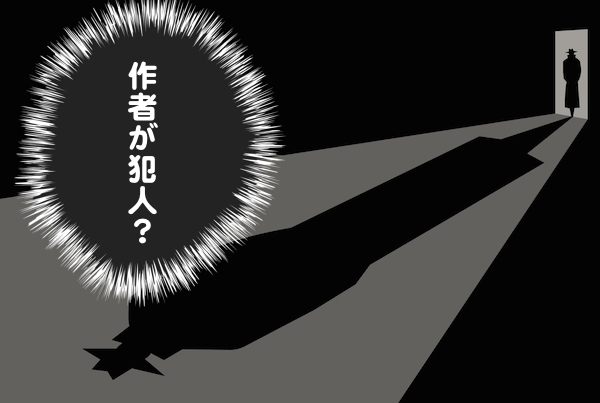
現代では、「美少女アニメ」や「残酷描写のある映画やゲーム」などがこうした模倣犯の温床として取り沙汰されることが多いですが、こうしたエンタメ作品を、犯罪を誘発する元凶とみなすような論調の始まりは、この時期の探偵小説に遡ることができそうです。
このように1930年初頭には探偵小説家は、頻発していた猟奇的な犯罪事件を媒介として、一方で「探偵」役として担がれながらも、他方で事件を誘発した間接的な「犯人」として断罪されるという、「いかがわしい」存在としてあったといえます。
(次ページに続く)
- 1
- 2

