山口瞳と川端康成の作品に”浅からぬ縁”が!? 「血族」の登場人物に迫る
直木賞受賞者である「山口瞳」。90周年に先駆け、財表作の一つ「血族」が電子書籍化されます。この「血族」に登場するある人物が別の作品に何度か登場していました。こちらの不思議な謎に迫ります!
二足のわらじを穿いたサラリーマン作家、山口瞳
31年間、延べ1,614回、死去するまで一度も穴を開けることなく、「週刊新潮」に連載され続けた伝説的コラム、『男性自身』シリーズや、高度成長期のサラリーマンと家族の日常を描いた『江分利満氏の優雅な生活』(第48回直木賞受賞作)など、その軽妙なタッチの作品で人気を博した、作家・山口瞳。
作家デビュー前には、開高健の推薦で寿屋(現サントリー)に入社し、宣伝部の社員として、PR雑誌「洋酒天国」の編集の他、コピーライターとしても活躍していました。
ハワイ旅行が当たる懸賞コピー、「トリスを飲んでHawaiiへ行こう!」が、その代表作として知られ、直木賞受賞後も暫くは、”二足のわらじ”を穿いたサラリーマン作家でもありました。

本年11月3日は、山口瞳氏の生誕90周年にあたります。それに先駆け、彼が、自らの両親の生い立ちを題材とした代表作の一つで、きわめて私小説的な作品『血族』(第27回菊池寛賞受賞作)が、小学館の文学レーベル、P+D BOOKSから復刊されました。
今回は、この『血族』に登場するある人物(作品の中で重要な役割を占めている)が、川端康成氏の代表作の一つ『山の音』の中にも、名は変わっていますが、何度か登場していた……という裏話から、両作家の不思議な縁を解き明かしていこうと思います。
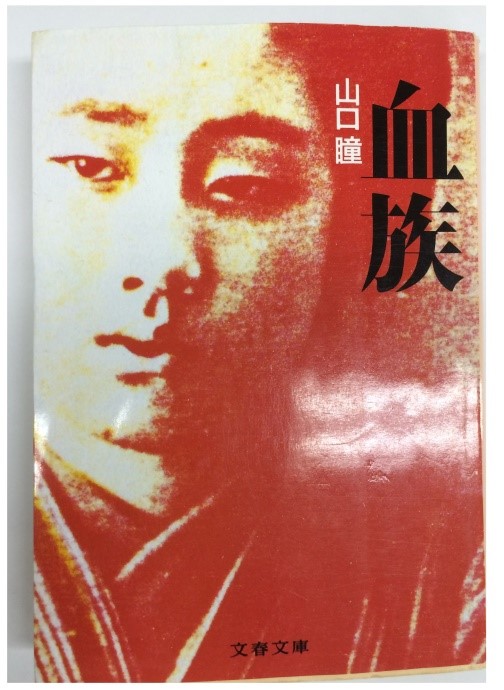
「血族」当時の書影
川端康成の作品に、「血族」の人物が登場?
『血族』は、母親がひた隠しにしてきた一族の恥となる秘密を、著者の山口瞳が暴いていく過程が、一つの核になっている小説です。
戦争が終わってから、妻・治子を迎え、鎌倉に住む瞳を始めとした山口家に、いつともなく、小久保文司・ハルという老人夫婦が住みつくようになります。母方の遠縁とだけ言われているこの夫婦が、どういう関係の親戚であるのか、また、そろそろ商売がうまくいかなくなって、逼迫してきていた山口家がどうして、こういう厄介者を抱え込まなくてはならないのか、山口瞳にとっては謎のままです。
小久保文司は、一見してお人好しというところがあり、近所の人たちにも愛されてもいますが、同時に、どこかタダ者ではないという感じが漂っているような人物です。妻のハルも、依怙地といったところがあり、山口家の家族の誰にでも可愛がられるわけにはいかず、その分だけ、瞳と治子の、若い夫婦を愛するようなり、そして、その息子、正介を溺愛するようになります。正介も、この子守をしてくれる夫婦を、ジイジとバアバと呼んで、親しみます。
この小久保夫婦が、山口家とは血のつながりがなく、遠縁というものでもないことを知った山口瞳は、衝撃を受けます。恐ろしいことだと感じます。「なぜ、私の母は、血縁でもない人たちを、終戦直後の、誰もが困窮していた時代に、面倒をみなければならなかったのだろうか」と疑問を持ちます。こうして、山口瞳は、母が隠し通そうとした『血族』の秘密を探る道を歩きはじめることになります。
ところで、この時期、鎌倉の山口家の隣家に住んでいたのが川端康成です。川端は、この時期の鎌倉を舞台に、『山の音』という長篇小説を書いていますが、その中で、山口家のことと、小久保文司のことを描いています。
さらに、山口瞳が、この辺りのことを、1954年に書いた『履歴』という短篇と、長篇『血族』の中で触れているのです。
山口瞳は『履歴』では、「父には家を売っても払いきれぬ借財が残った、その年の暮、我が家は東京に移住した。」と書いたあとに、「角川書店版昭和文学全集をお持ちの方は『川端康成集』321P下段3行目以降を参照」と、一文を挿入しています。
そして、この長篇小説『血族』では、「川端さんは『山の音』という小説で、小久保夫婦を、愛情を持って描いている」と書いています。
いま、山口家の書架にある「新潮日本文学全集」の「川端康成集」の「山の音」のページを繰ると、山口瞳か、奥さんの治子かの手で、該当個所に印が付けられています。
山口正介が、ジイジと呼んでいた小久保文司の名前は、『山の音』の中では、「雨宮のおじいちゃん」と変えられています。バアバの方には、川端は触れていません。
作中、主人公の尾形信吾の家の床の下で、野良犬のテルが子供を産みます。テルには飼主があって、鑑札をつけているのですが、飼主がろくに食物を与えないとみえて、飼主の近所の台所口を廻って、餌にありついていたようです。当時の日本では、そうした犬の飼い方はどこにでも見られた光景でした。
このテルという犬の処遇をめぐって、雨宮のおじいさん(小久保のジイジ)が話題になります。尾形家の嫁である菊子は、信吾にこう言います。
「『雨宮さんのおじいさんが、とてもテルのことを心配していらっしゃいますのよ。お宅でもらってやって下さいませんかって、頼みに見えましたの。親身なおっしゃり方で、私は困ってしまいましたわ。』」
そして、「雨宮というのは、テルの飼主の隣家だが、事業に失敗して家を売り、東京へ越して行った。雨宮のところに老夫婦が居候して、うちの小用も足していたが、東京の家は手狭だから、鎌倉に残されて、間借りしていた。その老人を雨宮のおじいさんと近所では呼んだ。」と説明が続きます。
さて、『山の音』には、もう一箇所、「雨宮さん」の商売のことを、信吾と菊子が話題にするシーンがあります。破産したが商人ゆえにたちまち盛り返して都内に家を買い、増築したので雨宮のおじいちゃんを再び引き取れるようになったことを話題にするのですが、それは是非、『山の音』そのものに当たって見つけてください。「夜の声」という章の4の中にありますというのがヒントです。
『血族』では、小久保夫妻は、遠縁などではなく、柏木田というところで、山口瞳の母親の一族の隣で、同じ稼業の経営者だったということが、後でわかるようになります。
川端康成は小久保ハルに、身の上話を聞かせてくれるようにせがんだと、山口瞳は書いています。そして、「川端さんの直感は正しかったのである。さすがに鋭いと思わないわけにないかない。小久保ハルは数奇な運命を辿った女である。」と、付け加えています……。
終わりに
いかがでしたか?
山口瞳が自らのルーツを辿る『血族』は、小学館、P+D BOOKSより絶賛発売中です。
「血族」の詳細はこちらからチェック!
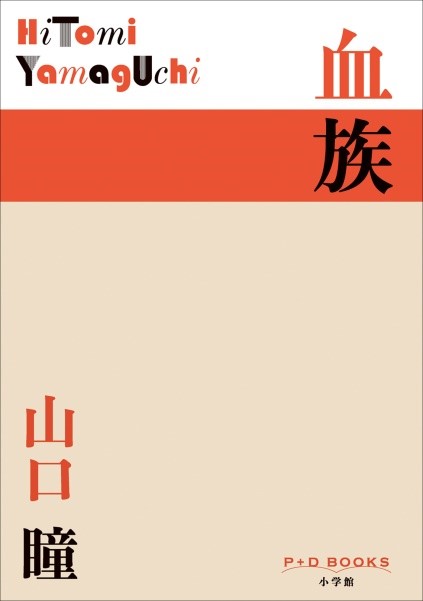
本書は、山口瞳自身の家系の謎に迫る本である。自分のことをほとんど語ることなく亡くなった母。美しく奔放で、どちらかというと豪放磊落な性格の母の出生について氏は何も知らなかった。幼い頃に見た光景、家に出入りしていた人たちの言葉、そして数々の資料をひもといて作者は自らの出自の謎に迫り、その過程を、母の思い出などを交えて綴っている。 登場する人物は、直接関わりのない人がイニシャルになっているのをのぞけば、親族もみな実名である。調べながら書いたのではなく、すべてが明らかになってから書き始めてあり、後に、事実を明らかするときのための伏線も張ってある。
作者は、母の死後、その母が一体どこでどんな家に生まれ、母方の親族は一体どういうつながりになっているのかを解き明かしていく。その結果みたものは・・・・・・。
亡き母への熱き愛と鎮魂をみごとに描破した菊地寛賞受賞作。
初出:P+D MAGAZINE(2016/01/22)






