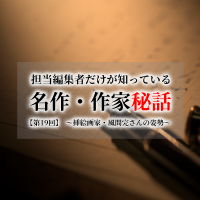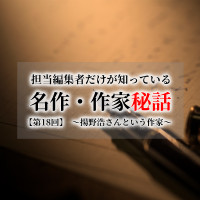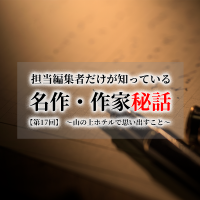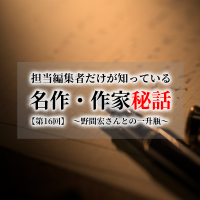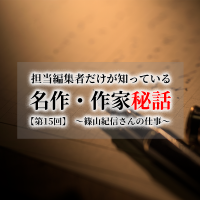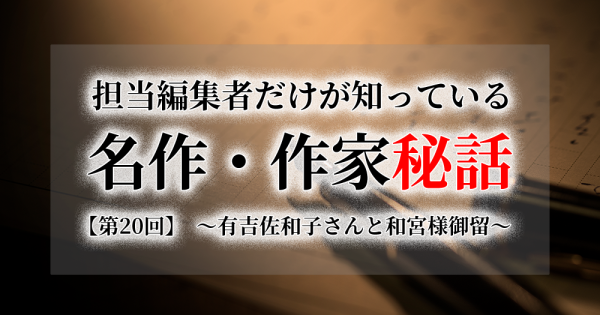連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第20話 有吉佐和子さんと和宮様御留
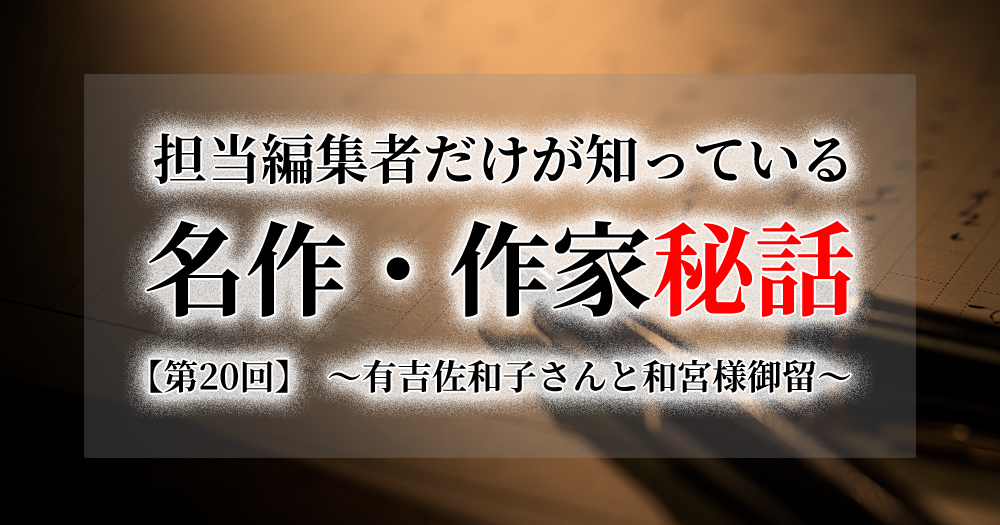
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第20回目です。今回は、大ベストセラー『恍惚の人』の著者・有吉佐和子さんとの秘話。『和宮様御留』が執筆されるに至った背景を、担当編集者だけが知る目線で語ります。
水口義朗さんという、とても変わった編集の先輩がいる。水口さんは、私の高校の先輩でもあるのだが、中央公論社に入社後、「中央公論」や「婦人公論」や「小説中央公論」の編集に携わり、副編集長や編集長になったりして、テレビ朝日のワイドショー「こんにちは2時」のキャスターを8年間も務めたあと、復帰して「婦人公論」の編集長を務めている。この経歴を見るだけでも、奇人と言ってよいほどの人であることが分かる。90歳になろうかという歳で、いまも現役の文芸評論家として、編集者でなければ書けないような生々しい視点から評論を書いている。

この水口さんは、野坂昭如さんのデビュー作『エロ事師たち』を書かせた人でもある。「小説中央公論」が、あと2回で休刊というのを、ポジティブにチャンス到来と考え、野坂さんに小説を書かせようと目論む。「野坂さん、ほら、ブルーフィルムの運び屋のおっさんのこと書いたらどう」と目配せし、『エロ事師たち』という題まで考えつき、終刊間際の「小説中央公論」に120枚ほどの小説を掲載した。
何の反響もないまま、作者・野坂さんと編集者・水口さんは顔を見合わせるしかないところ、「新潮」では三島由紀夫さんが、「これは世にもすさまじい小説で……醜悪無慚な無頼の小説であり、それでいて塵芥捨場の真昼の空のように明るく、お偉ら方が鼻をつまんで避けてとおるような小説なのだ」と書き、「文芸」では、吉行淳之介さんが、「文学作品として後世に残る傑作である。……作者の人間を見る冷たい視線が、そのまま人間を慈しみぶかくすい上げていることも稀有であり、作者の眼がういういしさと大人の円熟を兼ね備えているのも稀有なことである。あえて最上級の賛辞を呈する」と絶賛してくれたのである。このふたりの大絶賛を奇貨として、野坂さんは作家として活躍して行くことになる。
長々と我が先輩・水口さんのことを書いてきたが、それも、今年(2024年)の4月末、渡辺淳一さんを偲ぶ「ひとひら忌」の会で、いつもの通り、何の前触れもなく、イキナリ「有吉が『なんで大庭みな子さんばかりが賞をとるの』と言ったのが分かるんだよ」と言ったのだ。キョトンとしている私に向かって、なお、「な、有吉佐和子は『恍惚の人』でも『複合汚染』でも、介護問題でも、公害の問題でも、今の時代の問題を先取りしているんだよ」と付け加えたところで、大先輩の言わんとすることが飲み込めてきた。
1984年8月30日に亡くなった有吉佐和子さんは今年、没後40年になる。「真砂屋お峰」を担当して以来、親しい編集者のひとりであった水口さんは、柴又の帝釈天・題経寺の季刊の教誌「柴又」に、「有吉佐和子 没後40周年に向けて」という連載を書いていたのである。
久し振りに有吉佐和子という名前を聞いて、私の頭の中に、ふたつのリズムが響いていた。
──コンコンチキチン コンチキチン。
これは、有吉さんが「群像」誌に連載した『和宮様御留』という小説の通底奏音として響いている「祇園さんのお囃子の鉦の音」である。主人公のひとり、婢女のフキの身の内に響いているリズムなのだ。このリズムを口ずさみながら、フキが水汲みに精を出す冒頭のシーンは忘れ難い印象を残す大切なシーンだ。
もうひとつ、この小説の中に、響くリズムは「ヒンプク、ヒンプク」である。有吉さんの書いたところによると、「右足から先に踏み出した。左右、左右、と歩くごとに貧福、貧福と呟くのが公家たちの呪いであった。左のひの音が貧に通ずるところから生まれる迷信であったろう」ということだ。
和宮御降嫁を巡り、和宮側と関東所司代との板挟みに頭を悩ませている公家の橋本実麗は、「右足を一歩踏んでから、ヒンプク、ヒンプクと口の中で唱えながら」哀れにもうなだれて歩いて行くのである。
有吉さんは、こうした細かいディテールを描いて、読者にとって馴染みの薄い公家たちの生活をとても自然に伝えてくれている。
水口さんは、早速翌日、3回にわたって連載されている「柴又」誌のコピーを送ってくれた。
「編集者の編集始末覚え書より」と角書きがあり、メインタイトルは、「有吉佐和子 没後40周年へ向けて」となっていて、それぞれ、
「超ベストセラー『恍惚の人』の先見性と受難──私、芥川賞をいただきそこねているの──」
「『恍惚の人』につぐ『複合汚染』もベストセラーに〝有吉の文章は文壇の文章美学から外れている〟」
「『群像』大久保房男編集長への挑戦 虎穴に入って書いた『中国レポート』」
という副題がついている。
水口さんは、「中央公論」誌に有吉さんが連載していた『真砂屋お峰』をピンチヒッターで担当して、誤植を叱られて以来、『出雲阿国』を担当している。
3回目の「『群像』大久保房男編集長への挑戦」というのには、少し説明が必要かもしれない。
大久保房男さんの著書『文藝編集者はかく考える』(1988年紅書房刊)に、有吉さんにはじめて会った時のことが記されていて、水口さんは引用している。すなわち、
「私にはあなたの文章のよしあしはようわからんけど、文壇の文章美学から外れていることは確かで、文壇文士があなたのものをよく言わないのはそのせいじゃないだろうか」
と言い、結局「有吉のものを一行も『群像』に掲載したことがなかったのである。」
こうした経過があって、有吉佐和子さんが「群像」に、1977 年1月号から1978年3月号まで連載を掲載することになった。歴史小説『和宮様御留』である。
私は、社の大きな方針変更だったような感じもしたが、連載が決まると、社の内外からいろいろな声が聞こえてきた。やはり、文壇からの反発の声も大きかったと思う。
担当が私に決まったのは、「小説現代」編集部にいたことがあるから、こうしたベストセラー作家に慣れていると思われたからだろうか。
小説に沿って、和宮と、身代わりとなったふたりの少女の生涯を追ってみたい。
和宮は仁孝天皇と新典侍橋本経子との間に、天皇の8女として生を受ける。6歳のとき、有栖川宮幟仁親王の王子・熾仁親王と婚約しているにもかかわらず、攘夷か開国か、二分された国論を和らげるため将軍・徳川家茂への降嫁が計画された。いわゆる公武合体である。
和宮は、すでに熾仁親王と婚約していること、故郷を離れて東国で暮らす心細さ、そして、関節炎のために片足が悪いなどの理由から、薙髪して観行院と呼ばれた生母と共に、降嫁を拒む。
しかし、すぐに降嫁の勅命を受け、拒み通すわけにはいかなくなった。観行院たちは、ひそかに身代わりを立てることを計画、観行院の兄・橋本実麗邸の婢女・フキにその大役を振ることにした。事情を何も知らされないフキは、和宮の身代わりとして教育を受ける。
ある日、フキは、突然、本物の和宮がいなくなったことを知る。フキにとって孤独に苛まれるはじまりだった。
和宮のその後に関して、上州新田郡得川村(現在の群馬県太田市)にある満徳寺で薙髪して暮らしたようだと有吉さんは考えている。
偽の和宮となったフキは1861(文久元)年10月20日、京都の桂御所を出発し、東海道ではなく、峻険な木曽路を抜けなくてはならない中山道を通って、約ひと月後、ようやく板橋宿に着く。
この時、旅の疲れと孤独のためにフキの精神は狂い出して、「あて、宮はんやおへん」と叫んで泣き崩れる。「コンコンチキチン コンチキチン」と繰り返すフキを、このままでは、和宮の身代わりとして連れて行くことはできなくなる。
公武合体の計画の推進者だった岩倉具視は、薩摩藩士・土井重五郎の許嫁であった新倉家の宇多絵をフキの代わりにすることにする。宇多絵は赤みを帯びた髪をして、左手がないということがわかったが、御所風の召物なら、それを隠しておけるのである。
重五郎は高田村の新倉覚左衛門宅に赴き、娘の宇多絵を籠に乗せて、板橋宿へと向かう。すぐに新倉宅に舞い戻った重五郎は、中に手足を縛られ、猿ぐつわをされているフキが押し込められている籠を持ち込んでいた。奥の土蔵の中にひとりになったフキは、今は使われていない井戸を見つけ、「コンコンチキチン コンチキチン」と繰り返しながら、鶴瓶を探して、深い井戸の中を覗いてみる。
降嫁の和宮の一行は、11月15日に江戸に入り、九段の清水邸に到着。御所風のあり方と大奥風のあり方との角突き合いが繰り広げられ、その間に、新しい和宮となった宇多絵は書道と和歌の素養があり、利発な娘で、御所言葉と京なまりもすぐに覚えた。
翌文久年2月11日、和宮は家茂と婚儀を挙げる。
家茂は1866(慶応2)年7月20日に逝去。享年21。同じ歳の和宮は21歳で寡婦となり、剃髪して静寛院を名乗り、1877(明治10)年8月に箱根に転地療養のため赴くが、そのまま、9月2日に急死してしまう。享年32。
有吉さんが、和宮身代わりという大胆な説を小説にしたわけをいくつかあとがきに書いている。それを箇条書きにしてみると、
1)高田村の名主であったという新倉家の子孫の女性から、「和宮様は私の家の蔵で縊死なすったのです。御身代りに立ったのは私の大伯母でした」と当時は、荒唐無稽とも思われることを言われて、とても信じることはできなかったという経験をした。
2)しかし日がたつにつれ、例えば、和宮の足に関節炎らしい病があり、そのために骨格に異常があっただろうと思われるなど資料が目に止まるようになる。
3)勝海舟の「氷川清話」の中に、和宮がピョンと飛び降りて履き物を置き直したと書かれているのを読んだとき、宮様育ちのすることではないし、骨格に異常があった体ではできないことだと思い、新倉家の婦人の話を結びつけて考えはじめた。
4)さらに決定的になったのは、昭和42年に「増上寺 徳川将軍墓とその遺品・遺体」(東京大学出版会)が出版されたのを見たときである。和宮の両足に異常が認められず、そのかわり左手首がなかったのだ。宮家で幼い和宮は藪内流の茶道のお稽古などしているが、手首がなくてはできないことだ。
5)和宮生前の絵姿と、増上寺に没後納められた十二単衣姿の塑像を見ると、明らかに左手首がなかったことが分る。
6)増上寺の和宮の髪は赤毛であったが、家茂の内棺に納められていたのは黒髪だった。
私が担当になって、まず有吉さんと一緒にした仕事は、群馬県上田市にある満徳寺への日帰りの取材行であった。平日の午前中に有吉さんのお宅に車で迎えに行ったとき、有吉さんは、「編集者って忙しいから、土日の取材はしないようにしているの」と言ってくれた。
私にとっては、有吉佐和子という作家は、もう、『紀ノ川』(1959年)、『香華』(1962年)、『華岡青洲の妻』(1967年)、『出雲阿国』(1969〜1972年)など主要な作品のほとんどを書き、さらに『恍惚の人』(1972年)、『複合汚染』(1975年)などの超ベストセラーを立て続けに出している凄い作家というイメージがあった。
その作家が、細やかな気遣いをしてくれることに感激したのであるが、緊張していたせいだろうか、道中なにを話したのかほとんど記憶にない。
あとがきに、有吉さんは、満徳寺について、「本物の和宮は、私の設定では群馬県にある縁切寺満徳寺に逃れたとしているが、その寺を訪れ、墓所を見たところ、有栖川宮家にかかわりのある第十代の鏡誉本清尼の墓だけがないことに気がついて、改めて驚かされた」と書いているが、正直に白状すると、その時、私は、満徳寺に墓がないことを知って有吉さんが小躍りしていることの意味がよく分かっていなかった。そのあと、そばにある小さな役場に行って、何人かいた事務の人たちにいっぺんに気に入られた有吉さんが、彼らと、墓の存在のことを話しているのを聞きながらも、同じことだった。
帰りの車の中で、有吉さんは、第十代の住職・鏡誉本清尼は、有栖川家のゆかりの者で、歴代の住職の墓が一基も損なわれることなく並んでいるというのに、その墓だけがないということは、この人は和宮で、ここで薙髪して、生涯を送ったと設定してもおかしくないと説明してくれた。私は、和宮の身代わりになったふたりの少女たちのことを調べるのに没頭していて、本物の和宮の生涯のことは、頭の中から消えていたのである。
こうやって、有吉さんは、和宮の身代わりという仮説の証拠を固めていったが、しかし、この小説が発表された後も、替え玉説はあり得ないという批判も多く見られたが、有吉さんにとって、身代わりが実際あったかということは問題ではなく、そこに描かれた身代わりになった少女たちやそれを画策した周辺の大人たちのことが、文学作品としていかにリアリティを持って読者に迫るかということの方が重要なことだった。
第1回のゲラが出た。そのゲラを見て、いくつか削った方がいい無駄な文章があるような気がした。すでに、一流の作家になっている有吉さんに、ゲラの手直しを頼むことは可能だろうか。ゲラ直しに慣れているのだろうか。すべては手探りで進めるしか方はなかった。逆鱗に触れでもしたら、社を辞めればいいじゃないかと、悲壮な決意までして、有吉邸に出向いた。手直ししてほしい箇所を鉛筆で細かく指示してあるゲラを広げると、有吉さんはその指示に納得したら、「これは鉛筆の通り直していいわよ」と頷き、どうしてもこの文は削れないところは、そのわけをじっくり説明してくれた。もう、何年も付き合っている作家と編集者と同じようなやり取りが進んだ。
新連載の始まる号が刷り上がったとき、私は大きな間違いを犯した。楽しみに待っていた有吉さんに、刷り上がったばかりの「群像」を届けることをしないで、郵送してしまったのだ。
有吉さんは、そのことを水口さんにこぼしたようで、しかも、水口さんは取りなしてくれたらしい。すぐに有吉さんから電話があって、早く見たいから雑誌を届けてくれるように依頼する電話があった。私は失態を詫びながら、有吉宅に急行した。
有吉さんはできたばかりの「群像」の目次を開いて見ながら、「志賀直哉になったみたい」と顔をほころばせた。水口さんが連載で書いている通り、一行も「群像」に掲載しなかった大久保房男さんへの会心の復讐だったかもしれない。
こうして翌年1978年3月号で完結した『和宮様御留』は、この年、単行本として出版されて、瞬く間に大変なベストセラーになった。私は雑誌編集者を自認していたから、単行本としてどれほど売れたのかあまり興味がなかったが、あるパーティで会った営業畑の役員から、ありがとうと頭を下げられたのには驚かされた。それほど売れたのだろう。
その後、1981年に、私は文庫編集部に異動になった。一応、有吉佐和子さんとの直接の担当になることはないと思ったが、1984年になって調べてみると、1974(昭和49)年に出版されたまま、文庫化されていない『母子変容』という上下の単行本があることを知った。1973(昭和48)年、「週刊読売」に連載されたものだ。
新装版の文庫の宣伝コピーには、「フットライトを浴びる清純スター・葵輝代子は、母親の愛人とも知らずに、ひとりの男を愛するようになる……。母への激しい憎悪は、整形美容に駆りたて、清楚な美貌は、妖艶な女に変容してゆく。女の生の烈しさを精緻に描き切った有吉文学の傑作長編」と書かれているような問題作だ。
早速、有吉さんに連絡して、これを文庫化させてほしいと頼み込んだ。だが、有吉さんは、あれは好きな作品じゃないから、文庫化したくないと言う。
私は解説を橋本治さんに頼むつもりだから、ぜひ引き受けてほしいと返した。
「橋本治?」
有吉さんは少し怪訝そうな声を出した。
橋本治さんは、1977(昭和52)年、応募作「桃尻娘」で、第29回「小説現代」新人賞の佳作になった人だ。佳作には異例なことだが、「小説現代」別冊「Gen」に掲載され、翌1978年に、単行本として出版され、独特の話し言葉の小説として話題になっている。文庫化の交渉をしている1984年頃には、「桃尻娘」シリーズを軌道に乗せ、推理小説を出し、編み物の指導本や不思議とも言える独特の評論を出し、今や若者たちの圧倒的支持を受ける作家だった。
程なくして、有吉さんから、巻末解説を橋本さんが書いてくれるなら、文庫にしてもいいわよと電話があった。多分、橋本治さんのことを娘の玉青さんにレクチャーしてもらったのかもしれない。この当時、有吉さんは、玉青さんを通じて村上龍さんや林真理子さんたち若い作家を自宅に呼んで、話す機会を持っていたようだ。
文庫化された『母子変容』の下巻の巻末に掲載された橋本治さんの解説「理性の時代に」は見事なものだった。橋本さんは有吉作品のファンで、ほとんどの作品を読み込んでいて、だからそれぞれの作品の解釈も、有吉さんの作家としての足取りの解説も見事なものだった。
そして、「激しさは、それを〝知る〟か知らないかの、女自身の知性の如何によっていると。それを知り、そうである筈だということを前提にするのが女の理性だというのが、有吉佐和子に於ける、女性・性の位置づけである」という一文が、新しい有吉佐和子論になっているのだ。
この橋本治さんの有吉佐和子論が、その後、関川夏央さんや高橋源一郎さんなどの次の世代の作家たちに、有吉佐和子作品への新しい視線を向けさせることになったと思う。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。