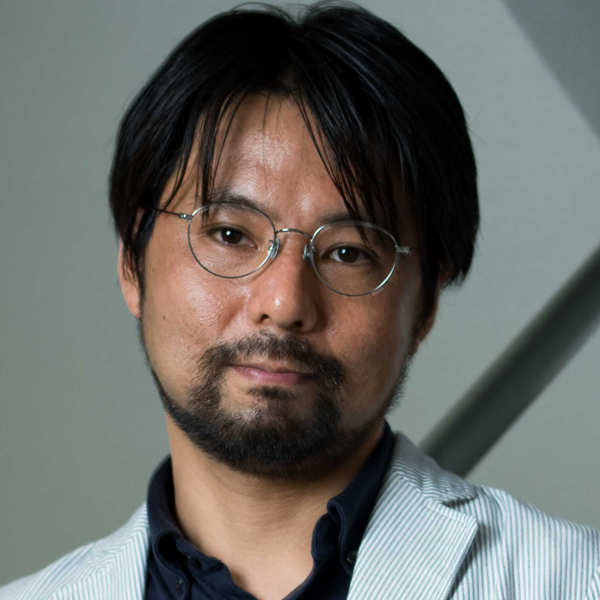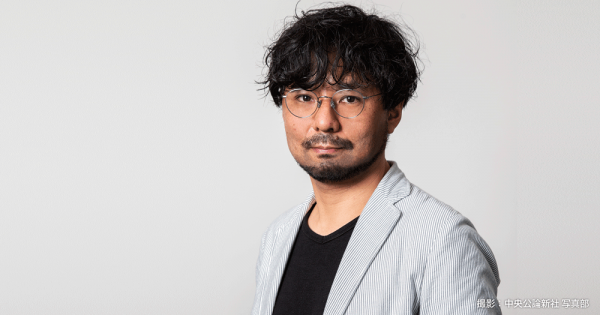葉真中 顕さん『ロング・アフタヌーン』
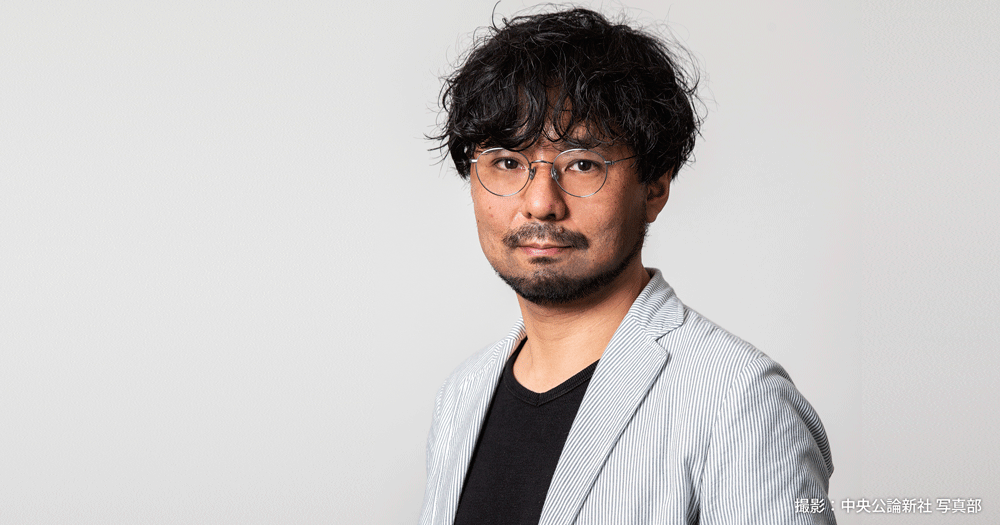
属性が違うから分からない、と片づけたくはないんです
一度も顔を合わせたことのない女性二人が、フィクションを通して共犯関係となっていく。葉真中顕さんの『ロング・アフタヌーン』は、現代女性への抑圧と、フィクションを書く/読むというテーマが浮かび上がる長篇。ミステリアスなシスターフッドの物語を書いた背景にはどういう思いがあったのか。
フィクションを書く女性、読む女性
作家志望と編集者。二人の女性の人生が作中作を通してシンクロしていく葉真中顕さんの『ロング・アフタヌーン』。これまでも女性主人公は描いてきたが、今回はまた新たな覚悟をもって挑戦した一作だ。
「自分ではすっかり忘れていたんですが、たしか最初は自分から遠い人を書こうと思ったんです。それで考えているうちに、自分が読んできたり見てきたりした作品には男性か若い女性が主人公のものが多く、上の世代の女性主人公が少なかったと思いあたりました。そういう属性の人は実社会でも何かしら見落とされがちな部分があるだろうということで、主人公にしてみることにしました」
そこから最初に浮かんだのは、五十代の作家志望の専業主婦。
「主人公像が決まった時点で、やはりジェンダーは大きなテーマになると感じていました。当然、自分と違う属性を勝手に書いていいのかという気持ちはある。こんなことを男性に書かれたくない、という意見が出てくるリスクも感じます。でも、この恐れが大事だという気持ちもあって。恐れながらうじうじ悩んで考えて書いていったほうが、マシなものが書ける気がするんです。その結果、至らないところがあったら反省していこうと思っています」
本作には、そんな主人公が書いた作品が二篇挿入される。
「主人公をフィクションを書く人にして、その人が書いた作品という形でフィルターを一枚通すと意味的に厚くできるし、いろんな読み方ができると思いました。で、作中作を入れるなら読み手が必要ということで、編集者の存在が出てくることになりました。狂言回し的な役割として構想した存在ですが、もちろん主人公の一人として動いてもらうつもりでした」
七年ぶりに送られてきた小説原稿
編集者の葛城梨帆のもとに届いた中篇の原稿。送り主の志村多恵は以前、短篇の新人賞に「犬を飼う」という応募作を寄越し、最終選考まで残ったことがある。受賞とはならなかったが、作品に惚れ込んだ梨帆は、新作を書いたら送ってほしいと多恵に伝えたのだった。しかし、それから実に七年も経っている──。
本書の巻頭に置かれているのが、その「犬を飼う」だ。少女が飼い犬を可愛がる微笑ましい話かと思いきや、後半にぎょっとする事実が明かされる近未来小説。これはもともと構想があって、何かの機会があれば出そうと思っていたのだとか。一方、多恵が七年ぶりに送ってきた中篇の題名は「長い午後」。冒頭の一文は、〈女の午後は長いというけれど、私の午後はいつ始まったのだろう〉。
「出典が分からないのですが、そういう決まり文句があったはずなんです。ひと昔前なら、アフタヌーンというと優雅なイメージがあったかもしれません。でも近寄って解像度上げて見てみると、決して本人が望んでいた長い午後ではないと分かってくる……みたいな意味をタイトルにこめたかった」
この「長い午後」の主人公〈私〉は、来月五十歳となる専業主婦。〝だらだらと続く女の長い午後〟を終わらせたい彼女は、死を決意して家を出たその日、偶然高校時代の同級生だった亜里砂に再会する。彼女のペースに引きずられて会話を続けるうちに、〈私〉は亜里砂に対して殺意を抱く、という展開。
この作品は、どうやら志村多恵の私小説のようだ。上司と結婚して仕事を辞めて家庭に尽くしてきたが、息子はすでに成人して家を出ており、定年退職した夫は彼女に厳しい。とにかくこの夫のモラハラっぷりにぞっとする。
「実際にはあんな百点満点のクソ夫もなかなかいませんよね(笑)。人はもっと複雑で曖昧なものですから。でも、ずっと抑圧されてきた人の主観で書くと、あんなふうに見えることもあると思う。作中作の形にしたことで、ひどい人間のひどさを堂々と書けるのは楽しくもありました(笑)」
物語の始まりの段階では、〈私〉は傷つきながらも素直に夫に従っており、旧来の家父長社会の価値観を内面化している部分がある。だが、亜里砂と再会して死を思いとどまった日から、彼女は少しずつ変化していく。
「自分の置かれた状況のまずさをはじめて言語化して、そこから自分で行動を起こしていく人の話にしようと思いました。もちろん、専業主婦のようなライフプランが駄目だと言っているわけではないです。問題なのは、そうした生活のなかで抑圧や暴力がある場合。〈私〉は抑圧に気づいて夫の支配から逃れたいと思うようになりますが、それでも、今まで彼女が専業主婦として過ごしてきた時間が無意味だったわけではない。そのことは意識しながら書きました」
ようやく前向きになり、小説家になって自立しようとする〈私〉だったが新人賞に落選、夫に「おまえなんかが書いた作文で賞なんて獲れるわけないんだから」などと馬鹿にされる場面は読んでいても辛い。
「夫が作家になろうとする妻を馬鹿にするのは、妻が自分より上の立場になったら嫌だからですよね。自分がマウントとれる相手をパートナーにしたがる男性って意外といる」
そこで立場が逆転できれば痛快だが、
「実際は何者かになりたいのになれない人のほうが多い。今回の小説のテーマからは外れますが、私は〝人はなりたいものになれる〟といった言葉は近代の呪いだと思っています」
また、夫と息子が喜々として会話する場面があり、これが実に醜悪。
「多恵にかまわずずっと二人で話している場面ですよね。男だけでわーっと話して許し合って、同席している女性のことはオミットしているわけです。私は男性の親子って最小単位のホモソーシャルだと思うんですが、その醜悪な形を書いてみました。『長い午後』の着地点は最初から決めてあったので、そこに向かって逆算して書いた場面でもあります」
そして物語は、不穏な方向へと動き出すのだ。
書き手と読み手の共犯関係とは
作中のさまざまなエピソードに関して、登場人物たちと同じように怒りや戸惑い、苛立ちを感じる人も多いだろう。葉真中さん自身、出発点は「自分からは遠い人」ではあったものの、執筆時には彼女たちになりきったそうだ。
「もちろん男性と女性には身体的な違いがあるし、私が体験できないことは多い。そこは挑戦の気持ちで書きました。ただ、属性が違うから分からない、と片づけたくはないんです。自分と同じ男性でも、世代が違うと分からないことがあったりするし、人間の属性のカテゴリーははっきり分かれるのではなく、グラデーションだと言いますよね。いろんな男性がいるし、いろんな女性がいる。それを踏まえつつ、家族など身近な存在を参考にしつつ、自分がこの女性だったらどう感じてどう反応するか想像して書くつもりだったんです。でも、やってみたら、まるきり他人を書いている感じがしなくて。うまく言語化できないんですが便利な言葉を使うと、今回はキャラクターたちが憑依してくれました。特に作中作は一人称ということもあって、あまり客観的に考えずに語り手が思っていることをそのまま書いていく感覚がありました」
一方、「長い午後」を読み進めながら、梨帆は〈私〉に気持ちを寄り添わせていく。実は彼女もまた、仕事や私生活において葛藤や後悔を抱えている。彼女には離婚歴があるが、その理由がなかなかデリケートだ。
「彼女の離婚の理由について良識を疑う人はいるだろうし、自分も必ずしも正しいとは思っていません。でも以前から、私には愛とか命というような、万人がよしとすることへの疑いがあって。みんなが肯定するようなことを選べない人はいる。そうしたことを私は継続的に書いているつもりです。ミステリで殺人を犯してしまう側の人物を書いたりもしますが、そういう人も切り捨てずにいたいというか。今回も、この切実なテーマが伝わる人には伝わればいいと思っています。実際、シビアな問題なので、肯定的でないもの含め様々な意見が出てくるかもしれませんが、作者としてそこは受け止めたいです」
〈私〉=多恵と梨帆、それぞれの姿からはフィクションを書くこと、読むこととは何か、というテーマも浮かび上がってくる。
「最初はそんなつもりはなかったんですが、書き進めるうちにそのテーマがどんどん強まっていきました。やはり、私にとってそれが切実な問題だからでしょうね。現実の人間は小説をひとつ読んで救われるほど単純ではないと分かっていますが、それでもやっぱりそういう側面はあると思う。今回の二人も、自己否定の状態から、書くことや読むことで何かを肯定していく形に向かっていきました。メインの二人だけではなくて、サブキャラの風宮華子という作家も、最初は梨帆に対する抑圧のひとつとして、単なる嫌がらせキャラとして出したんですが、書いているうちに彼女にもなんとかなってほしいと思えてきて(笑)。後半の風宮華子を巡る展開は最初の想定よりだいぶ厚みが増したものになりました」
書き手と読み手として、互いに顔を合わせないうちに引き寄せられていく二人。終盤には〈共犯者〉という言葉も出てくる。
「書く、読むって共犯関係だと思うんです。小説は誰かが読んで何か感じたり解釈した瞬間に完成する、共同作業なんですよね。ただし、それが必ずしも道徳的によいことだったり正しいこととは限らないかもしれない。それが小説の自由さだと思います」
本作を読んだ私たちもまた、新たな共犯者となるわけだ。
「今回は主人公たちがうまく憑依してくれて、梨帆のデリケートな部分以外は、書いていて非常に楽しかったです。そういう意味で手応えがあったし、いつもこんなふうに書きたいなとも思いました」
現在は、光文社の書き下ろしに取り組んでいる。
「『絶叫』『Blue』に続く、女性刑事の奥貫綾乃が出てくる作品の三作目です。80代の親が50代の引きこもりの子供の面倒をみる8050問題や、先ほど触れた〝人はなりたいものになれる〟という近代の呪い、さらに踏み込んで何かの役に立たないと人は生きていては駄目なのか、といったテーマ性を持たせるつもりです。自分にとって、いわゆる社会派小説の集大成となったらいいなと思っているところです」
次の秋冬くらいの刊行を目指しているそうだ。
葉真中 顕(はまなか・あき)
1976年東京都生まれ。2013年『ロスト・ケア』で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、作家デビュー。19年『凍てつく太陽』で第21回大藪春彦賞、第72回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞。他の著書に『絶叫』『コクーン』『Blue』『灼熱』などがある。
(文・取材/瀧井朝世)
〈「WEBきらら」2022年4月号掲載〉