明るさと上品なユーモアと 阿川佐和子おすすめ小説4選

対談の名手として知られ、その秘訣をまとめた著書『聞く力』がミリオンセラーになった阿川佐和子。インタビュアー、エッセイストのイメージが定着していますが、小説家としての顔も持っています。そんな著者のおすすめ小説4選を紹介します。
『ウメ子』――「へんな子のほうが、大人になったとき大物になる」。風変わりな転入生との出会いと別れとは

https://www.amazon.co.jp/dp/4094080090
本作は15歳の少女・みよが、幼少期に出会った忘れがたい親友・ウメ子のことを述懐する物語です。
神戸から東京の幼稚園に転入してきたウメ子。新入りにも関わらず、ふてぶてしく偉そうで、みよは最初反感を持ちます。しかし、誰にも媚びず、友達がいなくても超然とした態度のウメ子に、次第に惹かれてゆきます。
ウメ子はほかの友達とはどこか違ってみえた。気に入らないことははっきり言う。私なんか、友達に嫌われるのが怖くて、つい強い子の命令に従ってしまう。が、ウメ子は違う。(中略)いつもはだれも逆らうことのできないユカちゃんが、ウメ子にしてやられたのだ。あのウメ子のいさぎよい態度を見れば、だれだってそう認める。ほらみろ、男の子たちがみんな、ウメ子のそばを離れないでいる。みんな、ウメ子をすごいと思った証拠だ。こんなに気持ちのいいことは、久しぶりだった。
みよは、怖かったジャングルジムの登り方をウメ子に教えてもらって以来、急速に仲を縮めてゆきます。
ウメ子と歩いていると、毎日通う道が、ずいぶん違って見えるものだと思った。なにしろウメ子は、地面に落ちている小石まで、おもしろいものにしてしまう。ウメ子によると、石も生きているそうだ。熊笹の葉っぱの舟の作り方、食べられる木苺と毒苺の見分け方、大きな木に耳を当てるとチョロチョロ音がすることも、ウメ子に教えられて知ったのだ。
ウメ子は、街にやって来る紙芝居屋のトラックの荷台に隠れて乗りこめば、遠くまで冒険の旅に出られると、みよを誘います。ウメ子は母子家庭で、遠くのサーカス団で働く父に会いに行きたいと思ったのでした。2人の行方不明で大騒ぎになった園では、保護者たちから、「ウメ子は他の子へ悪影響があるから、退園させるべき」との声があがります。けれど、保護者たちの心配は杞憂に終わります。なぜなら、ウメ子はその後、父のいるサーカス団に遊びに行き、高い所から落ちて大怪我を負い、大きな病院に入院するため園を去ることになったからです。
ウメ子と一緒にいるときにはあまり気づかないのだが、ウメ子がいなくなると、たちまち感じる。ウメ子がいなきゃ、つまらない。(中略)ウメ子のような友達は、ずっと現れたことがない。
世界を広げてくれたウメ子との、鮮烈な出会いと突然の別れ。自伝的要素を含む本作で、第15回坪田譲治文学賞を受賞した著者は、好きな言葉として、児童文学者・石井桃子の言葉を挙げています。「子どもたちよ 子ども時代をしっかりたのしんでください。おとなになってから、老人になってから、あなたを支えてくれるのは子ども時代の『あなた』です」(著書『センス・オブ・ワンダーを探して』より)
たとえ会えなくても、ウメ子は、大人になったみよを、励まし支え続けてくれる宝物のような存在であり続けるでしょう。
『ばあさんは15歳』――15歳の孫と71歳の祖母が、昭和38年にタイムスリップする珍道中を描く
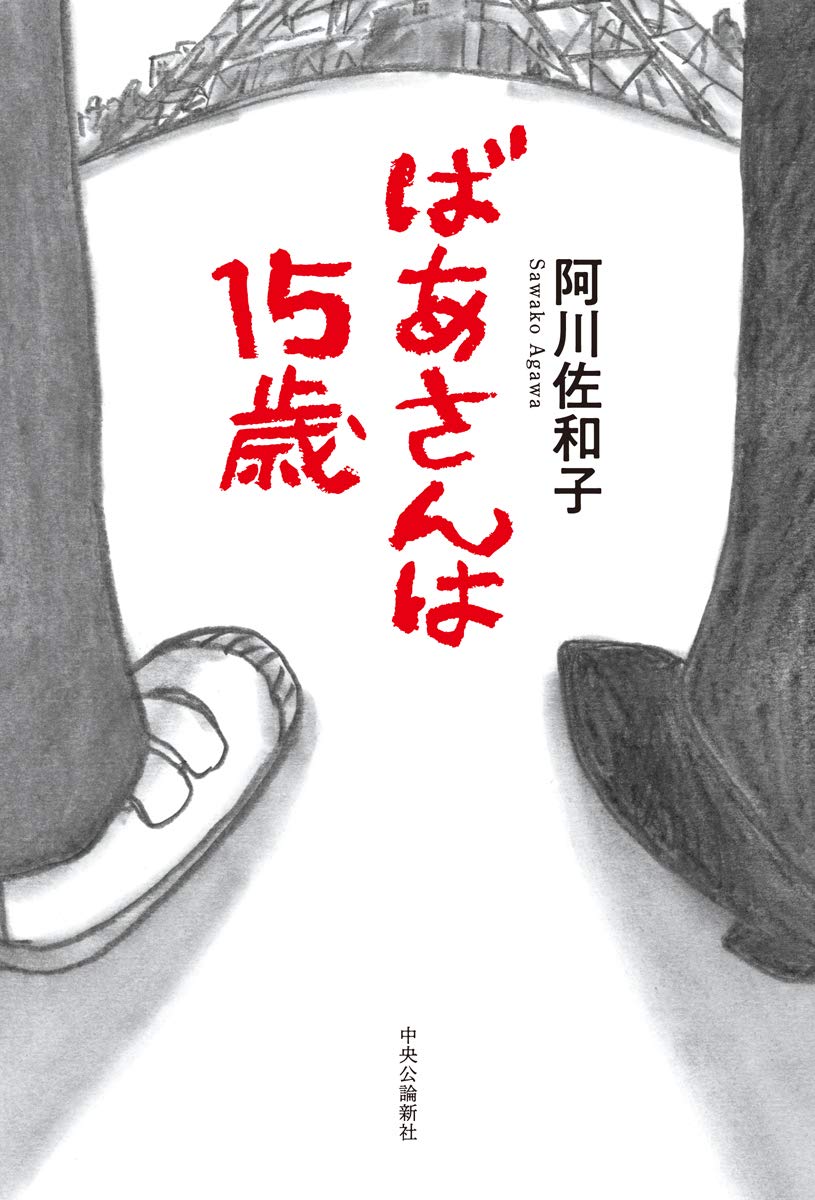
https://www.amazon.co.jp/dp/4120053776/
2019年、高校入学を控えた菜緒は、71歳の母方の祖母・
菜緒は昭和の居心地の良さを感じ始めている。道がわからなければ教えてくれる。見ず知らずの人間を家に泊めてくれる。素性も聞かずにご飯を食べさせてくれて、お風呂に入れてくれて、服まで貸してくれた。昭和って、なんだか人間関係が近い。もしかして不便なほうが人は優しくなれるのかもしれない。それに比べて今の人たちは、まるでロボットみたいだ。愛想が悪いわけではないけれど、なんだか心がない。他人と関わる時間を極力短くしたがっているように見える。
祖母の生家で、菜緒は、15歳の祖母・和とも出会います。孫にとっての祖母は、ずっとおばあちゃんのイメージですが、祖母にも若かった頃はあります。そこでは、店の跡継ぎ娘・和と、奉公人の節子、料理見習い・たか坊の間に三角関係めいたものがあったのでした。和とたか坊が婚約し、郷里の新潟に帰った節子は、昭和42年の
もしここで過去を変えてしまったら、その後の歴史がぜんぶかわってしまうではないか。ばあさんがたか坊、つまりじいさんと結婚しなかったら、娘の万里は生まれてこないわけで、当然、孫の私も生まれることはない。それ、困ります、ばあさん。
菜緒は菜緒のまま、現代に戻って来られるでしょうか――。本書はまた、オリンピック、新幹線開通など、当時を知る人には懐かしい風景を、知らない人には新鮮さをもたらしてくれる1冊でもあります。
『婚約のあとで』――姉のお見合い相手を紹介した仲人のおじさんと駆け落ちした妹。この婚約は破棄されるのか

https://www.amazon.co.jp/dp/4101184542/
化粧品会社で広報の仕事をする松村
ところで、波には、大学の海洋生物研究所で助手をしている3歳年下の妹・
米粒のようにプックと膨らんでいて、身体の大きさのわりに複眼の黒目が大きいので、なんともいえぬ愛嬌がある。透明な殻で覆われているために、体内のしくみが見える。規則正しく鼓動する心臓も、食べ物が腸を通って肛門から排出されるさまも、すべてお見通し。木の枝のような2本の触角をバンザイする格好で頭の左右に掲げ、ヒュイヒュイ泳いでいる。かと思うと、たちまち泳ぐのを止めて休憩に入り、思いだしたかのようにまたヒュイヒュイ泳ぎ出す。私はミジンコの、このヒュイヒュイぶりが好きである。小さいくせに世界観を持っている。この世に生を受け、終わりを遂げるまで、自分がなにをするべきか、心得ている。そして子供を産み落とすという大役を果たしたら誰にも迷惑をかけず、泣きもわめきもせず、静かに命を閉じるのだ。ミジンコを見ていると、人間なんて生物として修行が足りないとつくづく思う。
男性よりも恋愛よりも、ミジンコが好き。周囲は、碧をそういう娘だと思って憚りませんでした。しかし、碧は陰で鷹野のおじさんと不倫中。「クールな人に限って、激しい恋愛をしているものだ」と後に知人が言う通り、碧と鷹野は駆け落ちし、その事実を初めて知った周囲は騒然となります。しかも、碧は鷹野の子を妊娠していて産むつもりでいるらしいということにも。困ったのは波です。
剛志には相談しにくい。碧に好きな人ができて家を出てしまったことまでは話してあるけれど、その話をしただけで、予想以上に否定的な反応を示した。その剛志に、まさか相手が鷹野のおじちゃまだなんて、とても言えない。鷹野夫婦は私たちを引きあわせた仲人のような存在である。剛志のご家族が不快に思うだろう。私との婚約を考え直すかもしれない。
それでも意を決して波が事情を告げると、剛志は、「どうして中絶させなかったのか」と無神経な言葉を投げつけます。婚約者の冷酷な一面を見てしまった波の、マリッジブルーは収まりません。波はこのまま結婚するのか――。揺れる女性の心を描いた、第15回
『うから はらから』――アラフォー出戻り娘。父の再婚で、11歳年下の義母と32歳年下の義弟ができる? くすくす笑える家族コメディ
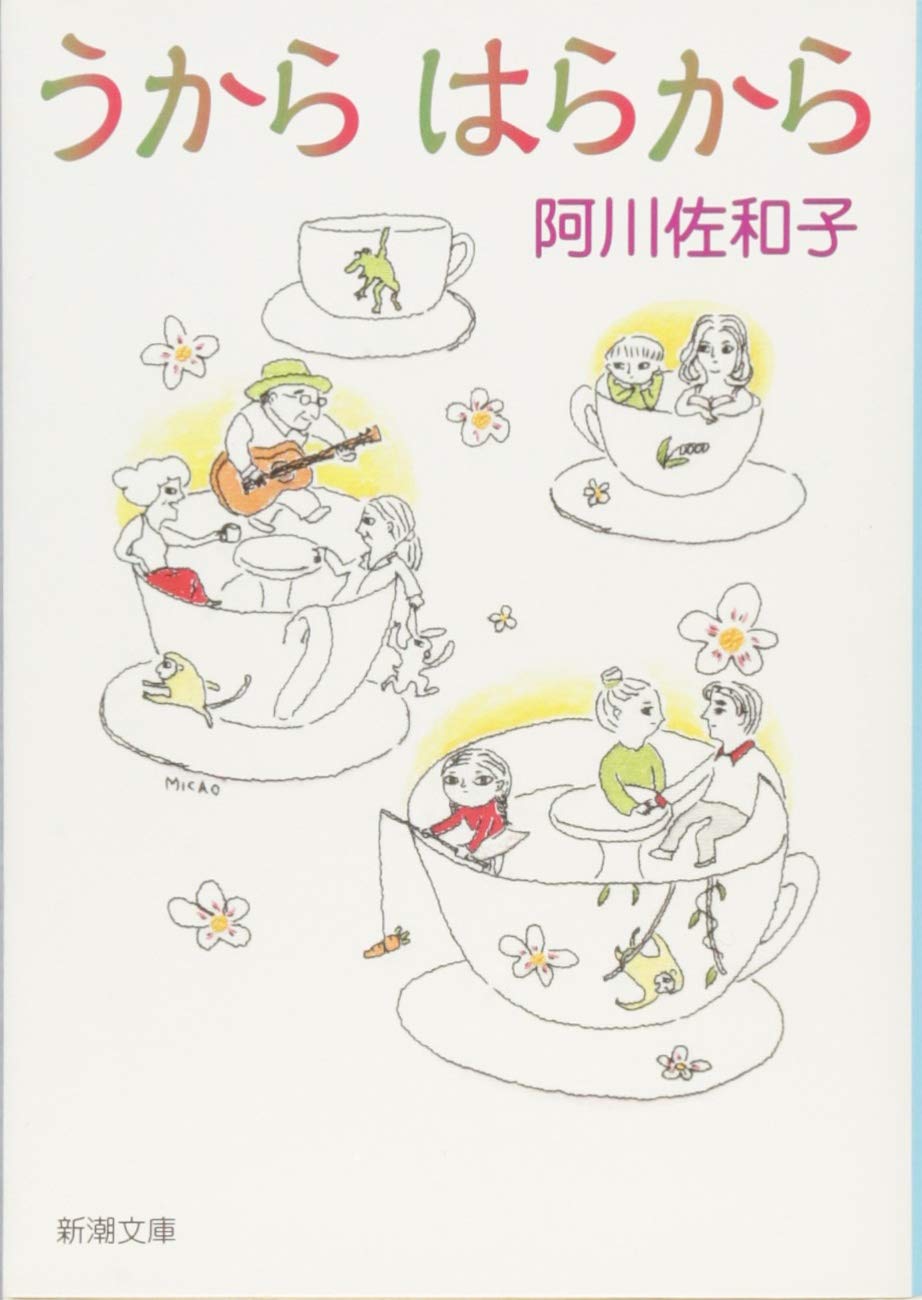
https://www.amazon.co.jp/dp/4101184569/
「あなたが生まれたあと、男の子が欲しいからもう1人作ろうってチチさんにお願いされたんだけど、きっぱりお断りしたの。どうしても欲しかったら、外でお作りくださいませってチチさんに言ったんだけど」
ということは、倫土は父の隠し子なのか。2人を家から追い出そうと躍起になる未来に、小生意気な倫土は、「そうキンキンしてばかりいるとオトコに嫌われるよ」、「ママが結婚したとたん、このおじいちゃん(父)のオムツ替えるのはイヤだからね」。頭の中がお花畑のような麻里子は「
「膵臓ってのはとても謙虚な臓器でね、病気になっても騒いだりしない。心臓とか胃とかは目立ちたがりだから、すぐに痛くなるんだが、膵臓は静かに我慢する。だから病気になっても発見しにくい。しかもだな、身体が死ぬと、自身の酵素で自分を溶かして姿を消してしまうんだ。なんとも奥ゆかしい臓器じゃないか。」
父の、新妻への過大評価に辟易する未来。しかし、未来もあまり父のことを責められたあり様ではありません。というのも、室田と別れて以来、焼けぼっくいに火が付いた未来は、ロバートと並行して、室田ともなし崩し的に肉体関係をもっているから。やがて、妊娠が発覚しますが、どちらの子か定かではなく、シングルマザーになる決意をし、女の赤ちゃんを出産します。この赤ん坊を可愛がったのは、意外にも、11歳にして叔父になった倫土でした。
血なんかつながってなくても、偽家族でも、けっこう楽しいことはいっぱいある。
親族同胞と書いて「うからはらから」と読みますが、いつしか来栖家には、別れた者も、血のつながっていない者も、わだかまりなく集まるようになります。みんなひっくるめて大家族のような大らかさ。そこでは、血縁関係など取るに足らないことと言わんばかりに、みんな楽しそうです。
おわりに
『作家の履歴書』によれば、阿川佐和子は、作家としての自身の弱点を、決定的な負を背負っていないこと――お金に困る、恋愛で手ひどい目に遭う、親に愛されなかった等の不幸な経験がない――にあると分析しています。恵まれた境遇が創作の
初出:P+D MAGAZINE(2022/03/23)

