朝吹真理子のおすすめ5選・境界が溶け出すような世界を味わう

2011年、『きことわ』で第144回芥川賞を受賞した朝吹真理子。その作品は、過去・現在・未来の時空を自在に行き来するものや、自他の記憶やアイデンティティが融合してしまうものなど、独創的な世界観を有しています。デビューから今までの小説3作、エッセイ2作を紹介します。
『流跡』――本の中から飛び出した文字が生生流転して流れ着いた先は? 鮮烈のデビュー作

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101251827/
本の内容が頭に入って来ず、毎日同じページばかり眺めている、という経験は読書人なら心当たりがあるところです。物語の冒頭は次のようにはじまります。
“……結局一頁として読みすすめられないまま、もう何日も何日も、同じ本を目が追う。本のくりだすことばはまだら模様として目にうつるだけでいつまでも意味につながってゆかない。追うばかりで一文字も読んでいない。”
人間によって読まれない限り、本の活字は、紙に付着したシミにすぎません。
“紙片に凝着していた文字の物質であるインクの粒子がくにゃくにゃとふるえはじめ、溶解し、紙片から浸みだしあてどなく四方へ流れてゆく。細胞液や血液や河川はその命脈のあるかぎり流れつづけてとどまることがないように、文字もまたとどまることから逃げてゆくんだろうか。綴じ目をつきやぶってそして本をすりぬけてゆく。流れてゆこうとする。はみだしてゆく。しかしどこへ――”
夢か現か幻か、本の言葉たちは意思を持った生き物のように紙から流れ出し、人間の舞人、船頭を経て、中年のサラリーマンへと融通無碍に変容します。サラリーマンは作中で、以下のような死生観を語ります。
“はやいか遅いかだけで、いずれこの身体も失せる。自分が死んだときの骨の焼け方ばかり考える。高熱によって皮膚のうちにたたえられていた液体がいくらかの水蒸気となり、清潔な
燐酸 カルシウムと細胞のかすもいっしょに煙として吐き出され、誰かがそれを吸う。空気といった流体にこまやかにまぎれ、光の粒子といっしょになったそれを知らずに吸い込む。この身体を構成していた有機的ななにもかもがこまやかに砕けて、目にもとまらない粒粒になってほうぼうに拡散してゆく。それが誰かの唇や頬をなぞったりとりこまれたりして肺にはいったりする”
生と死の境目が曖昧で、命は輪廻転生していくこと、自他の区別があやふやで融解してしまうような感覚が綴られます。著者は自身の生命観について、
“子供の頃から、自分はただ流れ去る一つの生体にすぎないと感じてました。今日に至るまでに沢山の生命体が死んで、まさに今この瞬間にも死んで、生まれつつもある。自分もいつか死ぬし、皆も死ぬんだという大きな流れの中の、一つの生に過ぎないと思えるので安心します”
と、文庫本巻末の対談で述べていますが、そうした考えを作品でも伺い知ることができるでしょう。
物語の筋を説明することが困難な幻想譚ですが、ページをめくるのが惜しいほど透徹した言葉を味わえる、清冽な作品です。
『きことわ』――人間の記憶と夢の曖昧さを、透明感のある筆致で綴った芥川賞受賞作
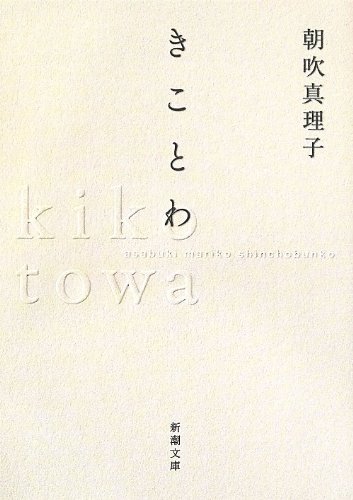
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101251819/
幼少期、葉山の別荘で共に過ごした、別荘所有者の娘・貴子と、管理人の娘・永遠子。別荘が処分されるのを機に、25年ぶりに再会します。共有する思い出、一緒に見たはずの景色……。あの街角にあったのは道路反射鏡だったか向日葵だったか、あの時降ったのは雪だったか凍雨だったか。話せば話すほど互いの記憶の齟齬が浮かび上がります。
“同じ場所の記憶であるというのにおぼえがまるでことなっている。記憶をおぎなおうとして、混乱を来して終わった。結局、互いの記憶の地層は雪崩をおこして年代が失われ、すっかりわからなくなっていた。”
“ふたたびその記憶を呼び起こそうとしても、つねになにかが変わっていた。同じように思い起こすことはできなかった。いつのことかと、記憶の周囲をみようとするが、外は存在しないとでもいうように周縁はすべてたたれている。かたちがうすうすと消えてゆくというよりは、不断にはじまり不断に途切れる。もはやそれが伝聞であるのか、自分の目の記憶なのか、判別できない。”
著者は、『文學界』2021年8月号で、人間の記憶について、
“何を記憶して何を忘れるかはじぶんの意思では決められなくて体がきっと選り分けてるわけだけど、その取捨ってなぞですよね”
と考察しています。
人間の、とりわけ幼少期の記憶は不確かなもので、それが現実の過去なのか、人から聞いた話だったのか、あるいは単なる夢だったのかさえあやふやで、時間の経過とともにたえず化学変化を起こしているようです。また、それらを、誰かの何気ない言葉や風景がきっかけで、前触れもなく思い出すこともありますが、それは自分でコントロールすることは出来ません。本作では、そうした哲学的な思索を、たゆたうような美しい文章で綴っています。
『TIMELESS』――恋愛至上主義・アイデンティティ神話・家族神話を問い直す
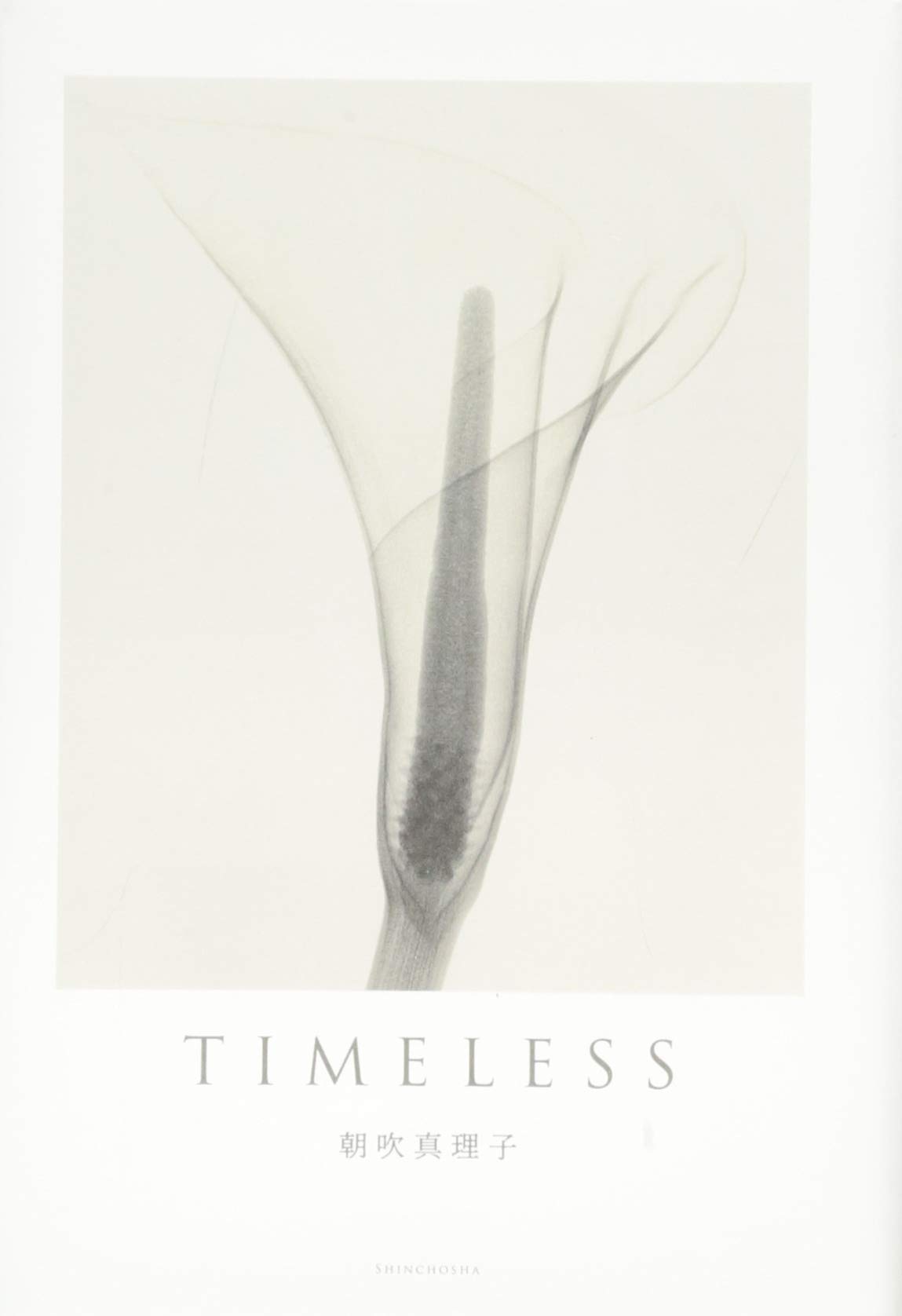
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103284633/
本作のヒロイン・うみは、高校の同級生の男性・アミとの結婚を控えた30歳前の女性。うみは、高校時代の友人たちとのおしゃべりを回想します。
“もしまたべつの生きものとしてこの世にあらわれねばならないとしたら、なにに生まれたい。
私は、クラゲに生まれ変わりたい、と言った。
ひたすら海流に浮遊する。意思らしいものがないところがクラゲの最も美しいところだ。クラゲのように、自然現象として水中にあらわれ海流にひたすら押し流されて死滅する。その、ほがらかな宿命に憧れている。クラゲもひとも、生きものは、死滅することだけは決まっている。それはとても平等なことだ”
根無し草のように生きたいと願う、うみ。人生に対して、無常観ともまた異なる、明るい諦念を抱いている彼女は、自我や欲の薄い、浮遊感のある人物として描かれます。
“アミは高校の同級生だった。アミと私のあいだに、恋愛感情はない。恋愛感情がないことを確認しあって、私たちは夫婦という関係をとりなした。好きなひとと子供をつくるのはこわいというアミに、それならば私と交配しようか、と誘った。アミは肯った”
被爆3世で、好きな人との間に子を持つことにためらいを感じるアミ。恋愛感情のない相手となら子供を作ることが出来ると考えているような、ラディカルな設定です。
“みながしているらしい恋を私はしたことがない。したい、とも思っていなかった。恋もセックスも、どっちでもいい。しなければいけないのなら、林檎農家の人工交配のように、花粉を綿球につけて、それをぽんぽんと雌蕊に塗布して、交配が成功すればいいのに。人を好きになる、という、理屈じゃないなどといわれる行為に落ちることがどうしてできないのか、分からない。しないといけないようなことなのかもわからない。むざんやなあ”
植物は、動物とは異なり、愛情がなくても交配できます。著者は、恋愛至上主義的な価値観に対し、恋愛しない自由があってもよいのではないかと読者に問いかけます。やがてアミは、妊娠中のうみを置いて行方をくらましますが、もともと相手への執着心を持たないうみは、そのことを意に介さず、子どもを出産します。
本作は、2030年代という近未来も描かれますが、その世界では、風邪程度での感染症で人が簡単に死んでしまうという設定になっています。現在のコロナ禍を予言するようで、著者の慧眼が光っています。
『抽斗のなかの海』――本の中の広い海へ、想像力の舵で漕ぎだす。著者初のエッセイ集
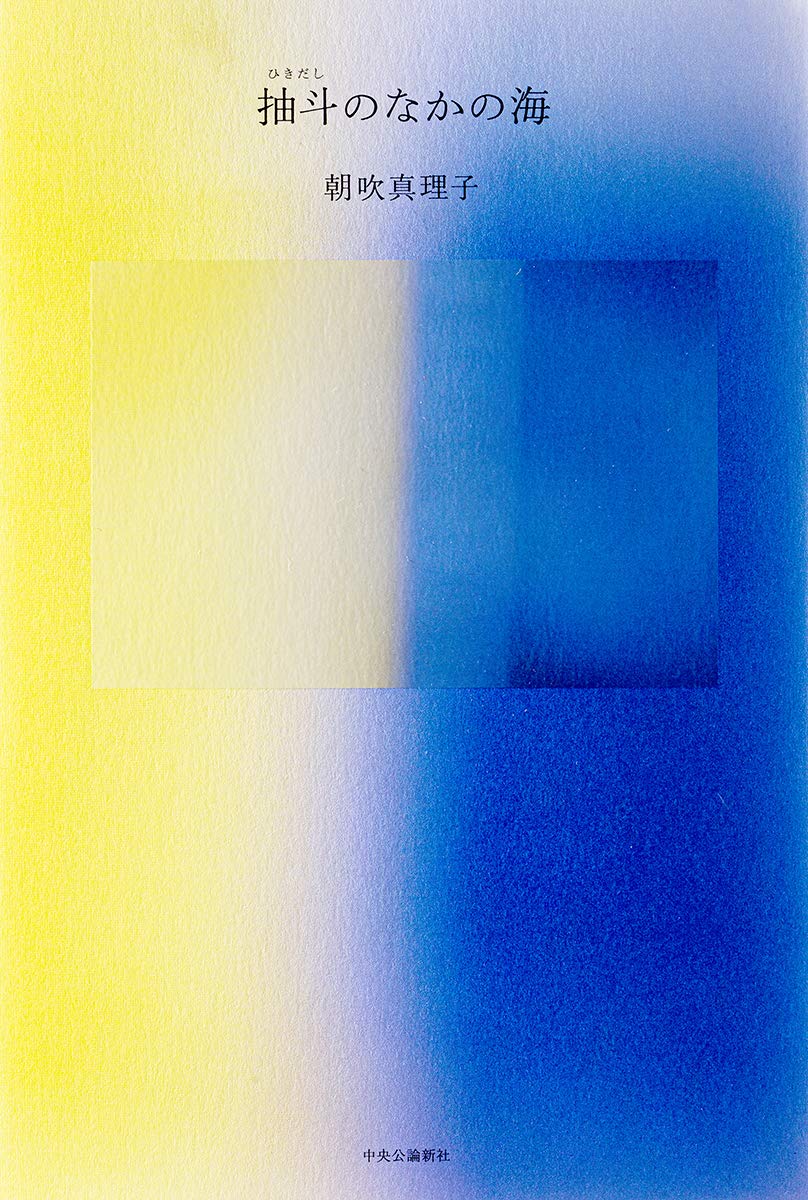
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4120052001/
幼少期の思い出、敬愛する小説家とその作品、家族のことなどを綴った、エッセイ集です。『抽斗のなかの海』という魅力的なタイトルに込めた思いを、著者は次のように説明します。
“なにかを書くときは、果てしない海にむかって、壜を投げるような気持ちでいる。それがいつどんなひとに届くかわからないけれど書いている。机の抽斗で書いたものを保存して閉じるときも、抽斗のむこうに、黒く波打つ海のような四次元がひろがっていると思っていた。「ドラえもん」のなかののび太くんの勉強机の抽斗みたいに、どこか無数のべつの場所と繋がっているような気がしていた。「ドラえもん」の藤子・F・不二雄が提唱したSF(すこしふしぎ)な話が、ふり返ると多い。”
本作でとりわけ印象的なのが、鉱石の雲母に関するくだりです。子どもの頃から雲母が好きだった著者。単に収集していただけなら、何の変哲もない思い出ですが、それだけにとどまりません。
“雲母にもっと近づきたくて、しきりに舌先で舐めてみる。舐めるだけでは近づけない気がして、雲母をひとくち囓る。雲母は脆いからくちのなかで砕ける。細かく歯ですりつぶして思わず飲み込んでしまった。中国では雲母が長生薬のひとつとされていたことを大人になってから知った。白居易も、雲母の粉末を匙で飲んでいる。舌で、雲母の先端を舐めつづけたせいか、私の舌先は、ほんのすこしだけだが、ふたまたにわかれている。”
オーストリアの精神科医・フロイトが提唱する心理的発達理論では、「口唇期」、すなわち、口は人間が快楽を感じる原初の器官であるとされています。ここでは、好きが高じて、舌を通じて雲母と著者自身が同化してしまった様子が描かれます。
“一度だけ、雲母の夢をみたことがある。落葉した並木道を歩いていると、落葉が雲母になっている。裸足の足のうらでぞんぶんに雲母を踏みしだく。雲母は「しゃっくりり、、」という踏み音がした。小学生のときにみた夢の話を、インタビューでしたことがきっかけで、音楽家の小島ケイタニ―ラブさんが、雲母を踏んでみたらいいと、薄くとうめいに剥した白雲母をたくさんくださった。六角形の板状結晶がぎっしり箱につまっていた”
著者が実際に、かそけき雲母を踏んでみたかは、本作で確かめていただくとして、このエピソードそのものが、エッセイを越えた幻想的な小説のようです。
著者の感性を形作ってきた人やものたちを垣間見ることのできる、ファン必読の一冊といえるでしょう。
『だいちょうことばめぐり』――匿名の死者たちの無数の声に耳を澄ませる。第2エッセイ集

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/430902873X/
「だいちょう」とは歌舞伎の台本をさす、「台帳」のこと。著者が学生時代に専攻していた近世歌舞伎の話を交えつつ、日々の思いを綴ったエッセイ集で、白眉は、石川五右衛門についての考察です。
“小さいころから好きな食べもののひとつに天津甘栗がある。天津甘栗が釜のうちで回転しながら焦げてゆくのをみていると、五右衛門のことをいっしょに思う。さいきんはフランチャイズの「ゆであげ」スパゲッティ専門店の看板絵を思いだす。多くの人が今も釜茹でされて死んだことを認識しているのだろう。昔の文献を読んでいると、一概に釜茹でだったとは言えず、天津甘栗のように、ごろごろと熱い鉄の上を転がっていたかもしれないのだった。”
様々な古い文献を駆使して、五右衛門の実像に迫る著者。一般的には大盗賊で極悪人のレッテルを貼られがちな五右衛門に次のように心を寄せています。
“生きるために悪の集団へと堕ちてゆくことは実際によくあったことだと思う。戦のときは重宝したくせに泰平になったら即座に切り捨てるというお上の態度を思うと武装集団が可哀想にさえ思えてくるのだった。歌舞伎座で、桜の散る中、「絶景かな」と声をあげている五右衛門をみると、当時無残に殺されていった、五右衛門に代表された盗人たちのことを、遠くで思う”
甘栗から石川五右衛門へと想像力が縦横無尽に飛躍する、著者の博覧強記にはもはや脱帽です。名もなき多くの死者たちにも、生きている者と同等に人権がある。著者は、そうした今は亡き者たちの声を聞き取るよい耳を持っています。
“京都の寺町通で古文書屋をのぞいていた。黴くさいダンボール箱に、たくさんの短冊がしまわれている。匿名の人々の声が、そこに蓄積している。一枚ずつみてゆくと、のっぺらぼうだった匿名の人たちのやわらかな部分、声や相貌、心の動きが、文字からたちあらわれる。そのなかに「電信機」という題詠の和歌の短冊があった。「たよりなき海の千里の外までもおもふこころのかよふなりけり」。尊政、という人が詠んだらしい。尊政さんの体は消えて、いったいどんな人だったのかも消えていったけれど、彼の心は、紙にずっと残っている”
「古い」ことが、とかく「悪い」と同義語で使われることが多い現代ですが、著者が、古いものへの理解と愛情を持っていることが伺い知れます。
おわりに
研ぎ澄まされた感性と、それを裏付けるたしかな知性。それらを併せ持つ著者は、唯一無二の輝きを放っています。ぜひ、その世界に浸ってみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2021/08/27)

