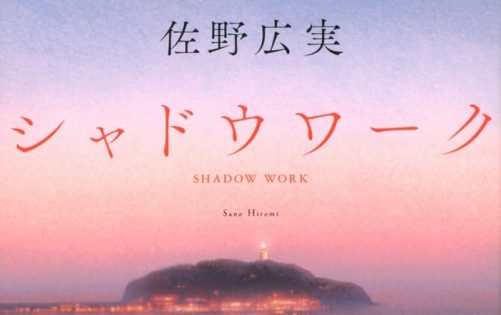【著者インタビュー】佐野広実『シャドウワーク』/江戸川乱歩賞作家がDVや夫の暴力から逃げ回る女性達の問題を抉り出す
傷付いた女達が共に暮らして再起を図る一風変わったシェルターを舞台に、DVの闇を描くミステリー! 創作の背景を、著者に訊きました。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
絶望の果てを見た女達が生きる世界――いま、注目の作家が「DV」の闇を抉り出す
シャドウワーク

講談社
1925円
装丁/welle design 装画/tounami
佐野広実

●さの・ひろみ 1961年横浜市生まれ。横浜国立大学卒。私立中高の国語教師や業界誌編集者の傍ら、99年に島村匠名義の『芳年冥府彷徨』で第6回松本清張賞を受賞し作家デビュー。『聖戦』『上海禁書』『菊の簪』等、歴史小説や伝奇小説まで幅広い作品を発表。20年『わたしが消える』で第66回江戸川乱歩賞を受賞し、佐野広実として再デビュー。前作『誰かがこの町で』のヒット以降、島村作品の復刊や電子書籍での刊行も相次ぐ。「新青年」研究会会員。160㌢、56㌔、B型。
法律やルールとは違う独自の物差しを持ち自分の頭で逐一考え、判断することが大事
舞台は湘南・江ノ電沿線。四方を廊下が囲む間取りが映画『麦秋』を連想させる一軒家を、2020年度の乱歩賞作家・佐野広実氏は、傷付いた女達が共に暮らし、再起を図る、一風変わったシェルターとして描出する。
「今回はDVや夫の暴力から逃げ回る女性達の問題を書こうとしたものの、逃げた先が普通の公営シェルターじゃ面白みがない気もしていて。その時、小津安二郎監督の映画を思い出して、原節子演じる主人公・間宮紀子の実家は使えるんじゃないかって思ったんです」
本作の主人公、その名も〈宮内紀子〉もまた、夫に左脚靱帯を刺されて入院中、看護師の〈間宮路子〉から特別に声をかけられ、江の島を望むその施設にやってきた。入居者は紀子も含め計4人。あとは腰越でパン工場を営む〈志村昭江〉が家主として同居し、同志の路子が時々様子を見に来る程度の文字通りの隠れ家だ。
帯に〈四日に一人 妻が夫に殺される〉とあるが、これは煽りでも何でもなく現実だ。だからこそ「今のままだといつかこうなりますよ」と、著者は彼女達の究極の選択をミステリーに描くのである。
*
99年に島村匠名義で松本清張賞を受賞後、主に歴史物や時代物を10作ほど上梓。そして一昨年、第66回乱歩賞受賞作『わたしが消える』で再デビューした佐野氏は、前作『誰かがこの町で』がブレイク中の話題の人だ。
「内容も地味ですし、そんなに期待もされてなかったと思うんですけどね(笑)。
ただ、反響を見る限り、読者はその架空の町を覆う無言の同調圧力のようなものをリアルに怖れ、共感してくれたらしい。『大昔の因習の村じゃあるまいし』と言う人がいるけど、そうじゃないんです。近代社会にも村社会体質や排他性は尾を引いていて、だから日本は今こうなっている。職場や学校やネット等でも似たことは十分起き得ると、メタファー的に読める作品ではあったと思います」
続く本作は実は乱歩賞候補作を大幅に改稿。DVは
「気づいていないだけで、つい隣にある問題だと思った方がいい時代になっています。ただし、世の中の現象や社会問題として取り上げるだけなら、単に作家が飯の種にしたに過ぎないともいえる。使う以上はその本質に何があるかを見極め、さすがにこれはまずいだろうという、発見や警告に繋がらないと意味がないと思うんです。
旧統一教会の二世問題もそうですけど、日常を否応なく脅かされた当事者には当人しかわからない不安や恐怖や怒りがあるだろうし、今起きている問題の多くは、生活に密着した場所で起きているように思う。だから余計怖いし、しんどいし、それがひいては政治や社会の問題にも繋がってくるという、人間関係や社会の話を私は書いているんです」
3回目の入院後、ついに逃げる決意をした紀子は、都内の公営施設を経てこのシェルターにやってきた。前の施設は期限が2週間で定員40名。対してここでは最大4名がゆったり暮らし、食事係も全て〈持ち回り〉制だ。パン工場の仕事にも就け、無事離婚が成立してここを出るまでには結構な給料が貯められるらしい。
皆でたっぷり食べてよく働き、夕食後はトランプや思考ゲームを楽しむ生活は、暴力を愛情と混同していた自分を省みる余裕を紀子に与え、連帯感もいや増した。全ては20年前にこの元別荘を買い、自立を見守る昭江達のおかげだが、その理想の空間が
本作では紀子の語りと、千葉県警本部から館山署に飛ばされた〈北川薫〉の語りが並走。元警察庁幹部の父を持つ夫のDVを告発し、返り討ちに遭った格好の薫だが、彼女は組織の論理に阻まれようとも断固闘うつもりだ。
そんな中、管内の岩場で変死体があがり、潮の流れや胸のシリコンに着目した薫は、遺体の身元を大井町在住の飲食業〈今井美佳子〉32歳と特定。が、他殺説を一蹴され、またしても孤立した矢先、美佳子のヒモが急死し、自分と似た暴力の匂いを嗅ぎ取った薫の足は、やがて東京湾を挟んだ向こう側、湘南へと向かう。
妊婦や高齢者に席を譲りますか
「特にミステリーの場合は刑事役がいないと何ともなりませんからね(笑)。日本には根強くタテ社会がはびこっていますから、組織の命令や空気に従い、犯罪にすら加担しかねないのは、別に男女を問わない。
つまりDVもパワハラも構造は一緒で、『でも世の中、そういうものだから』と、習い性になるのが一番怖い。本当はどうでなきゃいけないのかを自分で考え、ダメならダメと、我慢しないで言わなくちゃダメなんです。自分の問題なんだから。
もちろん上司や教師もその点は重々自覚すべきですが、例えば世界平和とか、聞こえのいい抽象的な言葉を丸ごと信じちゃうと、微妙な変質に気づけない。
物語後半、ある人が言う。
〈夫や父親だからなにをされても我慢しなくてはいけない、殺されても文句を言うな、そんな馬鹿な話はないわ。法律は殺すなと言うけれど、それは違う。踏みにじられてきた者にとっては、殺されるな、なのよ〉
それは常に命がけで生きてきた彼女達の魂の叫びであり、行動原理でもあった。
「もっと卑近な例で言えば、電車やバスの優先席以外は誰でも自由に座っていいのがルール。でも前に妊婦や高齢者がいた時に、あなたは席を譲りますか、譲りませんかって話なんです。
確かに法的に正しければ何をしてもいいという人はいるし、現に今はそっちの発想が優勢になりつつある。でも法律やルールとは違う独自の物差しを持ち、逐一判断することも、やっぱり大事だと思うんですね。例えば望まない妊娠をした人は全員中絶しろともするなとも、法律で決められるなんて御免でしょ。それは当事者が判断すべき問題で、その分責任は伴いますよという前提で、私は彼女達の決断を書いたつもりです」
紀子と薫、各々の選択を肯定するのも否定するのも読者次第。が、〈法律で裁けない悪意〉と日々向き合う彼女達の「殺すなではなく殺されるなだ」という台詞ほど、深い哀しみや怒りや当事者性をもって突き刺さる言葉もないのは確かだ。
●構成/橋本紀子
●撮影/朝岡吾郎
(週刊ポスト 2022年11.4号より)
初出:P+D MAGAZINE(2022/11/23)