北方謙三著『魂の沃野』(上・下)は壮大なスケールの歴史巨編。著者にインタビュー!
北方謙三が数十年来抱えていた構想がついに結実し、加賀一向一揆を生きた男たちを描くー血潮がたぎる物語が誕生! 「人の生き様を書くのが小説だ」と語る著者。 感動の歴史巨編の誕生秘話をインタビュー。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
加賀一向一揆を生きた男たちを描く血潮が滾る歴史巨編
『魂の沃野』(上・下)
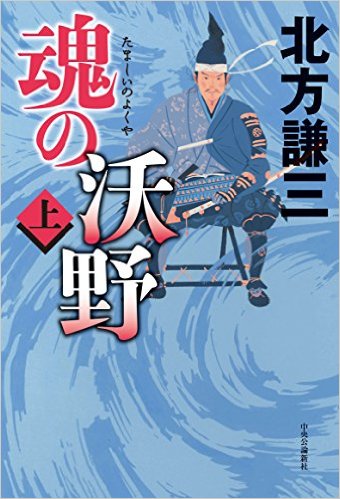
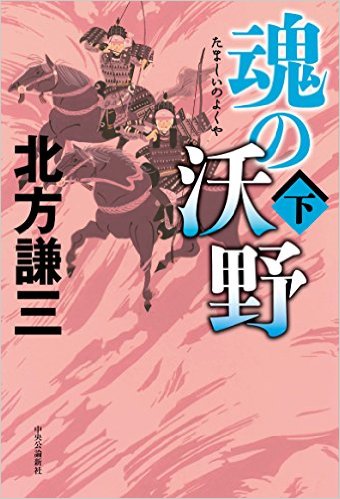
中央公論新社 各1500円+税
装丁/中央公論新社デザイン室
装画/西 のぼる
北方謙三

●きたかた・けんぞう 1947年佐賀県唐津市生まれ。中央大学卒。在学中に作家デビューし、81年、『弔鐘はるかなり』で注目される。83年、『眠りなき夜』で吉川英治文学新人賞。89年、『武王の門』で初めて歴史小説を手がけ、91年、『破軍の星』で柴田錬三郎賞、2004年、『楊家将』で吉川英治文学賞、06年、『水滸伝』で司馬遼太郎賞、11年、『楊令伝』で毎日出版文化賞特別賞、17年の歳月をかけ完結した全51巻の「大水滸伝」シリーズで今年、菊池寛賞を受賞。171㌢、78㌔、A型。
物語の舞台をどんなに広げたって所詮、地球。一人の人間の心の中のほうがずっと無限です
十五世紀末、加賀で起こった一向一揆はほぼ百年続き、「百姓ノ持チタル国」とも呼ばれるようになる。この時代に加賀西部の地侍の家に生まれた風谷小十郎は、本願寺宗主の蓮如とも、守護の富樫政親とも不思議な縁を結ぶ。昨日は味方だった友とも、明日は剣を交えざるをえない戦乱の世にあって、どう生きていくべきか、小十郎は絶えず自問せざるをえない。そのことは彼を、人を惹きつける、スケールの大きな人間に成長させもする。
*
主人公の風谷小十郎の、何ものにも囚われないしなやかなふるまいが魅力的だ。一向一揆という他に例のない史実の中に、北方氏は自身が造型した小十郎という傑出した若者を置き、自在に動き回らせている印象を受ける。
「もしかしたら、そういう名前の人間が実際にいたかもしれないよ(笑い)。あのあたりに、風谷峠や風谷郷という地名はあるんです。地名と人名はだいたい一致しますから、この時代かどうかはともかく、風谷小十郎という人間がいた可能性はあります」
冒頭で、蓮如との出会いが鮮烈に描かれる。十六歳の小十郎は、夜の山を歩いていて不穏な気配に気づく。〈黒い影がひとつ、木に抱きついていた。揺さぶっているようだ。そして泣いている〉。〈熊か。それとも猿か?〉と問う小十郎に、蓮如は〈人間だ〉と答える。型破りな蓮如の個性が、小十郎の心に刻みつけられる。のちに小十郎に送る〈けもののままで、けものではない心を〉という書簡の言葉を、蓮如はみずからここで体現しているようでもある。
「これは史実なんです。木に抱きついて泣くのはおれが考えたことだけど、あの山の中に蓮如がふらっと入っていって、周囲の人に探されるということはしばしばあったらしい。史実は一応調べるけれど、書くときにはいったん頭から拭い去ってそれに縛られないようにすると、蓮如が木に抱きついて泣いてる、ってことになるわけだね」
加賀の一向一揆を描くという構想は長年、温めていたものだという。
「歴史小説を書こうと本を読んで勉強し始めたとき、一番気になったのが独立国のことなんです。日本には歴史上二つだけ存在して、一つは九州に、征西府というのが十年続いている。もう一つが加賀。地の利があって、海の幸、山の幸があり、平野でコメがとれる。そういう場所を自治で百年、守り抜いたというのは大変なこと。
歴史の本にもあまり詳しくは書かれてなかったけど非常に魅力を感じて、その二つを調べたくなった。征西府は初めての歴史小説(『武王の門』)で書いて、日本の歴史を書くのはそろそろ終わりかな、と感じたとき、最後に一向一揆を書いてみようと思った」
守護の圧政に耐えかねて浄土真宗の信徒である百姓たちが一揆を起こす、といった教科書的な見方ではなく、複数の集団間の複雑なパワーバランスによって動いていくものとしてこの間の歴史が描かれている。
〈「加賀は、ひとつの岩ではない。石がいくつも集まっておる。その石さえも罅だらけで、信仰という水が滲みこんでいく」〉
将軍の下での国家統一を夢見る政親でさえもそのことは実感しており、こう語る。だからこそ宗教を恐れ、過剰に反応して力で抑えつけようとする。
中学、高校と、北方氏は東京の仏教(浄土宗)系の学校で過ごした。
「中学生のとき、増上寺の屋根に上って鳩を捕まえたことがあったんだ。屋根から降りたとたん、椎尾弁匡という有名な大僧正のところに引っ立てられていったんだけど、この人はにこにこ笑って『そうかそうか、鳩を捕まえたのか、すごいねえ』って。ただ、帰りぎわに『人間というのは、生きていると何があるかわからない。立ちすくむしかできないこともあるが、そのときはひとことだけ南無阿弥陀仏と唱えてごらんなさい』と言った。その言葉はいまだに頭に残ってる」
念仏の本質はそういうものだと思うと北方氏。この時のやりとりは、蓮如と小十郎の応酬に反響している。
人の生きる様を書くのが小説だ
戦のシーンでは、生身の人間同士が切り結ぶ恐怖がリアルに描かれる。小十郎の陣営に加わった藤次は、初陣で大小便を漏らすが、実戦を重ねるうちに、〈出そうとしても、糞尿など出はしない〉ようになる。後に武名をとどろかす小十郎にしても、初めの戦では、味方に腕を持たれてはじめて自分がふるえていることに気づくありさまだ。
群雄割拠の時代を描くが、作者が複雑な時代背景をわかりやすく説明することはない。
「ここはどこ、いまは何年っていうのは描写じゃない、説明です。できる限り説明は排除したい。小説っていうのは、最初に人間がいて、その人間が立ち上がってくるから読む人も興味を持つ。そうすると背景も少しずつわかってきて、全体の構造も見えてくる。歴史小説の書き方はそうあるべきだと思う」
後世の目で裁くかたちで善悪の線を引くこともしない。歴史では凡君とされる将軍足利義尚も、〈冬の虫と語り合〉うことが好きで、両親となじめない孤独な少年として描かれるし、一揆で打ち滅ぼされる守護、富樫政親もまた、〈心を開いて語り合える相手〉を捜す、一人の青年としてこの場に存在している。
戦乱の世は強者の共存を許さない。状況が変われば、かつてはともに戦った相手と切り結ぶことになり、家臣を死なせないために戦いを避けようとする小十郎も、出陣せざるを得なくなる。
青年の成長物語である『魂の沃野』はまた、喪失の物語でもある。
「青春ってものを考えると、喪失だったなあ、って思うんだよ。大事な友達だってなくしたし、恋人もなくした。純粋なものをいくつもなくしていった。ただ、それが本当に失ったことになるかどうか、というのはその後の生き方による。そういう、人の生きる様を書くのが小説だろうという気がしますね」
全五十一巻の「大水滸伝」シリーズを十七年かけて完成させ、今度は大陸の西に目を向け、テムジン(ジンギス・カン)の物語を描く。
「そんなに土地を広げるんですか? って言われるけど、所詮、地球だろ? おれはSF書けないし(笑い)。一人の人間の心の中のほうがずっと無限の世界ですよ」
●構成/佐久間文子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年11.11号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/11/22)

