【著者インタビュー】中森明夫『キャッシー』/超能力をもつアイドルの愛と復讐を描く
のぼせ症でよく鼻血を出し、周囲から揶揄われていた少女には、ある〈ちから〉があった――孤独のなかでアイドルを夢見た少女の、愛と復讐の物語。アイドル評論の第一人者としても知られる著者・中村明夫氏に、作品の背景を訊きました。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
ひとりのアイドルの愛と復讐―構想7年、執筆4年 アイドル評論の第一人者が描く衝撃と感動の長編小説!
『キャッシー』
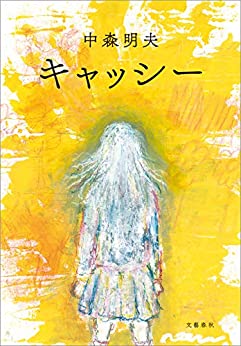
文藝春秋
1800円+税
装丁/野中深雪 装画/のん
中森明夫

●なかもり・あきお 1960年三重県生まれ。15歳で上京し、高校を中退。80年代よりコラムニストやアイドル評論家として各メディアで活躍し、新人類の旗手、「オタク」の名付け親としても知られた。主な著書・共著に『東京トンガリキッズ』『オシャレ泥棒』『Mの世代 ぼくらとミヤザキ君』『アイドルにっぽん』『午前32時の能年玲奈』『青い秋』等。また2010年には初純文学作品『アナーキー・イン・ザ・JP』を発表し、三島由紀夫賞候補に。独身、A型。
誰かが誰かを推し、仮託し、生じるもののある種、祭祀のような熱さを描きたかった
まずは装画のメラメラと黄色く輝く発光体のような、少女の後姿に引き込まれた。
「これは女優ののんさんが描き下ろしてくれたもので、こんな黄色だったのかって、著者の僕も驚きました。
主人公が超能力を発揮する前、世界が黄色く光って見えるというのが、かつてスティーブン・キング原作、ブライアン・デ・パルマ監督の映画『キャリー』(76年)に感銘を受けた僕のアイデアだったんです。でも、小説では黄色は『黄色』と書くしかない。それをここまで精妙で複雑な黄色に描けてしまう彼女自身、闘っていて、のんさんは本当にこの黄色を
アイドル評論家としても知られる中森明夫氏の最新小説、『キャッシー』である。生来のぼせ症で、よく鼻血を出しては
以来〈思念〉の操り方をも会得した彼女は、孤独の中でこう夢見るようになる。〈アイドルになりたい〉と。
*
キャリーと超能力と指原莉乃と―。10年前、あの大杉栄を現代に降臨させてみせた氏にとって(『アナーキー・イン・ザ・JP』)、この三題噺にも似た要素が今作の始点になったという。
「アイドルとは何か、興味のない人に説明するのって実は物凄く難しいんです。
正直、アイドルの多くは歌がうまいわけでも、美人なわけでもない。そんな売れる理由も努力の仕方もわからない中に売れる子と売れない子が出てくる。例えばAKBの総選挙で何度も1位に輝いた指原莉乃なんて、超能力者だとしか言い様がない。目に見えない、人を動かす力の存在を感じたんですね。その力を描くには評論より物語がふさわしく、超能力と言えばやはり『キャリー』だと。少女が覚醒し、自分を虐げた世界もろとも破壊する時のパワーったらなかったし、既に倣うべき古典ですよね。
実は5年前、映画『この世界の片隅に』で声優に挑戦したのんさんと対談した時も彼女をキャリーに
まずアイドルと超能力を結び付けた。さらにはAKBが存在しないパラレルワールドを描いてみようと。ダニー・ボイル監督の映画『イエスタデイ』は、ビートルズの音楽が消えた世界を描いていました。ああ、面白い。発想が近いなって。現実のポップカルチャーを消したり変更したりすることで批評性が際立つんですね」
本書は初章「黄色い目覚め」から終章「饗宴」まで〈おまえが黄色い世界を見ると、真っ赤な血が流れる〉〈キャッシー、おまえは黄色い信号機だ〉との何者かの語りで進み、中3になった彼女が校内の美女集団〈神ファイブ〉に奴隷扱いされ、中でも美しい〈月子〉の〈つまんないの〉という呟きに怯えた日々がまずは綴られる。
月子、火子、水子、木子、金子の5人は、音楽室の向こう側の部屋を〈サロン〉と呼んで私物化。教師も黙るほど君臨していたが、ある時、お茶やお喋りにも飽いた月子は〈透明人間〉に徹するキャッシーに目を付け、様々な屈辱的行為を強いるようになる。
「実はアイドルが出てくる小説って一人称でも三人称でも白けるんですよ。それはアイドルという存在自体が虚構だからじゃないか。それもあって今回はアイドルをめざす主人公に謎の人物が語りかける、二人称を選択しました。
学校にも家庭にも居場所がなく、手首を切ろうとするほど追い込まれた彼女の前にアイドルの神様が現われる場面があります。逆に言うと、そんな幻覚か奇跡を見るくらい酷い目に遭わなければ、キャッシーがここまで怒り、能力を爆発させることはなかったろうし、東京でアイドルになると踏み出すこともなかった。つまり1章の最後で月子たちと対決する河原のシーン、あの熱量を支える神様の存在を信じてもらえるかどうか。それが、2章以降、東京でアイドルへの階段を駆け上り、恋愛禁止のルールを破って札幌に飛ばされもする、彼女の物語を展開する大きなカギでした」
日本人は根っからのアイドル好き
上京したキャッシーが訪れたのは代々木。日本共産党が赤旗を掲げ、予備校やアニメ学校があるこの街に11年、〈YYG24シアター〉は誕生した。〈共産党にとっての革命、予備校にとっての大学、アニメにとっての肉体〉〈代々木は架空の町だ。リアルから遠い妄想の住人たちの場所だ。今、私はその「妄想」に「ユメ」とルビを振ってみたい〉とアイドル評論家中森明
「この代々木論、いいでしょ? 山手線だとちょうど秋葉原の対面で、新宿と原宿の間にあるのに影が薄い感じもいいなあと。そこを拠点にAKBならぬYYGが独自の文化を発信するパラレルな世界を描いています。他方、僕はこの国に古くからあるアイドルの起源にも触れてみたかったんです。天照大神や卑弥呼といった虚実を含む女神を祀ってきた日本人は、根っからのアイドル好きですよね。その古来からの歴史やアイドルの未来までもキャッシーの波乱万丈な人生を通じて描けるんじゃないかなって。
ニーチェが神は死んだと言い、現代は大きな物語が描けなくなったと言われます。だけど、例えばこの物語の世界内ではアイドルの神性が絶対だという約束事を信じてほしい。すると、かつての壮大な英雄叙事詩や、あるいは19世紀のディケンズやバルザックのような波乱万丈の物語の世界に繋がれるんじゃないか。そんな野望もある過剰なエンタメ作品のつもりです。何しろ、伊勢神宮や日本共産党本部、アイドル評論家・中森明
そう。そもそもアイドルとは単体では存在しえない媒体であり、あらゆる力が物理学上そうであるように、その作用は双方向性だ。
「つまり誰かが誰かを推し、仮託し、生じるものがアイドルなんでしょう。ある種、神聖で禍々しい祭祀のような熱さのエネルギーを描きたかった。コロナ禍で世界も日本も疲弊しています。誰もがマスクして家呑みでね。現状では致し方がない。けれど、せめて物語の世界では思いっきり熱いエネルギーを感じてほしい。そんな祈りも込めて書きました」
もう一つの世界。それはいつの世も現実を生き抜くために存在してきたのだ。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2021年2.19号より)
初出:P+D MAGAZINE(2021/02/21)

