五月病の心を軽くする、「カウンセリング本」セレクション

五月病に悩まされがちな季節。今回は、元気が出ないときでも読めて、ページをめくるだけでちょっと心が軽くなるような本を“カウンセリング本”と名づけ、おすすめの書籍を4冊ご紹介します。
「五月病」という言葉があるように、5月はなんだか気分の沈む季節。
新年度から新たな気持ちで仕事や勉強を頑張ってきた方も、ちょっぴりやる気に陰りが見えてきたり、そろそろひと息つきたい……と感じている時期かもしれません。
そんなときこそ、読書の力を借りたいところ。勇気をもらえるようなファンタジーや冒険小説、自分を奮い立たせられるようなビジネス書もいいけれど、元気が出ないときでも読めて、ページをめくるだけでちょっと心が軽くなるような本を探している方も少なくないのではないでしょうか。
今回はそんな本を“カウンセリング本”と名づけ、とっておきの書籍をご紹介します。悩みや不安の原因を探る本から精神科での診療が怖くなくなる本まで、五月病を解消に導いてくれるカウンセリング本の世界をお楽しみください。
精神科にも、もっと気軽に行ってみよう! ──『ラブという薬』(いとうせいこう・星野概念)

出典:http://amzn.asia/5LNR61O
怪我したら病院に行くように、落ち込んだら、すぐ相談に行けばいいと思うんですよ。だって、怪我の専門家は、外科医だし、心の傷の専門家は、精神科医やカウンセラーなんですから。
『ラブという薬』は、小説家やタレント、ラッパーなどクリエイターとしてマルチに活躍する、いとうせいこうが、自身の主治医である精神科医の星野概念と「普段、診察室でしている会話をみんなにも聞いてもらいたい」というコンセプトのもと行った対談を、1冊の本にまとめた作品です。
いとうが星野の“患者”になったきっかけは、いとうが長年続けている音楽活動の場にありました。スタジオで時報の音声を聞こうと117にダイヤルしようとしたとき、間違えて「119」にかけてしまったいとうの姿を見て、同じバンドメンバーの星野は「無意識的に119番を押しちゃったのでは?」と指摘します。
当時、「精神的な危機を迎えていた」と言ういとうは星野の鋭い分析に感心し、星野が勤務する病院に、カウンセリングに通うようになりました。
いとう モノを作って生きていると、精神的な危機って人生で何度かあるものなんだよね。(中略)そのときに「そういうときはカウンセリングを受けるといい」と言ってくれた人がいたんだけど、できなかった。(中略)
日本の場合は特に、なぜ弱音を吐くんだ、なぜ我慢しないんだ、っていうふうに自分でも思いがちだし、他人にも思われがち。だから、いざカウンセリングを受けても、他人にうまく話すことができない。でも、最初はそれでいいんだよね。星野 こと日本においては、今いとうさんがおっしゃったように、精神科に通ったりカウンセリングに行ったりすることが「恥」として認識されているじゃないですか。
いとう 胃の調子が悪いから内科に行くように、不安なことがあったら精神科の人に相談してみるっていうことが、ふつうにあっていいよね。
「不安なことがあったら精神科の人に相談してみるっていうことが、ふつうにあっていい」。そんないとうの言葉通り、本書は、カウンセリングに行くということのハードルをぐっと下げるやさしいアドバイスで溢れています。
いとう 星野くんが考える、いい病院の選び方って何?
星野 (中略)どういう医者ならいいかというポイントを考えると、正直、実際受診してみないとわからないというのが本音です。ただ、勤務医としての僕の単なる主観ですが、個人経営のいわゆる「クリニック」のほうがいろいろな先生がいるような気がします。(中略)
一方、勤務医は診察時間なども含めて病院のルールの中で仕事をします。出来高払いではなく給料制です。だから、突出して素晴らしい治療をしているところは少ないかもしれませんが、ありえない! みたいなことも少なく、平均点は高いと言えます。
カウンセリングを受ける病院の選び方から、実際にカウンセリングではどんなことを話し、どんな治療が行われるかということまで、いとうと星野の実体験に基づいた心の病をめぐる対話は、「ちょっと病院に行ってみたいかも」と考えている人の背中を押してくれること間違いなし。心の調子に違和感を覚え始めた人は必読の1冊です。
ベテラン精神科医の、“悩みすぎ”な日々──『鬱屈精神科医、占いにすがる』(春日武彦)

出典:http://amzn.asia/gWvrrla
誰にでも一度は覚えのある、漠然と不安な気持ち。鬱とは行かないまでも、無力感や不全感でいっぱいになって、何をするにも億劫──という気分のとき、私たちは音楽を聞いたりお酒を飲んだり、人に悩みを吐露したりすることで、そんな状態を打破しようとします。
ベテラン精神科医である春日武彦氏も、慢性的な“不安”に悩まされているひとりでした。そんな彼が現状から抜け出そうと選んだ答えは、なんと「占いにすがってみる」こと。本書では、心の医者である精神科医が、自分自身の心の問題を解決するために街の占い師にかかった日々のことが赤裸々に綴られています。
わたしは右に述べたような「不安感と不全感と迷い」に精神を覆い尽くされた状態に陥っている。生まれて物心がついて以来、ずっとそんな調子であり、心の底から笑ったことなんて一度もない。しかもここ五年くらいが、ことさらに不調である。幸か不幸か、うつ病というわけではない。性欲や物欲のあるうつ病は、医学的にはあり得ない。診断的には、パーソナリティーの問題といったあたりの話になるだろう。つまりこの苦しさは自己責任ということになる。神も仏もない。
自分を善人とは思わないが、ことさら悪人とも思えない。自己評価としては、小心者で世間知らずのプチ自己愛人間である。
……そんな皮肉めいた独白から始まるこの本は、ほとんどすべてのページが春日の私小説的な自己分析や内省に費やされています。カウンセラーにかかるのを「同業者に悩みを打ち明けるのは気が進まない」という理由で諦めた彼は、“居直り”と称して、インターネットで見つけた占い師のところに足を運んでみます。
運勢の周期について占い師は語り出した。(中略)当方は現在、最底辺の<衰退期>に位置しているらしい。それが「定め」であり、あと数年しないと、自分の思い通りの人生には近づかないらしい。
「運気が循環するっていいますけど、ここ数年は低迷し滞ったままなんです。動きが実感出来ればツキを待とうと我慢もできましょうが、どんよりと停滞してどうにもならないから辛いのです。もしかすると、もっと悪い状態になっていく可能性だって否定できない気がするなあ、今が最底辺という保証がないんだから」
「あなたはそう感じていらっしゃるかもしれませんが、九年周期は真実として受け入れたほうがいいですよ。停滞しか感じられない閉塞感こそが、まさに最底辺の時期にある証と考えていただきたいですね」
「この先数年も耐えろなんて、暴力みたいなもんだなあ」
春日は終始こんな調子で、愚痴とも悩み相談ともつかないような自分の心の状態を何人かの占い師に語り続けます。
占い師のことを馬鹿にしたり疑ったりしながらも、時折うっかり占い師の前で涙をこぼしてしまう彼の姿は人間臭さに満ちていて、シニカルで厭世的でありながらもどこか憎めない春日の人物像が、読めば読むほどくっきりと浮かび上がってきます。
日頃悩みがちな人ならば強く共感できるのはもちろん、普段あまりウジウジと悩むことはない人も、「考えすぎ」な人の思考を盗み見る気分で本書に手を伸ばしてみるのがおすすめです。
これからの「うつ社会」を生き抜くためのヒント集──『心の深みへ 「うつ社会」脱出のために』(河合隼雄・柳田邦男)
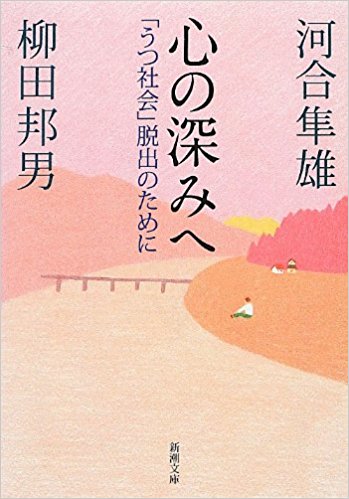
出典:http://amzn.asia/6XQtBfH
『心の深みへ 「うつ社会」脱出のために』は、数多のカウンセリングを手がけてきた臨床心理学者の河合隼雄とノンフィクション作家の柳田邦男が、心にまつわるさまざまな問題について自由に議論を繰り広げた対談本です。
本書では、実際に河合が患者と交わした会話や柳田が取材した事件といったエピソードを交えながら、「死」の扱い方、宗教について、これからの時代の生き抜き方──といった幅広いテーマが、多角的な視点で語られます。
柳田 最近、デス・エデュケーション、つまり死に備える生き方について学校教育や社会教育の中で取り組むべきだという動きがありますが、昔なら、自宅の畳の上でおじいさんやおばあさんが死ぬ、あるいは父や兄弟が結核で死ぬというように死が目の前にあったので、自然な形で死への備えを学ぶことができた。しかし、いまはほとんどの人が病院で死にますから、そういう状況がなくなった。だから、肉親の死に対しても、自分自身の死に対してもどう対処していいかわからない。(中略)
極端な話になるけど、小学校教育の中に死の現場を見学するというのがあってもいいと思っているんです。
河合 二○世紀は(中略)近代科学的な方法が相当なところまで進んだんですから、次の二一世紀は”ちょっとそれを反転させた時代にしないとおもしろくないと私なんかは思うんです。柳田さんがそのあたりをうまく表現されて、「二・五人称の視点」と言われていますが、そうした姿勢、人間関係がこれからとても大事になると思いますね。
柳田 困っている人や被害者や、病気の人たちに寄り添う気持ちを漠然とではなくて、意識的にももとうという意味で、私は二人称、つまり肉親の心情に近づくと同時に、専門家という三人称の冷静で客観的な判断をできる「二・五人称の視点」を提言しているんです。
……こんな風に、河合と柳田が語り、提案するしくみや考え方は、時に斬新で過激ですらあります。しかし、人生100年とも言われるこれからの時代を道しるべなしに生きる私たちにとって、大きなヒントにもなりうる言葉が本書には溢れています。
ふたりの議論は非常に真摯かつ白熱しており、もしかすると、読むだけでホッとできるような1冊ではないかもしれません。しかし、“生と死”や“心のあり方”について真剣に考え、自分の心と向き合いたくなったときには、ぜひ手を伸ばしてみてほしい名著です。
あの人もこの人も「鬱」だった! ──『サブカル・スーパースター鬱伝』(吉田豪)

出典:http://amzn.asia/dCzWfRP
リリー・フランキー、大槻ケンヂ、松尾スズキ──。これらの文化人たちは、皆鬱(あるいはうつ状態)になったことがあるという共通点があります。そんなサブカルチャー界の重鎮たち11名に、プロインタビュアーの吉田豪が「サブカル男は40歳を超えると鬱になる」というテーマで取材をしたインタビュー集が、『サブカル・スーパースター鬱伝』です。
本書に登場する“スーパースター”たちは皆、自分が鬱状態にあったときのことを赤裸々に語ります。例えばリリー・フランキーは、「鬱は大人の嗜み」とユーモラスに表現しながらも、
一番最初にこいつクオリティ落ちたなって気づくのは、編集者でもなく自分なんだよ。それに気づいたとき鬱が始まる。
鬱にならない人って、自分はいいものを書いてるつもりで、「寒くなったな、あいつ」って言われてるのを知らないまま一生生きてく。そんな人、いっぱいいるでしょ。
……と、文筆家にとっては死活問題である文章のクオリティに対するシビアな視点が、自分の鬱につながっていたと鋭く分析します。
また、離婚などのプライベートの問題が重なった時期に鬱状態に陥ってしまったという松尾スズキは、
(舞台を)やってるときは無理やり気持ちを上げるから忘れられていいんですけど、現実に戻ってきたときの揺り戻しがキツいんですよね……。もう何度空っぽのバスタブの中で泣いたことか。
と鬱のときの辛い心境を語り、さらには、松尾の小説の読者からの心ない声に追い打ちをかけられたと話します。
「つらいときこそ書くのが作家なんじゃないか」とか、死者に鞭打つようなことを(笑)。ホント、そういうこと言うヤツって何様だと思うよ。喫茶店だって「店主が病気なので休みます」みたいにやるじゃない。
「あの人も鬱状態になったことがあるのか」という驚きは、自分もいつかそうなるかも……という恐怖よりもむしろ、誰しも悩みや不安を抱えているという強い共感に結びつきます。本書は鬱を経験したことがある人はもちろん、漠然とした不安に日々悩まされている人にも、読後「不安なのは自分だけじゃない」と思えるようになる良書です。
おわりに
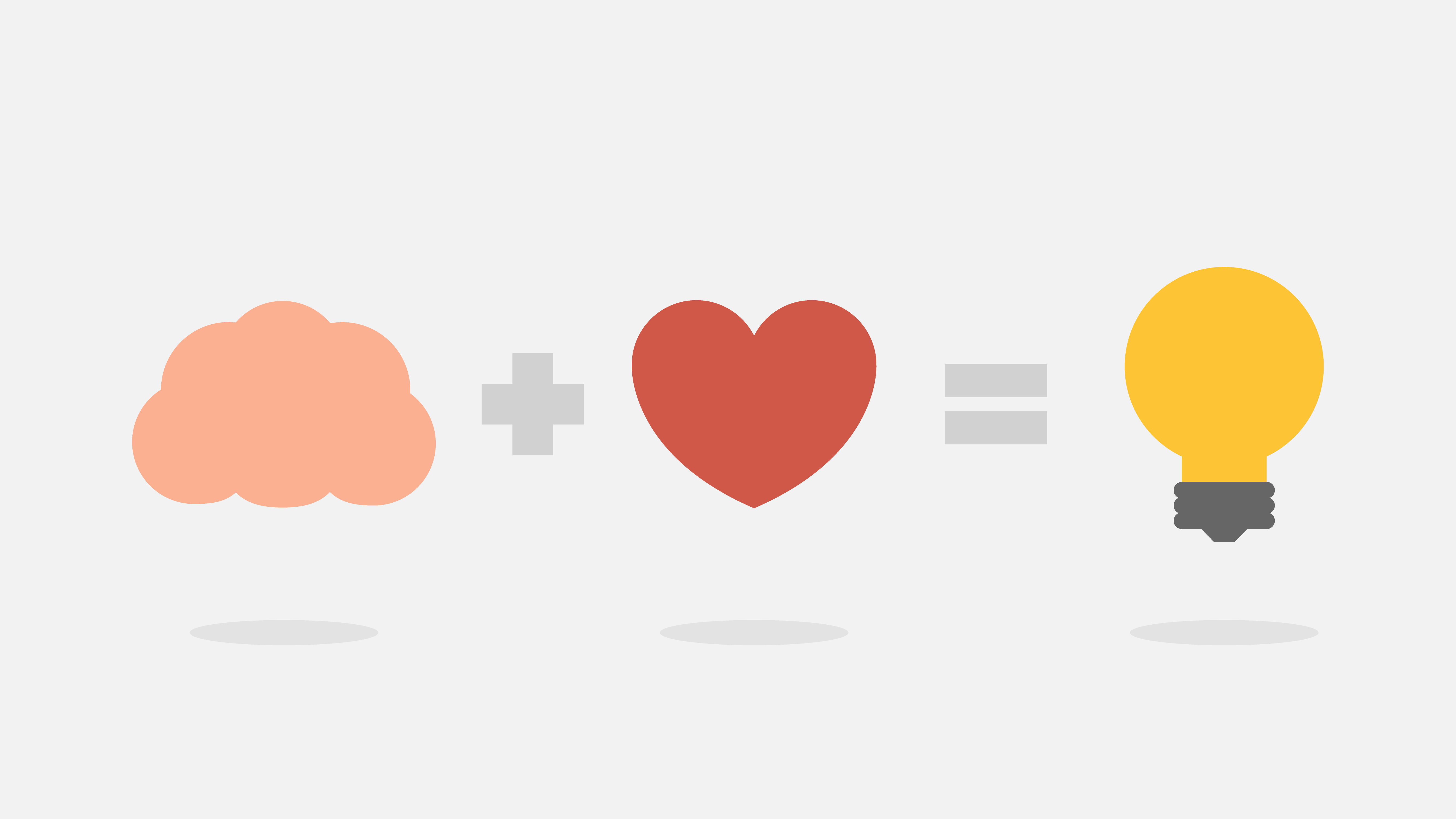
親しい友人に相談してみる。精神科にカウンセリングに行ってみる。あるいは、嫌なことは忘れて寝てしまう──。自分の心の悩みとの付き合い方はさまざまですが、強い不安の中にいると、そんな選択肢すら見えなくなってしまうもの。
今回ご紹介した本のページをめくりながら、自分の悩みにはどんなアプローチが合いそうか、自分に似合う洋服を選ぶような気軽な気持ちで考えてみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2018/05/23)






