明るい介護小説 超高齢化社会の必読書4選

超高齢化が進む現在。介護は、する立場でも、される立場でも、避けて通れない問題になっています。従来、介護を扱った小説というと、暗くて辛いというイメージが強かったのですが、今回それとは反対に、読むと笑えて元気が出るヒントの詰まった小説やドキュメンタリー4選を紹介します。
林真理子『我らがパラダイス』~高級老人ホームと安価な介護施設での高齢者すり替え事件~

https://www.amazon.co.jp/dp/462010826X
超高級老人ホームで働くアラフィフ世代の女主人公。自身の親が、そこよりもっと劣悪な施設で介護を受けているのと比べ、富裕層への羨望が抑えきれなくなった彼女がとった衝動的な行動とは……? 著者は、多くの女性から共感と支持を集め続けている人気作家・林真理子です。
入居に8000万円かかる介護付きマンション「セブンスター」で働く邦子。離れて暮らす実父が呆け始めたと、父と同居する兄から連絡を受けます。舅の介護を拒否する兄嫁に代わり、父をしばらく預かってほしいと押し付けられた邦子。そのことを職場の先輩・さつきに相談すると、思わぬ返答が。
「知ってる? ここはね、部屋がいっぱい余ってるのよ。私いつも思ってる。ああ、ここに自分の親、連れて来たいって。日本で最高の施設に勤めててさ、こんなところに親を住まわせられたらどんなにいいだろうって。従業員が勝手に鍵を開けるのは本当はいけないんだけど、私はここ古いし、時々、(部屋を開けて)風を入れてくれって頼まれてるのよ」
さすがにそれはまずいと、たしなめる邦子。しかし、さつきは一向に気にせず、邦子の父をセブンスターに入居するよう手引きするのです。けれど、秘密裏にうまく運びかけた計画は、邦子の父が誤って部屋の非常ベルを押してしまったことで、あっけなく上司にばれてしまうのでした。悪事が露見すれば、邦子とさつきは解雇されるでしょう。実際、上司の岡田は、邦子とさつきを叱責します。
これは犯罪でしょ。警察沙汰になってもおかしくない。セブンスターに入居する人たちは、人生の成功者だ。若い時から頑張って高い地位と収入を手に入れた。一生懸命働いた人たちが、快適な老後を送りたいって、あたり前の話でしょう。それを、何も努力しなかった連中がさ、いざ年をとって困ってます、何とかしてください、格差反対なんて言うのはさ、ものすごく図々しいよ
岡田の言い分に傷つき、腹を立てる邦子とさつき。彼女らの親たちもまた、精一杯働いてきたのです。仕事がたまたま時流にそぐわなかっただけで、決して適当に生きてきたわけではない。解雇されそうになった彼女らは、本来、妻以外の女性とは同居できない施設において、愛人を連れ込んでいる男性がいることを口外しないことと引き換えに、雇用の継続を取りつけました。そして、空き部屋に親を連れ込むよりも、もっと巧妙な手口を思いつくのです。
(セブンスターに入居する)星野さんに家族はいない。誰も見舞いに来ない。呆けて寝たきりの人は別にどこの施設でも同じだろう、こんないいところに住む必要ないって。だからその人(星野さん)に、うちの親が行くはずだった安い施設に行ってもらった。その代わり、うちの親がこっちに来たってわけ。私、一矢をむくいたい。一生懸命生きてきた親が、ないがしろにされる世の中が許せない。年をとればとるほど、こんなに差が広がる世の中、ひどいなあって
自分の親をどうしてもセブンスターに入れたいと思った主人公が、認知症で身寄りもなく、状況判断の出来ない利用者と、自分の親とを内密にすり替えるという、介護を扱った小説でも、深刻にならず、読者の好奇心を満たしてくれるエンタメ仕立てなっているところは、著者の本領発揮といえそうです。
阿川佐和子『ことことこーこ』~老齢の親を持つすべての人へ。実践的介護入門小説~
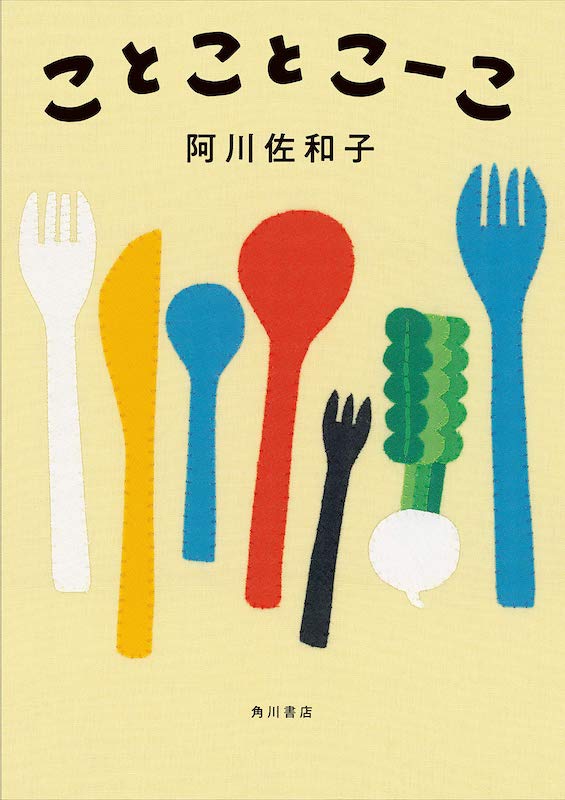
https://www.amazon.co.jp/dp/4041071011
夫に先立たれた70代の独居母のもとに出戻ったバツイチのアラフォー娘。母と娘が逆転したかのような日々の暮らしをコミカルに描きます。著者は、大ベストセラーエッセイ『聞く力』でお馴染みの阿川佐和子。
買って来たバナナを冷凍庫に入れる。銀行でおろしたばかりの10万円をどこにやったか分からない。「その話、何度も聞いた」と指摘すると泣き出す。71歳の母・琴子の呆けは、次の出来事で決定的になります。
仏壇の前に置かれた父の遺骨を目敏く見つけた。
「あら」トコトコ近寄って、何をするつもりかと思いきや、「これ、なあに? どこかへ片付けた方がいいんじゃない?」と言った。
「やだ、母さん。これは父さんのお骨だよ。母さんったら、しっかりしてよ。父さんは死んじゃったんだよ。今日、お葬式して、火葬場にも行ったでしょ! 覚えてないの?」
「そんな怖い顔で怒らないでよ。私はまた、なんの荷物が届いたのかと思っちゃったのよ。この四角い箱はなあに?」
「お父さんのお骨。宅配便の荷物じゃないんだよ!」
「佐藤晋さんって、死んだんだっけ?」
母を、病院の「もの忘れ外来」に連れて行った娘の
香子は、介護の先輩でもある友人らに話を聴きます。返って来た答えは、
「朝ご飯に何を食べたか忘れるっていうのは、単なる物忘れ。朝ご飯自体を食べたか食べなかったか忘れたら、それは認知症」
「一人で抱え込んだらこっちが壊れるよ。巻き込むの。あらゆる親切な人に頼るのよ」
「仕事と介護と更年期障害。災難ってさ、小出しでは来ないのよ。だいたい一気にドッカーンって襲ってくる」
「呆けた親を引き取るのは、(子どもたちのなかで)先に手を挙げた方が負け」
などという、実感の籠もったものばかりでした。
香子は、母の面倒を一人でみきれず、別所帯を持つ弟に相談します。すると、弟は、「母さん自ら、施設へ入りたいと、ちょうど自分のところへ電話があったばかりだ」と言い、母を施設に入れる計画を強引に進めようとします。ところが、香子が母にそのことを確認すると、母は「そんなこと、言ってない」の一点張り。母の物忘れがひどいのをよいことに、弟が嘘をついているのか、それとも、母は本格的に呆けてしまったのか。
本作のもう一つの読みどころは、介護に役立つ実践的知識が豊富に盛り込まれている点です。何度も同じことを聞いて来るお年寄りにイライラしないですむ方法から、デイサービスに行き渋る老親が喜んで通ってくれるようになる必殺技まで、介護をする人誰もが知りたいと思う答えがちりばめられています。
中島京子『長いお別れ』~認知症になることは、ゆっくりとさようならをしてゆくことだ~

https://www.amazon.co.jp/dp/4167910292/
認知症になった70歳の男性が80歳で亡くなるまでの10年間を、家族の視点でつづります。著者の中島京子は、『小さいおうち』で第143回直木賞を受賞した家族小説の名手。本作において、第10回中央公論文芸賞、第5回日本医療小説大賞を受賞しました。
元学校長にして図書館長、自他ともに認める謹厳実直な
たとえば、30半ばの独身の娘・芙美は父とこのようなやりとりをします。
「お父さん、わたし、また(交際していた男性と)ダメになっちゃったんだよ」
「そう、くりまるなよ」
「来ないよ。(彼からの)連絡なんて、来るわけない。だって、向こうはもともと」
「そりゃあなあ、ゆーっとするんだな」
「ていうか、意味不明」
なんだかわからないけど、とりあえず「ゆーっと」してみよう、と芙美は思った。芙美はティッシュペーパーをつかんで鼻をかんだ。
今まで、厳格な父相手に、恋愛の話などしたことがなかった娘。父が認知症になって状況が分からなくなったからこそ、初めて自分の気持ちを吐露できたのです。「くりまるなよ」、「ゆーっとするんだな」という父のアドバイスは言語不明ですが、それでも気持ちが通じたと娘は感じます。父と娘が新しく出会い直したといえるシーンです。
また、妻は夫について次のように分析します。
夫が認知症になったというと、人は気の毒そうに声をかけてくる。(もう、あなたのことも誰だか忘れちゃってるんでしょ? たいへんねえ)。ええ。忘れてますとも。夫は妻の名前を忘れた。それでも夫は妻が近くにいないと不安そうに探す。妻という明確な単語で意識しているかは別として、よく見る顔であり、自分の人生に欠くべからざる人物だということだけは自明の女性(として)
妻だという記憶は失っても、人としての感情は損なっていない昇平は、妻が病気になればいたわりの手で撫でさすろうとするのであり、妻はそれで満足なのです。
昇平の介護に当たるヘルパーたちは、
認知症老人を子供扱いしたり、何も分からない老人として扱ってはならない。QOL(クオリティ・オブ・ライフ)、人が自分らしく生きていると感じることのできる質的な幸福度をなによりも大切にしたい
との信念を持ち、最期まで介護される側が人間としての尊厳を保てるよう気を配ります。
そもそも、親が認知症になることと、突然死するのでは、どちらの方がつらいのでしょうか。高齢者はよく、「ポックリ逝けたら幸せ」と言いますが、残された家族にとっては悔いが残るものです。小説のラストで、認知症の新しい定義づけがなされます。
「認知症を(アメリカでは)『長い(ロング)お別れ(グッドバイ)』と呼ぶんだよ。少しずつ記憶を失くして、ゆっくりゆっくり遠ざかって行くから」
認知症になることを、必要以上に悲観せず、お別れするまでに心の準備をする時間が与えられる、と捉える新しい介護小説です。
信友直子『ぼけますから、よろしくお願いします。』~5人に1人は呆ける時代。呆けることをもう怖がらなくてもいい~
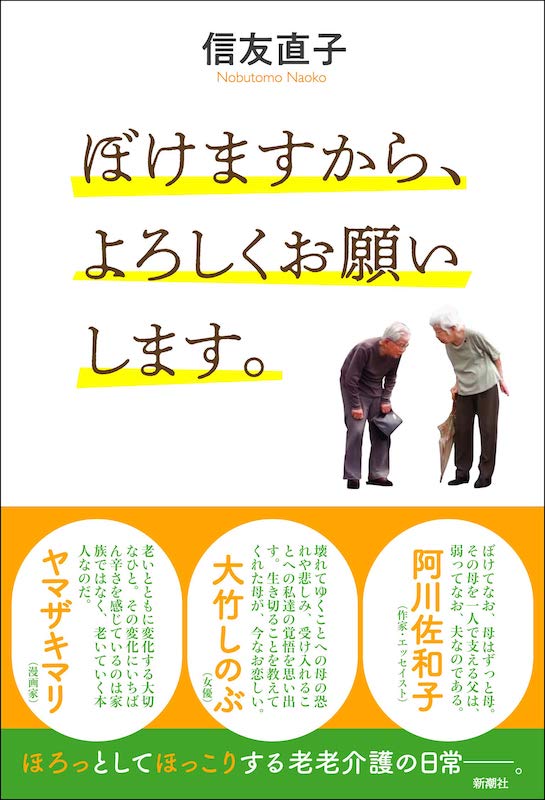
https://www.amazon.co.jp/dp/4103529415/
93歳の夫が85歳の認知症の妻を一人で世話する老老介護を、離れて住む娘の視点から綴ったドキュメンタリーです。著者の信友直子は、映像ディレクターとして、これまで多くのドキュメンタリー制作に携わってきました。
本作のタイトルにもなった「ぼけますから、よろしくお願いします。」とは、認知症が進行しつつある著者の母が、実際に言った言葉です。この言葉からも分かるように、母は自分の病状を分かっています。
ある夜、食卓に一人座る母の後ろ姿にハッとしました。母は、自分の飲んでいる薬「メマリー」の説明書きを読んでいたのです。そこには「認知症症状の進行を抑える薬です」と書かれています。背中を丸めて、その紙をじっと見ている母。私は、見てはいけないものを見てしまった気がして、そっとその場を離れました。涙があふれてきました。母はおそらく、何度かこうやって薬の説明書きを見ているんでしょう。自分が認知症だということを自覚して、気になって。自分がおかしくなっていることは、自分が一番よくわかるはず。一番苦しんでいるのは、母、本人なんだ。
認知症にかかって壊れてゆくこと。その変化を悲しむのは周りの人たちであり、本人の自覚は薄い、というのが従来の認識でした。けれど、一番辛いのは本人であるということを、具体例を挙げながら示した点に、本書の新しさがあります。
認知症を遅らせる薬「メマリー」の効果と副作用についても、つぶさに記録します。
母は「ふらふらする」と言いながらも薬には慣れたようですが、顔がむくんでいるのが気になりました。物忘れに関して言えば、効いているのかいないのか。でもひとつ、明らかによくなってきたことはありました。父曰く、「おっ母は、前はわしの言うことにいちいち突っかかりよったが、最近はそうでもないわ」そうなんです。母は性格的に穏やかになってきたようで、昔のような冗談を言って笑う楽しい母がだんだん戻ってきたのです。これが薬の効果であれば、母のためにも、そして母と24時間向き合って暮らす父のためにも、ありがたい変化です
介護離職しようか迷う娘に対して、頑なに老老介護を続けようとする父。ヘルパーに頼まなくても大丈夫だと言い切る母。老親の自尊心を傷つけないかたちで、いかにサポートするか、著者の模索は続きます。
超高齢化社会、誰もが呆けることを恐れています。けれど、「ぼけますから、よろしくお願いします。」と茶目っ気たっぷりに言えたらどれほど楽になれるでしょうか。そう言える相手がいる人は幸せかもしれません。
おわりに
ここで紹介した作品の著者たちは、皆、実際に親の介護を経験しているだけに、説得力のある作品となっています。今、介護に直面している人には、共感できる箇所が多いでしょう。これから介護をする人にとっても、よい参考書となるはずです。
初出:P+D MAGAZINE(2021/06/14)

