川上弘美のおすすめ作品4選・生き物の息吹を読みとる

芥川賞作家にして、現在、芥川賞選考委員を務める川上弘美は、「春の夜人体模型歩きさう」(句集『機嫌のいい犬』より)という俳句を詠んでいることからも伺えるように、元・高校の生物教師という経歴の持ち主です。彼女の小説には、多様な生き物が登場し、それは人間と同等な存在として描かれます。今回はおすすめ作品4選を紹介します。
『蛇を踏む』――踏んだ蛇が人に化けた。蛇と人の共暮らしを描く芥川賞受賞作
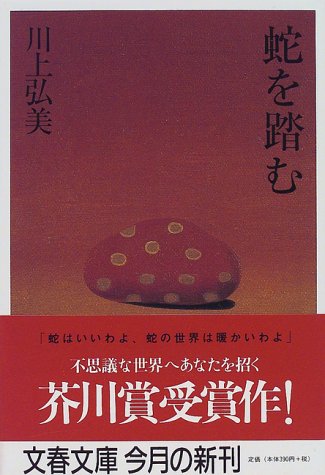
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4167631016
本作の語り手は、年若い女性・ヒワ子。物語は次のように始まります。
ミドリ公園に行く途中の藪で、蛇を踏んでしまった。
ミドリ公園を突っ切って丘を一つ越え横町を幾つか過ぎたところに私の勤める数珠屋「カナカナ堂」がある。カナカナ堂に勤める以前は女学校で理科の教師をしていた。教師が身につかずに四年で辞めて、それから失業保険で食いつないだ後カナカナ堂に雇われたのである。
蛇を踏んでしまってから蛇に気がついた。秋の蛇なので動きが遅かったのか。普通の蛇ならば踏まれまい。蛇は柔らかく、踏んでも踏んでもきりがない感じだった
その後、蛇は女に化けてヒワ子のアパートについて来ます。「あなたは何ですか」と問えば、「あなたの母です」と言い、ヒワ子の一人暮らしの部屋で掃除に炊事に、世話を焼きます。本作の特筆すべき点は、蛇がなぜ化けたり話したりするのか、説明が潔く省かれていることと、蛇が家に居つくことに作中人物の誰も驚かない点です。ヒワ子が事の顛末を勤務先の主人や寺の住職に話すと、彼らの家にも蛇はいて、厄介払いをすると身内に不幸が起こるとか、蛇女房は働き者でよいとか、肩透かしのような言葉が返ってくるばかり。そして、ヒワ子自身、突飛な展開を訝しんではいるものの、淡々と蛇を受け入れて暮らし始めます。著者は、「赤蟻に好かれしぶしぶ這はせたる」(句集『機嫌のいい犬』より)という俳句も詠んでいて、そこからは、生き物をむやみに排除しないという考えが伺えます。
「ヒワ子ちゃんはどうして教師をやめたの」
「消耗したからかもしれない」
教師に対して生徒が何か求めてくることは少なかったが、求められているような気がしてきて、求められないことを与えてしまうことが多かった。与えてからほんとうにそれを自分が与えたいのか不明になって、それで消耗した。与えるという気分も嘘くさかった。
孤独で厭世的な気分になっているヒワ子に対し、「あたたかい蛇の世界においで」と誘う女。反射的に拒むヒワ子に対して、女は容赦がありません。
引出しを開けると蛇が何匹も這いだした。私の腕から首をのぼり耳の中に入ってくる。外耳道に入り込んだ途端に蛇たちは液体に変わって奥に流れこむ。蛇を阻止しようとして首を強く左右に振った。耳の奥で水に変わった蛇が
粘 稠 性を増しながら内耳に向かう。ねばねばした水が三半規管のあたりを満たす。耳小骨を取り巻く。耳が蛇でいっぱいになり何も聞こえなくなる
蛇が異質な他者を暗喩しているならば、他者とつながる、ということが、言葉で言うほどたやすいことではないという読みができるかもしれません。一説によると、蛇は古来より母性のシンボルとも言われますが、(吉野裕子『蛇 日本の蛇信仰』より)ヒワ子は「蛇の世界」へ行くのでしょうか。
『龍宮』――もぐら目線から見た人間社会のおかしみをシュールに描く
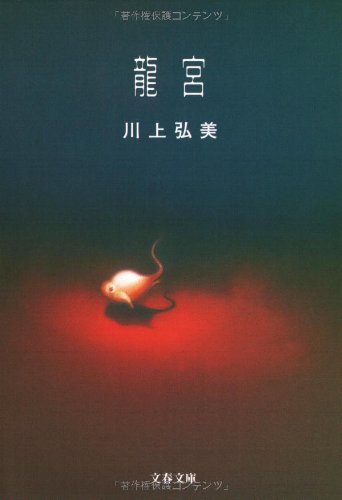
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4167631040/
本作は、蛸、河童など動物を主役にした奇譚集ですが、その中の一編「
鼹鼠は、人間の勤める会社へも通います。
近年入社してくる若い人間たちなどは、私の姿が自分たちとずいぶん違うことにも気がつかないようだ。異形のもののことを、あえて忖度しない、というよりも、気に留めようともしない、らしい。「かなり、毛深いんすね」と言われたことくらいはあるが、あからさまに凝視されたり、出自を問い詰められたり、ということもなくなった。十年ほど前までは、口さがない人間も多かったのだが
昨今の若者の、他者への関心の薄さを指摘する鼹鼠。また、昼休みに公園で弁当を食べていると、ホームレスと出会います。
「あんた人間じゃないだろ」
ダンボールにくるまった人間は私の手や足や顔をじろじろ見ながら言う。会社の若い人間なんかよりも、よほど私のことをしっかり観察している。
「人間じゃないですよ、むろん」と私が胸を張って言うと、ダンボールの人間は少し笑う。
「なにいばってんの、動物のくせに」
「なになに、人間だって動物の一種ではありませんか」
「ま、そりゃそうだな」
「人間だって動物の一種ではありませんか」という言葉は、川上文学特有のエッセンスと言えるでしょう。
「私」は、穴の中で飼っている人間について、次のような感想を持っています。
妻は今までに十五匹の子供を生んだ。小さな、
柔 毛 におおわれた、活発な子供たちだった。けれど生まれてしばらくすると、どれも死んでしまった。人間たちは、私と妻の子供が死んだことを知ったとき、さめざめと泣いた。死ぬのは当然の理 なのだから、たとえ死んだのが生まれたての子供であっても、私も妻も泣かない。拾ってきた人間の中には、自分の子供をくびり殺してしまったような者もいるのに、そういうのに限って、ことさらに大きな声で泣いたり身をよじったりする。人間のことは、よくわからない
一匹の動物の視点から見た人間の愚鈍さ、滑稽さを描くことで、人間社会や文明への批評となっている一作です。
『椰子・椰子』――生き物と過ごす不思議な春秋を、たおやかに描く
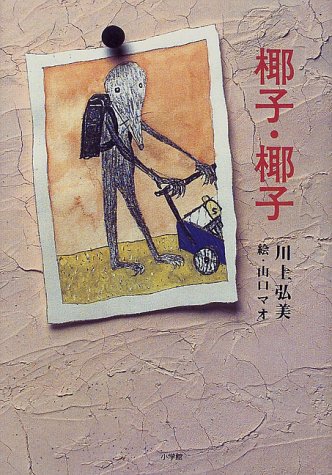
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4093861110/
家の前で出会ったもぐらとの記念撮影、家に住みついた鳥とのおかしいやりとり……。ファンタジーともSFともつかない、ちょっと奇妙で愛おしい日々を綴った日記文学です。
2月16日 雨
ベランダに大きな鳥が二羽住みついてしまう。巣を作っているので、つがいかと思ったら、兄弟だそうである。「鳥」と呼びかけていたら、「僕たちはジャンとルイです」と訂正された。そっくりの2羽なので、いいかげんに「ジャン」と言ったりすると、すぐに「ルイです」と直される。名前は立派だが、ふんは大量にするし、夜昼かまわず大きな声で鳴きたてるし、餌の残骸は散らすしで、そのへんの野鳥と全然変わりない。4月29日 晴
ベランダのプランターに野菜の種を蒔く。ジャンとルイに因果をふくめようと思い、土を掘り返してはいけないだの、新芽を仲間にふるまってはいけないだの、細かい注意をたくさん与える。2羽ともいちいち素直にうなずいていたが、話が終わると声をそろえて、「鳥の理性はあてにできませんぜ」と叫び、笑いながらどこかに遊びにいってしまった。8月30日 晴
奇跡実演講座が、公民館で開講される。その内容が『鳥と簡単な日常会話をかわす』である。いやな予感がしたが、案の定、「近所にいた野鳥を呼んできました」と紹介されたのはジャン(あるいはルイ)だった。「今日の気分はどうですか、最高ならAの紙、まあまあはBの紙、さえない時はC、さあくちばしでつっついてください」というような、カードによる間接的会話をいくつか行ったあと、ジャン(あるいはルイ)は、「クワア」と一声鳥らしく鳴き、窓から飛び去った。家に帰ってから問いただすと、「アルバイト、けっこういいペイですぜ」とくる
人を食ったような態度の鳥たち。ペットブームで動物を擬人化するあまり、ともすれば人間は、生き物と自分は互いに心が通じ合っているはずだ、といった、自分に都合のよい解釈をしがちですが、本作はそうした甘い幻想を吹き飛ばしてしまいます。そして、個々の生き物の習性を理解し受け入れる態度を教えてくれる作品です。
『神様2011』――東日本大震災の原発事故のあと、それでも私たちは散歩に出る
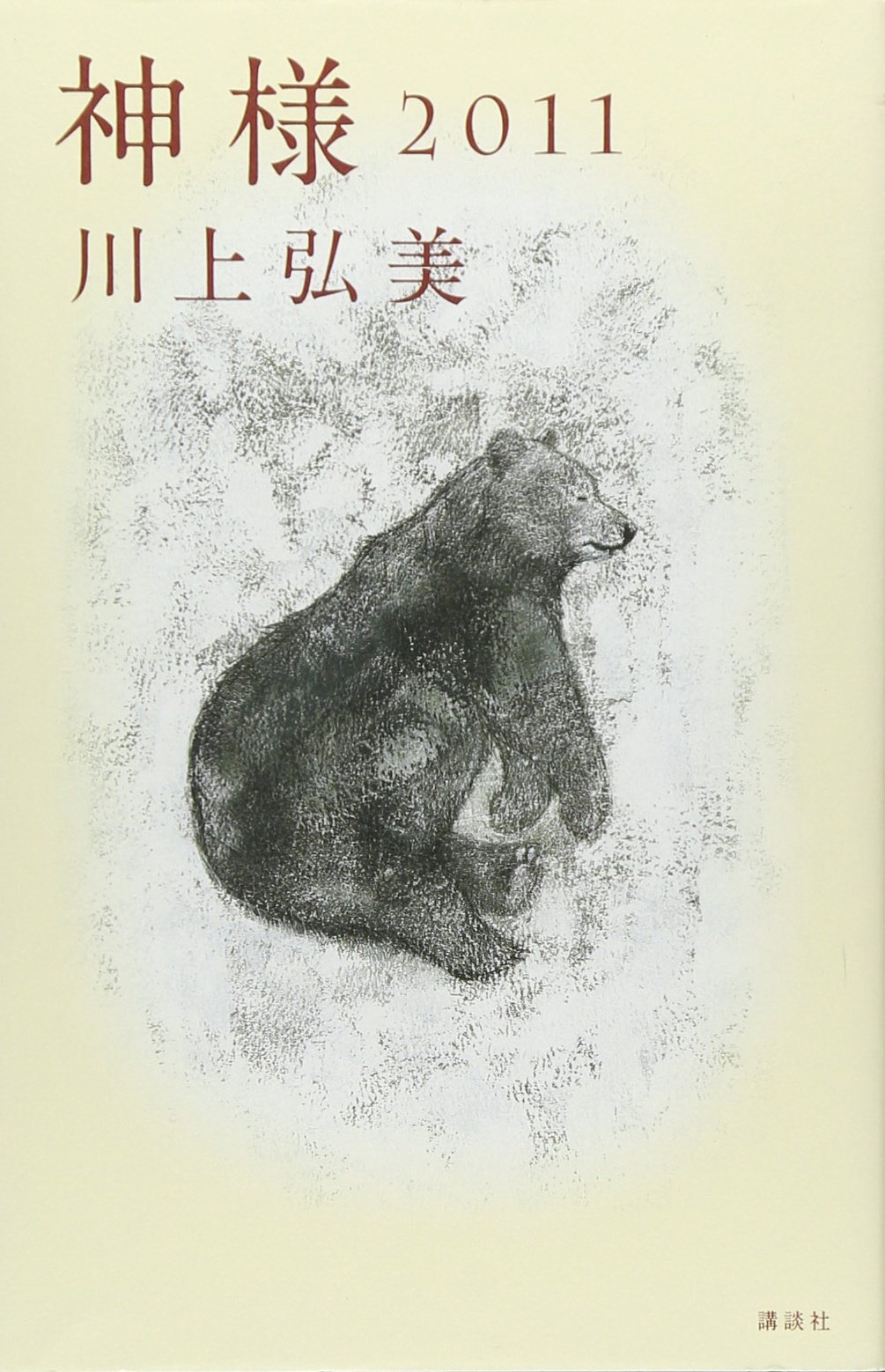
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062172321/
川上弘美のデビュー作『神様』(1993年)は、くまと人間が散歩に出るという、ほのぼのした可愛らしい物語で、ファンの多い作品です。『神様2011』は、東日本大震災に触発された著者が、『神様』を2011年版に書き改めたもの。ここで、『神様』と『神様2011』の冒頭を並べてみます。
くまにさそわれて散歩に出る。川原に行くのである。春先に、
鴫 を見るために、行ったことはあったが、暑い季節にこうして弁当まで持っていくのは初めてである
くまにさそわれて散歩に出る。川原に行くのである。春先に、鴫を見るために、防護服をつけて行ったことはあったが、暑い季節にこうしてふつうの服を着て肌をだし、弁当まで持っていくのは、「あのこと」以来、初めてである
「あのこと」とは、福島の原発事故のこと。散歩中、アスファルトか土の道か、どちらを行くか話すシーンがあります。1993年版『神様』では、2人は迷わず後者を選ぶのですが、2011年版ではどうでしょうか。
川原までの道は、土壌の除染のために、ほとんどの水田は掘り返され、つやつやとした土がもりあがっている。くまは、「僕は容積が人間に比べて大きいのですから、あなたよりも被曝許容量の上限も高いと思いますし、このはだしの足でもって、飛散塵堆積値の高い土の道を歩くこともできます。そうだ、やっぱり土の道の方が、アスファルトの道よりも涼しいですよね。そっちに行きますか」などと、細かく気を配ってくれる
靴をはいていないくまにとって、放射能で汚染された土の上を歩くのは死活問題です。原発の影響は、人間のみならず他の動物にも及んでいることがさりげなく描かれます。
そして、川原に着くと、くまは魚を漁って振る舞ってくれるのです。
「魚の餌になる川底の苔には、ことにセシウムがたまりやすいのですけれど」
放射性物質を気にしながら、くまは即席の干物を作りました。
また、散歩から帰った2人の別れ際の場面が印象的です。
「抱擁を交わしていただけませんか。親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」くまは言った。わたしは承知した。くまはあまり風呂に入らないはずだから、たぶん体表の放射線量はいくらか高いだろう。けれど、この地域に住みつづけることを選んだのだから、そんなことを気にするつもりは最初からない
不慮の出来事に見舞われても、ここで生きていく、という生の肯定。ラストに、読者は一筋の希望を見出せるでしょう。なお、本書は、1993年版『神様』も併録していて、比較対照しながら読めるようになっています。
おわりに
全ての生き物たちへの公平な眼差しと、人間中心主義への懐疑。「僕らはみんな生きている」というような心持ちになれる川上ワールド。皆様も冒険してみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2021/09/30)

